| �bHOME�@�b�@�b�|���b�@�bCAD�v�b�@�b�m�b�@�@�b���T�C�N���b�@�b���˗��b�@�@�b�p�ꃏ���|�C���g���b�X���b�@�b��ЊT�v�b |
������HotNews�i2007�N1���`�j
�@
|
�Q�O�O7�N11����
|
�@
|
�y�@�����̖��ԗÖ@�@�z
|
|
|
|
�@
�������~�Z |
|
�@ �@�������40�N�O�A�`���͊̑��Ɉ�����ᇂ��ł��A���m��w�̕a�@�ł��Ɣ��N�̖����Ɛ鍐���ꂽ���Ƃ�����܂��B�����`���̐E��ł́A�V�����̌��݂ɕK�v�ȎႢ�l�ނ����牽�Ƃ��Ă��`���̖����~�������ƍl���A���銿����w�i������w�j�̖����T���o�����Â𖽂����̂������ł��B���̍��͕�����v���̍Œ��ŁA�`���I�Ȋ�����w�͔ے肳��܂�������A���̖���͊��ɑ����̔N�z�ł������A�J���ɂ��v�z�����Ə̂��Ė����g�C���|�����������Ă����Ƃ�����Ăяo����ċ`����f�@���܂����B���̌��ʁA���̕��@�����Ȃ��ƌ����ē`�����Ă��ꂽ�̂��A���̖���̉Ƃɑ�X�`��邱�́w����x�ł����B�`�ꂪ����ꂽ�ʂ薈���������~�Z�����Ԃ��ċ`���ɐH�ׂ�����̂�2�����قǑ����A���C�����߂��Ă���A�a�@�Ō��������Ƃ���A������ᇂ���������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�S���������m��w�̈�t���ǂ����Ă��M�����Ȃ��ƌ����������ł��B
|
|
�@ �@�����Ƃ��A���������s�v�c�Ȗ��ԗÖ@�ɂ��Ăǂ��v�����A���̉��b���Ĉ�������{�l�̕v�ɐq�˂��Ƃ���u���������b�ɂ͊ւ��Ȃ����Ƃɂ��Ă���B�v�Ƃ̂��Ƃł����B�܂�Ȋw�I�ȍ������Ȃ��̂ŁA�����������ԗÖ@�ɗ����萼�m��w�̕a�@�ł�����Ɛf�Â��������m�����ƍl���Ă���悤�ŁA����͑啔���̒����l�̏펯�ł�����悤�ł��B��c��X�́w����x���p����������ɂ��Ă��A���̑��q�►�́w����x�ɔ����N���Ռp�������Ȃ��ƕ����܂����B�@
|
|
�@ �@ �s��̓~�Z |
�@
|
�Q�O�O7�N10����
|
�@
|
�y�@������C�̌��������@�z
|
|
�@���{�Ƃ̖��炩�ȈႢ�ƌ����A��I���̑O�ɐ_�O�Ő���������Ƃ������V���I�Ȃ��̂��Ȃ��A���l��������Ȃ����Ƃł��傤���B���O�Ɍ����͂��o���A����̐Ȃł͒��l�̑���Ɂu�؍��l�i��������l�j�v�Ƃ�����l���V�Y�V�w�ɂ��āA���ǂ��Ō����͂��o�������Ɍ�������������������܂��B�������{�̂悤�Ɍ������������āA��I�����ς܂��Ă���͂��o���ɍs�����肷��Ə����̂ɂȂ�Ƃ����܂�����A�͂��o�Ė������猋���ؖ������o���Ă��炤���Ƃ��V���̑���ɂȂ��Ă���悤�ł��B���̂ق��̈Ⴂ�Ƃ��ẮA�X�s�[�`�∥�A�����Ȃ��A���l����ْ������S�R�Ȃ��A�I�n���킴��Ƃɂ��₩�Șb��������ь����Ă��邱�Ƃł��傤���B�i��҂�����͓̂��{�Ɠ����ł����A���{�̂悤�Ȓ��l�̒������A�͂Ȃ��A�V�Y�V�w�̌o���Љ�◼�Ƃ̏Љ�Ȃǂ�����܂���B�u�؍��l�v�ɂ��1���Ԃقǂ̕ƁA�r���ŐV�Y�̂�������̈��A�A�㔼�ŐV�Y���g�̈��A�����ꂼ��2�`3���قNJȒP�ɂ����������ł����B���̑��P�[�L�J�b�g��A�w�ւ̌����A�ԉł���̂��F�����A���I��Ȃǂ�����A����͓��{�Ƃقړ����ł��B�̂̓��ӂȐl��2�`3�l���j���̉̂��̂��Ă���܂����B��Ȃ��q����́A���{�Ɠ����悤�ɉƑ���e�ʁA�{�l�����Ƃ��̗��e�̐E��̏�i�⓯���A�F�l�����ł����A�l�������{���͂����Ƒ����A���ؗ����̊ۃe�[�u�������v22�삠��܂�������A200�l�ȏオ�o�Ȃ��Ă������ƂɂȂ�܂��B���{�l�̎��������l���̑����ɋ����Ă���ƁA�܂������̏ꍇ�͏��Ȃ����ŁA500�`600�l���炢�W�܂鍥����������Ȃ��Ƃ������Ƃł����B�܂��A���ҏ�ɏ�����Ă����J�n���Ԃ͗[����5:30���炾�����̂ł����A���ۂɎi��҂��i����n�߂��̂�6:30������A�݂�Ȃ��A��n�߂��̂�9:00������ŁA���{�̂悤�ɂ������莞�Ԃ����߂��Ă���킯�ł͂���܂���ł����B��������Č��Ă���Ƃ�͂���{�̌�����I���Ƃ͂����Ԃ�Ⴂ�܂��ˁB |
|
�@�@�@�@
|
|
�@ �@�V�Y�̂��������A�̒��ŁA�������������������̂�1980�N�̂��ƂŁA�܂��v��o�ς̎���ŕ����Ȃ��A�n�����ɂ������H���Ŕ�I�������A�c���������������ċA���ė[�H�ɐH�ׂ��̂Ɣ�ׂ�ƍ��͑�Ⴂ�E�E�E�ƌ����Ă����̂���ۂɎc��܂����B�����������̍��́A��C�̕�Ȃ�͂Ƃ����鉩�Y�]�̂قƂ�̊O��i�o���h�j����ɂȂ�ƃA�x�b�N�ł����ς��ɂȂ��Ă������Ƃ��v���o���܂��B�Ȃ����Ƃ����ƁA��C�s���ł͏Z���ɒ[�Ɉ����A�Z�މƂ��Ȃ�����������ĉ��N�҂��Ă������ł��Ȃ��J�b�v���������������炾�ƕ����܂����B���̎���́A�܂��قƂ�ǂ��ׂĂ̐E�ꂪ���c�ŁA�����Ă������Ȃ��Ă���ʎs���̌�����30����Ƃقڂ݂�ȓ������x�ŁA�q�ǂ��������ƒ�͂��̕��������ꂵ���A�܂��Ƃ͐E�ꂪ���蓖�ĂĂ������̂ƌ��܂��Ă��āA�����ʼnƂ��Ƃ������T�O���Ȃ��A����ɏo������ʂ̏Z����Ȃ����������ł��B���������ĂȂ��Ȃ��Ƃ̊��蓖�Ă��Ȃ��ǂ���̗��e�̉Ƃ��������ߌ����ł��Ȃ��Ƃ����l�B�͒���������܂���ł����B |
|
�@ �@ |
|
�@ �@�����ɂ��Ă�������{�ƒ����̑傫�ȈႢ�Ƃ��āA���������s���A�V������������̂͐V�Y���̗��e�̐ӔC���Ƃ������Ƃ�����܂��B����͐̂��獡�܂ŕς���Ă��܂���B���̓_�͐挎���Љ�������̔_���ł��A��C�̂悤�ȓs��ł��܂����������ł��B������A����̍���̔�p�ƁA�V�Y�V�w���Z�ސV���̔�p����������̗F�l�ł���V�Y�̗��e�̃�������v�Ȃ����S���Ă��܂��B���������q�v�w�̂��߂ɏ��������V����3�k�c�j�̃}���V�����ŁA���̓�����p��Ƌ�ނ��܂ߖ�200�����i��3,000���~�j�������������ł��B��ɏq�ׂ�1980�N��ȑO�ɔ�ׂ�ƑS���傫�ȕω��ł��ˁB�����č���̍���ɂ͏��Ȃ��Ƃ�10�����i��150���~�j�͂������Ă���ł��傤�B�����d�����S�ł����A�����l�ɂƂ��Ď����̑��q�̍���͈ꐶ�Ɉ�x�̑厖�ŁA���̂��߂ɂǂꂾ���̔�p�������A����ɂǂ�ȓ�����F�l�����������́A���̐l�̎Љ�I�n�ʂ���͂��]��������̏d�v�Ȗڈ��ɂȂ��Ă���悤�ł��B����͒����l���ł��d��ƌ����Ă���u�ʎq�v�̖��Ɋւ���Ă��邽�߁A����ɒN�������A�ȏ����ǂ����邩�A�N�Ɂu�؍��l�v�ɂȂ��Ă��炤�����X�ɂ��̂������C���g���A���������O���獪������ƕ����܂����B�����̍���������q�̍���̕����d�v���ƌ�����قǂ������ł��B�ꏏ�ɍ���̍���ɏo�Ȃ�����C�l�̕v�ɂ��A�u��������͂���Ő��U�̑�d�����ʂ������B�����̏��ҋq�̐ȏ��₻�̑��̒i���͔��Ɏ����ɍl�����Ă��āA�[�������Ƃ̖ʎq���ۂĂ��B�v�Ƃ������Ƃł��B �@���q�̂��߂ɐe���ǂꂾ���̎d�x�����Ă��邩���A�����̏����ɂȂ�͔̂_���̌�������Ɠ������ƂŁA��C�s���̏ꍇ�́A�܂���C�s���ɐV���������ł��Ă��邱�Ƃ��A������C�o�g�̂��ł�������炤��O��ɂȂ邻���ł��B��C�l�͏�C�l���m�ŁA���ꂼ��̉ƒ�̏������قړ����x�̐l���m����������̂���Ԃ����Ƃ����l���́A�e�����͂������̂��ƍ��̎Ⴂ����̐l�B���܂������ς���Ă��܂���B����̐V�Y�̃����N�ƐV�w�̃`�F������́A���Z����̃N���X���[�g���m�ō��N27�A10�N�Ԃ̗����̖��Ɍ��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B�������ǂ������C�̏o�g�ʼnƒ�̏����ɂ�����قǑ傫�ȍ��͂Ȃ������ł��B |
 �@ �@�쓜�i�V�[�^���j |
�@
|
�Q�O�O7�N9����
|
�@
|
�y�@�����_���̌��������@�z
|
|
�@�䂪�Ƃ̂���`������\�n�I����ɂ͖��m�ȖڕW������܂��B����͍��N16�ɂȂ鑧�q�ɂS�N�エ�ł�������炤���Ƃł��B�Ȃ����ꂪ�ޏ��̖ڕW�ɂȂ邩�ƌ����A��ʂɒ����ł͑��q�̍��������s�����Ƃ��e�̐ӔC���Ƃ���Ă��邩��ł��B����̓n�I����̌̋��ł���͓�Ȃ̉��E�i���������j���ł������ł����A��C�̂悤�ȑ�s�s�ł������ł��B�Ƃɂ����q�ǂ�����������܂ł͐e���S�ʓI�ɐ��b������̂������ł͏펯�ɂȂ��Ă��܂��B |
|
�@ �@���A�n�I����̂���l���L���Ȃ֏o�҂��ɍs���Ă��āA18�ɂȂ邨�삳��������L���Ȃœ����Ă��܂��B���̖��̂��߂Ƀn�I����͂��낻�낢������������Ă��������������A���N���i����̍��N���A�܂藈�N2���̏t�߂܂Łj�ɂȂ�Ƃ�����ɂ����������ƍl���Ă��邻���ł��B�������͂������̎���A�e��������������߂�Ȃ�ĕ����I�߂��邩��A�{�l�ɔC���Ă��������̂ɂƌ����Ă���̂ł����A�{�l�͂܂�����Ȃ����A����͓����������̋߂��̑��̏o�g�҂łȂ�����߂�����A��e�ł��鎩�����܂������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ƃn�I����͎咣���܂��B�������{�l�̈ӎu�d���A���������͂����A�{�l�̋C�ɓ��鑊�肪������܂ł��������͉��x�ł����Ă����̂������ł��B�@�����łɂ�邽�߂ɗp�ӂ��ׂ����̂͒ʏ�A�z�c���W�g�ȏ�Ƃ��������ŁA���q�ɔ�ׂ�ƕ��S�͂����ƌy���A����ȊO�ɖ{�l������܂łɒ��߂������͂��̂܂�������̂ŁA����ŏ[�����Ƃ����܂��B |
|
�Z��̎���Ƃ�����o�҂��J���� |
|
�@ �@����Ȃ畉�S�̌y��������l����Ώ[���Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ȃ��_���ł݂͂�ȂȂ�Ƃ��Ă����q��~������̂��ƌ����A�Ƃɂ����Ռp�������Ȃ���Θb�ɂȂ炸�A���q����l�����Ȃ��Ƃ́A�������Ă������ڂ͂Ȃ����A�l����n���ɂ���A�܂Ƃ��Ɉ����Ȃ����炾�����ł��B�n�I������A��ɏ��̎q�����܂ꂽ���́A���Ƃ���̋@���������A���̎q���S�R�������Ă��炦���A2�N��ɑ��q�����܂�Ă���悤�₭�@��������A�n�I������łƂ��ĔF�߂Ă��炦��悤�ɂȂ�܂����B��l���q��������{���钆���ŁA�ǂ�Ȃɔ������Ƃ��Ă����q�����܂��܂Ŏq�ǂ��ݑ�����l�������̂͂��̂�����ɗ��R������悤�ł��B |
|
�@ �@�ł����N�A�Ӌџ���Ȃ��_���N����ݗ�����Ɩ����̂�����V��͂���Ő����ł���̂ł͂Ȃ��́A�Ǝ��������ƁA�u����͒������{������Ɍ����Ă��邾���ł��傤�B���烏���������Ƃ͊W�Ȃ��B�v�ƁA�������肵���������Ԃ��Ă��܂����B�䂪�Ƃ̋ߏ��̔_���ł͊��ɔ_���N�����S���Ɏx������Ă���̂ł����A����͏�C�̖L���Ȕ_���������̂��ƂŁA�������̎���͑S�R�قȂ�̂������ł��B
|
|
�o�҂��҂����H�鉮��B�����A�����i�g���p���j�A���݁i���D�ݏĂ��j�A�˗ޓ��Ȃ�ł�����B�����ǂ����Ă��E��̗��ĎD�ɂ́u���䌵�ցv�Ə�����Ă���B |
�@
|
�Q�O�O7�N8����
|
�@
|
�y�@��C�̒��H�����@�z
|
�@����̗[���Łu�I�t�B�X�r���ŏ�C�A�[�C�ɗ����𗊂ށv�Ƃ����L�������܂����B�A�[�C�i���H�j�Ƃ́A�{���͏f�ꂳ��Ƃ����Ӗ��ŁA�f�ꂳ��̒��ł���e�̖����w�����Ƃł��B�����Ď��ۂɎg�����́A�����̖{���̏f�ꂳ��ɑ��Ă͂������A���m��ʏ����ɑ��Ă��A�ߏ��̏����ɑ��Ă��A�N��ɊW�Ȃ��e���݂����߂ČĂт����邱�Ƃ̂ł���֗��Ȃ��Ƃł��B����`������̂��Ƃ��A�c�t���̐搶�̂��Ƃ��u�A�[�C�v�ƌĂт܂��B���̋L���̒��ŏЉ��Ă���̂́A�ŋߏ�C�̒n���̃A�[�C�ɗ���ŁA�I�t�B�X�r���œ����Ј��̂��߂ɒ��H������ē͂��Ă��炤��Ђ������Ă����Ƃ������e�ł����B |
|
|
�@ �@�u�S�t��(�p�C�C�G�p�I/������Ƃ����������肵�����������œؓ��̃~���`�Ɩ�����������̂���Ŏς�����)�v�u���S�i�`���A���V���c�@�C/�L���x�c���u�ߕ��j�v�u�y���r�i�`���c�p�C�j�ؓ��̓��g���j�v�u�_煊C��(�X�A�����[�n�C�^�C/���z�̃s���h�|�̕�)�v�u������(�`���B���N�^��/���̂��X�[�v)�v�������͂���}�l�W�����g��Ђ̐l����������̂����ɐH�ׂ������ł��B���������u��C�A�[�C�v�̗����́A�Ⴂ�T�����[�}����n�k����������������肵�Ă��Ē������[�����Ă���Ɗ��Ă��܂��B���̉�ЂŃ}�l�[�W���[������e�B������̘b�ł́A�u���Ђ̎Ј��͑啔������C�l�ŁA�ȑO��1��10��(��150�~)�̒��H�蓖���x�����Ď��R�ɐH���������Ă����Ƃ���A��Ђ̋߂��ɂ���̂̓��[�������ƃt���C�h�`�L���̓X�����ŁA���ɂ͂��������킷�l������Ȃǂ��āA�����F�X���傪�o�Ă��܂����B�����ŋߏ��̉Ɛ��T�[�r�X��Ђɗ���Œn���̃A�[�C�ɒ��H������Ă��炤�̂��Q�����������Ƃ���A�]���͏�X�ŁA�݂�ȑ喞�����Ă��܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł��B���̃A�[�C�͖������H��ɂ݂�Ȃ̈ӌ����ė����̃��j���[�����A����Ɋ�Â��\�Z�𗧂Ăĉ�Ђ̃}�l�[�W���[�̏��F�����炢�A���������s��֍ޗ����o���ɍs���A�T���ɂȂ��1�T�ԕ��̔�p���܂Ƃ߂Đ��Z���܂��B�ʏ�A���тƃX�[�v�̓I�t�B�X�̃L�b�`���ō��܂����A���̑��̗����̓A�[�C�������̉Ƃō���āA�����ɂȂ�Ɖ^��ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�ޏ������͑啔����50����65���炢�̏�C�̎�w�ŁA�q�ǂ��������Ɨ����A�Ƃɂ��Ă����邱�Ƃ��Ȃ��A��������ĉ�Ј������̗�������邱�ƂŐl���́u�]�M�v���ł���̂������ł��B����ɃA�[�C�����͎Ⴂ�T�����[�}����n�k�����������̉Ƃ̎q�ǂ��̂悤�ȋC������Ƃ������Ă��܂��B |
|
�u�S�t��v |
|
�@ �@�܂��A�ʂ̉�Ђɒ��H��͂��Ă���`�[�A�[�C�́u�������̊Ԃł͕s�����݂����Ȃ̂�����A�����̕��ʂ�20�l����Ƃ݂�Ȃ�肽����܂���B�����Ď��v�����߂���ƉƂ̂���ł͍��Ȃ����A�������̕����Ȃ��Ȃ邩��ł��B�v�ƌ����܂��B�`�[����͂����O�ɗ�����͂��A�݂�Ȃ��H�I���Ƃ��̕�����|�����A�H��ނ����ꂢ�ɐ���Ă���A���̓��̃��j���[���݂�ȂƑ��k���Č��߂邱�Ƃɂ��Ă��邻���ł��B����Ŗ����̋�����600��(��9,000�~)�A�ޏ��́u�ƂĂ��[�����Ă��Ė������Ă��܂��B�v�Ƃ̂��ƥ��
�@���āA���{�ł͂ǂ��ł��傤�B�{�����e�B�A�����̈�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������Ɛ��N�o���āA�����Ƃ̋ߏ��ɓK���ȉ�Ђ�����A���������A�[�C�ɂȂ��Ă݂Ă��������ȁA�Ǝv���Ă��܂��B |
|
��C�̋��s�X��̃I�t�B�X�r�� |
�@
|
�Q�O�O7�N7����
|
�@
|
�y�@�����̗��ނ��i���j�@�z
|
�@�����͂��̃z�b�g�j���[�X5�����ł��b�������A��O���ł̗��ނ��̂��̌�ɂ��Ă� �������Ǝv���܂��B �@���ǁA�����ނ��ɓ��ӂ���A���z�ʐςP�u�����蕽��4,000����(6���~��)�̗��ނ��⏞�����x�����A���̒n��̐V�����A�p�[�g���s�ꉿ�i��6�����甼�z���x�ŕ�������邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�܂����̂ق������ނ����l�͑S���A���U�ɂ킽��A�����蓖�ƈ�Ô�⏕�����A����ɂ���ȊO�ɐV�����Z���������ďZ�߂�悤�ɂȂ�܂ł̉ߓn�I�ȏZ���⏕�Ƃ��āA�����ނ����Ƃ̌��z�ʐ�1�u�����薈��8�����x�������Ƃ������Ƃł��B���ϓI�Ȕ_�Ƃ̖ʐς�300�`400�u���x����܂��̂ŁA1���ɂ�120���`160����(1,800���`2,400���~)���x�̗��ނ��⏞���ƁA�Ƃ���Ă���Ԃ͖���2,400�`3,200��(36,000�`48,000�~)�̏Z���⏕�A�Ȃ�тɐ��U�ɂ킽�薈����l�����萔�S��(��O���Ŕ_���Ƃ��ē������N���₻�̑��̏����ɂ��قȂ�)�̐����蓖���x�������͂��ł��B���������ė����ނ����l�B�̐����͈ꉞ���ׂƌ�����ł��傤�B�܂��Ⴆ��70�Έȏ�̍���҂����̐��т͗��ނ��⏞�������ς��2�����x��悹����A���ʈꎞ���Ƃ���20�������]���Ɏx������ȂǁA�ʂ̏����ɉ������z��������Ă���悤�ł��B |
|
�@ �@�ȏ�͑�܂��ȓ��e�ł����A���ނ��ɂȂ�n��̌f���ɐ����Ȑ����������\��o���� �ďڍׂ����J����A���łɕ⏞������ɂ����l�����܂�����A���x�͈ꉞ�M���ł�����̂悤�ł��B��������������̔_���o�g�̐l�́A���������Ȃ���тł����ɂ������ނ��ƌ����Ă��܂����B
|
|
�����n�܂����ƁX |
|
�@ �@5�����Ŏ��́u�Z�������̈ӌ����āA1�u�����蕽��5,000������6,000���A�ō�8,500���̕⏞�����x�����邱�ƂŁA�S���܂荇���������v�Ɛ\���܂������A����͂��������Ŕ�ь����u���������i�V�A�I�^�I�V�A�I�V�j�v�ƌĂ����R�~���A�܂�\�b�̈�ɉ߂��Ȃ������悤�ł��B�\�������܂���B |
|
�@ �@���ނ��v���ɉ������Ƃ��珇�Ɏ����n�܂����͖̂�1�����O�̂��Ƃł��B�ŏ��Ɏ��ꂽ�Ƃ́A���傤�ǎ����Z�މƂƐ���͂���Ō����������Ă���̂ł����A�����̂���l�̃w�C����͖���ňړ]���i�Ɩ��Ɍg����Ă��邽�߁A���炪���悵�ė����ނ����Ƃɂ����悤�ł��B�ȑO�͂悭��ɏ����ȃ{�[�g���ׂċ���߂��Ă��āA�����ԂŃU���K�j��߂�̂���`���Ă��ꂽ���Ƃ�����܂��B�Ƃ̎����n�܂������A�w�C����͂킴�킴��̂����瑤�ւ���ė��āA�����̉Ƃ���Ă����̂��������炶���ƌ�����Ă��܂����B
|
|
�Ƃ����ꂽ��(���[) |
�@
|
�Q�O�O7�N6����
|
�@
|
�y�@�u���l�v�@�z
|
|
�@�u���l�v�Ƃ͂ǂ������Ӗ����A������ɂȂ��݂̂Ȃ��l�ɂ̓N�C�Y�̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B�u���l�i�J�I�J�I�j�v�Ƃ́u�����@�Z���w�l���v���Q�����ɏȗ��������̂ŁA�܂��w�����̂��Ƃł��B�u���l�i�c���J�I�j�v�͍��Z�������w���܂��B�����ł�9�����V�w���ł�����A6��������܂ł������̃V�[�Y���ŁA���傤�Ǎ����͓������I���������A��������ƒ�̓z�b�ƈꑧ�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B �@�@�@�@�@�@ |
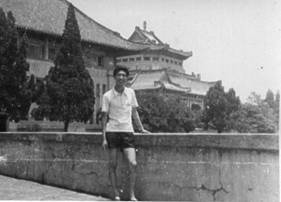 �����̑�w�i1970�N��j |
|
�@ �@���N�͒����̑�w��������30���N�ɂ�����܂��B�����ł�1966�N����1976�N�܂ł̕�����v���i�����S�y���������݁A�����A�o�ρA�Љ�A�v�z�A�����A�s�������������镪��ɋy���v�^���ł����A���Ԃ͓�����Ԃɋ߂������ƌ����Ă��܂��j�̊ԁA10�N�Ԃɂ킽�萳��Ȋw�Z����Ƃ������̂��قƂ�Ǎs��ꂸ�A��w���������~����Ă��܂����B1977�N5���ɂȂ��Ă���A����܂Ő��������̒��Ŏ��r���J��Ԃ�3�x�ڂ̕������ʂ�������������������u�m���d���A�l�ނd����v�ƌ����đ�w�����������ق̂߂����Ă���A�������_�����o�āA���ɂ��̔N�̕��ɑ�w�����ĊJ�����������̂ł��B |
 �����̑�w�i���݁j |
|
�@ ���̌�A��w��W����͖��N���������A���ɍŋ߂�1998�N108���l�A2002�N275���l�Ƌ}���ɑ������A���N2007�N�͕�W���570���l�ɑ��A����1,000���l������������ɒ��݂܂����B�S�̂̍��i���Ō���ƁA30�N�O��4.7%����2006�N�x��56.85%�ɂ܂ŏ㏸���A��w���ƌ����Ă��܂��������������݂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
|
|
�@ �@�V�����r�W�l�X�`�����X�����܂�Ă��܂��B�u���l�ۛG�i�J�I�J�I�p�I��/�Ή��Ɛ��w�j�v�Ƃ́A��w�̐������O�ɂȂ�ƁA���Ɏ����ɐ��b�����邨��`��������ق��ƒ낪�o�Ă��܂����B����Ɛ��w�h����Ђł́u���l�ۛG�v�ɂ��Ă̖⍇���̓d�b���P������10�����͂����������ł��B�����Ď��I�������́A�u���ߕۛG�i�y�C�����p�I��/�V�ё�����Ɛ��w�j�v�̖⍇���������Ă��܂��B�����Ԏŋ�J�����q�ǂ����˂��炤���߂ɉƑ����s������������ǁA���̉ɂ��Ȃ��e������`�����ɗ���Ŏq�ǂ��𗷍s�ɘA��čs���Ă��炤�Ƃ������̂ł��B�{�l�͎��������ŗ��s�������ƌ����̂ɑ��A�قڑS������l���q�ł�����A�e�Ƃ��Ă͐S�z�ł��܂炸�A�}築Ɛ��w�h����Ђɗ��s�̕t���Y���̂��߂̂���`������𗊂�ł���e���������������Ă��܂��B���ƌ����Ă����͂���18�ł�����A����ɑ��āA�f�Ŏ������������ōs���Ǝ咣����q������A��s�@�ʼn����֒������s�����Ă����Ȃ炨��`�������ł������Ə���������q�ȂǁA�����͐F�X�̂悤�ł��B
|
|
�@ �@��C���q�̃��[�N�i26�j�ƃ�������i24�j�ɁA���������ɂ��Ăǂ��v�����ƕ������Ƃ���A���̂悤�ɘb���Ă���܂����B�u�������͂��̂��������W���A������������\�o�Ă��Ă��܂��B�������̎���Ɣ�ׂĂ���ʎs���̐����͂��Ȃ�T���ɂȂ�܂����B���Ƃ��Ǝ��삪���܂�L���Ȃ��l����U��������ɂ���ƁA�����̂��Ƃ����܂��q�ǂ��̂��Ƃ��l���邾�낤�Ǝv���܂��B���������e�����̋C�����͂悭�킩��܂��B�S�z����̂͂킩�邯�ǁA������10���炢�̎q�ǂ��Ɠ����悤�Ɉ����̂́A���߂��ł��傤�B�S�z��������K�x�ȍs���̎��R��^�������������Ǝv���܂��B����`�������t���Y�킹�Ċē�����̂͋t���ʂɂȂ�ł��傤�B�O���l�͂����Ă��q�ǂ���18�ɂȂ����玩�������悤�ƍl���܂��ˁB�����̎q�ǂ����Â₩����Ĉ���Ă���̂͒����l�Ƃ��Ă�����ƒp���������ł��B����܂ʼnƂ̒��̍c��݂����ɐ������Ă��āA�����Ȃ莩�����������ŗ��s�������ƌ����Ă��A���e�ɔ������͓̂��R�ł��傤�B�Ԃ��^�]�������Ƃ��Ȃ��̂ɁA�}�ɉ^�]����ƌ����o���̂Ɠ������Ƃ��Ǝv���܂��B�������e��������A��͂蔽���܂���B�ł�18���炢�ɂȂ�A������x���������āA�ǂɂԂ������玩���őΉ���������o���o�����ł���悤�ɂ��Ă�肽���ł��ˁc�c�B�v �@ |
�@
|
�Q�O�O7�N5����
|
�@
|
�y�@�����̗��ނ��@�z
|
�@�o�ϔ��W�̓r��ɂ��钆���ł́A�e�n�ő�K�͂ȓy�n�J�����s���Ă��܂��B���R���̓y�n�ɏZ��ł����l�B�₻���ɂ����������͗��ނ��𔗂���킯�ł��B������L���Ȃ̔_�����Œn�����{�̓y�n�J���������ďZ�����������A���̌������̎�����P������A�����𐭕{�����ɕ����߂��肵���Ƃ������`���f�B�A����̏���{�ł�����Ă��܂����B �@��C�s�̓��v�ɂ��Ə�C��2006�N�x���ɂ��Ƃ̏Z���𗧑ނ��ɂȂ����s���̉Ƃ�76,900�˂ɂ̂ڂ�܂����i��܂��Ɍ����ď�C�̐l����1,900���l���A���̂�����70%����C�s�ɌːЂ�����l�A�c���30%�͑��̒n������̗����l�����ƌ����Ă��܂��j�B |
|
���ނ��ԋ߂̉ƁX |
|
���ނ��ԋ߂̉ƁX
|
|
�@ �@�����Z��ł���ꏊ����C�x�O�̔_�����ő�O���Ƃ����Ƃ���ł��B�����ł�1990�N��̏I��荠�����K�͂ȊJ�����i�݃n�C�e�N��n�����݂���A����ɔ����e��̐����{�݂₻�̑��̃C���t�����ǂ�ǂ�����Ă��܂��B4�N�قǑO�ɉ䂪�Ƃ̐�������ɂ��鐔���̔_�Ƃ���ĂɉƂ̌��đւ����n�߂����Ƃ�����܂����B������Ă݂�ƁA���̂�����̉Ƃ��܂��Ȃ����ނ��ɂȂ�炵���Ƃ�������������炾�Ƃ����̂ł��B���ނ��ɂȂ�̂ɂȂ��܂����ꂩ��Ƃ����đւ���̂ł��傤���B����ɗ��R���Ă݂�Ƃ���܂ŗ��ނ��̕⏞���́u�l���Z�i�A�������g�E�X����/�l�̓����ɉ����Čv�Z����j�v�������̂��A����́u���A���Z�i�A���c�A���g�E�X����/�����K�̐��ɉ����Čv�Z����j�v�ւƐ��ς�邩�炾�Ƃ������Ƃł����B�܂肻��܂ł̗����ނ��⏞���͈�l�����肢����ƌ��܂��Ă������̂��A1�u�����肢���炩�ւƕς��A�����K�̐��܂�Ƃ̌��z�ʐςɂ��v�Z����邱�ƂɂȂ����Ƃ����̂ł��B
��������4�N�قǂ������ŋ߁A���悢���������̂��̒n��̉ƁX�������ނ����ƂɂȂ�܂����B�����������Ԃ������Ēn���̖�����������q�A�����O���s���A�Z�������̈ӌ����āA1�u�����蕽��5,000������6,000���A�ō�8,500���̕⏞�����x�����邱�ƂŁA�S���܂荇���������Ƃ����b���܂����B���̂�����̔_�Ƃ͂����Ă�1����300�`400�u�قǂ̌��z�ʐς�����̂�1�˂�����150��������240�������x�̕⏞������ɓ���v�Z�ɂȂ�܂�(1���͖�15�~)�B���Ȃ݂ɏ�C�̃T�����[�}���̕��ό�����2,000����ł��B �@�����̔_���ł͐̂��炻�̓y�n�ɏZ�ݒ����đ�X�_�Ƃ�����Ă���Ƃ��啔���ŁA��̑��݂͂�Ȃ��m�荇���Ƃ����n�������łȂ����������̂ł���̂����ʂł��B�����đ����⑺�̋��Y�}�ψ���L�����̋����̂̈���ł��邱�Ƃ������A�����������ł͑傫�ȃg���u�����N���邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B���������ė��ނ��ɂȂ�ɂ��Ă��A���N���O�����L�܂�A���������̔������m���߂Ȃ��珙�X�ɋ�̍ł܂��Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B������ꂼ��̑����͓��S�s���������݂������Ă���ꍇ�������̂ł��傤���A���Ȃ��Ƃ��\�ʓI�ɂ͂��̂悤�ɂ��Ċۂ����܂�̂����ʂł��B |
|
�@ �@�ł�����`���ɋ������悤�ȃj���[�X���Ď��́A�����̊��������͂�قǂЂǂ����E�����Ă������A���邢�͑��̒n������h������ė��āA�n���̎���ׂ����������Ƃ̊W��z���n���ȓw�͂Ȃǂ������A�^�ʂ�̐�������s���悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����A�ȂǂƑz�����߂��点�Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�n�E�X�͔|�̔_�n |
�@
|
�Q�O�O7�N4����
|
�@
|
�y�@�����N�@�z
|
| �@ �@�����ō��N��600�N�Ɉ�x�������Ȃ��u�����N�i���̓̔N�j�v�ŁA���̔N�Ɍ������Ďq���ނƋ��^�Ɍb�܂�A���N���悢�ƌ����Ă��邻���ł��B�����Ƃ�����͐��N�O�ɒN���������o�������ƂŁA�Ռo�ɂ��������L�ڂ�����킯�ł��Ȃ��A�Â�����`���悤�ȍ����͓��ɂȂ��Ƃ������Ă��܂��B����ǂ��Ƃɂ����A�Ⴂ�l�̊Ԃł�������������Ȃ�Ȃ�Ƃ����N���ɂƂ����l�������A���N�͈��̌����u�[�����N���Ă���̂������ł��B �@ |
|
��C�̃f�[�g�X�|�b�g�\�O��(���C�^��)����Ί݂�]�� |
|
�@ �@1949�N�ɐV��������������܂ł̕����Љ�ł́A��������͐e�����߂�̂����ʂŁA�������̓����A���߂đ���̊������Ƃ����̂�������O�������ƕ����܂����B�悭�����̉f���e���r�h���}�̒��Ő̂̌�����������ƁA�ԉł���ɐԂ��z�����Ԃ��Ă��āA�N���C�}�b�N�X�ʼnԖ������̐Ԃ��z�������グ��V�[���������ɂȂ������Ƃ�����l���������Ƃł��傤�B���������ɉ��g�����܂��Ă���̂ł�����A���̎��ɖ{�l���m������̂��Ƃ��ǂ��v�����Ȃǂ͖��ɂȂ�Ȃ������킯�ł��B�������͐̂̂��ƂŁA���ł͐e�ɐ�Ε��]����ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂������B
|
|
�@����ɑ��ēs�s���̎���͑S���قȂ�܂��B��C�Ȃǂ̓s�s���ł́A���{�Ɠ����悤��30���߂��Ă��Ȃ��Ȃ��������Ȃ��l�������Ă��܂��B�d�����Z�����ēK���Ȉِ��ɂ߂��荇���`�����X���Ȃ��A�e���ɋ�������y�ł������X�A���̗��R�����{�Ƃقړ����ł��B�����Ō����Љ���ł�����A�����c�̂▯�ԉ�ЂȂǂ���Â���e�킨�������p�[�e�B�A���������c�A�[�ȂǁA���܂��܂Ȏ��݂��Ȃ���Ă��܂��B |
| ����Ȓ��A�ŋ߂ł́u�Nj�(�E�E)����Ёv�Ƃ������̂܂Ō���܂����i������́u�Nj��v�ɂ͓��{��Ɠ����Ӗ��̂ق��Ɂu�Ӓ��̐l��ǂ�������v�Ƃ������Ӗ�������܂��j�B�������������Ђ��o�c����X�ɍs����34�̉��N�̘b�ɂ��A�����̃X�^�b�t�͂ƂĂ��e�ɑΉ����Ă��ꂽ�����ł��B �u�K�[���t�����h���������Ă����ł����B�v�ƌ����ƁA �@�u�ł́A�����Ӓ��̐l��������ł�����A���ǂ����S�v���Z�X�ɂ킽��Nj�(�E�E)�T�[�r�X���������Ē����܂��B�ǂȂ��������łł��傤���H�v�Ƃ��̃X�^�b�t�B �@�u���܂���B�v �@�u�����ł����B�ł́A�Ȃ�ł������ɂ��T���ɂȂ��Ă݂ĉ������B�������ڂɂƂ܂�����������A���̕��̑�܂��ȏ����������������B���Ђ̂����郋�[�g��ʂ��āA���̕��̎��ʋΎ��ԂȂǏڂ����������גv���܂��āA���ꂩ�炨��l���w���R�x�o��@������x���ݒ肵�č����グ�܂��B���̏ꍇ�́A���������^���̎��Ō���Ă���Ƃ��������Ȃ��悤�ɂ����v�炢�����Ē����܂��̂ŁE�E�E�v �@�u����ŗ����́H�����܂ł��܂�����Ă��炦��̂Ȃ�A����������ł��傤�H�v �@�u����͓�Փx�ɂ���ĈقȂ�܂��B���ʂ̏��̎q�Ȃ�4,000���i��6���~�j�|�b�L���ł��������܂��傤�B�������Ȃ���Η����͒����܂���̂ŁA�����S���I�v �@�X���o�Ă��牤�N�́A����̓��b�L�[���ˁA������ĒT���āA�����q�������炱�̓X�ɗ���ł݂悤�A�ǂ����݂��������Ȃ���^�_�Ȃ���A�Ǝv���܂����B �@�����㉤�N�́A�o�X�̒��ŏo����������Ɉ�ڍ��ꂵ�A���Ƃ��������Ǝv���čĂт��̓X�֍s���Ă݂܂����B�X�Ŏ����b���ƁA���̃X�^�b�t�́A�킩��܂����A���ׂ������悲�A�������Ă��������܂��A�ƌ����܂����B �@���M���^�ő҂��Ă���ƁA����������Ђ��������Ă�3���������Ȃ������ɁA���z���������������Ƃ̘A��������܂����B �@�u�ޏ��̖��́A�ѐÍ�����A28�A���~��������Ђɂ��߂ł��B�����Nj�(�E�E)�Ɩ��̓W�J�����v�]�ł�����A�_�ɂ��������������܂��āA�Nj�(�E�E)�ɐ����v���܂����������ɂ́A�萔���Ƃ���8,000�����Ղ��邱�ƂɂȂ�܂��B����������́H�v �@�u���̑O�A4,000���Řb����������Ȃ��ł����B���ꂪ�ǂ����Ă܂�8,000���Ȃ̂ł����H�v �u�������ƁA����͂ł��ˁB���̕��̏ꍇ�͓��ʂȎ���������܂��āE�E�E�B�v �u���ʂȎ���H�v �u�͂��A�܂肱�̕��ɂ͂��łɃ{�[�C�t�����h����������Ⴂ�܂��̂ŁA�����I�ɒlj��Ɩ��������v���܂��B�v �u�lj��Ɩ��ƌ����܂��ƁH�v �@�u�����A�܂�ł��ˁA�w�Ԃ��x�Ɩ��ł��B�v�X�^�b�t�̐l�͂��܂�����ł��������܂����B �@���āA���N�����̌�_���̂��ǂ����́A�܂��m���߂Ă��܂���B�Ƃ�����A�����N�̍��N�A�����ł����{�Ƃقړ����ɂ���Ă���S�[���f���E�B�[�N�ɂ͗�N��葽���̃J�b�v�������������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł��B �@�@�@�@�@�@�@ |
|
��I�������郌�X�g�����̑O�ɂāi��C�x�O�j |
�@
|
�Q�O�O7�N3����
|
�@
|
�y�@�����̂���`�������@�z
|
|
�@ |
|
|
|
�@�m���Ƀn�I����͎͗����œ����҂炵���A�䂪�Ƃł�74�ɂȂ镃�����N�ŁA����10��������ǂ����֗V�тɍs���ė[���܂ŋA��܂���A�n�I����͌��\�q�}�����ɂ��Ă��܂��B�����͂��]���Ď肪�ނ��ނ�����ƌ����A���N����Ƃ������Ƒ|�����ς܂��āA�T�`�U�������炢�W���M���O�����܂��B���ю�������͓�ȏo�g�̂������A���p�̐S�������邻���ŁA�J���~���ăW���M���O�ł��Ȃ����͉Ƃ̒��łł�Ԃ������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�����W���M���O����ޏ��̂��Ƃ͋ߏ��ł��]���ɂȂ��Ă���ƕ����b���Ă��܂����B
|
 �n�I���V���ɑ|���W���������� |
�@
|
�Q�O�O7�N2����
|
�@
|
�y�@�N��с|�����̔N�z�������@�z
|
|
�@�N��с|�����̔N�z������ �@���N�̏t�߁i�������j�͂Q���P�W���ł������A�����ł��S���I�ɒg�~�ŁA���ɂȂ��g�����������ł����B���U�ɂ��������������{�Ƃ͈Ⴂ�A�����ł͑�A���̗[�H�������������̃N���C�}�b�N�X�ɂȂ�܂��B�����̐l�B�͂P�N���P���Ɍ����āA�P�N�̖�̐H���Ƃ����Ӗ������߂Ă�����u�N��сi�j�G���C�G�t�@���j�v�ƌĂ�ő�ɂ��A�Ƒ���e�ʂ��W�܂��Ă��y�����܂��B �@���N�̑�A���A�䂪�Ƃł͍��v�Q�W�l���W�܂��āA�傫�Ȋۃe�[�u���Q���݂͂܂������A����ł����Ԃ��l���o���قǂł����B�ǂ�Ȃ��y�����o�������Љ�Ă݂܂��傤�B |
|
�@ �@�܂���i�����c�@�C�^�I�[�h�u���j�Ƃ��āA |
|
�@ �@�ȏ�̗����͎�ɁA���N�V�R�ɂȂ�v�̕������A�ق��̐l���������`���܂����B���͖��N�t�߂�1�����قǑO����ޗ��̔��o�����n�߂܂��B�����ł����i�͎�w��������������������̂ł����A�t�߂Ȃlj����̍s���Ől���W�܂鎞�ɂ́A���ɏ�C�ł́A�����̓��ӂȒj��������Ă���邱�Ƃ��悭����܂��B |
|
|
�@
|
�Q�O�O7�N1����
|
�@
|
�y�@�����̈�l���q�����@�z
|
|
�@�����ł�1979�N�����l���q�����{����Ă��܂����A���̂قǁA���̌�ɐ��܂ꂽ��l���q��1���l�ɂȂ������Ƃ����܂����B���̐����{�����܂ŁA�ё����݂ł���������ɂ́A�S���t�ɐl���������قǍ��͂����ƌ����A�l���}�����咣�����w�҂����Q���ꂽ���Ƃ��������̂Ƃ͑�Ⴂ�ł��B �@���̈�l���q����Ɋ֘A���āA���̒����̈�l���q�͂ǂ�ȕ��ɍl���Ă���̂ł��傤���B���N26�ɂȂ邠���C�̈�l���q�͎��̂悤�ɘb���Ă���܂����B �@�u��l���q�i�Ɛ��q���j����͒����̏d�v�Ȑ���̈�ł��B���Ƃ��Ɛl�������������ł́A�l����}�����邱�Ƃɂ�苳�������A������ԂȂǎq�ǂ��B�Ɋւ�邷�ׂĂ̂��̂����P���邱�Ƃ��ł��܂��B���̐���̂������ŁA1980�N��ɐ��܂ꂽ�q�ǂ��B�͊m����70�N��ɐ��܂ꂽ�q�ǂ��B�����ǂ������𑗂邱�Ƃ��ł��܂����B����ɋߔN�̒����o�ς̖җ�Ȕ��W�ɂ���āA90�N��ȍ~�ɐ��܂ꂽ�q�ǂ��B�͕����I�ɂ͈ȑO�ɔ�ׂ����ƖL���Ȑ����𑗂��Ă��܂��B�e�B�����ׂĂ̕����]��͂������̎q�ɒ����������Ƃ���̂������ł��܂��B�����̑�s�s�ł͈�l���q�����łɒ蒅�����̂ŁA���͈�l���q�����ʂł��B�����������ɂ͗��ʂ�����A��l���q����ɂ͈����ʂ�����܂��B�Ⴆ�ŋߗ��������㏸�𑱂��Ă��܂����A�e�����������ƒ�̈�l���q�͔ߎS�ł��B�Z�킪����Ώ��Ȃ��Ƃ����̔ߎS�������������Ƃ͂ł���ł��傤�B�܂���l���q����������ߒ��ł͕����I�ɂ͖L���ł����_�I�ɂ͎₵���ʂ�����Ǝv���܂��B��l���q���Ǝ����̍l���◝�z�A�v��Ȃǂ𑊒k�ł��鑊��͐e���F�B�������Ȃ��̂����ʂł����A�q���Ɛe�̊Ԃɂ͕K���ǂ����݂��邵�A�F�B�ɘb���邱�Ƃɂ����肪���邩��ł��B����A�e�Ƃ��Ă͈�l�������Ȃ��̂����炷�ׂĂ̈������̎q�ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���A���̌��ʁA��l���q�̈˗��S�Ƃ킪�܂܂���������A���ꂪ���㒆���̈�l���q�̍ő�̓����ɂȂ��Ă��܂��܂����B�v �@ |
|
|
|
�@ �@�Ⴆ�A����_���o�g�̗F�B�́u�搶���w�A�㌋���i��Ɏq����ŁA�ォ�猋������j�v�Ƃ����̂��ƌ����Ă��܂����B�ޏ��͏\���N�O��17�ł������������ĉœ��肵�q������l����ł��̎q��������x�傫���Ȃ�A������20���炢�ɂȂ��Ă��牽�H��ʊ�Ō����͂����o���ɍs���A���̌�2�l�ڂ̎q���A���߂Ă̂悤�Ȋ�����Đ��̂ŁA�����͕��킸�ɍς����ł��B��̑��ł݂͂�Ȃ��猩�m��œ���͒m��n���Ă��邩��B���悤���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝ��͂����˂��̂ł����A��l�ڂ̎q����������Ȃɑ傫���Ȃ��Ă��邱�Ƃ����A�܂���������Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ����̂������ł��B���̂�����̘_�������x�����Ă����ɂ͔[���ł��Ȃ��̂ł����A�����̔_���ł͂���l���Ɠ��̗Z�ʐ��������Ă���̂ł��傤���B������ɂ�����ɔ_���ł͘V��̕ۏ�邽�߂ɂ��q�����������������Ƃ����`���I�ȍl�����͍������c���Ă��܂��B���������q�ɔ_�Ƃ��p������Ƃ����l���͂��܂�Ȃ��A�������o�҂��ɏo��Ȃǂ��ĉ��Ƃ����Č����āA���������Ăł��q�ǂ��B�ɗǂ�����������A�����͖L���Ȑ����𑗂点�����ƍl����e�B�������Ă��Ă���̂��m���ł��B |
| �@ �@����̑�s��A��C�ł�2004�N�Ɉ�l���q����̊ɘa�[�u��������܂����B�v�w�Ƃ��Ɏ����������g����l���q�ł���ꍇ�A�č������v�w�̏ꍇ�A���q����Q�҂ł���ꍇ�A�v�w�̂����ꂩ����C�s�̔_���ːЂ�L���A�����������ꂩ����l���q�ł���ꍇ��13��ނ̊�̂ǂꂩ������Γ�l�ڂ�ł��悢�Ƃ������e�ł��B���̌��ɍ��w���������̕v�w�����ƁA�x�O�̔_�����ɏZ�ޕv�w�����̒��ɁA���̑[�u�𗘗p���ē�l�ڂ̎q�����~�����Ƃ����l����������Ă��Ă͂��܂����A�S�̓I�Ɍ��āA���ɂ��̑[�u�ɂ���ē�l�ڂ̎q���ޕv�w���}�ɑ����邩�Ƃ����Ƃ����ł�����܂���B��C�ł͂���܂ł̐��蒅���A���ł͌����K����ɓ�����l����90%�ȏオ��l���q���Ƃ������v���o�Ă��܂��B���̂��ߍ��㌋������v�w�͑啔�����ɘa�[�u�̊�ɓK������ƍl�����܂����A���̑[�u�𐧒肷��ۂ̎Q�l�Ƃ��ď�C�s�̎s�X�n�ƍx�O�̔_�����S�̂��疳��ׂɒ��o���ꂽ��2���l��Ώۂɂ��čs��ꂽ�A���P�[�g�����ɂ��A���݂����q���̐��͕v�w��g�����蕽��1.1�l�ɂƂǂ܂�A�q���܂Ȃ��v�w4.48%�A�P�l�����ق����v�w81.7%�A2�l�ق����v�w13.7%�A3�l�ȏ�ق����v�w0.35%�Ƃ������ʂ��o�܂����B1983�N�̒����ň�g�̕v�w�����݂����q�ǂ��̐��̕��ς�2.04�l�ł������̂ɔ�ׂ�ƐS��I�ɏ��q���̌X�������炩�ɂ��������܂��B��l�����ł悢�Ƃ���v�w�̔����ȏオ�A�����₻�̑��q���ɂ������p���S���傫�����Ƃ����̗��R�̕M���ɋ����Ă��邻���ł��B �@�ȏ�̂悤�ȏ���A��C�Ɍ����Č����A������q���̐��͂��܂葝�����A2030�N�ɂ�65�Έȏ�̐l�����S�̂̔����ȏ�ɂȂ�Ƃ������Z��������A���Ȃ��Ƃ�28.8%�ɂ͂Ȃ邾�낤�Ɨ\������Ă��邽�߁A���̂܂ܐi�߂Ύ�N�w�̎Љ�I�o�ϓI���S���傫�Ȗ��ɂȂ邾�낤�ƌ����Ă��܂��B
|
|
�@ |
�@
�@


 �@
�@















