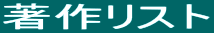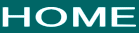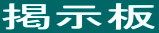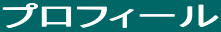月刊エッセイ 10/16/2005
「隠れピアニストの私」
「本岡類の今」にも書きましたが、9月の半ば発作的にキーボードを買ってしまいました。楽器屋の前を通りかかったところ、店舗改装のための大バーゲンで、なんとキーボードが15,000円ナリの価格で売られていたんですね。ちょうどピアノが登場する小説を書いていたところだったので、キーボードを練習すれば、ピアノを習う人間の気持が少しはわかるのではないかと、財布を取り出してしまったのです。
なにせ値段が値段だけに、本格的なピアノとは違っている部分も少なくありません。ペダルがないことは仕方ないにしても、強弱の機能がついていない。つまり、強く叩いても弱く押しても同じ音が出るわけで、早い話がフォルテシモもピアニシモもまったく区別できないのです。
しかし、そんな至らない点があったとしても、ちゃんと音は出ます(当たり前か)し、5オクターブもカバーできる。ボタンひとつでリズムも刻んでくれるし、やはり切り替えボタンを押せば、ピアノからハープシコード、サックスの音にまで変化してくれる。当然、ヘッドホンをつければ、まわりの人に迷惑をかけずに練習ができます。
えっ、これで15,000円だって? テニスのラケットの半分くらいの値段で、機能満載の楽器が買えてしまうのですよ。だいたい、ラケットなんてボールを叩くだけしかできない、つまりは布団叩きハエ叩きも同然の道具なのに、ガット込みで30,000円に近い値段で売られてる。日本における物の値段が、よくわからなくなりました。
で、さっそくキーボードを弾こうとしたのですが、そこで、はたと、私はまったくピアノが弾けない、いいや、楽器のことも楽譜のことも何にもわかっていないのに気づきました。
こうなったら、大きな書店に飛んでいくしかない。探し出しましたよ、「誰でもぜったい楽譜が読める!」「お父さんのためのピアノ教室」という 2冊の超入門書。ほんとうは「ベートーヴェン・ピアノソナタ集」なんてのを見栄はって買いたかったんだけど、それは猫に「資本論」や「ヘーゲル哲学」を買うのと同じ行為になります。しかし、レジに持っていくのが恥ずかしかった。ヘア・ヌード写真集を買ったりする時のように、上に世界経済の本でも乗せればよかったんですが、不幸にも買いたい本が見当たらない。
〈恥ずかしいこともいろいろ書かなきゃならない作家が、こんなことくらいで恥ずかしがって、どうする〉
己を叱咤して、2冊だけを持ってまいりました。
自宅に戻り、勇躍、2冊の本を参考にしながら、キーボードに向かった。ところが、ここでまた新たな事実が発見されたんですね。
おお、私は音の高い低いが、よくわからない!
むろん、鍵盤の左端と右端のキーを叩いて、どっちが高い音なのかはわかりますよ。でも、誰かに似たような場所にある任意のキーを叩いてもらって、どっちが高いか訊かれると、もう何が何だか……。
聞いただけで一つ一つの音の高さを認識できることを、絶対音感があるというんだそうです。また、いくつかの音同士の高低を認識できることを、相対音感があるというんだそうです(音楽理論の素養のない私が言うんですから、間違っていたら、ごめんなさい)。そして、私には絶対音感はむろんのこと、どうも相対音感すら怪しいことが判明してきたのですよ。
つまりは、楽譜を見て指を動かせば(むろん、たどたどしく)曲が弾けるのですが、耳から聴いて、それをピアノで再現することができない。
腹の立つことに、うちのカミさんは昔ビオラをやっていたせいでしょうか、音感のほうはけっこう良くって、ピアノなど習いもしないのに、楽譜なしでも有名な曲ならメロディーを弾いてしまうんです。そして、
「ああ、これはドか、次はソだから」
と、楽譜を見ながら悪戦苦闘している私をせせら笑うんですね。
練習は遅々として進みません。そのせいか、つい関心が別の方に向く。
けっこう、すごい発見をしたんですよ。「蛍の光」の歌詞を「仰げば尊し」の曲で歌っても、最後まで歌いきることができるんです。逆も可能でして、「仰げば尊し」を「蛍の光」の曲で歌うことができる。
こういうのはけっこうあるみたいで、「ドングリころころ」を「水戸黄門」のテーマソングに乗せて歌うことができるんだそうですね。皆さんも一度、お試しください。
しかし「蛍の光」が「仰げば尊し」で歌えて、「仰げば尊し」が「蛍の光」で歌えるのか。卒業にちなんだ2つの有名曲が入れ替え自由なんて、これはミステリーだなあ。私がまだミステリー作家だったら、小説の材料になるかもしれんなあ。
などなど考えてしまうんだけど、こんなふうに横道に逸れてしまっていては、ますます練習は進みません。
ここまで読み進めてきた方の中には、
〈今まで、ホームページの中でコンサートの話なんかよく書いてきてるんだから、本岡類はかなり音楽通だと思ってたんだが……〉
と疑問に思われる人もおられるかもしれません。
たしかに私は金もないのによくコンサートに行っております。月に 2回くらいのペースでコンサート通いをしていたこともあります。しかも、偉そうに、
「○○はピアノの音を響かせ過ぎて、曲の輪郭がぼやけている。きっと、ペダルの踏み過ぎだな」
「△△はリストやチャイコフスキーはいいけど、ショパンとなると、まるでダメ。ただ、力まかせに弾いているだけで、とくに今日のロ短調ソナタなんて、最後の楽章に壮絶感が出てなきゃいけないのに、そういうのが皆無だったね」
とか、言ったり書いたりしてるのだから、音楽評論家顔負けの理論家だと思われているかもしれません。
ところが、私、音楽理論や楽器の奏法については、まったくわかっておらんのです。この際、白状してしまいます。お代官様、お許しくだせえ、私、音楽を聴くのは好きなんだけど、ただそれだけで、ドもソもミも区別がつかないくらいに無学無知の男だったんですよ。
なぜ音楽的に無知無学な人間が頻繁にコンサート通いをして、挙げ句はキーボードまで買ってしまったのか? 私と音楽のつきあいを子供の頃にさかのぼって、ちょっと聞いてくださいな。
じつは私、子供時代にピアノを習ったことがあるんです。姉が習っていた関係で、うちにはアップライトのピアノがありました。そのため、母親は私にもピアノをやらせようと思ったんですね。で、小学校に入学するや、隣町のピアノ教室まで行かされることになった。
しかし、育ったのが田舎町ですから、男の子でピアノを習ってる子なんて他にいやしません。しかも、周囲には自然が溢れてる。ピアノの前に座って、しんねりむっつり鍵盤を叩いてるより、チョウチョやトンボを追っかけたり、フナやドジョウをとったりするほうが面白いに決まってる。楽譜の中にいるオタマジャクシよりも、池のオタマジャクシのほうに興味が行くのは、男の子として当然のことです。
結局、3カ月、教室に通っただけで、リタイア。以後、家のピアノにも手を触れませんでしたが、田舎の子供にとって、それで何の不都合も生じませんでした。
小学校や中学校では、当然、音楽の授業もありました。でも、今にして思えば、ひどい授業だったなあ。なにせ田舎でしょ(田舎、田舎と連発して、千葉県東金市の皆様には、心外かと思います。でも、当時は、ほんとに田舎だったんですよ)。音楽に必要な情緒性、芸術性なんて、微塵も感じられない授業だった。
たとえば、中学校の時「アロハオエ」という曲を習った。そう、ハワイの曲です。最後のところで、
「アロハオエ、アロハオエ、さらばハワイよ」
という歌詞があるんだけど、生徒の皆さんは情感たっぷりに歌うと思いきや、ぜんぜんそうじゃない。なぜか「オエ」の部分にひどく力を入れ、「オエッ」「オエッ」とやる。これでは、ハワイに惜別の情をこめるどころか、「あこがれのハワイ航路」の船に乗ってみたものの、船酔いになって、乗客全員が「オエッ」「オエッ」と吐いているみたいな感じになってしまいます。
そんなんでも、田舎の学校では許された。なにせ、子供は健康がいちばんという風潮に染まってましたから「元気があって、よろしい」になったんですね。
中学の音楽の先生は、優しそうな感じの女性でした。生徒がどんなふうに歌っても怒ったりはしませんでしたが、時々ひどく悲しそうな顔をしてた。もしかすると、心の中では思ってたのかもしれないな。
「音大で一生懸命、音楽を勉強してきた私が、どうして、こんな田舎のイモみたいな生徒に教えなきゃなんないのかしら。でも、地方公務員だもんね。給料は保障されてるんだもんね。我慢しなきゃね。毎日の授業は、我慢の代金みたいなもんだもんね……」
高校の選択科目は当然、音楽を避け、美術を選びました。
音楽とはまったく縁のない生活を送っていた私でしたが、大学に入って一変したのです。クラシック音楽フリークのA君の下宿で、ピアノ曲のレコードを聴かされたのです。一流のピアニストの演奏を聴いて、びっくりしました。姉が弾いていた「石ころだらけの川原をオフロード車で走る」ようなピアノとは、まったく異次元のものだったのです。こんな素晴らしい世界があったのかと、さっそく生協の売り場に行って、安物のステレオを手にいれました。最初に買ったレコードは、忘れもしない、ヴァン・クライバーンの弾くショパンのピアノ協奏曲でした。それをアパートの一室で繰り返し聴いたんだなあ。
レコードの枚数もしだいに増え、卒業の頃にはいっぱしのクラシック通です。リヒテルが来日した時には、チケットを求めて徹夜で行列し、同じく列にいた音大の女の子と親しくお喋りをしたりして、ま、それなりの満足感を得られていました。
しかるに、出版社に就職して、その満足感を破壊するような出来事が起こったのです。編集部の皆と飲みに行ったところ、宴たけなわの頃、先輩のBさん(男性)が店にあったピアノの前にすわって、ポロンポロンと弾き始めたんです。けっこう上手かった。とたんに女性たちが、うっとりしたような目でBさんを見つめるんですね。
そうです。私は、東海林さだおさんの漫画に描かれる「コンチクショー、コンチクショー」の状態に入ってしまったんです。その時、悟ったんです。小学校1年生の時、ピアノを 3カ月だけ習って放棄したのは、明らかな間違いだった、と。あの時、チョウチョやトンボを追いかける時間を少しだけ割いて、ピアノを習い続けていたら、今頃はどうなっていたんでしょう。絶対に人生変わってた!
だけど、忙しい生活の中では、あらためてピアノを習うなんて難しい。今でこそ、大人の音楽教室なんてのも珍しくはありませんが、私の20代、30代の頃には、大の男がピアノを習う場所も簡単には見つかりません。結果、
〈ああ、私にピアノが弾けたなら……〉
と、まるで西田敏行さんの歌う歌みたいな思いを抱きながら、この歳まで来てしまい、バーゲン品のキーボードと出会ったというわけです。
だから、小説の参考になればという理由ばかりではなく、なんというか、人生を取り戻したい(大げさな)といった思いもあって、楽器に向かっているのですよ。
しかし、音感がひどいのは仕方がないにせよ、もうちょっと指が滑らかに動かんのかなあ。こういうの、他人には見せられんよなあ。なにせ、
「コンサートってのは、評価の定まった大家じゃなくって、若手を聴きに行って、自分の耳で才能を見極めるのも楽しみなんだよ。そうだね、今年だったら、××××なんか素晴らしかったよ。あと5年もすれば、もっともチケットが取りにくいピアニストの1人になっていると、僕は保証するね」
なあんて、偉そうなことを言っているんです。ああ、他人には見せられない。
だから、私は部屋に籠もり、ヘッドホンをつけ、誰にも見られないようにしてキーボードに向かって んです。隠れキリシタンならぬ、隠れピアニスト。それが私の今の姿なのであります。