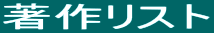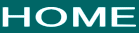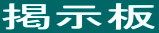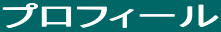月刊エッセイ 9/19/2005
「なんとなく大学、ワセダ」
先日、新作の取材のため、高田馬場の裏通りをうろついてきました。高田馬場といえば、私が通った大学が早稲田でしたから、かつてはよく行った街です。しかし、あれから30年の時がたっていますから、さぞや変わったかと思いきや、そりゃ多少は変わってるけど、雰囲気そのものはたいして変化していない。
〈あい変わらず、せせこましくって、ごちゃごちゃしたところだなあ……〉
というのが、正直な思いでした。
さらに言うならば、大学キャンパスのある早稲田周辺はもっと変わっていない。学生街を散策してみたところ、30年も昔にあった店がほとんどそのまま残っていて、なにか当時にタイムスリップした気分でした。
でも、それって不思議ですね。東京ほど変化が激しい街はない。ベイエリアなんて、別世界に来たのではと錯覚するくらいくらい大きく変わっているし、そこまでいかなくたって、23区内だったら、しばらくご無沙汰すると、どこがどうなのかわからないほど様変わりしている。去年、独身時代に住んでいた学芸大学(東急東横線)の駅前を訪れたところ、自宅のあったマンションは取り壊されているし、周辺は知らない店だらけで、大いに戸惑ったものです。
そんな東京の中で、なぜ早稲田周辺は時の動きから外れてしまったかのように変わらないのだろう?
社会に出てから長い時が流れ、少しは物事を客観的に見られるようになると、早稲田大学がかなり風変わりな学校であることに気づくようにもなりました。
いちばん最初に気づいたのは、ああ、なんて卒業生のまとまりの悪い学校だろうということ。私が入社した出版社のK社には、慶応大学出身者の「三田会」や立教大学の「○○会(すみません、名称を忘れました)」などがあって、盛んに会合を開いていたのです。しかしながら、我がワセダ出身者はろくに集まろうともしない。いや、いちおう「稲門会」というのがあって、社内実力者の副社長が会長を務めていたのですが、会合の通知がまわってきたことがない。編集部にいた早稲田出身の先輩に訊いてみたら、
「あんなのに出る人間、いるのかね」
という返事でありました。群れるのが大嫌いな私は、余計な束縛がなくて助かったと思ったのですが、一方で、なぜ他の大学の出身者とはこんなにも違うのか、最初の疑問を抱いたものです。
早稲田出身者のまとまりの悪さは、あまりにも数が多くて、親近感のようなものが湧かないのだという説が有力です。たとえば、慶応に比べれば1年間に約1.6倍の卒業生が出ている。とくにマスコミの業界では、それこそ石を投げればワセダに当たる。
これが知床理科大学熱帯植物学部や長野大学海洋学部などの出身者が、たまたま東京で出会ったとするなら、懐かしさのあまり、以後は親戚づきあいするに違いありません。独身男女なら、
「この東京砂漠で、わかりあえるのは、きみだけだよ」
とかなんとか言いながら、同棲するか結婚するかしてしまうかもしれません。
しかし、ワセダの場合だったら、相手の出身校が同じ大学だとわかっても特別な感情は何も湧きませんし、ごく稀に、
「いやー、あなたも早稲田ですか。私も、そうなんですよ」
なんて、親しげに近づいてくる者があれば、逆に、
〈だから、どうだってんだよ……〉
と、拒絶感や警戒感を覚えてしまうくらいです。
しかし、ワセダのまとまりの悪さは、卒業生が多過ぎるという理由だけではないような気もします。
「大学創立○○周年事業」とかで、卒業生から寄付を集めようとしても、あまりお金が集まらないと聞きます。卒業生の数では圧倒的に少ない慶応のほうが、お金がどんと集まるんだとか。そういえば、実家のほうに寄付金を要請する手紙がときどき届いているようですが、私なんて封を切ったことがない。友人に訊いてみても、
「えっ、そんな金、出したことないよ」
といった答が返ってくるばかりです。
ワセダには、卒業してしまえば、後がどうなろうか知らん、という薄情者が意外や多いんです。なぜ、なんだろう。
これは、早稲田大学を熱烈に愛して入学した者が少ないからなのかもしれません。
早稲田に入ってくる学生は、大きく3種類に分かれます。「在野精神」とか「早慶戦」とか、早稲田に憧れて受験してくるタイプ。それから、第1志望の国立大学に落ちて、仕方なく滑り止めの早稲田に入学する人間。そして、いちばん多いのが、なんとなく早稲田に入る人間なんですね。
高校時代の成績は、まあまあ良い。でも、国立大学は受験科目が多くて、大変そう。慶応はお金持の子弟が多いから、コンプレックスを抱くかもしれない。早稲田なら就職の時もそう困ることはないだろうから、ま、いいか。そんな思いで入ってくる人が圧倒的多数のような気がします。
そういう、なんとなく早稲田に入った連中が授業に出てみると、どうにも刺激のない、なんとなくな講座ばかり。いや、びっくりしましたねえ、1970年、大学に入って政治学の授業に出てみたら、17世紀イギリスの荘園制度がどうの、丸太小屋からアメリカ大統領が誕生したことがどうのと、そりゃ、政治学にとっては必要ではないと言うつもりではありませんが、教室の外では「安保反対!」とデモ隊が石を投げてるんですよ。少しは現実とリンクした授業をやってもらいたいんですが、そんなものどこ吹く風、ひたすらマイペースで講義は続けられているんです。
今だって、早稲田の先生でマスコミに登場している方は、きわめて少ない。なにもマスコミに登場することが偉いとは申しませんが、早稲田は文科系の大学です。社会にアピールしていかなければならないのに、それができる先生方がほんとうに少数なんですね。
そんなふうに、なんとなくな講義に出席して、前期後期の試験も楽に通してくれるから、なんとなく卒業してるから、「寄付金ください」の手紙が来たって、「そんなもん、知ったこっちゃないよ」という反応になります。
ともあれ、早稲田を卒業しても、あまりメリットはありません。慶応のように「三田会」を通じて、上司と親しくなることもありません。少し前まで、大手銀行のMOF担は東大OBで、やはり東大OBの大蔵省キャリアと親しくなり、自らも出世の階段を登るといったことがあったようですが、ワセダも場合は、そんな余祿は存在しないのです。ウェットな人間関係が苦手な私としては、好ましいことだと思ってはいるのですが……。
繁華街ともファッション街ともビジネス街とも離れた都の西北の一隅に固まって生活していると、浮世の常識から隔絶してしまう部分もあります。
忘れられないのは「学食スシ事件」でした。
回転鮨が普及していなかった当時、江戸前鮨は、早稲田の学生にとって高嶺の花でした。鮨なんて、なにかのお祝いの時に食べるごちそう、それもカウンター席に座るなんてめっそうもないことで、「あんたの食べる分は、ここの内側だけだよ、出ちゃダメだよ」と囲いで仕切られている1人分の桶の中の鮨を食べるのがせいぜい。それゆえ、
「スシ、腹いっぱい食べてから、死にてえ」
という魂の叫びを上げた学友もおりました。
そんなワセダマンたちが、上智大学に遊びにいき、学生食堂をのぞいたことがあります。そうしたら、ショーケースに江戸前鮨があった!
「おう、上智じゃあ、学食にスシがあるんだ。学生がスシを食ってるんだ……」
一同、息を呑みました。わが早稲田の学食や生協食堂で食べられるのは、カレーライスとかラーメンとか、がんばってもメンチカツ定食といった食べ物でした。なのに、ここではスシ。上智の江戸前鮨を賞味してくればよかったのですが、圧倒されてしまって、皆、すごすごと都の西北に引き上げたのを、よく憶えております。
しかし、社会に出てから、他大学の卒業生と話をしてみると、学食で江戸前鮨が食べられる大学は上智だけではなかった。時は高度成長時代も中期にさしかかり、世の中では学生ですら豊かになりつつあったのに、ワセダ村に住む我々はほんとうに世間知らずだったのでした。
豊かではない生活をしている我々の中には、田舎から届く仕送りの前になると、金が尽きて、わずかに残った米をおかゆにした食べたり、パンの耳を齧ったしていた者もおりました。
そんなに金がないのならバイトをすればいいじゃないか、と、おっしゃられるでしょう。チラシ配りとか、日払いのバイトは、当時だって簡単に見つかったのです。でも、やる人は少なかったなあ。バイトやらずに、
「俺は勉学に生きているのだから、バイトなんてやっている暇はない」
とか言って、書物に向かっているのなら、偉いものです。でも、彼らが読んでるのは、どこかから拾ってきた少年マガジンとかビッグコミックだった。漫画読んで、なんとなく仕送りが届くのを待ってる。
ここまでで挙げたのは、30年前の事例です。でも、ワセダ卒業生の後輩と会ったりすると、本質的な部分はあまり変化していない感じがするんですね。卒業後も大学のキャンパスを歩いたことが幾度かありますが、ファッションがどうにもダサい。勉学に勤しんでファッションにお金や気を回す余裕がないというのなら、それはそれで素晴らしいのですが、携帯メールの画面をひたすら眺めたりしているのだから、どうもそうではないみたい。
「電車男」のせいで、ひさびさにオタクが脚光を浴びていますが、オタクっぽいファッションもよく見かけました。そういえば、ゼミの後輩にクイズ研究会の出身がいたり、かつての担当編集者がミステリークラブ(正式名称は違ったかな?)に所属していたり、そうだ、私だっていっとき将棋部に籍を置いていたのだ。
そうそう、ワセダが好きなのは、お喋りなんですよ。議論と呼べば多少はかっこいいけど、実態は、そうたいしたこと話していない。話をして、なんとなく時間を潰す。
卒業から30年以上がたっていますが、いまだにサークル、ゼミ、語学クラスの同期生と時々集まって、話をしております。しかし、話の内容はそう深いものではなく、「よし、勉強会を発足させよう」なんてことには、絶対になりません。中年のオバさんのお喋りと大差はなく、うーん、要はお喋り好きなんだろうな……。
ここまで書いてきたことを読み返してみると、出身校の悪口ばかりを連ねてきてしまったみたいです。うじゃうじゃいる早稲田のOBに読まれて、道で会ったら、殴られるかもしれない。でもなあ、母校を熱烈に愛する人だって、ここ何十年かのワセダに“輝かしい光”がなかったことは、認めるんじゃないかなあ。だから、私はワセダに光が戻るのを願って、あえて苦言を呈しているのですよ(とってつけたような言い訳)。
卒業して30年以上の時がたちますが、いまだワセダ界隈との縁が続いております。
20代。卒業後、就職した会社にバス通勤をしていましたが、都バスの乗り換え停留場が早稲田だったのです。朝まだ眠気抜けておらず、ぼんやりと大学正門前を歩いていて、桜のいちばん下の枝に頭をぶつけたことが何度あったでしょう。
30代。中国語を早稲田の大学院に在学中の中国人留学生に習っていて、週に1度、大学のそばまで通いました。
40代。講師を引き受けた専門学校が高田馬場の近くにあり、これまた週に1度、通うことになった。そして、学生を連れて時々、早稲田の裏にあるオデン屋に行ったりもした。
そして50代。新作の舞台を探していたところ、条件にぴたり合うところが、高田馬場だった。
私とワセダとは、なにか引き合うものがあるのかもしれません。しかしながら、なんとなくなくな大学ワセダの魔力に影響されて、なんとなくな小説を書くことだけは避けなければならないと、これだけは胆に命じております。