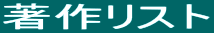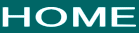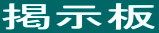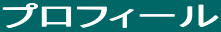月刊エッセイ 7/18/2005
小説の縦糸と横糸について
小説には、縦糸と横糸があります。縦軸と呼んでもよい縦糸は、物語を進行させる役割を担っています。一方、横糸(横軸)は物語を豊かにして、深みや味を出すものであります。
かつてミステリーを書いていた頃(なにか、すごく昔みたいに思えるなあ)には、縦糸作りにエネルギーの70、80パーセントを割いていました。導入部がどうやったらショッキングなものになるのか、トリックはどうするのか、登場人物のキャラクターも際立たせなければならない、当然ストーリーは意外性に富んでいて、最後にどんでん返しが待っている。なにしろ、ミステリーとかSFは読者の想像の上を行く展開が生命線ですので、どの作家も縦糸作りにかなりのエネルギーを費やしています。
しかし、ミステリーやSFの分野とは異なる小説の場合は、横糸の占める割合が大きくなります。ショッキングなシーンから始まって謎がどんどん深まり、最後にはそれが解けるなんていうストーリーで読者をひきつけることができませんから、必然的に〈小説の深さや厚みで勝負!〉となります。私の近著「夏の魔法」にしたって、縦糸は、
「離婚した元妻のもとで育てられ、15年間、会っていなかった息子が、主人公の営む牧場を訪ねてくる。引きこもり同然になっていた息子と父親の12カ月の物語」
と、本のオビに書いてあるとおりのもので、意外性やらどんでん返しなんて成立するわけもないから、もう横糸に力を注ぐしかない。そうですね、ミステリーを書く時の縦糸・横糸のエネルギー比率が「70対30」だとするならば、ノン・ミステリーの場合は逆に「30対70」くらいになっているでしょうか。
さて、その横糸をどうやってこしらえるかですが、それは簡単に言ってしまえば、
「日々の活動から得られるものを材料にして、こしらえる」
ということになります。
縦糸の作り方とは大きく違うんですね。トリックとかストーリーとかの縦糸は、パソコンの前に座っていたって思いつく。喫茶店でも思いつく。昔は、小説雑誌に載せる短編ミステリーのアイデアやトリックなどを考えるため、
〈よーし、思いつくまで、ここから出て来ないぞ〉
と決意を固めて喫茶店に入りました。すると、コーヒー2杯くらい飲むうち、不思議とアイデアが湧くんですね。とくに、外の歩道を行き交う人が見えるスターバックス・コーヒーのカウンター席などが頭を刺激するには、最適の場所でした。たとえば、「住宅展示場の魔女」(集英社文庫)の中に収められている「気持はわかる」は、千葉県は津田沼にあるスタバのカウンター席で道行く若い男女のファッションを30分ばかり眺めている時に浮かんだアイデアであります。
ところが、パソコンの前に座ろうが、スタバでコーヒーをがぶ飲みしようが、横糸のほうは浮かんでこない。しばらくの間、興味のある分野に首を突っ込む機会を失していると、とたんに何も浮かばなくなる。面倒くさいなと、初対面の人間に会うことをサボっていると、人の見方が平板になってくる。
つまり、範囲が広い試験に臨むのといっしょで、一夜漬けがきかないんです。
では、どんなものが横糸の材料になるかというと、小説なんか意識せずに日常生活で出会った出来事に、あーだのこーだの思いを揺らすこと。それらが材料になります。で、今回は最近、体験して思ったことをアトランダムに書き記してみます。
7月の上旬、大学時代の友人とビールを飲みました。その席で、サラリーマンをしている友人の口から「人生設計」なる言葉が出てきました。会社の状況が厳しくなって、当初、描いていた人生設計に変更を余儀なくされたと言うんですね。その言葉を聞いて、
〈へえ、人って、人生設計をして生きてるんだ……〉
と、新鮮な驚きを感じたのでした。
フリーランサーを長くやっていると、知り合う人もやはりフリーの人間が多くなります。そういう人たちは独身者も多いし、結婚していても子供のいない夫婦も珍しくはありません。そして、明確な「人生設計」も持っていないのが普通です(たぶん)。だいたい、定給もないフリーランサーに、人生設計を立てろといっても無理なんですよ。かく言う私だって、
〈人生、なるようにしか、ならんもんな……〉
と、思ってる。上手く本が売れれば印税生活だけど、下手をするとホームレスになることも、心の奥では覚悟している。
だから、給与生活をし、定年もきちんと決まっているサラリーマンの友人にたまに会ったりすると、新鮮な驚きを感じたりするのです。
そういえば、「人生設計」という言葉は使わないまでも、サラリーマンの友人・知人から、
「そろそろ家を建てなければ、ローンを払い終えることができなくなる」
「結婚したのが遅かったからさ、俺が定年になる時、まだ子供は高校生なんだよ」
なんてセリフは幾度も聞いたことがある。定期収入を得て、しっかり家庭を作り、マイホームを確保してあるカタギの衆は、きちんと人生設計をして己を律してるんだろうな。
幾度も脱サラを考えたが、家族を養うことへの不安で、とうとう会社を辞める決心がつかなかったという年配の方から、質問を受けたことがあります。フリーの生活を営んでいる人は、家族を養えるのか心配じゃないか、と。
私は、こう答えました。
「家族を養うことは大切かもしれませんが、それを優先順位の一番にしていては、いつまでたっても脱サラしてフリーになるなんてできませんよ」
その男性は目をパチクリさせてました。きっと、男たるべきもの、何をさておいても家族を養わなければならないと、常々思ってたんでしょうね。
人間、ある固定観念にとらわれていると、他の人も皆、同じ考えだという錯覚に陥ってしまう。そうなんだ。世の中の大多数は、人生設計しながら日々を送っているんだ。
5月末のある夜、エリック・ハイドシェックのコンサートを聴きに行きました。ハイドシェックはフランス人で、自由奔放な演奏をすることで知られたベテランのピアニストです。
その夜は「レクチャー・コンサート」と銘打たれて、ピアニスト自身のトークもまじえた、ちょっと変わった演奏会でした。そして、演奏も素晴らしかったのでしたが、それ以上に興味深かったのは、ハイドシェックのファッションと色気とでありました。
彼がその日、着用してきたのは、よくコンサートで着るタキシードではありません。黒い細身のズボンに焦げ茶のシャツ、そして、ネクタイの代わりに赤っぽいスカーフを締め、自分の星座だという獅子のペンダントをぶら下げています。そうした服装が、端正な顔と銀色の髪に恐ろしいほど似合って、強烈なフェロモンみたいなものを発散していたのです。
私は同性愛者でもないし、またハイドシェックは70歳に近い老人です。なのに、フランス語を喋る彼から強烈な男の色気を感じてしまったのです。
最近、中年男向けのファッション雑誌が売れていたりして、中年男性のお洒落が話題になっています。男のフェロモンを発散させる中年男を「エロいおやじ」とか呼ぶんだそうで(「エロい」が褒め言葉だとは知らなかった!)、街中でも上から下までラテンぽくまとめた服を着ている男性に会ったりします。
でもねえ、ほとんどの人があまりかっこよくないんだよなあ。男のエロス、大人のエロスを感じさせるというより、単にファッションだけが歩いているような人もいれば、なんとなく薄汚さを感じさせる人もいる。ハイドシェックの足元にも及ばないんだなあ。
とはいっても、ハイドシェックの真似をしても、どうにもならんだろうな。私がネクタイの代りにスカーフを締めたら、
「スカーフじゃなく、タオルでも首から下げたほうが似合うぞ」
と言われかねないし、星座にちなんだペンダントよりも、日本人だったら、やっぱ干支かねえ。私はうさぎ年だから、うさぎのペンダントして(おお、ミッフィー!)街を歩いたりすれば、これはコミックの世界であります。
男の色気とかいうのは(女もそうだろうけど)、やはり体の中から滲み出してくるものではないでしょうか。そして、ファッションは、体から滲みだしたものに、よりはっきりした形を与えるもの。バカンスを1カ月以上もとり、いくつもの恋を経験し、人生を楽しんだラテン民族にしか、大人の色気というのは産まれないのかしらん。
コンサートからの帰り、常磐線の電車に乗ったら、疲れた顔のオトーさんでいっぱいでした。酔った人も多くて、車内はファッショナブルのかけらもない世界でした。
いいや、男性ばかりではありません。女性たちの間で最近、セレブ・ジーンズとかいうのが流行っているそうです。アメリカあたりのセレブが着ているんだとかで、ステッチの糸の色を少し変えたものが2万円ほどで売られている。そうしたジーンズに、派手めのベルトをした女性が電車の中でも目立ちました。でもなあ、ジーンズに2万も出して、どうするんだろうか。それに、セレブなはずの女性が群をなして通勤電車の吊り革につかまってるってのもなあ。
日本人は高価な服を買うより、生活のほうを考え直したほうが、エロくて、セレブな民族になれるような気がするのですが……。
7月中旬の日曜日、地元で市主催の“シニアになる方々へのオリエンテーション”みたいな集まりが開かれました。私も次回作の取材のため、その集まりに足を運んだのですが、用意された椅子が足りなくなるほどの大盛況でした。高齢化社会を迎え、第二の人生をどう送るべきか模索している人々が多いというわけなんでしょうね。
かく言う私も、平日に行われている主婦やシニアのテニス・サークルに混ぜてもらっています。そこで気づいたのは、会員は大きく二つのタイプに分かれるということ。一つは、シニアだから無理をせず、ま、適当にやろうよ、というタイプ。そして、もう一つは、若い人ほど強いボールは打てないけど、やれるだけのことはやろうよ、というタイプ。当然、前者が圧倒的多数ですので、練習やゲームは、「テニス」というよりも「ラケット健康法」という色合いを帯びてきます。
スポーツばかりでなく、他の分野でも似たようなものです。
私の住む我孫子市には図書館が併設された巨大な公民館があって、時々、市内の美術や写真団体の展覧会が開かれています。私も図書館に行くついでに、壁に並んでいる作品を見たりするのですが、うーん、これが……。
どれも作品からエネルギーが感じられないのです。絵は、それなりに上手く描かれています。写真だって、今はカメラの性能が上がっているから、きれいに撮れている。だけど、見る人の心を動かさない。
アマチュアやシニア・アマチュアの作品ですので、プロ並みの出来上がりを期待するのは酷というものです。でも、技術的には劣っても、なにか気迫というか強いエネルギーというか、そんなものを発散している作品に出会ってみたい。
「プロは10枚描けば、どれも水準以上に仕上げる。私はアマチュアだから、そうはいかないけど、10作に1作くらいはプロ以上のものを描いてやる」
と、そんな意気込みで作品作りに励む人はいないのでしょうか。
スポーツをやっている人、作品を展示している人の個人個人を攻撃するつもりは毛頭ありません。「良い趣味をお持ちですね」と、心からそう申し上げます。でも、どれもこれも「あーあ」と溜め息が出るような作品ばかりを目の当たりにしていると、しだいに気持が暗くなってきます。
アマチュアやシニアの活動を支援するのは、大切なことだと思います。でも、
「シニアだから、こんな程度でいいよ」
と、弛めてしまうと、どこまで崩れていくかわからない。そんな恐さをこの頃、感じたりもしているのです。
最近、出会ったことについて、あーだのこーだの書いてみました。いや、実際には、ここに書いた何倍も、あーだのこーだの思うのです。そして、そのあーだのこーだのが、時間を置くと、小説の横糸へと変貌をとげていくのです。ですから、
「今、活動しとかなきゃ、将来、困る」
と、あっちこちに出かけるですが、真実を知らない人からは、
「あ、また仕事さぼって遊んでる」
そういった非難の声も飛ぶんでありまして、はい、残念と言うしかありません。