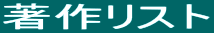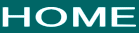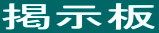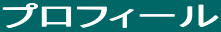月刊エッセイ 11/18/2004
■ 吾輩は“家なき子”である
てなタイトルをつけてしまいましたが、なにも私がホームレスになったわけではありません。なんと申しましょうか、世の中にはマイホームを取得するのに不向きな人間がいるということを、ちょっと書いてみたいんです。
私は18歳で実家を出てからというもの、この歳になるまで、ずーっと借家住まいで、現実問題としてマイホームを持とうと考えたりしたことは1度もありません。現在、2階建て4棟がつながっていて庭と駐車場がついた、いわゆるタウンハウスと呼ばれるところに住んでいますが、私の家を除く3軒が去年の暮れから今年にかけてマイホームを買い、相次いで引っ越してしまったんですね。
私の住む我孫子市(千葉県北西部)では、ここ1、2年、時ならぬ住宅開発ブームが起こっております。バブルの頃、相続税を現金で払わず、物納した物件が溜まりに溜まって、財務省がいっせい払い下げを敢行。安い値段で広い土地を仕入れた不動産業者が40坪くらいに切りわけて、土地やら建売住宅としてあちこちで売りに出しているんです。お隣さんたちも、そうした物件を購入したみたいですが、ご近所がみんな家を買って出て行ってしまうという現実を目のあたりにすると、
〈やっぱり、日本人というのは、マイホームを欲しがる民族なんだなあ〉
と、あらためて感じ入ってしまいます。
実際、私の友人だって、サラリーマン、公務員、弁護士、医師といった実業についた人間は、ほとんどがマイホームを取得し、中年を過ぎると、持ち家を所有するのが“日本の常識”といった雰囲気を作り出しているんですね。ところが、目をフリーランサー方面の友人に向けると、借家派がゴロゴロしていて、家を持っている方にしても「実家に住んでる」「親がもう1軒、家を持っていて、そこに転がりこんだ」「たまたまお金が入ってきたから」とか、なんとなく持っちゃったような人が目立ちます。実業に就いた人と、虚業(?)に就いた人とでは、家に対する熱意がびっくりするほどに違う。で、虚業派の1人である私が“日本の常識”に対する異論などを述べ立ててみたいと思います。
「家を借りてて家賃を払ってても、結局は自分の物にならないわけでしょ。だったら、マイホームのローンを借りて、それを返していけば、最終的には家が自分の物になるから、そっちのほうが絶対トクじゃん」
ああ、もう、幾度この言葉を聞いたことでしょう。これぞ、日本の多数派の意見。ごもっともでございます。おっしゃるとおりですよ。私だって、今まで払い続けてきた家賃を合算すれば、小さな家の1軒くらい建ったでしょう。
正論です。でも、その言葉を聞くと、人生、そういった計算ばかりでいいんだろうか、という疑問というか、なんか淋しい気分になってくるんです。ええ、「結婚するなら、やはり生活の安定してる人よね」とか「彼女にするんなら、美人のほうが自慢できるよな。たとえばスッチーとかさ」といった言葉を聞いた時と同じような……。
買ったら買ったでデメリットというものも、かなりあると思うんです。その1つが、そう簡単には転売して他の土地を移るというわけにはいかないこと。以前、日本企業の現地法人のバイス・プレジデントとしてアメリカに赴任、ピッツバークに住んでいた友人が、
「こっちでは住宅の値段が安定してるから、赴任中に家を買って、日本に帰る時にまた売ればいいという選択が気軽にできるんだよな」
と言っておりましたが、日本ではそうはいきません。値上がりして大儲けするケースもあれば、逆に土地バブルがはじけて売るに売れないというケースも珍しくありません。ダイオキシンの濃度が高いなどと報道された町では買い手もなかなかつかないでしょうし、今年の洪水や地震で、川沿いや活断層の上に乗っかってる土地は値段を下げても買い手は簡単には現れないでしょう。
つまり、買ったら最後、そこに住み続けるんだと、ある程度の覚悟は決める必要がある。でも、住んでみて、隣近所みんなが「ローズマリーの赤ちゃん」に出てくるような悪魔信仰にはまりこんでいる人たちだとわかったら、どうすればいいんでしょう。そこまでいかなくたって、どうも相性の悪いお隣さんとの間がこじれて、傷害だ殺人だって悲劇にまでエスカレートしたという事件は、新聞記事の中でよく見ます。
若い頃は、ほんとにお気楽に引越しをしておりました。杉並区の荻窪に引越した時は「西荻や吉祥寺の変わった喫茶店やバーで時を過ごしたい」というのが動機でしたし、目黒区の学芸大学に移った時は「自由が丘で女子大生をナンパできたらいいな」という軽薄なものでありましたが、ともあれ、新しい街に住んだ時は気分がけっこうハイになっておりました。
私の好きなテレビCMのコピーに、以前、三井のリハウスが流していたものがあります。うろ覚えですので細部は違っているでしょうが、たしか「人は生まれ変わる代りに、住み替えをするんだろうか」といったようなものだったと思います。
三井のリハウスは持ち家の住み替えですが、借家だったら、住み替えはずーっと簡単です。かりにあなたが都内に家を借りていて、なにか鬱っぽい気分が続いていたとしたら、どうしたらいいでしょう。答は、湘南に住み替えてしまうこと。茅ヶ崎あたりで水着の女の子の気になる腰つきを観察し、ホテル・パシフィックでランチして、地震のあとは津波見物をして、なぜかまわりの人に「今、何時」と訊いて、あたりかまわず「四六時中も好きだと言って」と言いたてれば、気分はもうサザン・オールスターズ。鬱病なんて吹っ飛んでしまいます。
気分転換のため奥さんや旦那さんを次々に取り替えることは、それはそれで楽しいでしょうが、簡単にはいきません。その点、住み替えだったら、明日にだってできる、ええ、そうなんですよ。
「2軒先のAさんとこの息子さんはね、まだ20代だってのに家を建てたんですよ。若いのに、偉いねえ」
じつはこれ、髪を切ってもらっている最中に、床屋のオバさんから聞かされた言葉なんです。Aさんが誰なのかは私は知らないのですが、お喋り好きのオバさんはそんなことにおかまいなしに喋り続けます。私の年格好から見て、このお客さんも家持ちの人と思い込んでのことでしょうね、20代で家を買う偉さを次々に語ってゆきます。“家なき子”としてはあまり面白くない話でしたが、椅子に縛りつけられ状態の私としては聞くよりありません。ほんとうは、
「20代で家を買うってことは、それだけ苦労を早く背負い込み、動きが取れなくなるってことです。気軽に引越しもできないし、この不況で残業も減って給料も減らされ、住宅ローンの重荷で鬱病になり、あげくは常磐線の電車に飛び込むかもしれませんよ」
とでも言ってやりたかったのですが、背後にいる相手はハサミやカミソリを持っている身、刺激をしては危険だと判断し、黙っておりました。
男子たるもの家を持って初めて一人前、といった考えは、昔からあるみたいですね。
以前、船橋市前原東というところに一戸建ての家を借りて住んでいましたが、そこでは、持ち家の人しか自治会に入れず、それ以外は“準会員”という身分でした。でも、“準会員”だと会費が半額でいいので、私などは半人前扱いされて大喜びでした。しかし、プライドを傷つけられた人もいるんだろうな。
いいや、そのくらいのことで驚いてはいけません。ちょっと田舎にいけば、持ち家でない人については
「あの人たちは、流れ者だから」
と陰で囁かれる地方もあるんだとか。でも、すごいねえ、「流れ者」ですよ、まるで日活映画の小林旭の世界(ちょっと、古いか)じゃありませんか。ギターかついで、馬にでも乗って、街中を流そうかしらん。駐車場には馬を繋いだりしてね。
横並び社会の日本では、そうした精神的圧迫に耐えられず、「俺は一人前だ」とばかり、家を買ってしまう人も少なくないようです(じつは、うちの両親もそうだったみたいです)。でも、フリーランサーは平気。日頃から、
「会社にお勤めでないのでしたら、手前どものカードをお作りすることは、ちょっと難しいかもしれません」
などという差別を受け、もう冷たい目には慣れっこになっていますので、「流れ者」だろうが「浮草」だろうが、何を陰で言われても動じたりはいたしません。
「僕ねえ、来年40歳なんです。今、買わなきゃ、家、買うことができないんですよ」
以前、つきあいのあった編集者のB君がマイホームを取得した時に言ったセリフです。
たしかにサラリーマンの方は、定年と住宅ローンの返済期間という問題を考えなければならないようです。40歳で25年のローンを借りれば、60歳の定年の時に退職金で残金を全額返済できるとか、ね。私の友人でも、サラリーマンになった人たちは、40歳前後の年齢で、スズメの群が電線から飛び立つみたいな勢いで、皆さん、マイホーム所有という空に飛び立っていきました。
でもねえ、皆が皆、定年とローン返済の関係から家を買って大丈夫かしらん。B君の勤める出版社は中規模。この出版不況の影響を、もっとも受けやすい規模の会社です。ずっと会っていないんだけど、最近その出版社の新聞広告を見ることが少なくなっていて、まったく余計なことでしょうが、B君のことを心配したりもしておるんです。
そういった定年とローンの関係を、私はまったく気にしておりません。作家に決まった定年はないからだろうって? 違いますよ。来年の年収がどうなるのかわからない作家に、お金を貸し付けてくれる銀行なんかないからですよ。ローンを借りられるわけもないなら、最初から期待していない。精神衛生に良いわけです。
だから、住宅を買うんなら、長年にわたってベストセラー作家を続けていた方が、
「お、気がついたら、預金通帳に×億円あるじゃないか。都心のマンションと軽井沢の別荘でも買うか」
といった感じで購入するとか、たまたま1作、大売れに売れた作家が、
「どうせ将来また売れない作家に戻るに決まってるんだから、ホームレスにならんよう、今のうちに小さいの買っておこう」
と口の中で呟きながら買うとか、ま、そんな感じになると思います。
色川武大さん(別のペンネーム・阿佐田哲也さん)の奥さんが「宿六 色川武大」というエッセイの中で、住む家について書かれていたと思います。ずっと前に読んだエッセイですので、間違って憶えている個所もあるかと思いますが、その点はお許しを。
で、色川さん、阿佐田哲也のほうで、ずいぶんと収入があったのですが、そのほとんどを競輪などのギャンブルや交遊などで使い果たし、マイホームはなし。将来に不安を感じ、唯一所有していた那須の別荘地に家を建てようかと、その土地を初めて見にいった。ところが、とんでもない山奥で、しかし、そこに住むしかないかと覚悟を決めた次の瞬間、2人とも自動車の運転免許証を持っていなかったことに気づき、愕然とする−−。
阿佐田さんといえば、「麻雀放浪記」シリーズで、とてつもない額の印税が入ってきたはずですが、計画性はまるでなかったみたいですね。
最近の若い作家の方々については、ベテラン編集者が「最近の若手は酒も呑まない。誘っても断わられるんですよ」とブツクサ言っているように、いわゆる無頼派、破滅派という人種はほとんどいなくなったようですが、預金通帳を睨んだり、株式新聞を読んだりして蓄財に励んでいる人はいないんじゃないかと思います(たぶん)。
まあ、そんなこんなで、私が将来、家を買うとすれば、何かのはずみで大ベストセラーが出てしまい、
「持ってても無駄づかいするだけだから、買っちゃうか」
というノリで買うことしか、可能性としてはないでしょうね。
しかし、そうだとしても「我孫子は意外に良い場所だから、ここにするか」と思った次の日には「温暖化するから、涼しいところのほうがいい。八ヶ岳の麓ならテニスもできるし」と変わり、さらに翌日には「のどや気管支が弱いから寒いところはダメだな。それなら伊豆半島か」などと日和ってしまうという有り様。かみさんにしても「都内のほうがコンサートや芝居が見れて便利だから、絶対に都内」と言ったそばから「でも、生活に困った野良猫のためのシェルターを作りたいから、田舎の広い場所じゃなけりゃ」と言い出し、支離滅裂です。
「分譲地売り出し」のノボリの立ったテントで、不動産業者と顔を突き合わせて話をしている人々を見ると、ああでなくてはマイホームの取得はできないかと思ってしまいます。私んとこは真剣さが足りない。アリとキリギリスの、まさにキリギリスのほうです。そして、心の中で、
「キリギリスとして生れた者はアリの生活を真似しても、しょせんは上手くいかない。キリギリスとして生きるしかないんだ」
と居直ったりするのです。