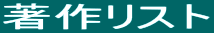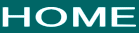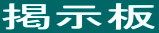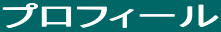月刊エッセイ 10/16/2004
■ ひねくれ者のスポーツ考現学(その2)
イチロー選手も大リーグの年間最多安打記録を達成したし、サッカーでも日本がオマーンを破って、ワールドカップのアジア最終予選に進出することが決まり、今はほっとしたような、しかし、気が抜けたような日々を送っております。
残り3試合で1本ヒットを打てばジョージ・シスラーの持つ記録に達するという早朝、私は夢にうなされました。夢の中で私はイチローになっていて、残り1本がどうしても打てない。ここで打てなければ、ファンの期待を裏切ることになる。ああ、どうしよう……目が覚めた私は重っ苦しい胃のあたりを撫でながら、これがプレッシャーってものなんだなと、つくづく感じたものでした。
サッカーのオマーン戦の前も気が気じゃなかった。なにしろ、この戦いに敗れれば、早くもドイツ行きがダメになる可能性大でしたから、もし負けたら、日本のサッカー界はどうなる、ファンはどうやって今後2年間を過ごせばいいのか。悪い想像ばかりが胸に湧いて、試合開始の時、テレビの前で胸の動悸が高まるばかりです。血圧の30や40上がってたろうなあ。
そんな野球やサッカーのことを心配している場合なのか。私は私を、そう叱りたい。
今、心配すべきことは、たくさんあるじゃないですか。次に出す小説は、はたして売れるのか。5年後、いいや、3年後、私は作家をやっていられるのか。出版界は先細りになる一方で、小説の未来も真っ暗じゃないのか。財政赤字は膨らむ一方で、日本は近い将来、破産するんじゃないのか。世界を覆うテロリズムの危険は、どこまで大きくなるのか。温暖化で気候が変わり、台風がいくつも日本を直撃した。これから、どんな温暖化地獄が待ち受けているのか。
冷静に考えれば、重大な問題がいくらでもあるのに、そっちの心配はせずにイチローの安打を案じて、夢にまで見る。私は自分自身をかなり冷静なタイプだと思っているのですが、そんな人間だって、好きなスポーツの前では判断力がかなりおかしくなる。イタリアなんかでは、職も金もないのに、贔屓のサッカーチームを追いかけて、試合についてまわっている男がどっさりといるそうな。そのあたりが、プロスポーツの持つ魅力というか、一種の魔力なのですね。
ところが、ところが、プロスポーツ界の真ん中にいる人間なのに、そういった魔力を理解できない者がたくさんいる。AとBを合併すればCという球団ができて、ファンもついてくる、と、単純に考えている経営者がいる。「現状から見ると、プロ野球は8球団くらいがちょうどいいんでしょうな」と公言する財界人もいたりする。挙げ句の果ては、こんな不合理な世界はない、すぐにでも辞めたいと、戦線からの逃亡を宣言した検察官僚あがりのコミッショナーまで出てきた。
あったりまえでしょ。プロスポーツを支えるのは、法律論や数字のやりくりだけではなく、反合理性、魔力、狂気といったもので、それがあるから、ファンは金と時間を注ぎ込んで球場に押し寄せ、おかげさまで選手たちは木の棒を振り回すだけで億という年収を得ているんです。そんな基本的なこともわからず、オーナーだ、コミッショナーだと偉そうにしてるんだから、冗談じゃないよ、ドン、ドン(机を叩く音です)!
すみません、つい興奮してしまいまして。
日常の常識を否定する反合理性、一種の狂気、魔力といったって、それは高いレベルのプロスポーツの世界に存在するものであって、我々が日頃たしなんでいるアマチュア・スポーツとなると、話は違ってきます。たとえば、今、私が入れ込んでいるテニス。平日の昼間に楽しむシニア・サークルに入っているので、若い、いや、中年の勤め人の姿もなく、男性はリタイアした元サラリーマン、女性は主婦といった構成で、当然のことながら、シャラポアや杉山愛の活躍する世界とは大きく異なります。
まず、ルールとは関係のない“暗黙の了解事項”というのがあるんですね。たとえば、「前後の揺さぶりを多用してはいけない」というもの。
プロのテニスでは、トップスピンの深いボールを打って相手を後方に押し下げたり、逆にネットぎりぎりのドロップショットでポイントを稼ぐという手法がよくとられます。でも、シニアの世界では、それをやると嫌われる。とくに、前のほうに短いボールを打つと、相手は最初から追いかけようともしない。ダッシュするのが嫌みたいなんですね。
レシーブで短いボールを打ったところ、対戦相手のオバさんから、
「最初から取れないようなところに打たないでよ!」
と、大声で叱られてしまいました。
「すみません、私が悪うございました。以後、前のほうには打たないよう気をつけます」
私としては謝るしかありませんでした。ルール違反したわけじゃないのにねえ……。
Iさんという75歳になる最高齢の男性会員の方がいらっしゃいます。私が生れる前からテニスをやっていて、
「戦時中にイモ畑にしてたところを、終戦後、コートに作り変えて、そこで球を打ってたんだ」
と、おっしゃる超大ベテランです。そのIさん、前のほうに打ったボールはまるで拾おうとはしない。横にはまだ動くのですが、前後には2、3歩しか動かず、ゲームの時、短いボールを打つと、
「いやいや、腰が悪くて、ダッシュがきかないんだよねえ」
とか言って、早々と諦めてしまいます。
私としても70代半ばの高齢者を苦しめる気にはなれず、彼氏がとれるところにボールを打つのですが、そうすると、大ベテランの妙技を見せ、素晴らしいスライス・ボールが返ってきて、今度はこちらが打ち返せません。勝つ手段はあるのに、それを使うことはできず、情をかければ、こっちがやられてしまう。どうすれば、いいのか。今、そのジレンマに悩んでおります。
「シニアは健康第一で、怪我をしないよう年相応のボールを打つべきだ」という“暗黙の了解事項”もあります。皆さん、250 グラム程度の軽いラケットを使って、緩いスライスやフラットのボールをポコン、ポコンと打って、楽しんでいます。
しかし、私はそれじゃ満足できない。20代の頃、自分自身は硬式テニスはやっていませんでしたが、テレビでよくプロの試合を観ていました。当時、憧れていたのが、スウェーデンのビヨン・ボルグという男性選手。金色の長髪をヘアバンドでとめ、強いトップスピンのボールを相手陣内に打ち込む姿がかっこよかった。
どうせテニスをやるんだったら、ボルグみたいなプレイをしてみたい。そのためには、ウエスタングリップの握りでトップスピンの球を打てるようにしなければなりません。そこで、コーチにトップスピンの打ち方を教えてくれと頼んだところ、
「あれは、下手すると肘を痛めるから、止めておいたほうがいいよ。シニアは、フラットとスライスだけで充分」
あえなく却下されてしまったのです。
年相応のテニスという部分が気に入りません。年齢にかかわらず、好きなようにプレイするのが、いちばんじゃないですか。それで肘を痛めても自己責任というものですよ。安全第一、その考え方が好きになれません。
こうなったら、本を読んでの自主練習しかありません。300 グラムの重めのラケットに替え、肘を故障しないよう鉄アレイで筋力を鍛え、練習に励みました。おかげで、少しはトップスピンも打てるようになったのですが、試合の時に多用すると、これまた嫌われます。トップスピンの強いボールは打ち返すのが難しいから、相手から〈ほどほどのボールを打ってくれよ〉といわんばかりの目で睨まれます。
テニスは楽しい。でも、シニアの集団でやっていると、それなりのストレスを感ずることも事実なのであります。
今まで軟式テニス(中学生の時)、卓球(予備校の寮で)、スキー(成人してから)と、いろいろなスポーツをしてきましたが、どれもイマイチで上手くはならなかった。でも、長い距離を走ることだけは得意で、中学時代は駅伝の選手でもあったんですよ。
駅伝といっても、まだ子供ですから1区間2キロか3キロを走る程度でしたが、市内中学対抗駅伝では2年生の時から選手に選ばれて、冬の道を走ってたんです。
長距離走が他のスポーツと大きく違うのは、走っている最中に関係のないことを、あーだのこーだの考える点です。テニスでもサッカーでも水泳でも、競技の最中にいろいろ思いを巡らすでしょうが、それはあくまでいかに勝つかということを考えるわけですが、長距離走は違います。
アラン・シリトーの「長距離走者の孤独」という小説があります。映画化されたので、ご存じの方も多いでしょうが、あの中でも、主人公の若者が走っている最中に自分の生きてきた道をあれこれ考えるシーンが出てきます。なにしろ、何十分も、場合によっては1時間、2時間と走るわけですから、レースのことを考えるだけでは時間が余ってしまい、自然いろんなことに思いが向くわけです。
私の場合は、2つのパターンがありました。まず、道路沿いに住む人が「頑張れ、頑張れ」と声援を送ってくる時です。〈ご声援ありがとう〉と、感謝するかと思いきや、じつは違うんだなあ。〈気楽に「頑張れ」なんて言うなよな。声出してるだけのあんたとは違って、こっちは苦しい中、走ってるんだ〉〈おいおい、どてらの懐に手を入れたまま、応援するなって〉なあんばかり思っていたんだから、やはり根性が曲がっているんでしょうか。
田舎道ですから、応援の人が途絶える中、独り走る時も多かった。そんな時は、こたつに入って(駅伝は真冬に行われます)、サイダーを飲むことばかり考えました。
〈なあんで、好きこのんで、こんな苦しいことをしてるんだろ。駅伝やってなければ、今ごろは、こたつの中で猫の頭でも撫でながら、サイダー飲んでるんだろうな。うう、サイダーが飲みたい。ミカンてのも、いいな……〉
頭に浮かんで出るのは、楽して飲み物を飲んだり、食べ物を食べたりしていることばかりでした。
山際淳司さんの傑作に「江夏の21球」という作品があります。日本シリーズで最終回ノーアウト満塁の大ピンチに立たされた江夏豊投手が、どうやって危地を切り抜けたのかが、1球ごとに心理をまじえて描かれた緊迫のノンフィクション書です。では、シドニー五輪のマラソンを舞台にした「高橋Qちゃんの42.195キロ」というものが書かれたとするなら、いかがなものになるでしょうか。きっと、食いしん坊のQちゃんのことです。
「5キロ地点、ハンバーガー屋の看板が見えた。ああ、食べたい。7キロを過ぎると、牧場があって、牛がいた。400 グラムもあるサーロインのステーキ、レースが終わったら、絶対に食べるぞ!」
なんて食べ物のことしか出てこないノンフィクション書になるのではないでしょうか。
誰しも自分と同じだと考えるなって? いいや、誰しも、長い距離を走っている最中は、欲求に忠実なことしか考えていないんじゃないかなあ。
話が横道にそれてしまいました。そんなふうに持久力には自信があった私ですが、自分よりずっと年上の方とテニスの練習をしていると、先に「休憩します」と、音を上げてしまうんですね。サラリーマンをもう何年も前にリタイアした人は、私が休んでいる最中も、ずっとボールを打ち続けている。
長距離走をしていたといっても若い時だけで、大人になってからは机の前に座る生活が続いていたから、こうなったんだろう。そう思っていたのですが、最近、別の解釈もできるんじゃないかと気づいたんです。
サラリーマンを長く続けてきた彼らは、けっして無理をせず、しかし、休みもせずに仕事をやり抜くことが大切だと知り抜いているからではないでしょうか。私みたいに年齢とは不相応に強いボールを打つのだが、すぐに疲れてしまう、つまり、今日は90点だけど、明日は0点というやり方では、勤め人としては失格してしまうことを熟知しているから、70点主義のテニスを続ける?
そういえば、私は去年の12月、練習中に転倒して手首の骨を折り、長期の離脱を余儀なくされました。あの時だって、とれそうもないボールを追いかけて、転んでしまったんです。無理をしなければ、ケガをすることもなかった。
と、するならば、彼らが前にきたボールを追おうとしないのも、長年の知恵から? スポーツにも、その人の人生が反映されるのかもしれませんな……。
いろいろありますが、それでもテニスは楽しい。
今の季節、赤トンボがいくつもネットにとまり、イナゴがコートに飛びこんできたりもします(市営コートは田んぼの真ん中にあるんです)。澄みきった青い空に黄色いボールを放り上げて、サーブを打とうとする時、
〈ああ、生きていてよかった〉
と感ずる、と書くのは、ちょっと大げさな表現でしょうか。