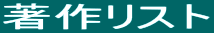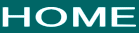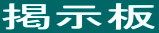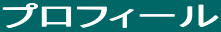月刊エッセイ 9/18/2004
■ ひねくれ者のスポーツ考現学(その1)
気候が良くって好記録が期待できる季節ではなく、なぜクソ暑い真夏に開くのかと疑問を持っていたアテネ五輪でしたが、結局、私もそれなりの時間をテレビの前で費やしてしまいました。時差がかなりあるので、早朝に至るマラソンなどは早々とテレビのスイッチを切りましたが、けっこうライブで見た人も多かったようで、翌日は眠そうな顔をしている人が目立っていた。
そういえば、4年前のシドニー五輪。時差が小さかったため、ライブ映像を観た人は今年よりもずっと多く、同業者の中には、オリンピック中継のほとんどを連日、観戦し、そのため睡眠時間を削って仕事しなければならなくなり、結果、大会終了直後、突然死したという運の悪い方もいらっしゃいました。合掌。
世の中の出来事を斜に構えて見ることの多い私ですが、そんな人間でも、最高レベルでのスポーツには心動かし、さまざまなことを思ってしまうことが、少なからずあります。
たとえば、今回のアテネ五輪でも、まさかあの井上康生選手があんな形で負けるとは想像もしなかった。そういえば、選手宣誓の時、言葉が出てこなくなったりした時から予兆があったんだなあ。勝負の世界でメンタル面がこれほど大きなウェートを占めてるとは想像を超えていた。怪我でろくに練習もできなかった谷亮子選手が優勝するとは、これまた予想してなかった。練習不足で勝てるんなら、練習とくに直前の練習って、やる意味があるんだろうか? まあ、細木数子の予言が当たらなくて、ホッとしたという部分もあったけれど。
浜口京子選手の「金メダルよりも大きな経験をさせてもらいました」とのセリフ。簡単に出てくる言葉じゃないよね。シナリオライターなんかが頭でこしらえたセリフだったら、むしろシラけてしまう言葉です。でも、実際に、確実視されていた金メダルを獲れなかった本人が言っただけに、これは心に響く。男子マラソンで観客に邪魔されて銅メダルに終わってしまったブラジルのデリマ選手。「邪魔をした人間を恨もうとは思わない」「神が私に与えた試練です」と、おそらく、いや、間違いなく本心から言ってました。もし、私が彼の立場だったら、
「競技管理に不手際があった。競技は無効だから、再レースを要求する。いいや、再レースして、もし、3着以内に入れなかったら、えらい損するから、1、2、3位の3人だけの再レースだ。それだったら、どう転んだって銅以上で、損にはならねえ」
息巻いて、そんなことを喚き立てていたでしょう。恥ずかしいねえ。
デリマ選手が立派だと感心した部分もありますが、それより強く感じたのは、キリスト教文化圏、とくにカソリック文化圏での、ものの考え方です。たいていの文明国では絶滅した「他人を恨まず」という考え方をする人が、カソリックの国ブラジルでは、まだ生き残ってるんですね。勉強になりました。
トップ・クラスのアスリートが全力で闘う姿は、観る人の心を大きく動かします。それは、日常ではほとんどくなった極限状態に追い込まれた人の姿の中に、人間の根源みたいなものを見いだすからかもしれません。実際、戦乱や飢餓の国にでも住まない限り、文明国では極限状態なんて滅多になく、私の場合、強い緊張で吐き気まで覚えた体験は、30歳になった頃、中型自動2輪の免許を取りに行き、上手く操れない400 ㏄バイクでS字やクランク・コースを回った時くらいです。情けない……。
しかし、心を揺さぶるのはあくまでも競技者の姿であって、伝える役割のアナウンサーや、見物あるいは応援団にしかすぎない観客が興奮しまくって、「負けるな!」「金メダルだ!」と、半分裏返った声で叫んでいる姿は、私にはとても美しいものとは見えません。アナウンサーも観客も、日頃から闘うための鍛練をしていたわけではないのに、こういう晴れ舞台だけで、興奮とか感動とかを共有しようとするのは、どこか虫の良すぎるような気がするんです。
多くの方は「虫が良かろうとなんだろうと、楽しめればいいじゃない」と言われるかもしれない。だけど、私には引っかかるんだなあ。
これは以前にも書いたことかもしれませんが、高校時代、私の通っていた千葉県のN高校は公立普通校にもかかわらず、野球の強豪校で、夏の甲子園予選の頃になると、級友が「皆で、応援に行こう」「一致団結しなくちゃ」と言い始めるのです。私は思ってることを口に出す性格の人間ですので、
「どうして、野球部や応援部の部員でもない人間が一致団結して応援に行かなきゃならないんだよ。一致団結、必要なし」
と言って、皆からの顰蹙を買ったものです。何も言わず、ただ応援に行かないのが、賢い人間のやることなんでしょうがねえ。
大学に入りました。早稲田大学でした。入学してすぐに、野球の早慶戦がありました。学生運動花盛りの時代でしたが、当時は早慶戦の前になると、キャンパスは野球のことでかなりの盛り上がりを見せていました。で、どんなものかと、私も行ってしまった。
今ふうのチア・ガールこそいませんでしたが、活発な応援でした。応援歌を歌う。チャンスとなれば、「慶応、倒せ!」と大声を上げる。むこうが「陸の王者、慶応」とがなりたてれば、それに合わせて「三田の色魔、テイノー」と罵る。隣の人間と肩を組んで「都のせいほーく」と校歌も歌います。
最初の頃こそ面白がっていたのですが、回が進んで、興奮が盛り上がっていくにつれ、私のほうはシラケてきました。
〈なんで、早稲田だ、慶応だって、興奮してがなりたてなきゃならないんだろう。どっちだって、似たようなもんじゃないか……〉
そうです。ここに集っている学生の中で、「大隈重信の在野精神にあこがれて早稲田に来ました」「文学部の○○先生の授業を受けたいんで、どうしても慶応に入りたかったんです」なんていう、はっきりした考えのもと、入学した人間は、どの程度いるんでしょう。だいたいが、私大受験者は早稲田と慶応はかけもち受験して、受かったほうに行くというのが普通だった。両方受かったら、
「慶応と早稲田の文学部じゃ、きっと慶応のほうが美人が多いだろうな」
「早稲田と慶応の法学部だったら、早稲田のほうが就職しやすいみたいだな」
そんな程度の動機で、早慶を決めていた。第1志望が国立大で、滑り止めに早慶を受けていて、国立に落っこって落胆し、サイコロ振って、早慶のどちらかに決めた人だっていたでしょう。
要は、当人にとっては、どっちだって大きな違いはなかったのです。にもかかわらず、「早稲田!」「慶応!」と、まるで積年の恨みの降り積もった「ロメオとジュリエット」のモンターギュ家とキャプュレット家の争いのみたいにやり合うのですから、しだいにシラケてきて、試合終了を待たずに、私は席を立ってしまいました。
いや、まだ、球場の内部で早稲田だ、慶応だと喚いているのは、まあ、好みの問題ですから、かまやしないでしょう。しかし、試合が終わると、街に繰り出します。早稲田は酔っぱらった学生が新宿・歌舞伎町コマ劇場前の噴水に飛び込むのが慣例となっていた。高田馬場の街でも、酔っぱらった学生がたむろして大声を上げていた。飲み屋のオバちゃんにはありがいイベントだったでしょうが、一般の人には迷惑だっただろうな。
〈楽しむんなら、自分たちだけで楽しみな。町人の方々は関係ないんだからよ〉
そんなふうに思って、友人にも言ったものですから、
「あいつは、ひねくれてる」
と、だんだんスポーツの応援には誘われなくなりました(当然か)。
こういうひねくれ者の私ですが、批判の目はスポーツそのものというより、多くはスポーツを取り巻く人々に向けられていたようです。しかし、そんな私から見ても、近年のオリンピックの競技、これでいいのかと疑問に思える部分が多々出てきております。
その筆頭は、競技の数が多過ぎること。先進国でしか大会が開けなくなるほどにオリンピックが肥大していることはよく言われますが、ほんと、なぜ存在するのか、わけのわからない競技が目立っているような気がします。
まずは、なんといっても競歩です。いいですか、人間が前進するためには「歩く」「走る」の2種類しかないんです(「逆立ちする」「這う」などもありますが、あまり一般的ではありません)。そのうち「歩く」は、ゆっくり進む時のもの。急いでいる時は、当然「走る」。なのに、なのに、ゆっくり進むための「歩く」で速さを競うんですから、これはもう矛盾もいいとこです。しかも、常にどちらかの脚が地面についていなければいけないとか、細かなルールがあって、小姑みたいな審判員がついてチェックしているのですから、なんか解放感がない。そうそう、美しさがないんだ。100 メートル競争にせよ、ハンマー投げにせよ、棒高跳びにせよ、究極をめざす競技の競技者にはフォームに一種の機能美がある。でも、競歩のあの歩き方に美しさがあるでしょうか。競歩をやっている方には申し訳ないんですが、これが正直な思いです。
水泳のバタフライも、わからない。これは私の持論ではなく、誰だったかがどこかで書いていたことですが、私も同感ですので、書くことにします。水泳の泳法には、それぞれ長所があります。速く泳ぐんなら、クロール。音を立てず、静かに泳ぐ(堀を渡って、敵陣に近づく時とか)のなら、平泳ぎ。そして、休み休み長い時間(乗っていた船が沈没した時とかね)、泳ぐんなら背泳ぎです。しかるに、バタフライには、こういった長所がない。すさまじい水しぶきを上げるし、いかにも疲れそうだし、速さではクロールに敵わない。もし、バタフライをオリンピック種目に入れるんなら、犬かきを入れたっておかしくないんじゃないかな。
日本で初めての金メダルを織田幹雄さんがとった三段跳びですが、これもよくわかりません。なんで、ホップ、ステップと、中間で2度も足をつかなきゃならんのでしょうか。走り幅跳びだったら、すっきりしています。どのくらい遠くまで飛べるかですから、これは崖を飛び越えたり、川を飛び越えたりする時に役立つでしょう。でも、どんなに三段跳びが得意だって、役に立ちゃしない。「ホップ!」とか叫んで、足をついたら、川にそのままに落っこったりしてね。ある友人が言いました。
「いやさ、川の中に大きな石か岩があってさ、そこに足をついて、対岸まで渡るのが、この競技の始まりだったんだよ」
すかさず私は反論しました。
「だったら、川の中の石のある個所は固定されてるわけだから、足をつく場所は、最初は4メートル先、次は5メートル先とか、決まってるはずじゃないか。だけど、三段跳びでは、どこに足をついてもいいんだろ。おかしいよ」
納得いく理由は、どうしても見つかりませんでした。
おおよそスポーツというものは、とくに水泳や陸上競技は、それが存在する理由が必要だと思うんです。走る競技は短距離走から障害、マラソンまで存在理由は言うまでもないことですし、槍投げは狩猟、砲丸投げやハンマー投げは戦争に使った武器、高跳びや棒高跳びは障害物を越える時の技術だし、それが現代のスポーツとして残っていたとしても、まったく違和感は感じないんです。でも、競歩みたいなものがあったりすると、かなりの不自然さを覚えてしまう。
こうした不自然さを感じてしまう競技は、他にもいろいろあって、たとえば、射撃。たしかに狙いを定めて、引き金を引くのは人間かもしれないけど、弾を飛ばすエネルギーは火薬から出てるんでしょ。バイクレースや自動車レースと同じで、スポーツはスポーツでもモーター・スポーツに近い存在で、オリンピックに入れるのは不自然な気がするけどねえ。
そんなこんなを思いながら、競技を観ていると、どうにも楽しめなくなることが、多々生じます。他の人々が「やった、金メダルだ!」「オジサン先生が銀メダル獲得!」とか言って、素直に喜んでいるのを見る時、私は損な性格なのかもしれないと、気持が少しだけ暗くなります……。
オリンピックは終わりましたが、スポーツ界の話題には、こと欠きません。プロ野球はどうなるのか、サッカー・ワールドカップのアジア予選を日本は勝ち抜けるのか。いや、そんな高い次元の話だけでなく、私が最近、凝っている中高年テニスには、アホみたいな話が山と転がっています。ああ、それから、信じられないでしょうけど、私は昔、駅伝の選手だったんですよ。そのあたりを、次回、書きたいと思います。