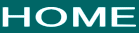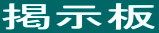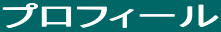�����G�b�Z�C�@�@�@�@�@�@�@8/15/2004
�� �u���悤�Ȃ�A�z�b�g�h�b�O�E�v���X�v
�@�����O�A�V����ǂ�ł�����A�N���u�z�b�g�h�b�O�E�v���X�v�i�u�k�Д��s�j���N���ŋx������Ƃ����L���������܂����B�g�x���h�Ƃ����̂́A�g�s��h���g�I��h�ƌ���������̂Ɠ������A�\�ʏ�̑̍ق��Ƃ���낤�Ƃ������{�Ɠ��̂����ŁA���ۂɂ́u�͂��A���悤�Ȃ�B��x�ƕ�ꂩ���S��܂����v�Ƃ������A�܂�́g�p���h�Ȃ̂ł���܂��B
�u�z�b�g�h�b�O�E�v���X�v�Ƃ����A�u�|�p�C�v���ƕ���ŁA1980�N��̎�ҕ������ے�����悤�ȎG���B�Ƃ��Ɂg�f�[�g�E�}�j���A���h�����蕨�ŁA���݁A30��A40��̒j���̒��ɂ́A���̎G���̌������܂܂ɏ��̎q�Ƃ̃f�[�g�����H�����l�����Ȃ��Ȃ��ł��傤�B���̎G�������I���ƂȂ�̂ł�����A�Ȃɂ�60�N��A70�N��ɗ������ւ��Ă����u���}�p���`�v�����N���O�ɋx���ƂȂ������Ɠ����悤�ȗ҂������o���Ă��܂��܂����B
�@�������A�P�ɗ҂������o���������ł͂���܂���B���́A���A30��̑O���̂R�N�قǁA���̐N���Ń��C�^�[�̎d�������Ă����̂ł��B32�̍ŏo�ŎЂ�ސE�������́A���̑O�̂V�N�Ԃ��I�W��������̏T�����̕ҏW���ʼn߂����Ă������߁A��ҕ����ɑa���Ȃ�A����ł͍�Ɗ��������Ă����̂ɍ��������o�Ă��邾�낤�ƍl���A���傤�ǁu�z�b�h�h�b�N�E�v���X�v�Ɍ�y�̕ҏW�҂������̂��K���A
�u������Ƃ�����ƁA���q�吶���W�Ƃ��f�[�g���W�Ƃ��Ɍ����āA��ނ���点�Ȃ����B���̎q���o�Ă��Ȃ��d���́A�������Ȃ�����ˁv
�@�Ɛ\������āA�߂ł�����ރX�^�b�t�̈���ƂȂ����̂ł��B�~�X�e���[�����M����T��ŁA���C�^�[�Ƃ��Ă̎d�������Č������L�߂�B����́A��Ƃ̊ӂƂ����ׂ��s�ׂł��傤�B�܁A����悭�Γǎ҃��f���̏��q�吶�ƒ��悭�Ȃ��Ă�낤�Ƃ������_���A�N�̖ڂɂ����������ł������ǂˁB
�@�����A�u�T�����������u�z�b�g�h�b�O�E�v���X�v���͂S��ɂP�x���炢�̃y�[�X�Ńf�[�g���W��g�݂܂�������A���̓x���ƂɃf�[�g�E���P�̃f�B���N�^�[���߂���A�f�[�g�E�}�j���A�����������Ƃ����킯�ł��B�Ó�̃h���C�u�E�f�[�g���A�y���V�����̂����܂�f�[�g���ɂ������������A�Ԃ̒��ł̉�b���ǂ�Ȃӂ��ɐi�߂邩�Ȃ�ă}�j���A������������������Ȃ��B
�@���������A�V�N�Ԃ��I�W�T�������G���ɂ��āA��҂ɂ��đa���Ȃ��Ă��܂����l�ԂɁA����ȃ}�j���A����������̂��A�����āH�@�����A��i�Ƃ������̂́A������̂Ȃ̂ł���B
�@���̍L�����̒��ɂ́A�i���p�̖��l�A�f�[�g�̒B�l�Ƃ�����l���A���Ȃ��炸������̂ł��B�܂��́A�����������l�Ԃ�T���o���B�����āA��ނ�����B
�u���Ƃ��A���̏��̎q�Ə��߂Ẵh���C�u�ɍs�����Ƃ��܂���˂��B����Ȏ��A���̎Ԃ͉��n�͂��Ƃ��A�G���W���͂c�n�g�b���Ƃ��A���I�^�N���ۂ��b�����Ă����܂��j��������ł��B�j���m��������A���������̂������낤���ǁA�ׂɔޏ��������Ă��鎞�̓��J�̘b�̓_���Ȃ�ˁv
�u�Ƃ���v
�u���̑O�A���ԓ��m�Ńh���C�u�ɍs�������A����Ȗʔ������Ƃ��������Ƃ��A�o�J�ȗF�B������ȃo�J�Ȃ��Ƃ�������Ƃ��A�ʔ����������̌��k�����Ă���ł��B����ƁA���̎q�̂ق��́A���̐l�Ƃ������Ă���ƁA���b�A�y�������Ƃ��낢�날���A�ƁA������ۂ������āA�����Ɛڋ߂ł���Ƃ����킯�ł��v
�u�Ȃ�قǁv
�@��L�̉�b�̒��Łu�Ƃ���v�u�Ȃ�قǁv�ȂLjӖ��̂Ȃ����Ƃ�ł��Ă���̂��A���Ȃ̂ł���܂��B�������āA�f�[�g�̒B�l���瓾���n�E�c�[��ҏW���Ɏ����ċA���āA�ʔ����ǂ߂�悤�ɂ܂Ƃߒ�������A�O���r�A�ōČ��ʐ^���B���悤�\�����Ă݂���ƁA����Ȃӂ��ɂ��āA���ʍ������Ă�������ł��ˁB
�@�ނ��A���W�L���ɂ��鎞�ɂ́A�֒��������邵�A�킩��₷���ȗ��������邵�A���Ȃ薟����ۂ����e�ɂȂ��Ă��܂������A�c�ƂȂ��Ă�����̂́A�ӊO��A���e�B�ɕx�g��������́h�i���[���Ƃ�����A�z�b�g�h�b�O�E�v���X���̌��t�Â����ɂȂ��Ă��܂����ł����B�C������ׂ��j���肾�����̂ł��B�����łȂ����A�ǎ҂ł����҂̎x�����Ȃ����̂ˁB
�@���������f�[�g���W�𒆐S�ɂ��āA�t�@�b�V�����A�V�F�C�v�A�b�v�ȂǂȂǂ���荬���A80�N��̔��u�z�b�h�h�b�O�E�v���X�v���͔���s���g�b�v�̉��������}�����̂ł��B�v���A���オ�������Ă��ꂽ�B
�@���́g�Ɛg�j���̌��ہh�����������ςɒ�`���Ă݂�A60�N��܂ł́A��������܂ł̓Z�b�N�X�̓_����A�Ƃ�������ł����B��m���Y���珯�i�O�Ɏ���܂ŁA�����̒��ɂ��A�P�{�̐����͂�����ƈ�����Ă����悤�ȋC�����܂��B
�@���ꂪ�A70�N��ɓ��鍠����q�b�s�[������w���^���̐�����A���̂����肪�ɂ��Ȃ��Ă����B�u��������v�u���O���v�Ƃ��������t���}�X�R�~�ɂ��悭�o�ꂷ��悤�ȂɂȂ�܂������A����ł��Z�b�N�X�܂ōs���̂́A������O��ɂ�����ƁA�g�^�ʖڂȁh�������������Ă���j���ɑ��������͂��ł��B
�@�Ƃ��낪�A�L�����p�X����w���^���̋�C��������������A�e�j�X��X�L�[�̃T�[�N���������������悤�ɂȂ���80�N��ł́A�j���̂����������傫���ς�����B���̎q�̂ق����A�����Ȃ�ĊW�Ȃ��A�e�����Ȃ�����Ȃ�Z�b�N�X���n�j��A�ƃV�t�g��傫���`�F���W�����Ă����̂ł��B�N���̒j���z�����������o���Ă��āA�����̃t�F�������ɏo��ƁA���̒��͐��̂��Ƃł����ς��ɂȂ��Ă��܂��j�̎q�������A���̃`�����X�ɂ��ƂȂ������Ă���킯�͂���܂���B�Ȃ�Ƃ��Z�b�N�X���������B���̂��߂ɂ́A�Ȃ�Ƃ����̎q�Ɛe���ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������j�̎q�����́A�����ăf�[�g�E�}�j���A�������߂��̂ł��B
�@����̓o�u�����̒��O�B����A�Ⴂ�l�̊Ԃł́A�����������o�u����Ԃɓ����Ă�����������܂���B�z�C�`���C�E�v���_�N�V�����Ƃ������킯�̂킩��Ȃ��W�c�̏������u���h�u���v�Ȃ�{���x�X�g�Z���[�ɂȂ�����A���������u�����X�L�[�ɘA��Ă��āv�Ȃ�ĉf����������Ȃ��B�z���_�E�v�������[�h�Ȃ邯�����������Ԃ��f�[�g�E�J�[�Ƃ��Ĕ��ꂽ�̂��i�p�������Ȃ���A�������̎Ԃ��Ă��܂��܂����j�A���̍��ł����B
�@�Ⴂ�l�̐e�������L���ł�������A�q���ɂ����Ղ肨��������^�����B�������������炦�Ȃ������āA���̂����o�C�g���R�Ƃ������B�u�z�b�h�h�b�O�E�v���X�v�̃��P�ɂ������āA���]�[�g�E�z�e���܂ŌJ��o������A�s���̃t�����X�����X�ŐH������������ƁA�����ǂ���̃o�u���B���̃f�[�g�E�}�j���A���G�����狳�������j�̎q�������A�������X�g�����ł������g���܂������͂��ł��B���̒j�̎q�������A���͒��N�̃I�g�[����ƂȂ��āA�}�O�h�i���h��g�쉮�Œ��H��H�ׂĂ���̂́A����̔���Ƃ��������Ȃ��̂ł��傤���ǁc�c�B
�@�������A90�N����O�����߂��鍠����A�܂��j�����ێ���͑傫���ω����Ă���͂��ł��B�ŋ߂̎Ⴂ�l�̂��Ƃ͂��܂�悭�m��Ȃ��̂ł����A�ǂ����g���������̐\�����݁h�݂����Ȃ��Ƃ�����l�������悤�ł��ˁB
�u���Ƃ������Ă���Ȃ��H�v
�u����A������v
�@�ĂȊm�F���������邱�Ƃ́A�܂��Ƃɗ�V�������Ƃ�����ł��傤���A���̌�̐i�s�������B�������̊m�F���s����ƁA�قǂȂ����u�z�e���ɍs������A�ޏ����ނ̕����ɂ����܂肵�Ă��܂��B
�@80�N���90�N��̈Ⴂ���ȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B
�@80�N��@�@���ۊJ�n���A�f�[�g���J��Ԃ��Đe���ɂȂ遨�B�Z�b�N�X����
�@90�N��@�@�������m�F�����遨�A�Z�b�N�X����
�@�����b���A80�N��ɂ������A�e���ɂȂ�Ƃ����������A�������Ă��܂��Ă���݂����Ȃ̂ł��B��ԂЂ܂������ɏ��̎q�ƃZ�b�N�X�ł���Ȃ�A�N�������Ǝ��Ԃ��g���āA�f�[�g�Ȃǂ��₵�܂���B
�@�������A����͑�s���ɓ˓��B�e����̏������͊��҂ł����A�o�C�g�̎��������ꂽ���́B���̏�A�P�[�^�C�����̎x�����Ƃ����K�v�o����x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�f�[�g�Ȃɋ��͂������܂���B
�@�ȏ�ɏq�ׂ��悤�ȗ��R�ŁA�f�[�g�E�}�j���A���G�������ނ��}�����͎̂���̂Ȃ���킴���Ǝv���Ă���܂��B�������A���ꂾ���ł��傤���B����Ă��鎞�̎G���Ƃ����̂́A�����Ȗʔ����l�Ԃ��W�܂���̂ŁA�������́u�z�b�h�h�b�O�E�v���X�v�ɂ��A��ɖ��𐬂����l�����������܂����B
�@�ЊO�X�^�b�t�Ƃ��ẮA��ɍ�ƂƂȂ����i�q��������A���͉��y�]�_�ƂƂ��Ċ��Ă��锋����������A�����S���ʼn�ƌ��G�b�Z�C�X�g�Ƃ��Đl�C�����i���V�[�ւ���A���ꂩ��A�ǂ��ł��������݂Ƃ��Ė{���ނ���A�ȂǂȂǁB
�@�Г��ҏW�҂Ƃ��Ă��A��ɑގЂ��ă^�����g�ƂȂ������Ƃ�������������A��Ђ͎��߂Ă��Ȃ����ǁA�e���r�ł悭��������R�c�ܘY����B
�@�����������A�����킢�킢�����Ȃ���A�A�C�f�A���������A���e�������Ă����̂ł�����A�G�����ʔ����Ȃ�Ȃ��͂�������܂���B
�@����́A���̎G����������Ă������������Ǝv���܂��B�Y�N��������̗���ŁA�����o�[���V�h�̈��݉��ɏW�����܂����B�傢�ɐ���オ��A����オ�邤���A�����̉̂��̂����ƂƂȂ�܂����B�Ȃɂ��딋����������̓T�U���E�I�[���X�^�[�Y�̑��n���̃����o�[�ŁA�M�^�[�̖���ł�����A�ނ����[�h���ɂȂ�B�i�q��������͎Ⴂ���A�����L�b�h�u���U�[�X�̈���Ƃ��Đ��E���܂���Ă����G�C�^�[�e�B�i�[�A���Ƃ�������������͂Ƃ����A�|�l�����܂��ܕҏW�҂ɂȂ����悤�Ȑl�ł�����A����͂����v���̉���ł���܂��B
�u�z�b�g�h�b�O�E�v���X�A�A�Y�A�i���o�[�����|�|�v
�@�ƁA�A�h���u�ō�����Ȃ�S���ʼn̂��܂���A���߂́u�g�A�c�A�o�I�i�z�b�h�h�b�O�E�v���X�̓������ł��j�v�ƁA�����G�����u�x�l�b�`�v�ł�����悤�ȐU��t������炩���āA�����A�����̂����ɖ�͍X���Ă������̂ł��B
�@�Ȃ��A����قǑ��m�ρX�̐l�Ԃ��W�܂������Ƃ����ƁA�����u�z�b�g�h�b�O�E�v���X�v�̕ҏW���́A�u�k�Ђ̖{�قł͂Ȃ��A�������ꂽ�ʊقɂ������̂ł��B�{�قƂ͈���āA�R�K���Ă̑e���Ȍ����ŁA�e�������ǁA��q���ڂ����点�Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ЊO�̐l�Ԃ����R�ɏo���肪�ł����̂ł��B����䂦�A�߂��܂ŗ������ɂ́A������Ɗ���Ă����āA��������A�ҏW�҂ɃR�[�q�[����点���肵�Ă�����ł��B�����������R���I�Ȑ��E�����������炱���A�G���̓��e�ɂ����C�������Ă��܂����B
�@�ł��A���͈Ⴂ�܂��B���h�ȍ��w�V�Љ��������āA�ҏW�������̒��ɓ��������ɁA�ЊO�̐l�Ԃ��C�y�ɖK�˂Ă����킯�ɂ��s���Ȃ��Ȃ�܂����B�Ȃɂ���A���������ƁA��t�Ƃ������̊֏�������B�����ŁA�A�|�����邩�ۂ������āA�߂ł��������ɓ��ꂽ�Ƃ��Ă��A�L�^��ɖ��O����������A���ُ����ɕt��������ꂽ��ƁA�₠�A�ʓ|���������ƁB���ꂶ��A�C�y�ɗ������Ȃ�Ă��Ƃ͂ł����A�ЊO�̐l�Ԃ̑��͎��R�Ɖ��̂��Ă��܂��܂��B
�@�����������V�X�e���́A������̏o�ŎЂ͂ǂ��ł����������A�e���r�ǁA�V���Ђƃ}�X�R�~�e�Ђ͎����悤�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��āA�܂��A�e����h������i�����V���_�ˎx�ǂł̎E�l�A�������R�c�̃t���C�f�[�P���ȂǁA���낢�날��܂������j���邽�߂ɂ́A�v�����Ȃ����ƂȂ�ł��傤���A�Љ�ƃ}�X�R�~�Ƃ̕��ʂ��������Ȃ��Ă������ɂ��Ȃ�܂��B�Ƃ��ɎG���ɂ��ẮA�O�̐��E�̕�����������ł��Ȃ����Ƃ��A����s���s�U�̑傫�ȗv���ƂȂ��Ă���悤�ȋC�����Ă���̂ł����B
�@�Ƃ�����A�������ׂĂɂ͎���������܂��̂ŁA�u�z�b�g�h�b�O�E�v���X�v���������ƂȂ����̂��A�����������Ɗ���邵���Ȃ��ł��傤�B
�@�ł��A�������̐V�h�ł̑呛���B����ȂɌ��C�������i�q��������͂S�N�O�A�}�����āA���͂��̐��̐l�ł͂���܂���B�i���V�[�ւ����āA���N�O�A�Ⴍ���ĖS���Ȃ��Ă��܂��B�i�q���{���S��@���Ă����̂��A�܂��ڊW�̗��Ɏc���Ă��āA���̋����̖邪�I���������̉Ẳԉ̂悤�Ɏv����̂́A 8���������߂��悤�Ƃ����G�߂̊����Ȃ̂ł��傤���B