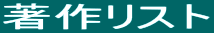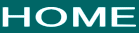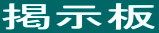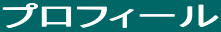月刊エッセイ 6/18/2004
■ 「私は、これを我慢できない」
韓国製のテレビドラマ「冬のソナタ」が、中年女性を中心にして大ヒットしています。私のカミさんも例外ではなく、土曜の夜ともなれば、ビデオをしっかりセットし、暇ができるやテレビの前に座りこんで、忘我の境地に入りこんでおります。
彼女の友人たちも皆同様だとかで、NHKだけでは我慢できず、レンタルビデオ店に走る者、インターネットで字幕付きの原語バージョンを観る者など、見方もさまざまで、寄ると触ると、「ヨン様」の話で持ちきりなんだそうです。おかげで、平日の昼下がり、駅前のイトーヨーカドーで、「ラララー」と、冬ソナのテーマ曲を誰かが口ずさむと、ついつい店内で大合唱が起こってしまうんだそうです(嘘です)。
「こんなに面白いもの、ないよ。勉強のためにも、観なさい」
と命ぜられて、私もインターネット配信のものを観ることになりました。最初のうちは面白かったですよ。画がきれいだったし、俳優もなかなか魅力的だったし、〈ほう、これは、ウケるのも無理ないな〉と思っていたんですけど、いやー、とんでもないことが起こりました。
たしか2回目の終わりの部分だったでしょうか、ペ・ヨンジュン扮する男子高校生が交通事故に遇って、重傷を負い、学校に来なくなります。女性の主人公をはじめとするクラスメートは彼が死んだとばかり思いこみ、これが“悲恋”の発端となるんです。
しかしね、この作り方はあんまりじゃありませんか。級友が交通事故に遭ったと聞けば、警察に問い合わせて、生きているのか死んだのか、確かめるのが普通じゃありませんか。いや、わざわざ警察に問い合わせるまでもありません。自分のところの生徒が事故に遭って、登校しなくなったのなら、学校当局だって、事実を確かめているでしょう。先生に、ちょっと訊けばいいんです。小学校低学年だったらともかく、高校生が、それもクラス全員、こんな程度のことできないなんて、信じらんなーい!
いくらなんでも、あんまりだと、私が抗議すると、カミさんは、平然として、
「じゃなけりゃ、ストーリーが成り立たないでしょ」
と言うのです。そのとおりです。男子高校生は事故で記憶喪失となって、アメリカにに渡る。そして、何年か後、記憶喪失のまま、なぜか女主人公の前に現れます。すでに婚約者のいる彼女は、亡くなった恋人の面影を強く残す男性に心惹かれ、それから三角関係の恋愛が繰り広げられるんです。たしかに、カン・ジュンサン(男子高校生の名前です)が死んだことになっていなけりゃ、このストーリーは成立しないんだよなあ……。
ストリーリーを成立させるため、筋が不自然になることは、ドラマでも小説でも珍しいことではありません。とくに、ミステリーは謎解きやトリックを効果的に見せるため、不自然な部分に目をつぶることも珍しくないジャンルです。
デビューして間もない頃、フェリーの中で人を殺し、死体を移動させるトリックを考え出して、小説に仕上げたこと(『南海航路殺人事件』です)があります。けっこう、よくできたトリックだと思ったのですが、その小説を読んだ某編集者が、
「なんで、こんなまどろっこしい殺人をやるんだろう。被害者をデッキに誘い出して、海に突き落とせば、当然、転落死として処理されるじゃないのかなあ。そっちのほうが楽だし、安全でしょう」
なあんて言いおった。そりゃ、そうですよ。だけどね、それじゃあ、ミステリーにならないの! トリック・ミステリーにするためには、あそこで被害者を単純に海に放りこむわけにはいかなかったの!
自らも不自然な展開の作品を作っている私ですが、それなりに許容限界の基準というものも作っております。不自然であるかもしれないが、まったくあり得ないことではない。それが、私が許容している基準なのであります。
でもねえ、冬ソナの場合は、私の基準を越えてしまっている。不自然な上、あり得ない展開になっているので、それ以上は観る気分になれず、第2話でリタイアすることになりました。以後も、時々、カミさんが冬ソナ拝観しているのを、横から観たりもしているのですが、〈なんで、こうなっちゃうの〉という場面が多々あって、思わず溜め息を漏らしてしまったりします。
伝え聞くところによると、韓国のドラマというのは、視聴者の意向にひどく敏感で、意向に沿った形でシナリオもどんどん書き変えていくんだとか。日本でも確かありましたよね、読者アンケートかなにかによって、筋立てが変わっていってしまう小説が。でも、そういうの、ドラマとか小説とか呼んでいいものでしょうか。作品というよりも、なにか妄想実現といったもののような気がするんだけど。
最近のアダルト・ビデオというのは、よく知りませんが、私が若かった頃にはロマンポルノというものがありました。下宿屋の女主人がなぜか色気たっぷりの未亡人で学生さんすっかりイイ思いをさせてもらったり、米を配達に行った先の美人の奥さんがなぜかひどい欲求不満状態だったり、なぜかセーラー服だったり、なぜか看護婦さんの服を着ていたり、なぜかスチュワーデスだったり(そんなにたくさんは観ていませんよ、あくまでも、つきあいでした)、若い男性の欲求、欲望、劣情、妄想をひたすら真面目に追求し、実現させた映画でありました。
で、読者の意向にただただ従った作品というのは、ロマンポルノに限りなく近いんじゃないかなあという気がしましてね。冬ソナも、そういった傾向のもので、恋愛ドラマというより“恋愛妄想実現バーチャル・リアリティ”と呼ぶ方がふさわしく ―― いやいや、もう止めておきましょう。街には「ヨン様、命」とマジックインキで腕に書き込みをしている主婦が多数いると聞きます。冬ソナの悪口とでも取られそうなことを書くと、どこで仕返しを受けるかわかったものじゃありません。
いや、いいんですよ。ペ・ヨンジュン様、素敵ですよねえ。冬ソナ、どんどん観てください。
我慢できないというと、ストーリーばかりでなく、言葉の読み方や意味にひどく厳密な人もいます。もう7、8年も前になりますか、『奥羽路 7冠王の殺人』というミステリーを出したことがあります。その際、私は「7冠王」を「ななかんおう」と読むものとばかり思っていましたが、「いや、違う。正しい日本語としては、『しちかんおう』と読むべきものだ」と力説した方がいらっしゃいました。詳しいことは忘れましたが、文法的に「ななかん」ではなく「しちかん」でなければ、おかしいんだとか。私としては、「ななかん」だって「しちかん」だって、漢字にすれば同じで、通じればいいんじゃないの、てな程度にしか考えていなかったんだけど……。
言葉を用いるプロとしては、かなり問題があるとは思いますが、日本語の正しい読み方とか、厳密なまでの意味とかいうのには、あまり興味を持っておりません。はっきり言って、かなりアバウトです。
数日前、電車に乗ったところ、すぐ隣に立っている年配の男性と女性との間で以下のような会話が交わされていました。
「このあいだ、うちの伜が電気屋でVDB買ってさ」
「違うでしょ、BVDでしょ」
「そうそう、BVDだった。しかし、あのVDBってのは、便利だねえ」
「そうよ、うちにもBVDあるけど、色もきれいだし、映画なんかも観れるみたいだしさ」「これからは、VDBの時代だよ」
オジさんはすぐに元の「VDB」の戻り、オバさんのほうは「BVD」のまま、話は弾んでおります。聞いていた私は「違いますよ。DVDですよ」と口を挟みたくなりましたが、聞いているうち、VDBなのか、BVDなのか、はたまたDVBなのか、私自身、何がなんだか、わからなくなりました。
でも、いいじゃありませんか。オジさんもオバさんも、円盤式電気映像再生機を念頭に置いて話していて、双方、話が充分に通じているのですから、何だっていいんでしょう。
アバウトといえば、私の父は私以上にアバウトです。以前、父が自動車のセールスマンと電話で話しているのを聞いたことがあります。
「エアコンはねえ、オートは高いから、アニマルでいい。アニマル・エアコンにしてちょうだい」
受話器に向かって、彼はこう申しておりました。むろん、アニマル・エアコンというのは、マニュアル(手動式)エアコンの間違いであります。しかし、アニマル・エアコンってのは、想像すると、楽しいですね。ハツカネズミが中に入ってて、足踏み式で輪を回すことにより、冷たい空気を送っているとか ―― 宮崎駿さんの映画みたいで、そんなのがあったら、ぜひ欲しいです。
しかし、ま、セールスマン氏にとっては、車を買ってもらえるんなら、マニュアルだろうがアニマルだろうが、かまやしないんでしょう。電気店の人だって、
「呼び方は、VDBでもBVDでも、いいや、DDTだって、かまやしません。買ってくれるお客様は神様です」
と言うに決まっています。
文芸家協会の名簿を見て、送ってくるのでしょうか、私のところには出版社からのダイレクトメールがよく届きます。その多くは「○○語源辞典」とか「××類語辞典」という辞典類で、1点もしくはセットでン万円するものも珍しはありません。そのようなダイレクトメールは即ごみ箱行きとなります。
ここだけの話ですが、私の仕事部屋には、小学館の新国語辞典が1冊あるきりで、広辞苑すら置いてないのですよ。
ん、まずいこと、書いちゃったかなあ。作家がこんなふうだったら、批判を受けるかもしれないなあ。でも、ほんとのことだから、仕方ないよなあ……。
むろん、私にも言い分はあります。私は言葉を厳密に厳密に使ったり、言葉遊びに興じたりするのは、好きではありません。というか、興味がありません。言葉一つひとつよりも、現実に生きている人間や社会と関わったり、観察したり、感じたりすることのほうがずっと面白いから、言葉をいじくりまわすのにエネルギーを費やす気になれないのです。
言葉の読み方や厳密な意味にはアバウトな私ですけど、反対に敏感な部分も持ち合わせています。それは、言葉の持っているイメージや色彩、それから文章のリズムなどです。先月号のエッセイで、自治会で行われる「ゴミゼロ運動」という言葉にいちゃもんをつけましたが、気持悪くて絶対に使えないという言葉も数々あります。たとえば、「こじゃれたお店」なんて言葉。どうして「しゃれた」に「こ」をつけるんだ! おお、気持悪い、ジンマシンが出る。「台所の小物たち」、おいおい、変なもんに「たち」をつけるな。許せん、ハエ叩き持ってこい!
言葉“たち”には何の罪もないのですけど、どうしても我慢できなものがあるんです。
言葉の選び方に加えて、文章のリズムまで合わないとなると、もう、これはどうにもならなくなります。私は70年代、80年代に数々のベストセラー作品を産み出したミステリー作家M氏の小説を最後まで読み通せたことがありません。勉強のためにも、読了しようと、幾度もトライしたのですが、そのたびに乗り物酔いか悪酔い状態になって、途中で本を投げ出しているのです。
これは、M氏が下手だとか、私が至らないとかの問題ではないでしょう。きっと、Mさんとは吸っている大気が違うんです。つまり、火星人と金星人の違いみたいな……。
こういう商売を長くやっていると、業界外の友人、知人から、
「○○○○みたいな本を書くと、売れるんじゃないの」
と言われたりもします。○○○○のところには、その時どきに流行っている小説や作家の名称が入ります。
でもねえ、そうはいかないんです。かりに○○○○みたいな作品を書くだけの能力があったとしても、それが自分の体質に合わないものだったら、書いている途中で悪酔いしてきて、ダウン。目の前に嫌な言葉がちらついて、「おーい、ハエ叩き持ってこい!」といった事態になること必定なのです。
作家というのは、案外、不自由な生き物なのであります。