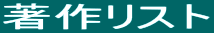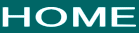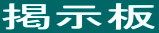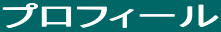月刊エッセイ 4/20/2004
■ 「命ほど大切なものはない」って、ほんとうですか?
ずいぶんと騒がしい4月となりました。
日本人合計5人がイラクで拘束されてしまいました。5人とも幸い解放されましたが、最初に捕まった3人の救出は大騒ぎでした。皆さん、新聞やテレビなどでよくご存じだと思いますので、細かくは書きませんが、「命はなによりも大切。どんな手段を使っても、3人を救うべき」と「いや、政府が渡航自粛の勧告を出している地域に入りこんだのだから、自己責任だ」という論の二つの間で、日本の世論が大揺れだったように思えます。そして、結局は「死なせるわけにはいかないよね」ということで、ともあれ政府も民間機関も動いて(どこまで効果があったのかは、わかりませんが)、無事、3人の帰還となり、まあ、めでたしめでたしの結果に、ほとんどの方が胸を撫で下ろしているといったところでしょう。
でも、おかげで、帰ってきた3人は、家族の強い戒めもあって、イラクが安全な状況になるまでは、再び彼の地の土を踏めないことになるようです。つまり、イラクでの拘束が終わったら、今度は日本の国内で、ある意味の“拘束”に近い状態になってしまったわけですね。18歳のNGO少年やストリート・チルドレンを援助する女性活動家も無念でしょうが、それ以上に、たまらないのはフリーカメラマン氏でしょうね。戦争を撮りにいったのが、戦乱が治まるまでは入国しないというんですからね。
今回の騒ぎ、どこかおかしいんじゃないかなあ、と思ったのは、私だけでしょうか?
何がおかしいのか。ごく大雑把に言えば、「命は大切」と「自己責任」がごちゃごちゃになった挙げ句、戦後の日本を支配している「どんな無様なかっこうになろうとも、死なせてはダメ」という空気に押し流され、人質となった当人も家族も、政府も民間団体も、精神的にあまり幸福とはいえないフィナーレを迎えてしまったという部分でしょう。
ここで、問題を少し整理してみます。あまり言われていないのですが、けっこう重要なこととしては、拘束された3人は誰も「僕らを助けてくれ」「自衛隊を撤退させてでも、我々を救ってくれ」と訴えたわけではないののです。むろん、銃やナイフを突きつけられているのですから、心中「助けて」と叫んでいるのは間違いないでしょうが、「どんな条件を飲んでも」と現実に言ったわけではありません。にもかかわらず、家族や支援団体が「政府は全力をあげて救出にあたるべきだ」と主張して、逆に反感を買ってしまった。その挙げ句の“人質帰国後の行動自粛”なんですね。
じつは私のカミさんのところにも、支援団体に関係しているらしい友人から「政府が全力で救出にあたるよう求める署名要請」のメールが届きました。でも、渡航自粛や退避勧告の出ている国に行ったんだから、ここまで政府のお世話になるのは、おかしいんじゃないかなあ。
家族も支援団体も政府を頼るべきではなかったのです。自分たちの運動と、人質自身の努力(自分たちはイラク国民の敵ではないことを主張し、誘拐集団を説得するとか)で、助かる道を目指すべきだったのです。政府に頼まなければ、助かる確率が低くなるんじゃないかって? それは低くなるでしょう。でも、仕方がない。助かる確率が低くなって、不幸な結果を招いてしまったら、それはそれで受け入れるしかないのです。
これまでの戦争で、多数のジャーナリストやボランティアの方が亡くなりました。ベトナム戦争だって、沢田教一さんをはじめとする幾人ものカメラマンが死んだり行方不明になっている。作家だってそうです。開高健さんは戦争の中での人間を知りたいと、戦時のベトナムに渡りました。開高さんはアメリカ軍に同行し、ベトコンの待ち伏せ攻撃を食らって包囲され、死を覚悟したといいます。その時、同行のカメラマンが写した写真が残っていますが、そこには風前のともしびとなった自分の運命にすっかりしょげかえっている開高さんの姿が写っています。
私の小説のテーマは「戦争と人間」ではありませんから、わざわざ戦地にいくつもりはありません。しかし、もし戦争がテーマだったら、恐る恐る戦乱の地に行っているでしょうし(さすがに今のイラクには行きませんが)、他の作家だって同じ行動をとるものと思われます。そして、流れ弾にあたって昇天という可能性だって無きにしもあらず。
ボランティアも同じです。私の友人に、大虐殺の直後にアフリカのルワンダに救護活動のため赴いた女医さんがいます。拘束こそされませんでしたが、かなり恐ろしい目にあったと言ってました。
ある種の職業の人間は、死のリスクを冒さざる得ないのです。
たとえば、警察官、医師、トラック運転者とかね。警察官が、
「ぼく、万が一、刺されたら恐いから、逮捕にはいかない」
と言い、医師が
「病気うつされたら、困ります」
と感染症の患者の治療を拒絶し、長距離トラックの運転者が、
「事故が多いから、雨の夜の東名高速は走りません」
と運転拒否したら、社会はまわっていきません。
でもねえ、時々、とんでもないことを言う“プロ”がいるんですよ。10何年か前のことでした。昭和天皇の戦争責任をめぐって、発言者の長崎市長が右翼に拳銃で撃たれた事件がありました。その事件の直後、テレビに出演していた売れっ子の社会評論家が、
「こうした事件が起こるんなら、ぼくら、テレビで何も言えなくなっちゃいますよ」
と言っていた。おいおい、ふざけたこと言うんじゃないよ、と、私は怒りました。
たしかに凶器を用いた暴力は恐ろしい。それに対する反対やできる限りの防御はしていかなければならない。しかし、撃たれたり刺されたりするのが恐くて、発言を控えるというのでは、言論のプロとして失格です。「事故が恐いから、条件の悪い時は走りません」と言っている運転手みたいなもんですよ。
もうちょっと突っ込んで言いましょう。「命以上に大切なものはない。なにがなんでも死ぬのはダメだ。死ぬの奴はバカだ」とする考えは、自由を勝ちとってきた先人に対する冒涜のような気がするのです。多くの先進国では、発言や行動の自由がかなりの部分まで保証されています。でも、そういった自由は初めから用意されていたものではないのですね。先人たちが命をかけて闘いとってきたものなんです。
フランス革命では、多くの市民が絶対王政と闘いました。第2次大戦中は、ナチスに反抗してレジスタンスが銃を取りました。多くの人が命を失いましたが、おかげで、今のわれわれが自由を楽しむことができているのです。もし彼らが、
「私、何があっても死ぬのやだもんね」
と言って、無抵抗な状態だったら、ヨーロッパにはいまだルイ38世とかヒットラー3世とかがいて、権力をふるっていたことでしょう。
命は大切です。でも、時には、それが失われるリスクを冒してでも、しなければならないことがあるのですよ。
イラクでの拘束事件が起こる少し前には、六本木ヒルズの回転ドアに挟まれて子供が亡くなったり、公園の遊具でケガをしたりする事件が相次ぎ、“危険な遊具”の撤去も行われたようです。回転ドアは、それまでにも事故が多発していたそうで、安全管理者の責任はきわめて重いものでしょう。でも、ここも危ない、あそこも危ないと、子供の行く場所すべてを極端なほど安全にしたり、立ち入り禁止にしたりするのは、はたして正しいことなのでしょうか?
私が小学生の頃は、遊ぶ場所には危険がいっぱいありました。川で溺れたり、氷が割れて池で死んだりする者が学校で2年間に1人くらいは出たような気がします。木から落ちてケガをするなんて、珍しくもないことで、それゆえ、子供たちは、どんな行為が危険なのか、身をもって覚えていきました。
でも、今は違うんですね。少し危険だと、「子供の命は何よりも大切だ」という観点から、すぐに立ち入り禁止になってしまう。
安全とは言えない環境の中で子供時代を送ってきたため、危険に対する予知能力はそれなりに持っていると、私は思ってきました。が、海外よりずっと安全な日本国で安全ボケしたのかもしれません。私自身、外国で危ないことに2度ほど出会っています。
1つは大学時代、アメリカのヨセミテ公園に行った時です。夜、散歩するのが好きな私は、そこが日本であるかのような感覚で、夜中の自然公園を歩き回りました。そして、なんの問題もなく泊まっているキャビンに戻ってきたのですが、窓から外を見て仰天。すぐそばで、大っきな熊がゴミを漁っているではありませんか。ノーテンキにも、私はその近くを通って帰ってきたのです。まあ、公園内の熊さんですから、そう凶暴ではないでしょうが、いちおうは熊です。なにかに驚いて、ガブリとやられていた可能性もあったことでしょう。
もっと現実的な危険は、10数年前、インドネシアのジャワ島にあるボロブドール遺跡に行った時に起こりました。石造りの遺跡の階段をえっちらおっちら上って、最上階までたどりついた。そこで周囲の景色を見ようと、何気なく後に1歩下がったんですね。さらにもう1歩と思った時、なにかイヤなものを感じて、後を振り返ると、そこには何もなく、すぐ下の階へと落ち込んでいるではありませんか。高さは4、5メートルくらいかなあ。下も石ですから、落ちて運が悪かったら頭を打って即死、運がよかったとしても大ケガは免れなかったでしょう。日本だったら、観光客が来る場所で危険な個所があったら、必ず柵が設けられています。でも、外国は違う。すべては自己責任で、ガードも何もない。日本と同じだと錯覚していたら、とんでもない不幸に遭います。
今回イラクで拘束された人たちも10代から30代前半と、皆さん若い世代です。きっと、「子供の命、安全は何よりも大切だ」という精神の下、極めて安全な環境で子供時代を送ってきたのではないでしょうか。それゆえ、危険に対する感覚がいまひとつ育っていなくて、武装勢力に拘束されるという事態を招いてしまったんではないでしょうか。そんな気もしています。
たしかに命は大切です。でも、その基準だけですべてを律しようとするならば、将来、もっと大きな危機を招いてしまいます。
いろいろと騒がしくも物騒な春だけに、今回は真面目なことを書いてしまいました。