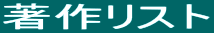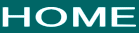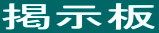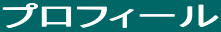月刊エッセイ 3/20/2004
■ 勉強になります ―― 「白い巨塔」など
この欄で、コンサートに行っただの、テニスで転んだだのと、そんなことばかりを書いているため、作家というのは遊んでばかりいると、お思いの方も少なくないでしょう。また、所得税申告の際には、本代や映画や芝居のチケット代まで経費として認められることが多いので、「おいおい、必要経費といったって、自分で楽しんでるだけじゃないか」と友人から非難の目を向けられることもあります。
でも、違うんですよ。文筆業者にとっては、そういったものの多くが、仕事をする上での勉強になっておるのです。そこで、今回は、どんなふうに勉強になっているかを、書いてみましょう。
(1)「白い巨塔」
今週の木曜、最終回を迎えてしまいましたが、言わずと知れた超高視聴率のテレビドラマです。おおっと、こう書いてはいけないのかもしれない。もともとは山崎豊子さんの小説なんですからね。でも、私、山崎さんの原作も読んでいないし(不勉強!)、前回、田宮二郎さんが主役を演じた時のドラマも観ていないので、今回フジテレビ系で放映されたものについて、思うところを記します。
最終回は40パーセントに迫る驚異的視聴率を出したんだそうで、その理由は老若男女を問わず、観てもらえたことだといいます。なにしろ、私の知人の小学5年になる子供のクラスでは、ほとんど全員が「白い巨塔」を観ていて、この番組を知らないと、仲間に入っていけないんだとか。児童たちがうちそろって、レインコートの裾を蹴飛ばしながら廊下を歩く「総回診ごっこ」なんてのを、もしかしてら、やっていたのかしらん。
じつは、私もこの番組にはハマってしまいまして、ええ、最後の3回くらいは、涙なしには観れなかった。私、けっこうクールなタイプで、テレビや映画を観て、涙ぐむなんて、滅多にないんですが、今回は違った。うーん、よくできているドラマでした。
しかし、作家としてはハマっているばかりではいられません。すごく勉強にもなりました。とくに脚本。過去に「GOOD LUCK 」などのテレビドラマや映画「赤い月」を手がけた井上由美子さんの脚本ですが、これがじつに巧みだった。
主役の財前教授はガリガリの権力志向の人間ながら、時々、弱さも見せる。一方、その対極として存在している里見先生は、愚直なほどにイイ人。まあ、わかりやすくて、クリアな人間の描き方で、その他の脇役、財前の奥さんや愛人、里見の奥さん、医局員、医事訴訟に関わる弁護士なども、ほんとうにわかりやすく描かれています。こんなふうに、わかりやすく、クリアに人を描くと、下手をすれば底の浅い作品になってしまう。しかし、クリアな人間像を上手く組み合わせることによって、今回の場合、底が浅くならずにすんでいるのです(むろん、高度医療はどうあるべきかというテーマが背景にあることも大きいのですが)。
わかりやすく、分析してみましょう。クリアな人間像は、たとえば、ルビーやダイヤといった1個の宝石です。それ自体は美しいものかもしれませんが、やはり1個の宝石でしかありません。それら“宝石”をいろいろと組み合わせ、医療はどうあるべきかという“純金の王冠”の上にちりばめていったのが「白い巨塔」だったというわけです。単純な光しか放たない一個一個の宝石だって、それをいくつも組み合わせることによって、燦然と輝く“王冠”となるのです。
対して、今まで自分が書いてきた小説は、どうだったのだろうと、つい考えてしまいました。人間は複雑な存在だということで、登場人物の1人1人を必要以上に複雑に書いてしまった傾向があったような気がします。1人1人が複雑に描かれると、多数を組み合わせた場合、全体がぼんやりしてしまう結果につながりかねません。ムムム、反省、反省……。1人1人の描き方は単純でも、組み合わせによって全体を深いものにする手法。これは、ほんとに勉強になりました。
しかし、勉強になったのどうのという問題よりも、「白い巨塔」は終わって、サッカー五輪代表のアジア地区予選も終わって、これから何を楽しみに生きていけばいいんだろう。そっちのほうが、大きな問題のような気もしております。
(2)「ラスト・サムライ」と「シービスケット」
こっちは、アカデミー賞候補となったハリウッド映画です。前者は渡辺謙さんが助演男優賞、後者は作品賞などにノミネートされ、どちらも無念の涙を飲みましたが、話題になっただけに、両方とも観てしまいました。
圧倒的人気を誇ったのは「ラスト・サムライ」のほう。トム・クルーズ扮するアメリカの軍人が明治維新の日本にやってきて、反乱軍の捕虜となり、しかし、サムライの武士道に魅かれていくという筋立てですが、観た人に訊いてみると「すごくよかったよ」という声が圧倒的でした。新聞の宣伝にも「1000万人が観た」と書かれていましたので、そうとうなヒットだったんでしょう。
で、私の感想。悪い映画じゃなかったし、それなりに楽しめたけど、すごくよかったわけではない。まあ、75点くらいかな、というのが、正直なところです。
引っかかった点はいろいろあるのですが、その最大のものは、刀と銃との戦いの優劣の問題。明治初期から300 年近くも前の戦国時代、長篠の合戦で、すでに決着はついているはずです。勇猛を誇る武田の騎馬軍団が、鉄砲を揃えた織田・徳川の連合軍と戦い、壊滅的な敗北を喫した。それ以後、馬と刀では鉄砲には立ち向かえないことがはっきりしているのに、映画の中では、明治の時代になっても、刀を手にしたサムライが鉄砲を揃えた政府軍に襲いかかり、「あわや勝利!」という状況を作り出しているのです。途中で、なぜか忍者も登場したりして、盛り沢山。ハリウッド映画のせいかもしれませんが、富士山に芸者ガール、新幹線が一同に会している、外人さんの描いたイラストのような気もしてきたのです。
私と同様、75点くらいかな、と評した人々は、こうした事実とはあまりにもかけ離れた部分が引っかかったみたいです。でも、一方では、「そんな歴史的事実なんで、どうでもいいじゃない。娯楽作品は楽しければOKなんだから」と思った人は、高得点を与えたみたい。たしかに、よほどの害でもない限り娯楽作品は事実と異なってもいいんだという考え方もあるでしょう。要は、観る人の意識によって、点数は大きく違ってくるという、当たり前の結論になってしまいましたが……。
ある新聞には、日本人が保守化したから「ラスト・サムライ」がウケたんだ、という分析がありました。アメリカ人が羨ましがるようなサムライの末裔が自分たちだという思いが、日本人のプライドをくすぐったというわけです。
でも、それだって、事実とは、ちょっと違うよねえ。たしかに葉隠精神で生きたサムライもいたでしょうが、江戸時代の武士がサラリーマン化していたことは、さまざまな資料で明らかになっています。それに今という時代を見ていると、とても日本人が、武士道を実践したサムライの末裔だとは素直には思えなくて ―― 私は、あまりにも極端に事実から目を背けることはしないほうがいい、と考えておるのですが。
次は「シービスケット」です。アメリカが大恐慌の頃、人生につまずいて失意の底に沈んだ男3人が、どうにも調教できない小柄なサラブレット「シービスケット」と出会う。そして、この馬の素質を見抜いた男たちが、レースに挑み、最後にはアメリカ最強馬を負かすという、実話に基づいた映画なのであります。
「人間、1度や2度、人生につまずいても立ち直れる」というテーマが全編に貫かれた映画で、1920、30年代のアメリカの風景が美しいし、サラブレットが疾走する姿も爽快で、ある意味、単純ではありますが、さわやかで、観た人に勇気を与える出来上がりになっていて、私は「ラスト・サムライ」よりも高い得点を、こちらのほうに与えたのです。いや、アメリカ映画としては「ダンス・ウイズ・ウルブス」や「セント・オブ・ウーマン」の次くらいにくる佳作だと思っているのです。
しかし、多くの人の評価は違って、あの映画を観た人の中には「よくわからなかった」と言う人も少なくありません。私の知人に競馬狂いがいます。その方は、アメリカから競馬映画が来たと聞いて、封切られるや、映画館にすっ飛んでいきました。しかし、ガッカリしての御帰館。「面白くも、なんてもねえや」と、ひとこと言ったそうです。アメリカの競馬界を内側からとらえた映画だと、期待して観に行くと、たしかに裏切られるでしょうね。
もしかすると、私がフリーランサーという境遇の人間だから、「シービスケット」に共感できたんじゃないかという気もしています。フリーの人間にとって、成功しなかった場合の挫折とか失敗とかは、珍しくもなくあります。その点で、リスクを恐れずにチャレンジするアメリカ文化と似通った部分がある。でも、日本人の多くは、終身雇用(日本企業が変わったといっても、そう簡単にはレイオフやクビになったりはしません)の中で生きてきているので、人生における深刻な挫折を味わう人は今のところまだ少数なんじゃないかな。だから「1度や2度つまずいても立ち直れる」というテーマの重みが、日本人には今ひとつピンとこなかったのかもしれません。
(3)「フジ子・ヘミング」
行ってきました、東京文化会館に。ピアニストのフジ子さんのコンサートです。私はあまり行く気はなかったのですが、菅野美穂さんが主演したフジ子のドラマを観たかみさんが感激して、インターネットで、わずかに残っていたチケットを2枚注文してしまったのです(安い席にもかかわらず、2枚で14,000円!)。
行って驚きましたね。いや、演奏以前に客層が、いつものクラシック・コンサートとはまったく違う。クラシックのファンは「若い頃、レコードたくさん聴いたぞ」という暗そうなオジサンと(私も、そこに含まれる)、「音大の学生なの」っていう感じの若い女性が大多数を占めるのですが、その日は、オバサン軍団がずらりと着座しております。ここは東京文化会館ではなく、明治座か新橋演舞場ではなないかという錯覚にとらわれてしまったほどです。
そして、演奏が始まると、パラパラ、パラバラ、プログラムをめくる音が聞こえる。主催社のアホが何を思ったのか、音の出やすい薄くて固い紙でプログラムを作ったので、フジ子さんのピアノを伴奏するみたいにパラパラ音が続きます。演目はドビッシーやショパン、リストなどの小曲ばかりです。1曲が終わるたびに拍手が起こるのですが、最後の音が消える前に手を叩き出す客もいて、どうにも雰囲気をそがれます。
なぜか男性の声で「ブラボー」と叫ぶのも2度ほど聞こえました。近くにいたお客さんが囁きます。
「あれ、サクラなのよね」
えっ、サクラって何なんだ? 胸には、疑問の思いも生じます。
演奏が終わって、会場を出ると、フロアでCDを売ってました。「フジ子さんのCDですよ」と、大声で呼びかける男性の声が「ブラボー」と叫んだ声に酷似している。むむ、あれは人気を煽り立てるための「ブラボー」だったのか? なにか底知れぬ疑惑を感じ取ったのでありました。
肝心の演奏はといえば、華やかな音色を振りまいて、得意としているリストの「ラ・カンパネラ」やショパンの「雨だれ」は、さすがに素晴らしかった。でも、平凡な演奏も多かったし、「英雄ポロネーズ」のように、力が入りすぎて“階段から転げ落ちた”みたいなものもありました。早い話が、玉石混交。まあ、フジ子さんは、他のクラシック・ピアニストとは違って、私は弾きたい曲を弾きたいように弾くのよ、というスタンスで演奏に臨んでいるのでしょうから、こういうのもありかなあ、とは思いました。
フジ子さんといえば“奇跡のピアニスト”としてNHKテレビに幾度となく取り上げられ、民放のドラマにもなり、話題になった人であります。そのせいでしょうか、年間、かなりの数、大ホールで開かれるコンサートは、ほとんどがソールド・アウト。チケットが日本人ピアニストの倍くらいの価格で売られているにもかかわらず、です。
こんなふうな売れ方をしているのも、数の限られたクラシック・ファンではなく、いつもはコンサートなどに来ないオバサン層にアピールして、チケットを買わせたからなんでしょう。そして、そうなったのも、やはりテレビの威力なんだろうな。
ものすごーくいい演奏なのに、ろくに客が入っていないコンサート(たとえば、今年だったら、つくば市で開かれたスチーブン・コヴァセビッチのピアノ演奏会)もあるってのに、これでいいんだろうかと、複雑な思いも抱いたわけです。
ということで、テレビやら映画やらで、勉強になったことを書き連ねてみました。えっ、ほんとうに勉強になったのは(1)だけじゃないかって? いやいや、違うんです。あーだのこーだの考えることが、作家にとっては勉強なのですよ。