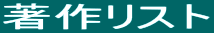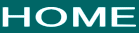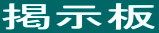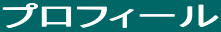月刊エッセイ 11/20/2003
■ 「余暇は、よかよか」(その2)
ひと月が過ぎるのは早いですね。各種のシンポジウムを聞きに東京まで出かけたり、テニスをしたり、郷里に住んでいる両親のケアをしたり、猫と遊んだり、むろん生活のメインである原稿書きをしたりしているうち、11月も半ばを過ぎていて、いけねえ、ホームページのエッセイを書くの忘れていた、という結果になってしまいました。失礼いたしました。
先月は、下手な駄洒落タイトルをつけて、テニスと将棋について書きました。後半の今月は、クラシック音楽とスキーについて、であります。
中学時代やっていた軟式テニスが、硬式へと変わって、テニスを再開したことは、前回書きました。同じように、昔、時間を費やしていた趣味が復活したものに、クラシック音楽の鑑賞があります。今年だけでもずいぶん行きましたし、今、買ってあるチケットはといえば、11月の末が、お隣の柏市でジェビツキとかいうポーランドの若手ピアニストがコンサートをやるというので買い、12月が東京文化会館で都響の定期演奏会、明けて1月が池袋の東京芸術劇場でジャン・ギャン・ケラスというチェリストの協奏曲を聞くことになっていて、それから、先日テレビ放映されたフジ子ヘミングのドラマ(管野みほが主演したやつです)を観たカミさんがどうしても聴きたいと言い出して、フジ子ヘミングのピアノ・コンサートのチケットも買ってしまって……ああ、そんなに時間はあるのか、財布の中身は少なくなる一方だし、と、今は少し後悔もしております。
なぜ、これほど行くようになったかといいますと、常磐線沿線の我孫子市に引っ越したからなんですね。常磐線の快速に乗れば、東京文化会館のある上野まで30分ほどだし、地下鉄の千代田線を使うと、赤坂のサントリーホール、渋谷のオーチャードホール、NHKホールまで乗り換えなしで行くことができるんです。
こんになにもしょっちゅうコンサートに行くとは贅沢だと思われるかもしれませんが、じつは上手く選べば、クラシックのコンサートというのは、かなりの格安で楽しむことができるんですよ。たとえば、都響(東京都交響楽団)が東京文化会館で開く定期演奏会にはEX席というのがあって、そこではなんと1500円でコンサートが楽しめてしまうのです。安い席だから音が悪いかといえば、けっしてそうでなく、演奏者が見にくいとか、その種の難点は多少ありますが、コンサートホールとして設計された会場(その点、NHKホールは良くないという話を聞きます)ならば、音響の点で大きな問題はありません。1500円なら、ポップスのコンサートよりもはるかに安く、いいや、映画より安いのですから、仕事の帰りにふらりと立ち寄って、音楽を楽しむというのは、チープだけどお洒落な大人の趣味といえるのではないでしょうか。運が良ければ、ものすごい熱演にも出会えて、「儲かった、儲かった」と言いながら、家路に就くということになります。
私がクラシック音楽を趣味とするようになったのは、大学に入ってからです。1970年代の当時は、音楽好きな男子学生は、ビートルズやローリングストーンズなどのロックを楽しむ者と、クラシック好きとの2派に分かれていたと記憶します。そして、たまたま友人にクラシック狂がいたため、彼の影響を受けて、私もレコードを聴くようになったというしだいであります。
しかし、そうしたきっかけはともかく、ロック派とクラシック派は、性格的にも大きな違いがあったような気がします。早い話が、クラシック派は自分の世界に入りこんでしまう人間が多かったな。
大学時代、私がクラシック狂の友人A君の下宿を訪ねた時のことです。階段を二階へと上がっていくと、彼の部屋からはベートーベンの交響曲が聞こえてきています。
「おおい、入るよ」
と声をかけて、引き戸を開くと、A君はステレオに向かって、一心不乱にタクトを振っているのです。大音量のせいで、私が来たのにも気づかない。ちょうど第4楽章の最後のあたりを演奏しているところで、ジャン、ジャン、ジャーンと、ステレオが終わりの部分を鳴らして静かになると、ようやく私に気づいたようです。そして、タクトを手にしたまま、上気した顔で言うのです。
「よう、村岡(私の本名です)。聴いてたか、良かったろう。ベームの振り方で指揮してみたんだ」
おいおい勘弁してよ、と思いました。たしかに、かかっていたレコードは、カール・ベーム指揮のウィーン・フィルのようですが、彼はただタクトを動かしていただけです。かりに、ステレオの前で猫が顎を掻いていたとしても、同じ音楽は流れたはずです。
自分の部屋で自分の世界に入りこむのなら、まあ、いいでしょう。でも、見ちゃったんですよ、銀座のランブル(もう、なくなってるだろうな)という名曲喫茶で。中年のおじさんが、楽譜をテーブルの上に置いて、スピーカーから流れてくる交響曲に合わせて、持参の指揮棒を振っている。公衆の面前で、そんなことするなって。しかし、名曲喫茶なんて、クラシック狂いのおかしな連中ばかり集まっていたから、奇異には受け取られなかったかもしれないね。
かつては、音楽家のほうも、自分の世界にどっぷり入りこんでしまうタイプ、よくも悪くも“唯我独尊的”な人間がほとんどだったような気がします。指揮者だったら、僕が聴いていた頃は、カラヤン、ベーム、バーンスタインの三人が人気を集め、その前の時代には、ワルター、アンセルメ、クレンペラー、さらに遡って、フルトベングラーなんていう、個性がそのままタクトを振っているような方々がクラシック界の中心となっておりました。
ところが、20代の後半あたりからなんとなくクラシック音楽を聴かなくなり、20年以上もたって再びこの世界に戻って気づいたんですね。音楽家も指揮者も“唯我独尊的”な部分がえらく少なくなっている。どの方もテクニックは凄いし、洗練されてもいるんだけど、剥き出しの個性みたいなものが無くなってるんだなあ。純粋な音楽性という部分では向上してるんだろうが、なにか皆、同じ方向を向いているような気がする。
そんなことを感じていると、先日、新聞紙上で似たようなことを言っている人を見つけたんですね。クラシックのCDが売れなくなっているんだそうです。その理由として、年間に数百枚のCDを買うというその方は、最近はどのアーチストを聴いても大差がない。大差がないなら、買っても仕方がない、と言うんです。なるほど、クラシック音楽は、他のジャンルとは違い、同じ曲をさまざまなアーチストが演奏しているのですから、どれを買っても大差がないんなら、新しいCDをわざわざ買ったりしないよね。
私の好きなCMのコピーに、三井のリハウスだったかな、「人は生まれ変わる代りに、住み替えるのかもしれない」(一部ちょっと違っているかもしれません)というものがあります。人は生れ変われません(たぶん)。だから、他の人の世界に束の間、自分を重ね合わせるのです。A君だって、きっと、あの時、カール・ベームに自分を重ね合わせていたんです。そして、次の日には、カラヤンになりきっていたのかもしれない。
とかく、プロは純粋性、完璧性に重きを置きがちです。音楽の世界ばかりではありません。将棋だって、小説だって、同じです。でも、強い個性に裏打ちされない純粋性というのは、ファンの心を惹きつけないのではないでしょうか。個性や世界観という“雑”な部分も、表現の世界には必要になってくると思うんですが。
一時は、ずいぶん凝ったのですが、ここ十年以上、まったくやっていないものに、スキーがあります。
今から二十年以上も昔は、自分の車でスキー場まで行くということもなかったし、宅急便なんて便利なものもなかったので、あの重いスキー道具をうんしょとかついで、電車に乗って、はるばる雪国まで出かけたのです。夜行列車に乗って、朝、むこうに着くと、さっそく滑り始めたりしてね。あの熱心さは、いったい何だったのだろう?
いいや、私ばかりではありません。ここのところ、スキー人口、とくに若い人のスキー人口が年を追って減少し、スキー場も次々に閉鎖となっているそうです。その訳として、最近の若い人はもっぱらケータイやテーマパークで時間もお金も使ってしまい、遠くて寒いスキー場までわざわざ出かけていかない、という理由が言われています。たしかに最近の若者を見ていると、“楽じゃないこと”は避ける傾向がありますから、お金使って、寒い思いをする、しかも、上手く滑れるまで時間もかかるスキーは敬遠されるのかもしれません。でも、それだけの理由からでしょうか? ちょっと角度を変えて、考えてみましょう。
20代の頃、私(あるいは私たち)がスキー場に出かけたのは、なにもスキーを滑るだけのためではありませんでした。もう一つの理由があった。それは、女性グループと時間を気にすることなく楽しむためでもありました。
今の若い人には信じられないかもしれませんが、1970年代というのは、結婚前の女性が男性と同じ宿や部屋に泊まったりすることは、そう簡単に許されるものではありませんでした。男性と旅行に出かけるなんて、親にばれたら、大変な騒ぎになった。
ところが、スキー旅行だけは別だったんですね。スキーじゃ、日帰りはできない。まあ、グループならいいかと、女性側の親たちも大目に見たんです。
それだけに、冬が近づくと、今年は誰を誘おうか、誰とスキーに行こうかと、男も女も心を浮き立たせていたものです。早い話が、スキーを名目にした、一種の泊まりがけ合コンだったんですな。
それだけに、どんな相手とスキーに行けるかが、勝負を分けた。惨めな経験もあるんですよ。あれは、もう会社に入ってた頃だったな。男3人、年末に山形県は天元台スキー場に宿を予約したんです。ところが、OKをにおわせていた女性グループが、いざ誘ってみると、ああ信じられないことに「NO」の返事。狙っていたグループが駄目となって、一同落胆のあまり、第2候補に声をかける気にもなれない。
「くそっ、こうなったら、北海道まで行って、純粋に滑りまくろう」
と、半ば自棄になった誰かが(私じゃなかったと思う)が言い出して、北海道行きの航空券を買ってしまったんです。
行き先は、ニセコ高原。寒かったよお。スキー場はガラガラで、パウダースノーを滑っている昼間はまだよかった。しかし、宿に帰ってからが惨めだった。男ばかりじゃ、ただ酒呑むしかない。なんで、高い金使って、こんな遠くて寒いところまで来なきャならなかったのか、納得のいく答を見つけることができなかったのであります。
一方で、上手く女性たちのグループを誘えた時は、楽しいかったね。なにせ、若い男女が、時間を気にすることもなく、呑んだくれたんだもの。いちおう男女別の部屋も取ってあったけど、アルコールが大量に入ると、そんなものどうでもよくなってくる。で、いろいろあったりして、えーと、ここでは書けないような事態になったことも、あったようななかったような、うーん、遠い記憶で、はっきりしないなあ……。
でも、今は違います。わざわざスキー場まで合コンに行かなくたって、男と女の関係は急速に、イージーに進展するようになっています。1週間前に知り合った2人の間で、
「きみの誕生日、アンバサダーホテルのツイン、予約したよ」
「わあ、嬉しい。ディズニー・シーで遊んで、夜はディナーね」
なあんて会話が交わされているようですから(けしからんのう)、東京から1時間以内の手近な場所ですべてはすんでしまうのです。
社会学的に言いますとね、早い話が、スキー場というのは、若い男女が接近するための“手続きとしての場”としての機能を持っていた。でも、そんな手続きが必要ない時代になってしまうと、スキー場の必要性も大幅に減ずるというわけです。これが、スキーが衰退した大きな原因じゃないかなあ。
ともあれ、私は経験上、そう思うんでありますよ。
さて、先月から、テニス、将棋、クラシック音楽、スキーと4つの娯楽について論じてきました。しかし、この4つとも、若い頃に始めたもので、考えてみると、中年以降に新たに身につけた趣味というのはないんですね。別なところでも書いたと思いますが、やはり、遊びというのは、習得する“旬の時期”ってものがあって、それを逃すと、なかなか身につかない。
そういった意味でも、若い人には、ケータイやテーマパークにお金を使うんじゃなく、一生つきあっていける“遊び”に、時間と金とエネルギーを費やしてほしいと思っておるんですが……。