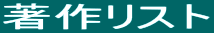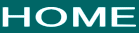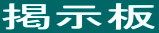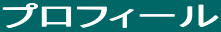月刊エッセイ 9/16/2003
■ 私が出会った“バカの壁”
ここしばらく新刊書のベストセラー上位に居すわっているのが、解剖学者・養老孟司氏の『バカの壁』であります。手軽な新書判の本ですから、もうお読みになった方も多いでしょう。私も先日、読みました。
まだお読みでない方に、ごくごくごく簡単に内容を語れば、以下のようになります。よく言われている「人間、話せばわかる」というのは嘘で、話してもわからない人たちが大勢いる。それは、ものの見方を固定化している人たちで、たとえば、「パレスチナはテロリストの巣窟だ」と頭から決めつけている人間と、「イスラエルのユダヤ人は侵略者だ」という一念で戦いを挑んでいる人間とでは、どんなに話しあったって、なかなか分かり合えるものではないというわけです。つまり、バカの壁とは、バカな人間が壁となって人の行く手を阻んでいるのではなく、人をバカ(カチカチの石頭)にしてしまう壁(ガチガチの固定観念)があるという、そういう題名なのです、たぶん。
言われてみれば、当たり前のことなのですが、ぼんやりしていると、なかなか気づかない。そうしたことを的確に、わかりやすく指摘したのだから、そしてタイトルもなかなか目立つものですから、なるほど、ベストセラーになるのも当然だと、私も感心したわけなんです。
だけどね、あるんだよなあ、どこの世界にも「バカの壁」ってのが。出版業界にも、当然あります。
何年か前、某誌の編集長であるA氏とトラブったことがあります。氏から依頼された小説を私が書いたわけですが、書きあがったものを、彼はどうしても認めようとしない。まあ、作家と編集者との間の見解の相違というのは、時々あることですから、話しあっていけば、解決点は見い出せるだろうと、最初は私もそう深刻に考えてはいなかったんです。ところが、話しあっても、まったく距離は縮まらない。A氏は私が書いたものを全否定しようとするのです。
A編集長は文芸畑ではベテランの編集者です。これが理想的な文芸作品だというのを頭の中に持っていて、以前に、私が出した新刊小説の文章に直しのペンを入れて郵送してきたことがあり、その熱心さには恐れ入りましたが、自分の文芸観を押しつけてくるのに、ちょっとばかり嫌な思いをさせられた憶えもあります。私が書いた作品は、氏自身の中にある“文芸基準”からかけ離れたものだったのでしょう。だから、否定しにかかった。
これで私が世渡りの上手い人間だったら、最近の傑作だと言われているような小説の書き方を取り入れるでしょうし(早い話が真似て)、そうするならば、A氏は、
「いや、なかなか良い作品じゃありませんか」
と、褒めたたえたに違いありません。
しかし、私は「過去の文芸基準など気にする必要はない。その時、その時のテーマにいちばんぴったりした書き方で書けばいいんだ。失敗するかもしれないけど、冒険も必要」という立場に立っていますから、二人の話が一致するはずもない。結局、すったもんだの挙げ句、決裂。その作品は、別なところで出版する結果と相成りました。
B君は、A氏とは反対に、入社してあまり時もたっていない若手の文芸編集者でした。彼は、自分が求める新しい作品というのはこういうものだ、みたいな意識を強く持っている青年でした。その彼が人事異動で新担当者になったのですが、私の作品が自分の世界とは大きく違ったものだったらしく、最初の電話で、
「本岡さん、なんでこんなもの書くんですか」
と言ってきましたので、こちらとしては仰天しました。初対面の相手ならば、少しは言葉を選ぶのが普通ですが、B君は悪い意味での“今時の若者”で、人間関係を円滑に進めるのが苦手な青年のようでした。
それでも、我慢して、おつきあいしたのですが、彼が固定意識を捨てないのだから、話はあっちこちでぶつかります。とげとげしい雰囲気のうちに打ち合わせをするうち、B君の顔つきが変わって、突然のように言ったのです。
「私、本岡さんの担当、下ろさせてもらうわけにはいかないでしょうか」
またまた仰天しました。寄稿家と編集者の対立は珍しくもありませんが、相手の目前で「やーめた」発言をするのは、めったにあることではありません。B君は顔面を硬直させ、ものも言わずに打ち合わせの場所から去っていきました。あーあ……。
立場は違っても、作家と編集者は同じく文章を生業としている者同士ですから、話せば、完全にとはいえないまでも、ある程度は理解し合えるのではないかと、かつては思っていました。しかし、世界観があまりにも違って、しかもガチガチの固定観念を持っている相手とは、話しても一致点、妥協点を見いだすことは極めて難しい。膨大な時間とエネルギーを無駄に使うということに、ようやく気づきました。人生、そんなに長くはない。こうした相手とは、今後つきあわないぞ、と、今は心に決めているのです。
小説家としての仕事を離れても、バカの壁には、時々出会います。
先日、ある会合で「日本人の劣化」について話しました。話が終わると、高齢男性の方が発言を求めてきました。その方が主張するには、日本人はまったく劣化していない、たとえば自動車だって家電だって世界一ではないか、と。そして「あんたの言うことは、話にもならん」と、全否定してくるのです。
こちらとしては、日本人が劣化したのではないかということを、産業、経済、身近な話などを例に出して話すのですが、頭から受けつけないのでは、話す甲斐がありません。その方は80歳に近いお年のように見受けられました。きっと、日本が絶好調だった1970年代、80年代に現役時代を過ごし、その頃の思いが頭の中で固まってしまい、状況の変化を受けつけないんでしょうね。
「バカの壁」っていうのは、若者から老人まで広く蔓延しているみたいです。
心の中にガチガチの固定観念(壁)を持っている人は、壁の外側の意見に出会うと、頭から否定しにかかります。この否定病も恐いのですが、もっと恐いのが、逆に壁の内側に入って来た意見に対しては、異常なほど寛大になることです。つまり、自分と同意見に出会うと、すべてを許して、受け入れてしまうんですね。たとえば、時々、テレビ番組の投書欄なんかに出てるでてるでしょ。
「○○は、最近のドラマにしては人の情愛をよく描いていて、大変に感動した。とくに親子の愛は、ああ、我が意を得たりと、思わず膝を打った」
なあんてのが。自分と思いを一つにするものが、久々にテレビ画面に登場したので、手放しで褒めたたえているのです。
私の友人のC君は、なかなかの好人物です。しかし、彼には一つだけ大きな欠点があります。人の話をろくに聞かず、自分の意見ばかり(それも、かなりの固定観念に基づく)を喋りまくるという欠点です。自分の意見ばかりを喋るのでは、相手をなかなか説得できません。そして、相手が自分の意見に同意してくれないとわかると、今度は、
「どうして、わかってくれないのよ。長いつきあいなのにさ」
懇願と甘えの態度に出てくるのです。しかし、「君の意見は、よくわかった。まったく、そのとおりだ」と嘘をつくわけにもいきません。一方的に喋りまくるという行為が一種の“壁”を作っていることに、彼は気づかないんですね。
そのC君が数年前、ネズミ講まがいの悪徳商法にひっかかって、ン百万円損をしたと聞きました。けっして頭も悪くない彼が、どうして単純な悪徳商法に引っかかったのか、不思議に思ったのですが、同時に、やっぱりそうなったかと、納得する思いも心には生じました。
ここからは、想像なんですが、悪徳業者というのはプロですから、被害者になりそうな人間をいろいろと研究してくるはずです。そして、C君のようなタイプだったら、壁の内側に入ってしまえば、簡単に攻め落とすことができると考えたのではないでしょうか。そんな手でアプローチされると、C君なんかは、
〈ああ、僕の考えをわかってくれる人もいるんだ……〉
と、全面的に相手を信用してしまうんじゃないかな。
バブルの頃に、地上げ屋さんから話を聞いたことがあります。当時、地上げ屋というと、立ち退きに応じない住民の家にダンプカーで突っ込んだりして、悪評が高かったのですが、私が話を聞いた地上げ屋氏は、
「私くらいのプロになると、相手に感謝されながら、立ち退いてもらえるんですな」
と、言うのですよ。脅かしたりは、絶対にしない。相手の家に通いつめて、徹底的に話を聞くんだそうです。そうするうちに相手も少しは気を許して、自分のことを話すようになる。たとえば、こんなことも言うようになる。
「ほんとは、こんな都会のごみごみしたところじゃなくて、故郷に近い、海の見えるようなとこに住みたいんだけどねえ。ただ、年を取ると、あんまり不便な田舎も困るけど」
そういった話を聞くと、地上げ屋氏は、ぴったりあった土地を探してくる。今住んでいる家を立ち退いたお金で、海に近い土地を買って、家を建てることができるし、いや、お釣りがくるくらいだから、悠々自適の老後が送れると、数字を挙げて、話をするのです。気を許した相手から、そこまでされると、かなりの人間がコロぶ。
とくに、当時、地上げの対象となる地域に住んでいたのは高齢者が多かった。高齢者は心の“壁”を高くしている。その壁の内側に入ってしまうと、自分の味方だと思って、全面的に信用してしまうんですね。地上げ屋だけでなく、高齢者向けの詐欺、悪徳商法を働く連中も、似たようなアプローチの仕方をするみたいですけどね。
「私たちは、夢を売る商売をしてるんです」
高そうなスーツを着込んだ地上げ屋氏は、そうおっしゃっていましたが……。
ン百万円を損したC君は、つくづくといった感じで言っておりました。
「ダマされた頃は、仕事が忙しかったりして、友達と会って話をしたりすることもほとんどなかった。やっぱり、いろんな人の意見を聞くなきゃいけないよなあ」
そう、そうなんですよ、C君。損得とは関係なくつきあっている友人の話には耳を傾けなければならんのですよ。今後、彼が大きな災難に遭わないことを、私は心から祈っております。
心に壁を作っていると、柔軟で幅の広い発想ができなくなります。また、悪意を持って近づいてくる相手が、壁の内側にもぐりこんだ時は、大変なことになります。
凡人には、まったく壁(固定観念)のない人生なんて送れっこありませんが、できるだけ低いものにしておいたほうがいいんじゃないかな。でも、どうやったら、壁を低くできるのか?
私が見たところ、高い壁を作っている人は、他人の話に耳を傾けない傾向があるみたいです。また、自分の足を使って現地まで行き、自分の目で何が起こっているのか確かめてみるのを面倒くさがる人に多いみたいな気もします。そうです。インターネットのHPを見て、自分の意見とは違うものを見つけると、頭に血が上ってしまうあなた。パソコンの画面を見るだけで、外に出るのが嫌いなあなた。もし、あなたの毎日がそんなふうにして続くのなら、壁はどんどん高くなりますよ。
「バカの壁」というのは、血管に付着するコレステロールみたいに、日々の生活の中で、どんどん厚く高くなっていくみたいです。そこで最後に、今月の標語を一つ。
「“バカの壁”は生活習慣病です」