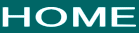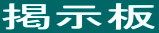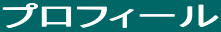月刊エッセイ 7/17/2003
■ 『鎖された旅券』−−小説タイトル考(後編)
今月もまた小説のタイトルについてであります。
前回は、『悲しみよ、こんにちは』などサガンの作品を例にとって、正反対のイメージを持つ言葉を組み合わせるタイトルの効果について少し書いてみました。
現実世界では、「悲しみ」みたいなものに、「ああ、よくいらっしゃいました。どうもどうも、こんにちは」と歓迎する人は、まずいません。ですから『悲しみよ、さようなら』とするのが自然なネーミングなのですね。しかし、『悲しみよ、さようなら』とか『悲しみよ、あっちへ行け』なんてタイトルの本が書店の店頭に並んでいたとしても、当たり前すぎて、人の気持を捕まえることはできません。あくまでも『悲しみよ、こんにちは』だから、人は、
〈なんだ、こりゃ……〉
と引っかかって、つい注意を向けてしまったりするのです。
こんなふうにイメージの正反対の言葉を組み合わせるタイトルは、本の世界ではしばしば使われている技法なのです。たとえば、かつてベトナム戦争を描いて話題になった開高健さんの『輝ける闇』なんてのが、そうですね。これは強烈なタイトルだと思います。闇は光のない世界なのに、光を放って輝いている。真っ黒な輝きとでも言いましょうか、本のタイトルから閃光が放たれているような気がして、つい目がそちらに釘づけになってしまうじゃありませんか。
じつは、この手法、私もよく使わせてもらっています。とくに1990年代の前半にこれを多用し、『白い手の錬金術』『鎖された旅券』『ガラスの王』などのタイトルを自作につけました。つまり、「錬金術」なんてのは半ばインチキみたいなものですから、本来は「黒い手」であるはず。「旅券」は、それを持っていれば世界各地に行くことができますから開かれたイメージのものです。そこに「鎖された」という言葉をつけることで、「飛べない鳥」みたいな感じになってくる。「王」様は鉄のように強いのが普通ですが、割れやすい「ガラス」をくっつけることにより、当時の(今もかな)ひ弱な大学生を表現しようとしたのです。
こうしたタイトルをつけた私の本は、売れて増刷になった、はたまた惨敗したと、販売成績はさまざまでしたが、題名としては、気に入っているものが多いんですね。正反対のイメージを持つ言葉を組み合わせることにより、人の注意をひきつけるという手法は、小説のタイトルだけでなく、商品のネーミングなど、さまざまなところに応用が効きます。皆さんも、ネーミングに行き詰まった時など、この手法を試してみてはいかがですか。
今まで述べたやり方とは違い、同じイメージの言葉をくっつけることで、威力を増そうとする手法もあります。私の場合、『真冬の誘拐者』『秋の殺人者』などがそうで、こっちのほうが広く使われている手法なんですね。もっとも、最近は『GO』『最悪』『秘密』といったふうに、ワン・ワードで勝負みたいなタイトルが流行りらしくて、うん、売れている作品が多いから、まあ、いいんだろうけど、個人的には、どこか手を抜いている感じがして、あまり好きになれないんですけどねえ……。
「本岡さん、今度は、ちょっと動きのあるタイトルにしましょうよ」
と、編集者から言われることもあります。動きのあるタイトルというのは、ごろんとしたジャガイモとかダイコンみたいなやつでなく、えーと、例を出しましょうか、有名な作としては『ライ麦畑でつかまえて』『アルジャーノンに花束を』『赤頭巾ちゃん気をつけて』『限りなく透明に近いブルー』といったような躍動感のあるタイトルなんですね。上手くいくと、これはとてつもない威力を発揮する。村上龍さんの『限りなく透明に近いブルー』が出版されてセンセーションを呼んだ時には、その内容ばかりではなく、タイトルの上手さも業界では話題になったものです。
不朽の青春小説と呼ばれているサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』には、思い出があります。恥を忍んで申し上げますと、大学生の頃の私は、この小説をかなりエッチなものと勝手に想像して買ったような気がします。つまり、好きな女の子をライ麦畑でつかまえて、麦畑の中でイイことするような内容じゃないかって……。
だって、歌にもうたわれてるじゃありませんか。「誰かさんと誰かさんが麦畑−−」なんて。男性ホルモンが過剰なほど分泌されていた青春期の頃は、「麦畑」と聞くと、自動的に想像をそちらのほうに働かせていたようなのです。
ところで『ライ麦畑でつかまえて』って、どんな内容でしたっけ。間違いなく読んだはずなのに、内容はまったく憶えていないのです。中身は記憶に残してないのに、本を読んだ動機とタイトルだけはしっかり憶えている。つまりは、それほど威力のある題名だったというわけですね。
『限りなく透明に近いブルー』や『ライ麦畑でつかまえて』のように動きのあるタイトルは、上手くいった場合の威力が格段に大きい。でも、作るのが難しくて、私に関しては、今までにぴったりくるタイトルが思いついたためしがなく、最期には諦め、いつものようにジャガイモやダイコンみたいにごろんとした題名をつけているんです。
結局『窒息地帯』となった小説のタイトルを考えていた時は、
「『湿地帯、燃えて』なんて、どうだろうねえ」
と提案して、インパクトが弱いと、編集者から即座に却下されたし、『鎖された旅券』の時は、
「『幸福への赤い旅券』ってのを考えたんだけど」
「似たような映画のタイトルがあったんじゃないですか」
となって、どれも上手くいきません。私には、ネーミングの才能がないんです。
しかし、他の作家の方も同じらしく、書店の店頭に並んでいる本も、動きのあるタイトルが付けられているものは少なく、この手法の難しさが窺えます。
タイトルがなかなか決まらなかったり、出版社サイドに押し切られたりすると、作家の側がブチブチと不満を漏らすことも珍しくはありません。以前、タイトルに「か」という1文字を加えるかどうかで大揉めとなり、編集者と作家が険悪な状態になったいう(どんなタイトルかは、ここで書いてしまうと、当事者がわかってしまうので、特に秘す)話も伝え聞きました。
私の場合は、タイトル決定については、比較的おうようなほうだと思います。お互い、論を尽くしたのなら、出版社サイドの主張するタイトルに決まっても、あまり文句は言いません。ただし、タイトルの根本部分から意見が異なった場合は、事態はちょっとばかり難しいものとなります。
先年、出版した『絶対零度』は、私が考えていたタイトルは『光を!』でした。私としては、人生のどん底まで突き落とされた男が光を求めて彷徨い、再生する物語を書いているつもりでした。ミステリーとは異なるスタンスでした。しかし、出版社としては、ミステリーとして売りたかった。つまり、作家と出版社が考えていることが根本から異なっていたのですね。同床異夢とでもいいましょうか、こうした作家と出版社の関係はけっして幸せではないはずで、いろいろ考えさせられるところの多い仕事ではありました。
こんなふうに、本のタイトル付けというのは、なかなかに大変なもので、作家も出版社も頭を悩ますのですが、そんな労苦に冷や水をかけるようなことを、友人のA君が言ったのです。
「本岡さん。間違いです。タイトルの良し悪しで本の売れ行きが決まるんじゃありません。売れた本のタイトルが、良く見えるだけなんですよ。競馬だって、そうでしょ。大レースに勝った馬の名前は、強そうに見える。もし、クラシックに勝っていなければ、ライスシャワーなんて農協の精米機みたいだし、トウカイテイオーはまるで街道ヤクザの親分じゃないですか。だいたい、あれだけ売れた『アルジャーノンに花束を』にしたって、冷静に見てみれば、センスもインパクトもないタイトルじゃありませんか」
私が上手く反論できないでいると、彼は調子に乗ります。
「出る本、出る本がベストセラーになる宮部みゆきにしたって、タイトルは、そんなに素晴らしいもんじゃない。『火車』『理由』に『クロスファイアー』なんての、ほんとフツーのタイトルです」
なるほど、宮部さんの小説のタイトルは、どれも悪くはないのですが、〈あ、やられた〉と感服するようなものはありません。酒に酔っていたA君の発言はさらに過激になってゆきます。
「宮部みゆきの名前があれば、題名が「あ」だって「い」だって「う」だって売れるんです。出版社がベストセラーを出したいんなら、宮辺みゆきとかいう新人をデビューさせればいいんです。読者が間違って買いますよ」
「そりゃ、その昔、大人気だったエノケンと間違えるだろうと、エノケソ(そ)という芸名で興行を打った喜劇役者がいたそうだけど、今の時代、そんなことしたら、ソク訴えられるぞ」
「だったら、本物の宮部みゆきを探してくるんですよ。広い日本だ、もう一人くらい宮部みゆきという名前の女の人、実在してるでしょ。本名だったら、どこも文句を言えないはずだから、本岡さん、あんたが本を書いて、その人の名義で出版すればいい」
もう、めちゃくちゃでした。
まあ、冷静になって考えてみれば、「売れている本の題名が良く見えるだけ」というA君の主張にも一理あって、もしかすると、タイトル付けに四苦八苦している作者や出版社は無駄な努力をしているのかもしれません。しかし、タイトルというのは本の題名ですから(なにか『スターというのは、なにしろ星ですからねえ』と発言した長嶋サンに似てきたなあ、大丈夫かなあ)、やはり良いものを付けてやりたいと思うのは、産みの親としては当然のことではないでしょうか。
今書いている長編小説にしても『掟』という仮のタイトルが良いものかどうか難しいところですし、企画中の短編集にしたって、短編の一本を全体のタイトルにするか、全体のタイトルを新たに考えるか、頭を悩ませているところです。
というわけで、小説の中身と比べれば、ほんの僅かな文字数のタイトルですが、作家や出版社がいろいろ苦労しているということが、おわかりでしょうか。では、では。