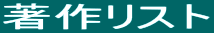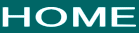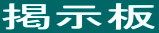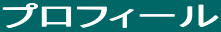月刊エッセイ 6/16/2003
■ 『ブラームスはお好き』−−小説タイトル考(前編)
今年はブラームスの生誕170 年なんだそうで、クラシック音楽業界では、ブラームスの曲を選んだコンサートが数多く開かれています。じつは私、クラシック音楽の中ではブラームスがいちばんのご贔屓なのでありまして、それゆえ、ビンボー人の私にとっては巨額ともいえるお金を払ってサントリー・ホールにロリン・マゼール指揮のバイエルン放送交響楽団演ずるバイオリン協奏曲や交響曲4番を聴きにいったり、はたまたその対極ともいうべき地元のアマチュア・オケの交響曲3番を聴いたりして、さらには今週末には交響曲1番と3番を聴きに行く予定になっておるのです。
これだけブラームス大豊作の年なら、さぞや私めが喜んでいるだろうと、皆さんはお思いでしょうね。じつは、私も今年は愉しめるぞと、コンサート・スケジュールを見ながら胸躍らせていたのですが、いろいろ聴いてみると、そんなに愉しくはないんです。説明がちょっと難しいんですが、好きな曲には「これがベスト演奏だ」という固定観念みたいなものが頭の中にできあがっていて、それ以外のものを聴いたりすると、どこかで拒絶反応が起こってしまうのです。
たとえば、交響曲4番は、その昔レコード(CDではないよ)で聴いたブルーノ・ワルター指揮のコロンビア交響楽団の演奏がベストで、それが頭の中に残っているものですから、現代の名指揮者の一人であるロリン・マゼールの4番を生で聴いても(巨象の大群が全力疾走するみたいに迫力満点の演奏でしたが)、イマイチ感動できないんです。つまりは、いちばん好きな世界には新入りが参入するのが難しいということなんでしょうが、これは他の分野にも当てはまりそうですね。
日本的で尽くすタイプの女性と恋愛して、彼女は自分にとって満点の女だと思っていたのに、不慮の事故かなにかで死別した場合、次の恋人も同じタイプだとすると、前の彼女と比べてしまって、どうしても不満が生ずるそうです。そんな場合には、まったく別なタイプ、外向的で自由な女性を恋人にしたりすると、前の彼女と比較もしないし、また新鮮感もあったりして、上手くいくんだとか−−えーと、私は何の話をしてたんだろう。女性論を展開するつもりも、演奏評をするつもりもないんですよ。なんというか、ブラームスをたくさん聴いたものだから、それをマクラに振って、そう『ブラームスはお好き』というフランソワーズ・サガンの小説のタイトルに移って、さらには小説のタイトルについて、あれこれ書こうと思ってたんですよ。ちょっと、回りくどかったかな。
小説家にとって、自作のタイトルをどうするかは、大きな問題なのであります。小説は上手く書けたのに、ぴったりするタイトルが浮かばず、ウンウン言うのはよくあることですが、この点で、フランソワーズ・サガンはセンス抜群の人だと思っております(翻訳者のタイトル訳がすばらしいのだ、という説もありますけど)。デビュー作の『悲しみよ、こんにちは』からして、インパクトが非常に強い。新人にとっては、与える印象を強くすることが世の注目を集める必要条件なのですが、この点で、大きな成功をおさめている。続く『ブラームスはお好き』も良いタイトルだし、さらに続々と出版されていく『冷たい水の中の小さな太陽』とか『愛と同じくらい孤独』なんてのも、恋愛モノとしてセンスを感じさせられるもので、つい手にとってしまいたくなります。
もう、ずーっと昔のことになりますが、私が大学を卒業して、某出版社の某女性誌編集部に配属された時、ちょうど『愛と同じくらい孤独』が発売されました。雑誌記事のタイトル付けに苦労していた編集者が集まった会議の席でも、この本のタイトルが話題になって、皆で似たようなものを考えてみようということになりました。しかし『愛と同じくらい幸福』という平凡極まりないものから始まり、『愛と同じくらいの性生活』『愛とおなじくらいお金』『愛と同じくらい毎日のお献立』など、ろくなタイトルが出てこずに、結曲、自分たちのセンスのなさを思い知らされたのでした。
「さすがは、サガンだねえ」
「そう、さすがはサガン。どのタイトルも、すばらしい」
「なんだか、意味はよくわからないけど、迫ってくるんだよねえ」
そんな会話が交わされたのを憶えています。
実際、サガンの本のタイトルは、冷静に考えてみると、意味がよくわかりません。『愛と同じくらい孤独』だって、どの程度の孤独なんだかさっぱりわからないし、『悲しみよ、こんにちは』というけれど、私は「悲しみ」になんかにわざわざ「こんにちは」と言いたくありません。『ブラームスはお好き』と問われれば、「はい」と答えますけど、『冷たい水の中の小さな太陽』と言われれば、「非科学的に過ぎる」と反論したくもなります。でも、小説のタイトルとしては、これが感覚的にぴったりくる。
こうした「感覚で勝負!」といったタイトル付けは、女流作家の独壇場のようで、ここ数年で私が感心したのは、林真理子さんの『不機嫌な果実』とか、山本文緒さんの『恋愛中毒』とか、女性の作品ばかりです。対して、男性作家は、どうしても直接的なタイトルになり、私なんかも、
〈よーし、今度は、雰囲気出すぞ〉
と意気込んでも、出てくるものは『「不要」の刻印』『絶対零度』などという、ジャガイモがごろごろ転がっているみたいなタイトルになってしまいます。
しかし、サガンのタイトルには、感覚的なすばらしさだけでなく、人を惹きつける別のテクニックも使われています。『ブラームスはお好き』は除くことにして、『悲しみよ、こんにちは』『冷たい水の中の小さな太陽』『愛と同じくらい孤独』の3つから、そのテクニックを探り当ててください。解答は、今月のエッセイの末尾に記しておくことにいたしましょう。
ところで、こうした小説の顔とでもいうべきタイトル、どんなふうに付けられるのか、ご存じでしょうか。いや、もっとわかりやすくいうなら、タイトルを付ける権利は誰が持っているのか、ご存じでしょうか。
じつは、私もよくわかっていないんです。タイトルが決まる過程も、その時その時でまちまちだし、タイトルを付ける権利も、作者側にあるのか出版社側にあるのか、判然としていないんです。ふつうは、まず作者がタイトル候補を担当編集者に伝え、二人であれやこれや協議する。それが出版会議にかけられ、正式決定するのですけど、いつもそうとも限らない。我が業界の通例となっている「力のある側の意向が通ってしまう」という論理が、ここでもまかり通ってしまうんですね。
たとえば、私の最初の長編小説には『飛車角歩殺人事件』という、なんとも珍妙なタイトルがつけられています。じつは、これ、私がまったく与り知らぬところで決まった題名なんですよ。
プロ将棋の世界で次々と人が殺されるという、このミステリー、今となってはもうすっかり忘れてしまったのですが、私はいくつかのタイトル候補名を担当編集者に提案し、彼はそれをひっさげて出版会議に臨んだはずです。しかるに、会議終了後に私のところにかかってきた電話。
「いやあ、びっくりするような題名になっちゃんたんですよ」
含み笑いの声が、今も耳に残っています。
「決定タイトルは、へへへ、『飛車角歩殺人事件』」
「なんですか、そりゃあ……」
「飛車の駒が送られてきて、最初の殺人が起こり、次は角の駒でまた殺され、3人目は歩の駒でしょ、だから、『飛車角歩殺人事件』」
私ではありません、上司がつけたんです、と、担当編集者。その上司という方、小説の中身のほうはまったく知らず、部下に「どんな内容だ」と訊き、概要の説明を受けると、エイヤーッとばかりにタイトルをつけてしまったんだそうです。
呆然としましたが、まだ1冊の本も出していない駆け出し作家に拒否権はありません。「嫌だ」と抵抗したら、出版してくれないに違いありません。泣く泣く、その題名で行くことにしました。
ですが、世の中は皮肉なもので、『飛車角歩殺人事件』はそこそこの売れ行きとなって重版がかかり、また、その小説を読んだ他社の編集者からの注文も入るという結果を生んだのです。だけどねえ、記念すべき最初の本が『飛車角歩殺人事件』だなんて、大きな声では言えないよなあ、サガンの『悲しみよ、こんにちは』とは比べてしまうと、顔が赤くなりますよ……。
どんどん本が出版されて、どれも売れた1980年代の“出版黄金時代”には、半ば勢いでタイトルがつけられたことも多々あったようです。とくに新書判ノベルズの場合は『殺人事件』とつけば売れ行きが良かったから、なんでもかんでも『○○殺人事件』になってしまった。話題作が出ると、それと共通点を持つタイトルがつけられ、たしか高橋克彦さんの『写楽殺人事件』が江戸川乱歩賞をとって大ベストセラーになった直後、別な作家の方が出した本が『歌麿殺人事件』で、これまた売れたと記憶しております。西村京太郎さんが列車を題名にしたトラベル・ミステリーを売りまくると、他の作家が出す本も列車名ばかりになり、JRの特急列車に乗ると必ず殺人事件に出っくわすのではないかとの錯覚に陥る事態となりました。小説のタイトルも、流行りものの一つとなったというわけです。
しかし、小説のタイトルが流行りものになると、その弊害も現れてきます。私、新書判ノベルズで出した時には『武蔵野0.82t 殺人事件』というタイトルだったものを、文庫にする時、『飛鐘伝説殺人事件』と改題したことがあります。というのも、ノベルズを出版した時には『特急××1/60秒の殺意』とか『○○駅2分23秒の死角』とか(正式題名をはっきりは憶えていないけど)そういったタイトルの本が売れてたんですね。それゆえ、編集部の方が、数字付きでいきましょうよ、と言うのです。私が書いたそのミステリーは、お寺の釣鐘が空を飛んで行き、人を押し潰して殺すという荒唐無稽な作品でした。
「で、本岡さん、釣鐘ってのは、どのくらいの重さがあるんでしょう」
「800 キロ前後のものが多いと訊いてますけど」
「じゃあ、0.8 トンか。うーん、どうせだったら、もう少し細かくいったほうがいいかもしれませんねえ」
なんていう会話が交わされて、結果、『武蔵野0.82t 殺人事件』になったというわけです。
ところが、文庫版が出るころには、もう“数字ブーム”はどこへやら。で、『武蔵野0.82t 殺人事件』では何の意味だかわからない、という意見が出て、『飛鐘伝説殺人事件』に変えられたのであります。
表紙に注釈は入れておきましたが、文庫化する時の「改題」なんて、あまり褒められたことではありません。今後、本を出す時には、流行りものではないタイトルをつけたいと考えております。
さて、先に出しました問題の解答であります。『悲しみよ、こんにちは』『冷たい水の中の小さな太陽』『愛と同じくらい孤独』に共通するテクニックは、おわかりになりましたか?
それは、正反対のイメージを持つ言葉を上手くつなげて1つのタイトルにするというテクニックなのであります。「悲しみ」は陰気なイメージを持つもので、「こんにちは」という陽気なイメージとは正反対。「冷たい水の中」は寒色系だし、一方、小さくたって「太陽」は暖色系。「愛」は恋人同士の愛でも人類愛でも複数の人間で共有するものであって、孤独とは対極に位置するものです。こんなふうに正反対のものをくっつけることで、疑問効果みたいなものが生まれ、読者の心を惹きつけるのです。
来月は、こうしたテクニックなどを含め、小説のタイトルについてのさまざまな側面を書き進めてみたいと思います。では。