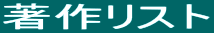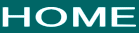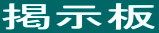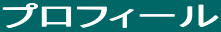月刊エッセイ 5/17/2003
■ フリーランサーとは何か(後編)
類は友を呼ぶといいますか(ダジャレじゃありませんよ)、フリーランサーをしていると、カメラマン、ライター、落語家、棋士、画家、翻訳家などなど、やはりフリーランサーしてる友人・知人はたくさんおりますが、一般にはフリーという職業は珍しいらしく、さまざまな質問を受けます。そのうち、よく受ける質問を選んで、あれやこれやお話しをして、今回は最終回であります。
「どうやったら、フリーになれるんですか」
おいおいおい、なんて質問するんだ、と思ってしまいます。フリーなんて、自分が「私はフリーのカメラマンです」と宣言すれば、それでフリーランサーになれるわけじゃありませんか。医師や弁護士などとは違い、法律で定められた資格が必要だというわけではないんですよ。
でも、気持はわかります。本屋に行けば「○○になる法」なんて本や雑誌が売られているわけですから、きっとさまざまなフリー職業に就くためのコースがあると思われているんでしょうね。たとえば、翻訳家ならば、専門学校に通って技術を習得するとか、プロに弟子入りして下訳をこなすとかね。
言っちゃいましょう。たしかに、そうしたコースはあります。もっと踏み込んで言うなら“手続き”と“コネ”がけっこう大きな比重を占めていたんですよ。「いたんです」と過去形を使ったのは、今は手続きとコネが通用しなくなりつつあるからなんですね。
たとえば、フリーのカメラマンになる典型的なコースは次のようなものでした。まず写真学校を卒業してから、プロ・カメラマンに弟子入りして、助手として働く。助手というのは労働基準法も最低賃金法も適用されないような過酷な世界ですが、そうした手続きを踏んで働いているうち、雑誌社の編集者とコネができます。そして、頃合いを見計らって独立、知り合いになった編集者から仕事をもらって数をこなすうち、腕前も上がり、めでたく一人前になるというわけです。
いーや、1970年代、80年代の人手不足の時代には、そうした面倒くさい手続きなんてのが省かれて、コネだけで出版の世界に入りこんできた人も少なからずいたようです。歌舞伎町のバーで水割りを作っていたバーテンさんが、呑みに来た雑誌編集者に「おい、酒作って暇があったら、仕事手伝ってくれよ」と言われて、翌日にはシェーカーではなくペンを持って取材に走り回っていたという話も聞いたことがあります。ああ、そうだ、知り合いに“対人恐怖”の気があるライターさんがおりました。初対面の人に次々会わなければならない職業の人間が対人恐怖症とはおかしな話ですが、ふつうの会社に就職できず、コネを頼りに雑誌の世界に入ったというわけです。なにしろ、人と喋るのが苦手というんですから、ろくな仕事もできなかったでしょうが、なんとかライターをやっていたのですから、今思えば不思議な時代でした。そいうえば、牛が就職面接に訪れ「人間だったらよかったのにね」と言われている就職情報誌のテレビCMが流れてたのも、この頃だったな……。
作家だって、コネが必要だと思われていたようです。私はパーティーが大嫌いで、各種の文学賞パーティーにも出ない人間ですが、ある編集者から、
「本岡さん、パーティーには積極的に出て、編集者との顔つなぎをしたほうがいいよ」
そう忠告を受けたこともあります。しかし、コネというのは短期的には威力を発揮しても中長期的にはあまり意味がないと、私は考えているものですから、彼の忠告はありがたいとは思いつつ、しかし、パーティーには相変わらず出ておりません。
しかし、そうした“手続き”と“コネ”が幅を効かす時代は終わりに近づいているみたいです。手続きという形式的なものや、コネという日本的なものが生き残っていけるほど、甘い時代ではなくなったというわけですね。
先日、ある編集プロダクションの社長と話をしていた時、
「もう、もう雑誌の下請け取材を受けている時代じゃないですよ。ページ単価はカットされるし、締め切りまでの日時も大幅に削られて、まともな取材ができゃしない。下請けじゃなくて、こっちからいろんな会社に企画を持ちこんで、フィフティー・フィフティーの関係でやっていかなきゃ展望が開けないですよ」
と言われました。
そういえば、ハリー・ポッターの作者も、コネなし手続きなしの身で、何社も出版社をまわり、ようやく出版にこぎつけ、あれだけのヒットを飛ばしたのです。この先、日本も欧米と似た環境になっていくことでしょう。
「フリーは、なんたって体力だね」
これは外の人間から受ける質問ではなく、フリーランサー自身がよく発する言葉です。なにしろ、フリーというのは個人事業主ですから、労働基準法など適用にならず、どれほど長い時間働いたってお咎めは受けません。それゆえ、体力がある人間ほど収入が多くなるのは自明の理ではあります。
二十何年か前になります。とくに有名な人でもないのに、当時もう年収一千万円を軽く超えているカメラマンの方がおりました。彼はどんな仕事も断らず、いつもニコニコ笑みを絶やさず、朝から夜中まで重いカメラバックをかついで現場から現場へと移動しておりました。あーでなくちゃ、フリーは勤まらないのかと、サラリーマン編集者だった私は、溜め息をつきながら見ていたものです。
たしかに、どんな世界でも、体力がないより、あったほうがいいに決まっています。しかし、サラリーマンとは違って、フリー・ランサーは自分で自分の仕事量を決めることができるので、やり方によっては、体力がなくてもやっていけるのが、この世界の面白いところです。
じつは、私の場合、体力的に自信がないため、フリーの道を選んだという面もあります。昔から、どちらかと言えば虚弱な体質で、季節の変わり目には体調を崩して、学校を休んだりもしていました。とくに、出版社に入って、週刊誌に人事異動になってからが辛かった。
週刊誌の仕事というのは、週に一度は締切りで徹夜になります。徹夜の日は朝の5時くらいになると、頭がボーッとして、原稿の直しも小見出しをつけるのも、かなり怪しくなる。しかし、同僚たちは元気いっぱいいつもと変わりなく仕事してるんですな。しかも、早朝、ようやく原稿を印刷所に送り終えると、誰かが、
「おーい、これから築地に鮨、食いに行こうよ」
と声をかけ、同調する者たちは、いっせいに朝食に出かけるのです。よくまあ、わざわざ築地まで行って食事をする体力が残っているものだ。むろん、私は仮眠室に直行です。こうした状況を前にして、私は決意したのです。同じ土俵で闘っては、勝負にならない、と。で、フリーに転身したという部分もあるんですよ。
全盛期の笹沢左保さんが月に千枚の原稿を書き、眠らないよう、座らずに立ったままペンを走らせていたというのは有名な話です。が、体力にまかせて仕事を続けていた(ついでに酒も浴びるほど飲んでいた)フリーランサーが60歳を前にしてポックリ逝った話も、よく聞きます。まあ、塞翁が馬で、人間、何が幸不幸を分けるかわからないということなんでしょうね。
「フリーで食えなくなったら、どうするんです」
いやあ、胸にグサッとくる質問ですね。勤め先が無くなったからフリーになったという話は時々聞きますが、逆は成立するんでしょうか。長年、野放図な生活をしていた人間を雇ってくれるところがあるんでしょうか。
いや、かつては、フリーをやめた人間が避難する場所がなくもなかったんですよ。それは、大学の先生。
新設大学が雨の後のキノコみたいに生えた時代、教員が足りなくて、よくフリーの人間が専任講師や助教授として迎えられたりしたものです。私の知り合いにも、外国から帰ってぶらぶらしたのが、次に会ったら地方大学の助教授の名刺を持っていたなんてことがありましたし。
なにしろ大学教授になるには、教員免許が必要ありませんから、ある分野でそれなりの実績を示せば、採用されてた。私にしても、40歳になったかならない頃、ある大手出版社の編集者から、こんなことを言われました。
「○○女子大から、文学部の助教授を推薦してほしいと頼まれましてね。本岡さんの名前を出したんだけど、むこうは、もっとお歳を召した人を望んでたみたいで」
作家なんて何をやるかわからない。だから、若い作家だと、うちの学生に手を出すかもしれないと、女子大当局は危惧したのでしょう。私の助教授就任は露と消えてしまったのですが、昔は、こんな話そう珍しくもなかったような気がします。
しかし、今は、若い世代の減少で、大学の倒産が言われている時代です。有名人なら、学生を集めるのに役立つということで、教授に迎え入れられるようですが、フリーランサー崩れなどに職を提供してくれる学校はまずないと思われます。
だったら、フリーランサーとして失敗したならば、どうなるのか。うーん、「ホームレス作家」なんて本を書いた人もいるし、某芥川賞作家がホームレス寸前だという話も聞いたし……。
でもねえ、フリーランサーとホームレスの違いって、どこにあるんでしょうか。私の友人の友人に、さる雑誌が廃刊になってから3年間、まったく仕事をしていないというイラストレーターがいます。一方、ホームレスは古雑誌を集めて専門の業者に売ったり、ダフ屋から頼まれて巨人戦のチケットを買う行列に加わったりと、いろいろ仕事をしているみたいです。つまりは、フリーランサーとホームレスは、住む家があるかないかの違いしかないのではないでしょうか。
おやおや、なにか話が暗くなってきましたねえ。でも、現実に、フリーランサーの多くは、
〈今の仕事がだめになったら、どうしよう……〉
などと深刻にはなっていないのです(たぶん)。フリーの生活を続けているうち、精神的にタフになっていて、
〈まあ、なんとかなるだろう。そのうち、寿命もつきて、この世ともお別れもできるだろうし……〉
と考えているはずです。タフでなきゃ、こんな不安定な職業、長く続けていられわけがないのです。これが結論。
さて、3回にわたり、フリーランサーなるものの正体を明かしてみました。どうです、あなた、参考になりましたか。そう、そこで悩んでいるあなたですよ。
〈給料は上がらないし、人手が減らされて、仕事もきつくなってるからなあ。もう会社やめて、フリーになっちゃおうか……〉
どうですか、これでもフリーランサーなりたいですか? フリーランサーには、向き不向きがあります。少なくとも、3月号のエッセイの最初の質問をしそうな方は、あんまり向いていないと思いますけどねえ、念のため。