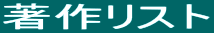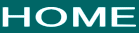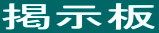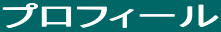月刊エッセイ 4/19/2003
■ フリーランサーとは何か(中編)
先月は、「作家やっていくには、年にどのくらい稼がなければならないんですか」「フリーはいいなあ。自分の好きなように仕事ができるんだから」という、よく言われる二つの質問、感想から、フリーランサーというのは、いったいどんな種族なのか、その実態を書いてみました。今月は、その第2弾です。
「定年ないんでしょ。いいよなあ、フリーは」
これはサラリーマンの友人からしみじみと言われる言葉です。サラリーマンには60歳という定年があります。いや、最近では、リストラとか子会社への完全転籍なんてのが多くなって、私の大学時代の友人の多くも50歳にさしかかるあたりから、今までの会社とは異なる名刺を差し出すようになっています。どんなに気に入っていた仕事でも、定年になれば、離れるしかない。だから、理解はできるんです。
でも、違うんだなあ。フリーの世界には、サラリーマンよりもっと厳しい“定年制”というのがあるんですよ。
ひところ「フリーランサー35歳定年制」なる言葉が囁かれていました。フリーの職業、とくに漫画家、ジュニア小説作家、プログラマー、コピーライター、現代風俗をレポートするライターなどは、35歳を過ぎると、時代に感覚がついていけなくなり、また体力もなくなっていくので、自然、脱落するという意味です。実際、漫画家などは、次々に新しい才能がデビューし、しかし、発表する雑誌には限りがありますから、少し古手になると、ページあたりの原稿料が高くなっている関係もあって、
「○○先生、もう、うちの雑誌では扱えないね」
という言葉とともに、ポイされる例も少なくないようです。以前、この「35歳定年制」の真偽を、ドラクエ(ゲームソフトですよ、わかってますよね)の開発を手がけている某有名プログラマーに訊いてみたことがあります。すると、
「追い込みの時期には泊まり込みも増えてくるから、並の能力の人で間はそのあたりで体がきつくなり、脱落していきますね。だけど、センスが抜群だったら、年齢なんて関係ありませんよ」
しごく、まっとうな答が返ってきました。たしかに漫画家だって、手塚治虫さんや石ノ森章太郎さんみたいな人は、亡くなる直前まで仕事してましたもんね。でも、多くの並才フリー・クリエーターやライターにとって35歳から40歳というのは、一つの関門となっているようです。
私にも経験があります。7年間にわたってサラリーマン向けの週刊誌の編集者をやって、32歳で出版社を辞めたのですが、“近頃の若い男女の生態”に疎くなっていたため、当時デート特集を売り物にしていた「ホットドッグ・プレス」誌の編集者をしていた後輩をつかまえ、
「おい、女子大生の取材をやらせろよ」
とまあ、一種の強要をしたわけです。むろん、小説の勉強のためですが、(もしかしたら、もしかして、うふふふっ)といった思いが心の一部分にはあったことも否定いたしません。
取材を始めたばかりの頃は、とくに違和感も感じず、インタビューができました。ところが、32歳からの数年間というのは、急速にオジさん化が進むんですねえ。そのうち、どうもぎこちない質問を連発する場面が多くなる。就職を控えた4年生だったらともかく、まだ高校生気分が抜けない新入1年生が相手だったら、何を訊いていいのかわからなくなって、当然、原稿の出来も悪くなる。そして、35歳になったある日、自らに引導を渡す時がやってきたのです。
その日、編集部から指示された取材対象者はひとりの女子高校生でした。「○○ちゃんを守る会」とかいうのもできている超美少女で、珍しく私も舞い上がってしまったほどでした。そして、困ったのは、その子があまり喋らない子だったこと。いやいや、私が彼女とはまったく違った空気を発散させているオジさんだったから、喋ってもらえなかったのかもしれません。こっち側とあっち側の空気が、明らかに違ったのです。喋るのは私ばかりで、心はアセリ、アセリ、額はアセ、アセであります。
原稿の出来も最悪。まあ、これが本業でもなかったので、担当編集者に
「俺、今日で引退するから」
と宣言し、私のライター生活はあっけなく幕を閉じたのでありました。
しかし、一方で、長持ちする分野がないわけではありません。医療や健康法、料理などの実用物ライターの分野がそれです。地味だし、一人前になるまで時間がかかりますが、いったん認められれば、歳をとっても仕事はついてくる。
Kさんという医学物のライターがいます。私がまだ青年だった頃、りっばな中年でしたから、私がりっぱな中年になった今、彼はもうりっぱなおジイさんになっていることでしょう。当然、ライター業は引退したかと思っていたら、健康物の雑誌などで時々、彼の名前を見るのです。まだ、やってたんだなあ。牛みたいな体格に、朴訥な性格、いつもにこにこしながら宮崎訛りの言葉を喋るKさんは、お医者さんたちに愛されていて、きっと仕事が切れることもないのでしょうね。
ほんと、この実用物の分野は息が長いです。そういえば、以前「料理の鉄人」というテレビ番組に「料理記者歴40年(だったと思うけど)、岸朝子さん」なるオバさんが出てましたね。
だったら、小説家はどうなのか? 小説家の場合、新本格派ミステリーなどの例外を除けば、30代半ば以降にデビューするのが普通ですから、35歳で定年を迎えるなんてことはありません。ただし、「毎年が定年」でもあるのですよ。
出版界が好況の時代には、本の内容さえ良ければ、同じ出版社で2冊の失敗(つまりは売れなかったということ)までは許される。3冊連続して売れなければアウトと言われていたものが、今は出版社にも余裕がなくなって、1冊惨敗すれば、次を出すのが極めて難しくなります。「あの作家は売れない」という情報は、数字となって、業界中に広まりますから、油断していると、有名な賞の受賞者であろうと、かつて話題作を出した作家であろうと、すぐに実質的な定年を迎えることになります。このあたり、小説業界はじつにクールにできております。
しかし、大ベストセラー作家となれば、話は違ってきます。どんな作家でも歳をとれば全盛期に比べて売れ行きは落ちてくるものですが、もともとのファンが多いから、まるで売れずに本を出した出版社が赤字になるというケースはまずありません。多少でも黒字が出れば、出版社としては本を出しますから、一度でも頂点を極めたような作家は“定年”になることもなしに、一生、仕事ができるわけです。
でも、筆はやはり衰えてくるので、陰口をたたかれることが多くなります。あの偉大なる松本清張氏だって、晩年の小説は、引き締まって緊張感がみなぎった全盛時代のものに比べると、ずいぶん間延びした作品が目立つようになった気がします。口の悪い文芸編集者などは、
「チョロチョロ、ダラダラ、年寄りの小便みたいな小説を書くようになってきたねえ」
ひどいことを言っておりました。
スピーチと同じで、小説も変わりばえしないことをダラダラ書くようになると、もう自主定年にしたほうがいいのではないでしょうか。しかし、自分から「もう書かないよ」とはなかなか言えないのが、小説家の性(さが)みたいなものだとは思います。
①「おまえ、フリーなんだから、幹事やってよ」
②「フリーは、みんな経費で落とせるんでしょ」
③「俺にさ、おまえの小説、ただで送ってくれよ」
上の3つは親しい友人から言われることの多い言葉で、それぞれまったく関連性を持っていないように見えますが、どれも、ある共通した“認識”がもとになっているみたいです。つまりは、フリーランサーというのは、大雑把でドンブリ勘定的な日常を送っているに違いないという認識ですね。
①は、同窓会の幹事やボランティア的な雑事を押しつけられたりする時に言われる言葉。「俺たちサラリーマンは会社に行かなければいけないけど、おまえはブラブラしてるんだろ」という意識が、言葉の裏から感じ取れます。でも、半分はそうなんだけど、半分は違うんだなあ。
たしかに、フリーランサーはよほど重要な用事が飛び込みで入らない限り、自分の予定は自分で決めることができます。ただし、サラリーマンと大きく違うのは、仕事以外の予定を入れた場合は、完全無報酬の労働になることです。
サラリーマンが平日にボランティア活動をする場合は、有給休暇を使って会社を休むことになるでしょう。つまり、ボランティアをやっても、会社からの給与は出るわけです。対して、フリーの人間が仕事を休めば、その分の収入がなくなってしまうのです。まるで、自分の羽根を抜いて織物を織った夕鶴の鶴みたいな(それほど、美しくはないか)話じゃありませんか。
時間は自由になるので、世のため、人のため、友人のために一肌脱いでやりたい気持は充分に持っていますが、やり過ぎると、貯金通帳の残高を眺めて青ざめるのが、フリーランサーという人間なのです。
②も、時々言われますねえ。豪華な食事をしたって酒を飲んだって、必要経費で落とせるからいいじゃないか、というわけです。しかし、これは大いなる誤解です。たしかに、小説家などは他人から話を聞くことも仕事の一環ですから、税務当局も取材費としてその分の税金を免除してくれます。が、誤解しないでください。わずかな税金が免除されるだけで、かかったお金がどこかから補てんされるわけではないのです。
これで年収が2000万円もあれば、「必要経費で飲み食い、ほほいのほい」と喜んでいることもできるでしょう。でも、多くのフリーランサーは貧しくて、その半分、いや三分の一以下の収入しかない者が大半ですので、飲食費などにお金を使っていると、ほんとうに必要な取材に資金がまわらないことになります。結果、必要経費で落とせるか否かに関わらず、「ほほいのほい」と喜ぶようなことはできないというわけです。まあ、ごく一部の高額所得者フリーランサーは高級外車を次々に乗り換え、経費で落としてるみたいですがねえ、少なくとも私には無縁の話であります。
③は、作家の家なら自分が書いた本は山積みになっているだろう。一冊くらいただでくれよという意味です。が、これも誤解です。
多くの人は、自分で書いた本だから、いくらでも無料で手に入るだろうと考えているみたいですが、じつは作家は自著を出版社から買い取っているのです。10冊だけは“見本”として無料で受け取る権利があるのですが、残りは定価の70%で買うことになってるんです。つまりは2000円の本なら1400円で買って、取材協力者などに贈呈しているのです。1400円といっても、塵も積もれば山となるで、冊数が増えればけっこうな金額になるので、余分の本を自宅に抱え込んでおくことはしないものなのです。
むろん、自費出版をされる方は全部の本を買い取り、また自費出版まがいの出版契約を結んだ場合は決められた冊数を作者自らが購入し、家中が自分の本だらけになるようなケースもあるみたいです。しかし、プロ作家となると、自分が書いた本は意外に持っていないものなんです。
なにか、ずいぶんとセコイこと、書いちゃったなあ。でも、これらは事実なんです。フリーランサーがずぼらな生活をしているのは事実ですが、一方で、こうしたセコイ現実に直面していることも、ご理解ください。
「フリーランサーとは何か」は二回で終わる予定でしたが、書くことがまだありますので、来月号を最終回といたします。ではでは。