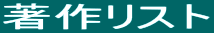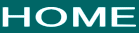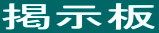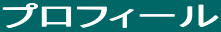月刊エッセイ 3/17/2003
■ フリーランサーとは何か(前編)
作家というのは基本的にフリーランサーであります。ところで、フリーランサーとは何ぞや、ということになって、手元の辞書(新選国語辞典・小学館)を引いてみると、「専属でない、自由契約の俳優、歌手、記者など」となっておりますが、そのとおりであっても、しかし、具体的にはどんなものなのかよくわからない。
で、今回は、フリーランサーとは、どんな人種でどんな生活をしているかを、よく訊かれる質問などを中心にして解説してみましょう。
「作家やっていくには、年にどのくらい稼がなければならないんですか?」
けっこう多いんですねえ、この質問。おもに、サラリーマンやOLといった会社勤めしている人から、この種の問いかけを受けます。きっと、勤め人の人は、まず生活のベースとなる給料をもらって日々の生活をしているから、こうした質問が出るんでしょう。
たとえば、大学を卒業したばかりの新入社員だって、基本給が20万円程度もらえて、それに各種手当てがあって、ボーナスも加えれば、年収で350 万円から400 万円くらいにはなる。そこから税金や健康保険を引かれて、残ったお金でワンルームマンションの家賃や食費、彼女とのデート代を捻出し、ピンチの月は「たまにはババーンといこうよ」というカトちゃんのCMに乗せられて消費者ローンを借りるんだろうけど、いちおうは入ってくる収入の中で生活ができるようになっているんですね。
だから、フリーランサーだって、衣食住の費用を出して、それから作家だったらパソコンなどの備品購入、取材費もかかるから、いったい年にどのくらい稼げば生活ができるのだろうかとの疑問を持つのは当然のことかとは思います。
ところが、大愚問なんだねえ、これが。なぜかと申しますと、毎年、毎年いくら収入があるのかは、ほとんど予測がつかない。その年が終わって、収支決算を締めてみなければ、黒字になっているのか否かもわからない時もあります。
たとえば、ある盲導犬の一生の写真集を出してベストセラーになったカメラマンさんがいます。彼の場合、写真集を出すため、十数年間、犬もとに通ってシャッターを切り続けたそうですが、その間、その仕事から得られた収入はなかったはずです。そして、写真集としてまとめたところ、大ベストセラーとなり、巨額の印税収入が入ってきた。
作家の収入も似たようなところがあって、私の場合も、収入から必要経費を引いてみるとマイナスになっていて、源泉徴収の税金を全額戻してもらった年もあれば、映像化権料や文庫印税が思わぬ時期にまとめて入ってきてホクホクしたりする年もあったりして(まあ、滅多にないけどね)、来年の年収の予測などまるでつかないのです。
でも、だったら、赤字の年はどうするの? どうやって生活をしているの?−−といった疑問が出てくるでしょうね。
これは、もうフリーランサー個人個人で、まったく対処の方法が違うのです。
いちばん恵まれているのは、実家がお金持の場合。私の知り合いの女流作家で、お父上がアパート一軒遺してくれたので、その上がりで悠々自適、小説を書いている方がいます。また、フリーの彫金デザイナーとか、元手のかかる商売の場合は、実家がお金持の場合が多いと聞いております。
しかし、実家がお金持でお金の心配などせずに仕事に励めるような人は、あくまで少数派です。そうでない場合は、どうやって不安定な生活を補っているのか。まず考えられるのは、アルバイトです。ある文芸評論家が講演会でこんなことを言っていたそうです。
「作家の家にいくと、必ずヘルメットとツルハシが置いてあるんです」
今はさすがにそんなことはないと思うんだけど、昔は、生活のため、道路工事のアルバイトとかしてたんでしょうねえ。
ツルハシはともかくとして、私も30代から40代の初めの頃までは、ペンを使うアルバイトをよくしていました。コラム、取材、リライトといった文筆仕事で、こういうアルバイトをしている人は数多くいます。
でも、この出版大不況、文筆バイトの数も減ってきたため、噂では肉体労働に精を出しているフリーランサーも出てきているとか。また“ヘルメットとツルハシの時代”が来るのかなあ。でも、公共工事も削減されるというし……。
また既婚者では、別な手を打つことも可能です。男性既婚者の場合、奥さんが働いているケースが多いですね。私の大学時代の友人はほぼ全員がサラリーマンになっていて、奥さんは専業主婦をやっている人がほとんどなんですが、社会に出てから知り合ったフリーランサーの方の奥さんは仕事を持っている人が大半です。そりゃ、そうでしょう。ダンナの年収が来年はいくらになるのかわからないでは、恐ろしくて専業主婦なんてやってられません。かくいう私のところも、かみさんは技術翻訳の仕事をしております。
要するに、働ける者が皆、働いていれば、そう恐いことはないわけで、私の知り合いに「本人はフリーライター、妻はフリーの作詞家、娘はフリーター、息子はフリーカメラマン(だったと思うけど)」という一家があります。全員がフリーなんだから、各々浮き沈みはあるでしょうが、一家として考えれば、安定しているみたいですね。
というわけで、どのくらい稼げばやっていけるかなんて、答えようがないんですな。
「フリーはいいなあ。自分の好きなように仕事ができるんだから」
こうした言葉も、会社勤めしている人からよく聞きます。気持は、わかります。組織に属していれば、好むと好まざると業務命令には従わざるを得ませんし、嫌いな上司ともつきあわなきゃいけないし、転勤辞令が下りれば、アフリカだってグリーンランドだって赴任しなければならない。その点、フリーランサーは命令とは無縁の世界に生きているのだから羨ましいというわけです。
でもね、フリーといっても、100 パーセント自由に仕事をやっているわけではないんですよ。作家でも自分の意見がほとんど通るのは、ごく一部のベストセラー作家くらいで、あとは編集者(と、その背後に控えている出版社の営業部員)と、あーだのこーだの意見のすり合わせをしなければならないし、中にはウマの合わない人間もいるけど、そう簡単には喧嘩もできない。けっこう忍耐強く仕事をしてるんですよ。
でも、まだ署名原稿を書ける人間はまだいいのかもしれない。辛いのは、無署名原稿(つまり、雑誌の編集部で作ったという体裁をとっている原稿です)専門で生活しているライターさんです。編集部の手足となって、編集部の要求する原稿を書かなければならない。自分では上手く書けたと思っても、記事になってみると、ずたずたに直され、元の姿などほとんど残っていない。少しでも文句を言おうものなら、
「この記事は文責・編集部なんだから、どう直そうと、こっちの勝手だ」
と一蹴され、それに対して不満の態度をあからさまにすると、次からは仕事が来なくなって、失業状態になります。ライターをはじめとして、カメラマン、レイアウトマンと、雑誌で働いているフリーランサーの8割、9割が、こうした立場の人ですから、フリーとはいえ、宮仕えよりも自由度が低く、ストレスもたまるのかもしれません。
しかし、その一方で、どんなに立場の弱いフリーランサーだって、自分の仕事は自分で選択できるという自由は持っています。
「もう芸能人のスキャンダルを追いかけるのは、嫌だ。環境問題の取材を専門にやるぞ」
と決心すれば、そっち方面の取材者になることができます。ただし、取材の依頼が来るとは限らないのが難しいところですけど。
私にしたって、プロとしてのスタートはユーモア・ミステリーやトリック・ミステリーでした。それが、いつしか社会的なテーマの強いミステリーやブラック・ユーモアの短編へと変わり、思うところあって、今は“脱ミステリー”を目指しております。
こうした点、「人事課に行け」と命ぜられればリストラの手伝いをしなければならないし、アラスカ支店行きの辞令が出ればエスキモーにクーラーを売り歩かなければならないサラリーマンよりは気楽だとは思います。
とはいえ、“専門替え”には、思わぬ落とし穴が待っていることがあります。その昔、ある動物写真専門の写真家がおりました。狸や鹿といった日本の野生動物ばかり撮っていたのですが、収入が少なくて、生活できない。そこで、自らの意思を曲げ、需要の多い芸能人の写真を撮ることにしました。
そして、女性のタレントを撮るという初仕事の日、彼は服装を整え、勇んで撮影現場に出かけました。そこまではよかったんですが、たった一つだけうっかりしていた点があった。新しい名刺を作っていなかったんですね。
彼はカメラマンのこういう者ですと自己紹介して、自分の名刺を手渡したそうです。そのとたん、女性タレントが目を白黒させた。なぜって、名刺には「動物写真家」という肩書が入っていたんですからね。その後、彼に人間を撮る仕事がまわってきたかどうかは、私、聞いておりません。
仕事替えが自由ならば、住む場所を変えるくらいは、ランチを食べるレストランを変えるくらいの気楽さでやってしまいます。私自身、プロ作家になってから、7回引っ越しておりますが、先日、ある児童文学者の方から引っ越し通知のEメールが来て、そこには「17回目の転居です」と記してありました。
でも、私の引っ越しなんてのは、東京周辺をウロウロしているだけですから、可愛いものです。その時の気の向くまま、日本全国、世界を転々としている人も少なからずいて、たとえば、佐々木譲さんなんて、私が学芸大学に住んでいた時は中目黒にいて、ともに東横線の生活を楽しんでいたのに、いつのまにかニューヨークに飛んでいってしまいました。帰ってきたら江戸情緒の残っている谷中に住み、しかし、そうこうしているうちに北海道のニセコなんぞに居を構えてしまいました。
サラリーマンの方の中には、マイホームを建てたとたん、遠隔地への転勤が決まり、泣く泣く新居を後にする人がいる、なんて話をよく聞きます。ある会社では「マイホームを建てると、転勤の辞令が出る」というジンクスもあるそうですが、フリーランサーにとって、その種の心配は皆無なのであります。
もっとも、マイホームを建てるといっても、フリーランサーではまず銀行ローンを組めないから、家自体が持てない。なあんて、ひどいことを言う人もいますけど……。
今回は、フリーランサーの経済事情と生活の自由度について記してみました。次回は、別の側面を書いてみたいと思っております。