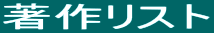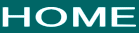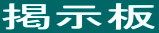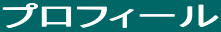月刊エッセイ 2/16/2003
■ 私が体験した日本人の"劣化"
先週の日曜、友人宅に遊びに行った際、私はお土産にマロンケーキを持っていったんですね。ところが、まさにケーキを切ろうとした時、表面に青カビがぽこぽこ発生しているのを発見。そのケーキは前日の夜に買い求めたばかりのものだったので、小さなショックでした。この冬の時期、火を通してある焼き菓子に1日やそこらでカビが生えるわけもありません。しかも、調べてみると、そのケーキの箱には、製造年月日や賞味期限の表示もない。
断固、抗議しなければなるまいと、翌々日(翌日は店が休みだったもので)、私の住む町のケーキ屋Aまで足を運びました。これがヤクザだったら、
「おい、おまえ、俺を食中毒で殺したいのか」
すごむところでしょうが、私は紳士であります。静かな口調で店の経営者を呼んでもらい、それから、
「奥で話したほうがいいでしょう」
と、他の客のいる店先から奥へと移動しました。そこで、持参したケーキを見せたのですが、そのとたん、店主の顔色が変わりました。「申し訳ありません」「すみません」と言って、頭を下げるばかり。
結局、代金を返してもらい、「お詫びのしるしです」と差し出された新しいケーキを受け取って帰りましたが、私の気持はどうもすっきりしません。というのも、なぜケーキにカビが生えてしまったのか、また賞味期限も記していない食品をどうして売ったのかという疑問に対して、店主がはっきりした答を言ってくれなかったからです。きっと、漫然と並べておいた商品を、アルバイトの女の子がとくに注意することもなく売ってしまったんでしょうね。
そのケーキ屋はフランス風の焼き菓子がけっこう美味しくて、私も贔屓にしていただけに、残念です。今度からは、古くなっていないか心配しながら買い求めなければならないじゃないですか(そんな思いまでして、買いたくはないか……)。
その十日ほど前にも、別な店で小さなトラブルを体験しました。友人と私のかみさんとの3人で、やはり市内にある喫茶店Bでランチを食べました。食事後、レジに立ったアルバイトと思われる女の子がどうも不慣れらしく、上手くレジスターを操作できない。店の奥にいる女主人に指示を仰いで、ようやく打つことができて、
「6200円をちょうだいします」
ちょっと高いかなあと思ったけれど、その日は風邪気味で頭がぼんやりとしていたので、そのまま払ってしまいました。ところが、あとで計算してみると2000円以上も高い! 100 円や200 円ならともかく、ランチで2000円以上も多い額をボッたくられたのですぞ。この場合は、証拠となるものがなかったので、私の泣き寝入りとなりました。
だけどさ、店で働かせる前に、店主はレジ打ちの教育くらいできなかったのか。レジの前で女の子が悪戦苦闘しているのを知ってるんだったら、どうしてその場に出てきて、間違っていないか、チェックしなかったのか。きっと、まあ、いいや、と思って、店の奥から出て来なかったんだろうな。私も甘かったけどさ……。
こうした“いいかげんさ”が原因となったトラブルに、ここ数年、悩まされてるんですね。さる大手電話会社が二度にわたって、まったく身に覚えのない料金請求をしてきたことは、昨年12月29日の「本岡類の今」に書きました。また、ある老舗の大手出版社でトラブルが起こった際、編集上層部が「面倒くさいことはやだよ」と言わんばかりに逃げ出して、呆れ果てた私が断交を宣言したことは、11月9日の「本岡類の今」で書きました。そして、昨年の7月には下手をすると命にも関わるトラブルにも遭遇してるんですよ。
私の乗っている車が7月に車検を迎えました。我孫子市に引っ越してきて初めての車検で、信頼できる修理屋も知らなかったので、ちょうど近所のガソリンスタンドで宣伝していた整備システムを利用することになりました。車検代行サービスではありませんよ。ガソリンスタンドで預かった車を整備工場まで運んで整備し、車検にパスさせるというやり方で、時々テレビのCMでもやってるあれですよ。
私の車は7年走っている高齢車ですので、パーフェクト・コースという安心安全を売りものにしているコースを選びました。おかげで、ブレーキパッドをはじめとするさまざまな部品が交換され、それなりに高いものになってしまいましたが、安全には替えられないと、納得はしていました。
ところが、車検が終わって、半月ほどもたった頃、段差を乗り越えた時など車からカラン、カランという異音がするようになったのです。どこから聞こえてくる音なのか、なかなか判定ができなかったのですが、いろいろ試した結果、ブレーキを軽く踏みながら段差を通過した時には音がしないことから、ブレーキ系統のトラブルと判断。これはきっと車検整備の時おかしなことをしたな、と考え、整備を頼んだガソリンスタンドに車を持ち込みました。すると、
「すみません。ブレーキのディスクを挟む部品があるんですが、そこのネジが一本外れてたんですね」
と、おっしゃるわけです。2本のネジで止まっているはずが1本しかなく、部品がブラブラして音が出ていた、と。おいおい、もう1本が外れたら、部品が脱落してブレーキが効かなくなるじゃないか。
これは車検整備の時、ブレーキをいいかげんに組み上げたからに違いない。私は怒って、担当者は平謝り、無料で再チェックをすると約束しました。
しかし、私は釈然としません。なぜ、ネジの締めつけがゆるくて外れてしまったのか、納得のいく回答がなかったからです。そのガソリンスタンドでは、車の返却の日時が二度も変更になったり、かなりアバウトな仕事をしているみたいでしたし。
小さなことでしたら、いくらでもあります。さるDIY店で、泥棒が窓をこじあけたら、ショックをセンサーが関知して、ブザーが鳴るという防犯グッズを買い求めました。ところが、感度が良すぎて、窓のそばを人が足音高く歩いたりすると、けたたましく警報音がなってしまい、とても使いものにならない。メーカーは感度のチェックをろくにやらないで出荷したんだろうな。
1万円以上もする将棋ソフトを買いました。しかし、そのソフト、反応がトロくて、操作性も悪くて、しかし、そのくらいならなんとか我慢ができますが、「千日手」という反則を平気でやってくる。将棋を知らない人には理解できないかもしれませんが、サッカーゲームでいうならば、オフサイドが反則に取られないと同じようなものです。これは欠陥商品だとメーカーに抗議して、返品、返金となりました。
でも、なんでだろう。「千日手禁止」のプログラムを入れておけばいいのに、それをやっていない。まあ、勝った負けたが楽しめればいいのだろう、と、その程度の認識で商品を市場に出してしまったのではなかろうか。
うちのセナちゃんのために、キー付きの猫ドアを買いました。猫の首輪に電子キーをつけ、それに反応して、猫ドアのロックが解除されるという仕組みの商品です。ところが、かなりの値段がしたにもかかわらず、欠陥ありといってもいい商品。猫がドアに対して、正面から接近してくれば、めでたくロックは解除となりますが、斜めの方向からアプローチされると、錠はかかったままで、セナは家へ入ることができません。
だけどね、きちんと正面から入りなさいと猫に言っても、むこうは理解できないでしょ。動物相手の商品を作っているのなら、なんでそんなことくらい計算に入れて設計しないんだろう。そうした商品を、販売会社はろくなチェックもなしに市場に出してしまうんですから、理解に苦しみます。これも抗議の上、返品。
これだけではありませんが、挙げていくときりがないので、このへんで止めにしておきます。かつては旧ソ連で作られたテレビは火を吹くと馬鹿にしたり、外国で買い物をすれば店員が釣り銭を間違えるが日本ではそんなことはないと、我々日本人は誇りに思っていたものですが、いつの間にか、わが国もいいかげんな国の仲間入りをしてしまったんじゃないかなあ。
日本がこれほどおかしくなったのは、バブルの頃からだったと思います。とくに1980年代の後半から90年の前半あたりにかけて、私はよく怒っていた。
今でもよく覚えているのは、昼下がりに神楽坂の近くを歩いていた時のことです。お腹がすいていて、ちょうど新規開店のレストランを見つけたので、入ってみました。ところが、注文してから30分たって40分たっても何の料理も運ばれてこない。店内では招待客と思われる客もいて、彼らのところには料理は運ばれてくるし、店のオーナーもお愛想をふりまいていますが、一般客である私はほとんど無視状態。さすがに堪忍袋の尾が切れて、オーナーを呼んで抗議し、
「料理は、もう要らない」
と宣言して、店を出ました。招待客を呼んで、歓談したければ、開店する前にそうしたセレモニーをすればいい。いったん一般客を入れたからには、プロに徹して、サービスをするべきなんです。
どうもあの頃から、いいかげん仕事や大甘仕事が横行するようになったみたいですね。日本でだったら、どうやったって楽に生きていけるさという甘い思いがずっと続いて、ここまで来ちゃったんだろうな。
そして、わが業界もそうした傾向が続いてるんじゃないかという懸念が大いにあるんです。思えば、1980年代は、皆さん大甘だった。無名の新人作家だって、新書判ノベルス1本書けば初版だけでも200 万円近くにはなった。増刷や映像化も簡単におこなわれたから、年にノベルスを3本ばかり書けば、面白おかしく生きて行くことができた。雑誌だって、そうです。女性誌の中には、溢れかえった広告を収容するするために創刊されたものもあって、
「うちの雑誌は売れ行きは、あまり気にしていないんです。広告がたっぷり入ってますから」
なんて公言する編集者もいた。そんな風潮が続くうち、編集者も寄稿家も地力みたいなものを失っていったんじゃないかねえ。
2年ほど前だったかな、ちょっと話題になった長編新人賞の作品がありました。書いた若い作家氏は、新聞のインタビューで、
「取材はまったくしていません。現地にも行っていません(日本国内だぜ!)。参考文献を読んだだけで書きました」
なんて言っていました。そんなことで面白い小説が書けるものかと、その小説を図書館で借りて(ごめんなさい、買わなくて)、読んでみました。
目のつけどころが良くて、それなりに面白かったですよ。でも、なんとなく薄っぺらで、読み終えたら、何が書いてあったか半分以上は忘れてしまった。
ここ何年か、そんな本が多いんじゃないかな。センスはいい。アイデアもいい。迫力もある。でも、薄っぺらの感じのする本。そんな本に、読者は1600円、1800円というお金を出すものでしょうか。
今の出版大不況。一般社会と同様に、業界の人間の“劣化”がその根底にあるような気がしているんですよ。
今月は、ずいぶん暗いことを書いたように思われるかもしれません。でも、劣化を自覚することによって、初めて新しい展開が期待できるんじゃないのかな。筋肉が落ちているのなら、筋肉をつければいい−−そう思って、私も創作のウエイト・トレーニングに励んでいるところなのであります。