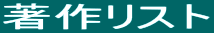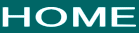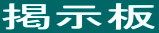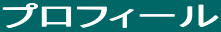月刊エッセイ 1/20/2003
■ グルメな私
昨年の年末、実家に帰った私は、両親からすべての餅を取り上げて、正月、自宅に戻りました。
おお、なんと酷いことをするのか。本岡類は食べる物にも困っているのか。そう、お思いの方もいらっしゃるでしょうが、事実は違います。実家は農村部にあるので、近所から餅をいただくのですが、なにしろ両親は80歳に近い高齢者。正月早々、餅を喉に詰まらせて頓死でもされたら、取り返しがつかないと思ったんです。名のある病気で正々堂々、亡くなるのならともかく、餅と戦って討ち死にでは、
「救急車で病院に運ばれた時には、すでに息がなかったそうです。最後の言葉は『うう っ』でありまして、皆さん、餅は凶器です。取り扱いには注意しましょう」
喪主の挨拶で、そんなことを言うしかないのでは、格好がつきません。
両親、とくに餅好きの父は落胆の色を露にした顔になりましたが、そこは心を鬼にして、私は実家にあるすべての餅を奪い取ったのです。
実際、今年の正月には、東京だけでも18人だったか19人だったかのお年寄りが餅を喉に詰まらせて亡くなったり、意識不明の重体に陥ったりしたと、ニュースでは言っていましたので、私のとった対応はけっして間違ってはいなかったと信じていますが、父親の顔を思い出すと、申し訳ないことをしたかな、との思いも湧いてきます。たかが餅ですが、餅好きの人間にとっては、キャビアやフォアグラにも勝る食品だったかもしれません。
人間、だれしも「他人が何と言おうとも、私は、これが好きだ」という食べ物を持っているみたいです。で、私の場合は「湿けたせんべい」「冷めたピザ」「黄色になりかけた青い(正しくは緑の)バナナ」の三つが、その“譲れない食品”なのであります。
「湿けたせんべい」は、前歯がせんべいをカリカリと噛み砕くのではなく、グニャリとせんべいを断ち切る感触が、たまらない快感。「冷めたピザ」は、冷えて固まったチーズがより強く己の存在を主張しているような気がするし、「黄色くなりかけた青いバナナ」は大人の匂いをさせ始めた女子高校生(30年くらい前の女子高生ですよ。今の汚ギャルではありませんよ)の色香に似ているとでもいいましょうか。
ただし、この“三大美味”は世間の人にはなかなか理解されないようで、今は亡くなった義母から「変わってるねえ」と言われ、侮蔑の目で見られたことは、私の中でいまだ心の傷として残っています。かつて小渕さんが総理大臣になった時、アメリカのメディアから「冷めたピザのようだ」と低い評価を下されましたが、私からすれば“冷めたピザ”というのは最大級の賛辞で、その時は、アメリカ人もわかっちゃいねえな、と思ったものであります。
しかしね、最近では、私の味覚の感覚が正しいことも少しずつ理解されてきたようで、スーパーマーケットでは「濡れせんべい」などと名付けられた“湿っけ系”のせんべいが人気を集めています。正しいことを言い続けていれば、いつかは世間も目が覚めるというわけですね。
「冷めたピザ」は、宅配のピザを2時間ばかり放置しておけば、それで完成となります。また「黄色くなりかけた青いバナナ」もスーパーで青いバナナを選んで(最近の店では、完熟したものばかりを並べる傾向があるので、青いバナナは買いにくくなっていますが)、適当な時に食べてしまえばいい。それらに対して「湿けたせんべい」は作るのに多少の努力が必要です。美味しい「湿けせんべい」をぜひ食べてみたいという方に、今回は極秘の製法をとくにお教えいたしましょう。
時期は、やはり梅雨の頃が最高です。梅雨の頃に作るせんべいは、とくに“6月もの”と称して、珍重しています。いろいろ試してみましたが、素材は海苔のねっとり感も同時に楽しめる品川巻なんかが最高だと思います。
まずは、せんべいの袋を開けます。そして、そのまま、2、3日、放置します。そこで大切なのは、どんなに食べたくても、開いた袋の口から手を入れ、せんべいを取り出し、口にほうりこまないということです。口の開いたせんべいの袋が目の前にあるのに、せんべいを食べてはならない ―― 簡単そうに見えても、せんべい好きには、かなりの忍耐を必要とします。
2、3日が過ぎ、頃合いを見計らって、一つ、試し食いしてみます。前歯が湿けたせんべいにぐにゃりと食い込み、もうちょっとで切断できる寸前で、固い部分に突き当たるといったくらいの湿りけ加減がベストです。もし、ぐにゃっとなったまま切断できてしまうのなら、湿度を吸収しすぎで、それはせんべいではなく、餅に近い存在となってしまいます。
「おれは、まだ、せんべいだ」
そう最後の抵抗を示す証としての固さが残っているのが、せんべいの心意気というもので、スパゲティの茹で方の「アル・デンテ」に通ずる部分があります。
そのあたり、市販されている「濡れせんべい」は、よろしくありませんね。製法の違いからでしょうか、ぐにゃっとしたまま、前歯で噛み切れてしまう。こうしたせんべいを、“だらしな湿けせんべい”と呼んで、私は一段、低い格付けをしております。やはり「湿けせんべい」は手作りに限りますね。
それから、あと一つ付け加えるとするなら、猫を飼っている家では、口を開けたせんべいの袋を、猫が飛び乗れる場所に置かないことです。猫という動物は、興味を示した食べ物は、とりあえず舐めてしまうという性癖を持っております。うちでも、飼い猫のセナが何度、せんべい袋の口に頭を突っ込もうとしたかわかりません。いや、何度かはぺろぺろ舐めてしまったかもしらんなあ……。
今まで述べたように、私はグルメなのであります。しかし、私の小説の中には、おいしく食事をするというシーンが、あまり出てきません。出てきたとしても、あっさりしたものです。
口に入れた瞬間は、普通の米と変わらなかった。が、噛んでみると、違った。舌が、ほのかな甘さを感じ取った。
それは、白米ばかりでなかった。
筑前煮に入っているニンジンやゴボウにしても、いつも食べているものとは違ったし、「こうすると、いちばん、よくわかる」と、田島が皿に味噌だけを載せて出してきたキュウリは、歯触りが良いばかりでなく、はっきりと野菜の味がした。(「神の柩」より)
テーブルに届いた生牡蠣と白ワインが、その場の空気を元に戻してくれた。牡蠣は海のジュースをたっぷりと含んでいたし、よく知られた名称がついているわけでもないワインは、癖もなく、喉をすっきり通っていった。(「絶対零度」より)
読み返してみて、自分でも感ずるけど、あっさりと書いてますよねえ。池波正太郎さんや開高健さんといったグルメ作家が、読んでいてよだれが出てくるような食事シーンを書いているのに、この違いはどういうことなのでしょう?
きっと、自分が好きな食べ物を書いていないからじゃないかと思います。だったら、好物の“三大美味”を登場させたらいいだろうと、言われるかもしれませんが、どうも上手くいかないみたいです。
試しに、やってみますか。そうですね、私立探偵の佐藤が調査対象者の鈴木を尾行してイタリアンのレストランに入ったシーンを書いてみましょう。
貧乏探偵の佐藤は財布の中に入っている札を頭の中で数え、いちばん安いピザを頼むことにした。少し離れた席に着いている鈴木は、どうやらコース料理を注文したようだ。
やがて、注文のピザがテーブルに運ばれてきた。とろけたチーズが熱を発している。じつに旨そうだが、ここで手を出してはいけない。とけたチーズは歯ごたえがないし、熱は舌の感覚も奪うのだ。
少し待った。チーズはだいぶ落ち着いてきたが、指で触れてみると、まだ温かくて、柔らかい。
〈早ーく、冷たくなーれ……〉
〈早ーく、冷たくなーれ……〉
ピザを眺めながら、探偵は念じた。
待った。指で触れてみた。まだ充分な固さにはなっていなかったが、我慢しきれず、佐藤はピザをつまむと、口に運んだ。歯がチーズとパイ地を噛み切る快感、舌が明快な味を感じ取る。
〈こりゃ、いいチーズを使ってる……〉
幸福感に浸ったあと、探偵は調査対象者のことを思い出した。
鈴木の姿はない。しまった、逃げられた。
これでは、商売になりませんね。「湿けたせんべい」が登場する官能小説というのも、難しいようです。晴彦が美紀をめでたく自分の部屋に誘い込んだあとのシーンです。
「なーに、このおせんべ。袋の口が開いたままよ」
美紀が訊いてきた。
「いいんだ。それは、自家製の湿けせんべいで、旨いんだぞ。一つ食べてごらん」
彼女は、品川巻をつまむと、口に放り込んだ。口を動かして、妙な顔をする。
「あんまり感心しないなあ。ねえ、それよりも ―― 」
美紀が顔を寄せてきて、唇を重ねた。醤油の匂いがした。晴彦が舌を差し入れようとすると、彼女の前歯に貼りついていた何かが、ねちょりとからみついた。
〈こいつは、品川巻の海苔だ……〉
かまわず舌を差し入れると、歯と歯の間に挟まっていた何かがとれた。醤油の味がした。
〈こっちは、湿けせんべいのかけらか……〉
どうしても、官能的にはならんでしょ。
かくして、私はグルメなのにかかわらず、好みが個人的にすぎるので、小説の中には登場させられないのです。異端というのは、悲しいものですね。
ところで、正月が開けてから、実家に電話してみました。餅を喉に詰まらせて死者が続出したことを言い、私の判断が正しかったことを自慢すると、父からは思わぬ答が返ってきたんです。
「餅は食ったよ。隠してたのがあったんだ」
好きなものは、そう簡単には手放せない、と続けて、笑うのです。
うーん、さすがは年の功。うまく隠したものだ。私は、まだまだ甘い。
イラクのフセイン大統領も見習うべきだと、思ったものでありました。