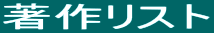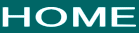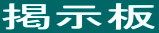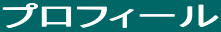月刊エッセイ Back number
[2002年3月]
■ 今月は真面目です ―― ブックオフを、あえて弁護しちゃう
1月号、 2月号のエッセイについて、「ウケ狙いが見え見えですね」という評をいただいて、いささか傷ついております。ウケを狙うのはプロとして当然のことですが、それが透けて見えるとは、やはりまだまだ未熟なのでしょうね。また、あまりふざけたことばかり書いていると、本岡類はこの程度の作家かと思われるのがシャクですので、今月は真面目にいきます。なに、つまらなそうだと? ま、そう言わず、読んでください。
最近、ネット上などで、「本岡類の本は図書館で借りて読んでいる」「古本屋で本岡類の本を買った」などという書き込みをよく見るようになっています。たしかに、図書館は借りる人で溢れかえっているし、私の住んでいる我孫子市の周辺にはブックオフをはじめとする大型古書店がいたるところにできております。しかし、この図書館や大型古書店は、漫画喫茶と並んで、作家や出版社から怨嗟の目で見られています。そのココロは、ただ一つ。どんなに本が読まれても、作家や出版社には、それについての金が入ってこないからです。
「出版社は社員に高給を払っているし、作家も高額所得番付に名前を並べてるから、まあ、いいじゃないか」
などと、おっしゃる方がいます。が、実態は違うんですぞ。確かに大手出版社の社員の給料は高いけど、その一方で、「あそこが危ない」「○社が銀行管理に入った」などの危険情報が最近ではしょっちゅう業界内で飛び交い、事実、大リストラが行われたり、吸収合併されたりする老舗出版社も少なからず出てきております。ましてや、作家の高額所得者となれば、ごくごくごくごく少数で、大多数の作家は取材費の捻出にも四苦八苦している状態です。
だいたいが、作家というのは、ビンボー者であります。たとえば、10何年か前になります、私がイギリスに取材に行かなければならなかった時(「鎖された旅券」という作品です)、預金残高が少なくて、直行便はおろか北回りのチケットも買えず、大ディスカウントの南回り(しかも、クアラルンプール乗り継ぎ)で行ったことがあります。ちょうど同じ時期、お金をたくさん持っている知人のドラ、い、いや、その、ドラキュラ、いや、違う、ご子息が、まだ中学生なのにファーストクラスでイギリスに行ったのと比べると、なんたる大差かと、世の不条理を嘆いたものです。ロンドンに着いてからも、ホテル代を節約するため、当時、家族で英国留学していた友人宅に転がりこみました。宿代代わりに友人の子供の子守りをしつつ、取材したことを覚えています。
他の人たちも似たようなものです。私の敬愛する○氏がヨーロッパ取材をする時、使った航空会社は、ルフトハンザでもなく、エールフランスでもなく、当時、大ディスカウントされていたアエロフロートでした。じゃがいもみたいなスチュワーデスを眺め、がたぴし揺れる飛行機で現地に着いた○氏は精力的に取材をこなし、それが傑作「○ル○ン飛○指○」(空欄を埋めよ)となって結実したのは、見事な作家魂といえましょう。
そうした元々ビンボーだった作家たちが、ここ数年さらに窮乏化しております。具体的な数字であげると、1990年くらいまで、中堅クラスの作家の初版部数(ハードカバーの場合)は8000部から10000 部くらいだったと記憶しています。それが、出版不況のひどい昨今では、4000から7000部くらいに激減しています。さらに増刷の声は滅多に聞かれず、文庫化された時の初版部数も少なくなり、そうだな、著作から得られる総収入は半分程度になっているのではないでしょうか。
数年前、新たな文芸団体が旗揚げしました。プロの文芸団体の総会は平日の夕方から開かれるのがふつうですが、そこの発足の会は休日に行われました。会に出席した編集者が言うには、
「一部を除いて、ほとんどの人が平日は別な仕事をしていますからね」
つまりは、プロとはいえ、専業が成り立ちにくくなっているのが、昨今の状況なのです。早い話が、「日曜作家」が増えてきている。
日曜作家。それは別に悪いことではありません。直木賞を取ってからも広告代理店勤務を続けていた方もいますし、ずっと銀行に勤めながら小説を書いていた人もいます。しかし、他の仕事との兼業を続けるには、(1)頑健な体(2)不屈の精神力(3)会社の理解と、三つの条件が揃わなければなりません。が、大不況の昨今、とくに(3)の条件をクリアするのが難しい。
「あいつ、小説なんか書いているから、仕事ができないんだ」
などという陰口も言われるでしょうし、リストラが始まれば、真っ先に対象者となるに決まっています。三十代の初め、私も二年間、兼業作家をしたことがありますが、体力的に無理だったし、なによりも取材の時間を取るのが思うにまかせませんでした。経済的な理由から日曜作家が増えるというのは、けっして良いことではないと思います。
出版不況の原因のすべてが、大型古書店や図書館にあるとは思っておりません。構造改革のなされていない古色蒼然とした出版業界の体質が、その原因の多くを占めているのでしょうが、やはり古書店や図書館の影響も少なくない。では、図書館、古書店をまとめて、ばっさりと切り捨てて良いものか? 答えは「ノー」であります。なんとなれば、私も図書館や古書店を大いに利用している。文句を言っている出版社の社員もブックオフで本を買っている。ついこの間も、古書店で田口ランディさんの「コンセント」750 円ナリ、山本文緒さんの「プラナリア」950 円ナリ、買っちゃった。田口さん、山本さん、ごめんよう…。
そうそう、古書店に関しては、こんな思い出があります。もう時効でしょうから、書いてしまいましょう。
数年前、中央区の図書館で佃島に関する企画展示会が行われ、私にも展示用の色紙を書くよう依頼がありました。そして、色紙を書いた謝礼として、中央区が編纂した古地図集のの復刻版が送られてきたのです。たいそう立派な本でしたが、現代社会を描くのをもっぱらにしている私に、古地図は猫に小判。よし、これを売って、取材費の一部にし、傑作を書けば、送ってきた人の失礼にもならないし、古地図集の供養にもなる。そう考えて、神田の古本屋街まで行ったのです。古地図専門店で、店番をしていた親爺は、
「うーん、この本、ずいぶん出回ってるからなあ」
と、難癖をつけながらも、12000 円で買ってくれたのです。
その金を握りしめて、私、鮨屋に直行しました。
ともあれ、私の場合は、限られている取材費を有効利用するため、古書店を利用しているのですが、一方で、それとは違った理由から、図書館や大型古書店通いをしている人も数多くいるようです。それは、ふつうの新刊本ルートでは手に入らない絶版本や在庫切れ本を手に入れるためです。
最近では、本が絶版になるまでの期間は短く、2年ほどでその運命になってしまうものもあります。また、版元在庫切れという扱いになるのも、そうとうに怖い。読者が「買いたいです」と出版社に電話をかけても、「倉庫にないからお売りできません」と答えが返ってくる、あれですよ。なぜ、新たに刷らないかといえば、増刷は最低でも2000部くらいの部数となりますから、
「そんなに刷って、売れなかったら、在庫品になっちゃうなあ」
と、出版社の営業担当者は考え、アクションを起こさないのです。
そんなことがあって、書店には新刊書かベストセラー書しか並ばず、それ以外は手に入らなくなる。でも、それって、おかしいでしょ。新刊書とベストセラー書しか、入手できないなんて。
そして、そんな入手困難な本を読めたり、買えたりするのが、図書館や大型古書店なのです。つまりは、従来の出版流通ルートに開いてしまった大穴を補うのが、両者というわけです。もし、独裁者が現れて、図書館と大型古書店の閉鎖を宣言したとしたなら、本の世界は索漠としたものになるに違いありません。
とはいえ、今のままでは、出版社も作家も疲弊する一方。まさに「ヤマアラシのジレンマ」ですねえ。で、私の考えを述べます。
ここまで来ちゃったんなら、著作権法や図書館法を改正して、新しいルールを作るよりないんじゃないかなあ。
つまりは、大型古書店で販売された本についても、何パーセントかの金額は出版社や作者に支払われるようにする。これは、本の裏にあるバーコードを上手く利用すれば、可能だと思われます。また、図書館が購入する本は、貸し出しを前提にして、倍の値段で買ってもらう。増えた費用をまかなうため、図書館は借りる人から、一冊につき、200 円くらいの料金を取ればいいんです。
ただで本が借りられたり、安く本が買えるのは、魅力的なことです。でも、それで出版社や好きな作家が消えてしまったら、元も子もないんじゃないかな。
しかし、まだ上記のようなシステムが整っていない今。私の本について言いますと、絶版本や在庫切れ本は、どうぞ図書館や古本屋を利用して、お読みください。そして、新刊書市場で流通している本は、まあ、二冊に一冊くらいは、正規の値段でお買いになっていただければ、私の頬も自然に緩んでしまうのですが…。「絶対零度」お買い求め、ぜひ、よろしく。
ああ、今月は真面目な文を書いてしまった。真面目に書くと、肩がこるなあ。誰か、肩でも揉んでください。