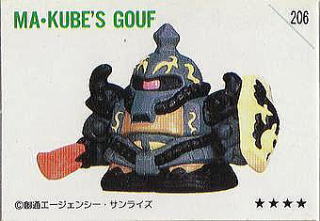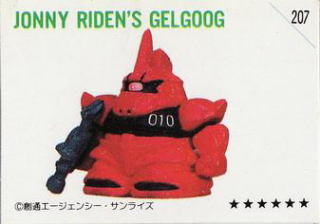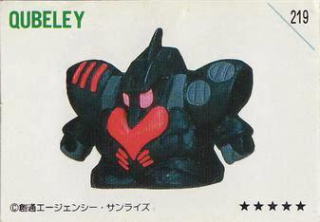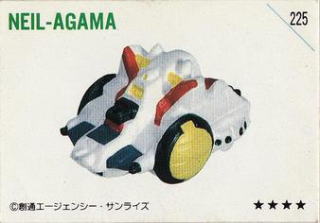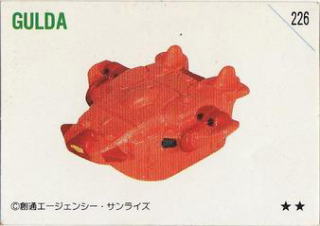SD写真シール No.201〜300
凡例
シール通しNo./キャラNo./
| 所属 |
封入弾 |
入手困難度 |
画像
|
シール裏面解説 |
| 備考 |
ガンダム13弾
201/134/Sシール有り?
| ネオ・ジオン軍 |
復刻10弾? |
B |
 |
ドーベンウルフ AMX-014
H:25.9m W:74.5t
ネオ・ジオン軍ニュータイプ用モビルスーツ。ラン
ドセルのビームポッド「インコム」と両腕は本体
から分離しモビルスーツの死角から攻撃をかけ
ることができる。 |
『EB グリプス戦争編』によれば、本機は元々ムラサメ・オーガスタ研究所でサイコガンダムmk2.の小
型普及版としてG-V(註26)というコードネームで開発されていたが、第一次ネオ・ジオン紛争時にネ
オ・ジオンがティターンズ併合の際に接収され、頭部やサイコミュシステムなどを改造して少数を制式
採用した機体である。サイコミュシステムは一般人に扱えるものとして特筆され、この技術は宇宙を
漂流していたサイコガンダムmk2.をネオ・ジオンが回収、徹底的に調査し開発したものである。同時
にAMX-015も同じコンセプトで開発されたが、AMX-015がファンネルを運用するのにNT能力を必要
とするために扱いは限定され、AMX-014のほうが火力では劣るにもかかわらず評価は高い。
1/144「ドーベンウルフ」インスト(文献79)によれば、本機はMA並のジェネレーターを持ち、専用のビ
ームライフルを胸部のメガ粒子砲と直結させることによって戦艦を一撃で葬る大型メガ粒子砲になる
他、対艦ミサイル×2、(ガザDと同型)対MSミサイル×24、インコム、有線分離式両腕メガ粒子砲、
ビームサーベル等を装備している。また腕部メガ粒子砲の導入が決定する前は、ヒートロッドが装備
されていた事も記載されている。これは腕部による電撃機能を持たせ代替されたものと考えられる。
なお、指揮官機(ラカン機)は腕部がレーザーによる無線制御分離方式になっており、分離後の基部
には隠し腕が取り付けられていたが、外面的には一般機と変化はない。
なお、本機は造反したグレミー軍にしか存在せず、ラカンはグレミー軍カラー塗装を拒否していた。 |
202/135
| 所属軍なし(ジオン共和国?) |
23弾? |
B |
 |
キャトル
忘れ去られたコロニー「ムーンムーン」に奉られ
ていたコロニー建造用機械。50年以上昔に作ら
れたモビルスーツの祖先とも呼べるものである。
"キャスク"とも呼ばれる。 |
ニュータイプ100%コレクション『機動戦士ガンダムZZ』によれば、ムーンムーンのヒカリ族に、機械の
無力さを象徴するものとしてご神体として奉られていた。劇中では動力源が太陽電池であるとの描写
がされていたが、機体下部や背部に機体制御用のノズルが存在することから化学ロケットも併用して
いたと考えられる。メインスラスターはホバー方式。
モノアイを使用しており、宇宙世紀初頭にモノアイの概念が存在していたことになり興味深いが、70年
代前半に開発が行われたMS-01等がこれを参考としていたのか、それとも宇宙世紀においては一般
化していた概念であったのかは不明である。 |
203/136
| エゥーゴ |
23弾? |
B |
 |
コアトップ
H:19.9m W:30.9t
ZZガンダムの上半身は分離変形させることによ
りコア・トップとなる。コア・トップは単独で戦闘機
としての機能を持つ。武装は二連装メガビーム
ライフルが装備されている。 |
12弾のコアベース(191/125)と合体してGフォートレスになることができる。
ZZの上半身(Aパーツ)に、ZZの二連装ビームライフルが機首となって構成されたもの。機首となるビ
ームライフルには操縦席があり、ここから機体を操縦することもできるが、更にコアファイターが合体
した状態(コントロールもコアブロック側に移行)のほうが機体としては安定する。 |
ガンダム14弾
204/137
| ジオン公国軍 |
23弾? |
B |
 |
ザンジバル
ジオン軍が開発した高機動巡洋艦。単独で大気
圏突入ができブースターをつけることで宇宙へ
打ち上げることもできる。初期は前部に目くらま
しの投光器がついていたがメガ粒子砲に取り換
えられた。 |
来るべき地球侵攻作戦に備えて建造された史上初の大気圏内外航行可能な巡洋艦。リフティングボ
ディ構造を持ち、大気圏内を単独で飛行できる。『センチュリー』によれば、主砲は火薬式の600ミリ連
装無反動砲で、大気圏内での曲射弾道効果を目的に搭載されたと記載される。搭載機数はMS6機
が基本であるが、シャア大佐が運用した艦(ランバ・ラル大尉が地球に降下した艦で、後にメガ粒子
砲仕様に改装され、MA試験部隊と共にシャアに任された)はMA×2(MA-04X、MA-05)にMS×3(M
S-09R)であった。配備の遅れと高コストのためか建造数はさほど多くないようである。
初期型は別項を立てるべきであった(137A)。
なお、『ミリタリーファイル』にはティベ級と共にMS-14を運用できる数少ない艦と紹介しており、またエ
ース部隊の旗艦として青く塗装された「キマイラ」が描かれている。 |
205/138
| 地球連邦軍 |
23弾? |
B |
 |
Gファイター
RX-78ガンダムの強化用パーツ「Gパーツ」同士
が合体したガンダム支援用重戦闘機。本来、ガ
ンダム輸送用として開発されたためエンジンパ
ワーが強く上にガンダムを乗せることができる。 |
Gメカの基本形がこのGファイターである。この中央にRX-78を挟んで輸送形態となったものがGアー
マーである。『1/250 Gアーマー』メカニカルファイル(文献80)によると、Gファイターのビームキャノン
はガンキャノンの長距離ビームライフル以上の出力を持ち、連続使用でガンダムのビームライフルの
3倍(約45回)の連射が可能であると記述される。また、操縦系はコンピューターと連動していないの
で手動系操縦のほうが機動性が良く、パイロットの技量で性能に差が出るとも記述される。
劇中(TV版)では、しばしばセイラ准尉のGファイターがアムロ少尉のRX-78-2を乗せて高速機動戦
闘を行った。連邦版のサブフライトシステム用法と言える。 |
206/139
| ジオン公国軍 |
23弾? |
C |
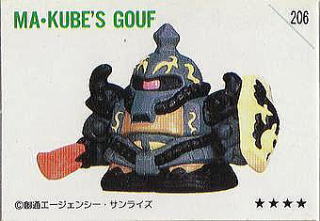 |
マ・クベ専用グフ MS-07B
H:18.5m W:80.0t
通常のMS-07Bグフを、装甲だけ改修、飾りつけ
をしたマ・クベの専用機。性能は、普通のグフと
全く変わらない。実戦には一度も使用されず、基
地内の飾りのようなものであった。 |
西部アジアの鉱山採掘基地司令であるマ・クベ大佐用にカスタムアップされた機体。『MSV』では、カ
スタムアップされたグフの中で最も有名な機体であるとする一方、戦闘部隊以外でのカスタム機は珍
らしい、とも記述される。また、『コミックボンボン』83年9月号には個人的改修も多かったとの記述があ
り、これらのことからカスタム機は複数存在したが、ほぼ全て戦闘部隊における高官用(指揮官用)と
してカスタムアップされたことが読み取れる。劇中で確認される、左腕にヒートロッドを持ち右腕にハン
ドマシンガンを持つ機体は、そのような機体であった可能性がある(註27)。
なお、シール解説にある「実戦には一度も使用されず」という記述は当時の資料では確認できない。
その一方で、『Z10本』には「性能が多少アップした」とも記述されている。劇中でマ・クベ大佐は軽々と
MAX-03アッザムを操縦していることからも、この専用グフも戦闘部隊としてではないまでも、マ大佐
によって効果的に運用されていた可能性が高いといえる。 |
207/140
| ジオン公国軍 |
23弾? |
B |
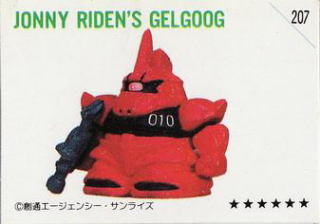 |
ジョニー・ライデン専用ゲルググ MS-14B
H:21.0m W:106.0t
MS-14の初期生産型24機はエース部隊用とし
てパイロットに応じたチューニングが施された。
その中の1人、ジョニーライデン大佐の機体は赤
と黒に塗り分けられ、めざましい活躍をした。 |
『MSV』には、ボタン1つで14Bはブースターを着脱でき、14Aと同じ運用ができたと記載される。また、
逆に14Aもわずかな改造で14Bとなったとも記される。
14Bの1号機はジョニー・ライデン専用機となったことが『MSV』には記載される。また、ライデン自身が
第一中隊の隊長となったことも記される。
14Bはビームライフルももちろん装備できるが、エース部隊においては、特殊なロケットランチャーや
360mmバズーカを運用したいたようである。
生産機数について、近年のMG系資料では67機とするが、これは『1/144 リゲルグ』インストにおける
14の生産機数と同じ値であり、何よりエース部隊以外で55機運用されていたということになるため、
信憑性は微妙である。やはりエース部隊含めて67機が実戦参加したというのが妥当であろう。 |
208/140A
| ジオン公国軍 |
23弾? |
B |
 |
シャア専用高機動型ゲルググ MS-14B
H:21.0m W:106.0t
「赤い彗星」ことシャア・アズナブルもエース部隊
へ召喚されたがキシリア・ザビ少将の命令で直
接ア・バオア・クー防衛へ向かったためこの機体
は使用されないまま終戦となった。 |
写真シールの中でも特に物議をかもす設定の機体。MSV当時からその設定は存在せず、にゃご神に
よるオリジナル設定だと思われる(註28)。
そもそも、シャア大佐は独立第300戦隊(ニュータイプ部隊)の司令官となるために宇宙に呼び戻され
たことが『1/144 シャア専用ザク(限定版)』メカニカルファイル(文献81)に記されており、その時に与
えられたのがYMS-14初期生産型25機のうちの1機である。この時に14B用のブースターも同時に与
えられていた可能性はあるが、シャアがブースター装備のゲルググを使用した描写は現在まで存在
せず、その可能性は限りなく低いと思われる。寧ろ、ノーマルの14A用にデータを取ってフィードバック
させるために、敢えてブースターなしの機体をシャアに与えたのではないかと考えられる。 |
209/140B
| ジオン公国軍 |
23弾? |
C |
 |
高機動型ゲルググ MS-14B
H:21.0m W:106.0t
ジオン軍は少数精鋭のエース部隊を編成しMS
-14の改造機を専用機とした。この専用機は増
速用ブースターか、ビームキャノンパックを追加
装備し主にコレヒドール暗礁空域でテストを重ね
ていた。 |
エース部隊には、ライデン機と合わせて12機が配備されたと『MSV』には記載される。ライデン機以外
の詳細については明らかになっていないが、少なくとも『1/144 ゲルググキャノン』ボックスアートから
は、通常の14Aと同様のグリーンカラーの中隊長機(第2or3中隊長)が存在したことが明らかである。
(こちらは別項(140C)を立てるべきであった)
また近年の『MSV-R』において、06Rと同様のスラスターに改造された14RBなる機体が発表された。
しかし、当時から現在に至るまで、このスプリンター迷彩塗装の14Bが確実に存在するという資料は
ない。『1/144 ゲルググキャノン』インストには、14Cの制式色を「特殊部隊が使用したグリーン系」と
する記述があり、これをスプリンター迷彩と仮定するなら14Bにも同様の塗装が施された可能性はあ
る。
なお、『MSV』には、ア・バオア・クー緒戦でエース部隊の14Cが12機、ティアンム艦隊に攻撃をしかけ
サラミス級巡洋艦2、改コロンブス級空母1、MS14、セイバーフィッシュ22の損害を与えるが、14Cも2
機が撃墜され3機が中破したとある。また『コミックボンボン』83年4月号には、ア・バオア・クー攻防戦
で62機を撃墜したものの、8機に損害を受けたという記述がある。このことから、ア・バオア・クー緒戦
の段階でエース部隊は14Bが12機、14Cが7機という状況になり、更に攻防戦で8機が撃墜あるいは
大破・中破したことになる(そのうちの1機はライデンの14B、またもう1機はクルツの14Cであろう)。
エース部隊でさえも非常に損耗率の高い戦いであったことがこれで分かる。 |
210/141/Sシール有
| なし |
復刻10弾? |
B |
 |
パーフェクトガンダム
H:18.5m W:80.0t
「プラモ狂四郎」こと京田四郎がサッキー竹田と
戦うために作ったオリジナル・ガンダム。右手の
二連装ビーム砲、肩のキャノン砲など武装も充
実している。 |
サッキー竹田のパーフェクトジオングに対抗して作り上げた改造ガンダム。
当時の少年たちには本当に憧れの存在で花形的扱いであったが、今見ると・・・。
デザインは大河原邦男や小田雅弘やクラフト団でもなく、ファーストガンダムの作画を手がけていた
板野一郎氏であったことが『1/144 パーフェクトガンダム』インスト(文献82)に記載される。これによ
ると作画当時からお遊び的に、「武装の塊ガンダムVS足つきジオング」と書いていたということなの
で、両者は歴史的に古く、MSVの初原と言ってもいい存在である。
ボンボン当時はまことしやかに「PF-78-1」という型式番号まで与えられていた。
『MSV』は後半になって、ミリタリー色を前面に出す方向から、ジョニー・ライデンというエースパイロッ
ト個人へ人気が移り、MSVシリーズのキット最終作がこのパーフェクトガンダムだったことからも分か
るように、本来の世界観展開と異なる方向に行ってしまい、終息を迎えたことは非常に残念だった。 |
211/142
| ティターンズ |
23弾? |
B |
 |
ハンブラビ飛行形態 RX-139
H:17.9m W:56.8t
パプテマス・シロッコがジュピトリスで試作したこ
のハンブラビは機動力をあげるためにM・A形態
へと変形することができる。 |
型式番号上では、ゼダンの門(ア・バオア・クー)製であるが、劇中の発言などからシロッコが直接製
作したと考えるほうが自然である。ガブスレイの例からしても、偽装的なナンバリングであったか、あ
るいは最終的な組立・調整が該当工廠で行われたのか、どちらかだったのではないかと思われる。
機体そのもののスペックはマラサイやバーザム等よりも劣るが、MAに変形できる運用法から総合的
な評価は高い。可変機構も複雑なものではなく、試作機で終わったのが不思議なくらいである。
MA時には、背部のビームカノンと腕部のクローをメインの武器とし、エイのような形態になる。
なお、フェダーインライフルはガブスレイのものを流用している。 |
212/143
| ネオ・ジオン |
復刻10弾 |
C |
 |
ジャムルフィン AMA-01X
H:17.2m W:58.5t
ネオ・ジオン軍量産型可変モビルアーマー。本
来は高速攻撃用のモビルアーマーが基本形だ
が格闘形態へ変形することができ試作型には
頭部ユニットが仮設されている。 |
『1/144 ジャムル・フィン』インスト(文献83)によると、当初はMA-08ビグザムの系統を引く大型MA
として開発されていたが、戦況の悪化に伴い、完成されていた胸部に急造の頭部、腕部、脚部を取
り付けて実戦投入されたとある。その結果ロールアウトした機体がMA-05ビグロの態様に似たのは
、旧ジオン技術(MIP関連?)がベースとなっているからであろう。その一方で、『ジ・アニメ』86年11
月号には、本機はもともとガザ・シリーズとして計画されていたとの記述がある。計画最初期に仕様
が何度も変更された機体の可能性がある。やっと完成した試作機3機が「3Dチームに与えられた。
急造された機体の割には非常に評価が高く、劇中でもジュドー搭乗のZZガンダム及びビーチャ搭乗
の百式を相手に互角に戦っている。コア3の戦いではハマーン軍として参戦しているが、主戦場には
出てこず、消極的な戦いをしている。「ジャムルの3D」チームが内紛を嫌ったのかは明らかでないが
、その後のチームと機体の行方は不明である。
なお、これ以降ネオ・ジオンはNT用のNZナンバー以外のMA及び可変MAを制式採用していない。
ネオ・ジオン敗戦による国力の低下で、コストがかかるMAや可変MAは敬遠されたものと思われる。 |
213/144
| ネオ・ジオン |
復刻10弾? |
B |
 |
ザクIII改 AMX-011MC
量産が見送られてしまったザクIIIの1機を強化
人間となったマシュマー・セロ専用機として改造
を加えた機体。武装強化、航続距離を向上させ
てありマシュマーはこの機体で最後までハマー
ンを守った。 |
シールにはなぜか記載されなかったが、当時からH:25.3m、W:71.4tの設定が存在する。
一般的に知られる型式番号はAMX-011MCであるが、『EB グリプス戦争編』では「AMX-011S」との
表記になっており興味深い。また、『1/144 ザクIII』インストにおいては、MC型はノーマルAMX-011
と並行して、宇宙戦を重視した形で開発が進められたとの記述がある。以上のことを好意的に解釈
すれば、ザクIII改は、ノーマルのザクIIIのS型パッケージ仕様として同時期に開発が進められたもの
の、ザクIII自体が少数の生産ということになったためにその上位機種であるS型パッケージも量産す
る必要がなくなり、試作品としての機体が上級士官カスタムとして下賜されたのではないだろうか。
また『ジ・アニメ』86年11月号には、マシュマー専用として調整されたバイオ・センサーが搭載されて
いるという記述があり、準サイコミュ機であったことが分かる。
その一方で、クィン・マンサと一緒に出撃したグレミー軍の中にザクIII改とおぼしきグレー塗装の機
体が確認され、わずかながらも複数の機体が存在したもの(S型パッケージとしての)と考えられる。
なお、EBによれば、スカートやプロペラントタンクの大型化により機体の取り回しが遅くなったが、パ
イロットの技量によってそれをカバーしているという記述が見られる。 |
214/145A
| 地球連邦軍 |
復刻10弾? |
B |
 |
コアファイター FF-X7
ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクの中核をし
める小型戦闘機。コアブロックに変形、合体する
ことによりコクピットへとなる。バルカン砲、小型
ミサイルを装備している。 |
『MSV』及び『MSVハンドブック』に非常に詳しい開発経緯が掲載される。
FF-X7 コアファイター自体は、連邦軍が開発するモビルスーツのコクピット兼緊急脱出用としての小
型戦闘機という位置づけであるが、機体の開発自体はハービック社に与えられたFF計画の一連の
流れの完成形であると言える。航空機の技術自体は電子戦や監視衛星の併用などの概念も含め20
世紀末から連邦政府統合後もほとんど変わることがなかったが、宇宙用大艦巨砲主義の発達により
それに伴う宇宙戦闘機の開発が始まった。当時、連邦軍に供給する軍事メーカーは、老舗であると
ころのヴィックウェリントン社と後発のハービック社があったが、経験の浅いハービック社は比較的実
験機の要請が多く、各方面での再確認的内容を持つ機体を次々と開発した。これがFF計画である。
FF計画は大きく4種の用途の機体を開発する事となり、その内容は、1.高高度戦闘機 2.小型戦闘機
3.空間戦用戦闘機 4.空間戦用攻撃機である。2はFF-4 トリアーエズとして、3はFF-3S セイバーフ
ィッシュとして順当に開発を終えたが、1の高高度戦闘機はエンジントラブルを抱えたまま0079年初
頭のジオンの奇襲を受けている。高高度戦闘機としては、FF-6 TINコッドと、型式番号不明(註29)
のフライダーツがあり、前者はデュアルターボジェットエンジン、後者はロケットエンジンを使用する。
ジオンの奇襲によって連邦軍内でもMSの重要性の認識が高まり、学習機能を持つ高度コンピュー
ターを搭載して短期間での戦闘力の向上及びパイロットの保護を目的としたコクピット兼戦闘機の開
発へとシフトした。この結果、開発途中であったFF-6とFF-X7がプラン統合し、FF-X7 コアファイター
としてロールアウトしている。
FF-X7は、機能形状による燃料量や武装に制限があったが、格闘性能は良好なために通常戦闘機
としても採用され少数が量産されている。RXシリーズの核としてはRX-75×4、RX-77×5、RX-78×
8として最低でも17機、他に予備機として数機、更にFF-X7bst コアブースターの核として15機存在す
るため、30機以上が生産された計算になる。
なお、セイバーフィッシュをはじめとするFF計画系や劇中にも登場したフライマンタ、デ・プロッグ、ファ
ンファン、パブリク、ドラゴンフライ、デッシュなどの航空機系はガシャポン化されなかった。 |
215/145B
| エゥーゴ |
復刻10弾? |
B |
 |
ネオコアファイター FXA-07GB
パイロットの生存率を高くするためRX-78ガンダ
ムなどの採用されていたコアファイターをZZガン
ダムは再び採用している。Aパーツ・Bパーツと
合体するとコア・トップ、コア・ベースになる。 |
アナハイム製。アーガマには3機が配備された。バルカン砲及び、マイクロミサイルを8発装備。オプシ
ョンとして機体下部にハードポイントがあり、ミサイルランチャーを搭載することも可能。構造的には華
奢であるが、機動性は非常に高い。 |
216/146
| なし |
復刻10弾? |
B |
 |
パーフェクトズゴックキャノン MSN-07FC-B
コミックボンボンオリジナルMSデザインコンテス
トの最優秀作。格闘戦用に作られたMSM-07ズ
ゴックに強化装甲と支援用キャノンを装備したも
の。水中から敵基地に近づき強襲爆撃ができ
る。 |
『コミックボンボン』87年6月号で募集し、同8月号で発表されたSDガンダムデザイングランプリの最優
秀賞作品。シールの機体解説はオリジナル。また『SDガンダム カラー完全大図鑑』(文献84)では、
シャア専用ズゴックを素体として、背中のブースターは2倍の出力という記述があるが、こちらもここで
しか見られない記述で信憑性は微妙なところ。背中のキャノン砲については実弾系なのかビームキ
ャノンかは言及されていない。額にハイメガキャノン砲があるらしいので、少なくとも一年戦争当時の
MSではないであろうと思われる。
後年、『ホビージャパン』2000.7月号で作例化された。
「パーフェクト」という呼称が、当時の中二病的存在であったことを如実に示す好例である。
作者の東京都の竹本 亨さん、見ていたら連絡ください。 |
ガンダム15弾
217/147
| エゥーゴ |
復刻10弾? |
B |
 |
フルアーマーZZガンダム FA-010B
H:19.86m W:87.2t
ZZガンダムは可変モビルスーツの弱点である
装甲の弱さをカバーするために追加装甲を装備
しフルアーマーZZガンダムとなった。この装甲に
はメガ粒子砲なども装備され武装の強化も行わ
れている。 |
コア3での最終決戦の直前で使用された仕様。
アストナージの独断による仕様で、装甲強化の他に、各種スラスター追加、背部ミサイルポッドの追
加などが行われている。この形態ではGフォートレスに変形不可能であるが、戦況的に可変は不要と
判断の上でこの仕様になされたものと考えられる。
腰部のメガ粒子砲は1発しか撃てず(エネルギーCAP方式か)、ラカン隊と交戦してマイクロミサイルを
撃ちつくしたところでこの装甲をパージし、素体のZZガンダムに戻っている。
なお、ハマーンとの最終決戦においては、この仕様のスラスター及びマイクロミサイル増設を保持し、
メガ粒子砲や各部装甲をオミットした別タイプの強化装甲仕様が確認されている。
本来ならば、写真シール仕様が「FA-010A」、最終決戦仕様が「FA-010B」だったのではないか。
この最終決戦仕様は別項(147A)を立てるべきだった。 |
218/148
| ティターンズ |
復刻10弾? |
B |
 |
ガブスレイ(飛行形態) RX-110
H:26.5m W:56.2t
高出力バーニアを多数備えるガブスレイの飛行
形態へ変形することによってメインバーニア16
基全て後方に向けることができ、その出力を全
て使いきることができる。 |
解説の16基というのはサブスラスターのことであり、本来の設定は22基のメインスラスターである。
シロッコの設計らしく、変形時には後方に大推力を集めるというのはメッサーラと同じである。MS時の
脚部はMA形態時のマニュピレーターとなるために、脚部そのものにはメインスラスターは備えられて
いないものと考えられる。つまり、高速機動力に対してのマニュピレーターによるAMBAC機能は比較
的小さいと考えられ、MA時には小回りが利かない推進剤を食うスタイルの戦闘を余儀なくされる。
これは対MS戦・対艦戦時にも有利とは言えず、戦線に急行するぐらいしか役に立たない。これが可
変MAを含むMAの衰退につながったものと思われる。
なお、ガブスレイは脚部だけMA形態になる中間形態も存在するが、ガシャポン化はされなかった。 |
219/149
| ネオ・ジオン |
復刻10弾? |
B |
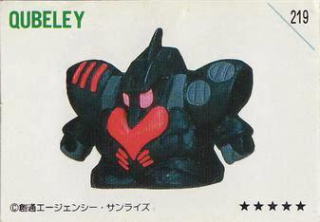 |
量産型キュベレイ AMX-017
H:18.9m W:62.1t
グレミー・トトが率いるニュータイプ部隊の専用M
S。背中に自在に動くアクティブカノンを装備。
ファンネルも30基に増設され火力を強化させて
ある。 |
放映当時はAMX-017表記だったが、現在ではAMX-004Gと併用されている(註30)。
グレミー率いるニュータイプ部隊が搭乗するキュベレイ。通常、ガンダム世界において量産型というの
はワンオフの試作型より性能が劣る場合が多いが、量産型キュベレイに関しては試作型よりも性能
が高いという設定になっている。但し、それでも経験値の少ない覚醒直後のNTパイロットはその性
能を完全に引き出せたとは言えず、パイロットとしても経験値の高いキャラ・スーンの攻撃に結果的
に全滅することになった。
後年、「ガンダムUC」において量産型キュベレイのパイロットはかねてから噂されていたプルシリーズ
が搭乗している描写があり、命令実行者(マスター)のグレミーが戦死した動揺から動きが鈍り撃墜
された様子が描かれた。プルは12番まで番号が明らかになっており、量産型キュベレイが少なくとも
10機実戦投入されたことが判明している。
なお、クィン・マンサの随伴機として搭乗した時は、グレミー軍がほぼ全機種に施したグレー系塗装
で搭乗しており、別項(149A)を立てるべきであった。しかし、このグレー系塗装は時間経過と共に
いつの間にかこの青紫系の本来のカラーリングに戻っている。 |
220/150
| ジオン公国軍 |
復刻10弾? |
B |
 |
ザク マインレイヤー MS-06F
H:17.5m W:78.5t
8000機以上が生産されたザクにはいろいろな
バリエーションがあった。この機体は宇宙空間
の機雷施設用のランドセルをつけたもので12発
の機雷をつみ、5倍の航続距離があった。 |
『MSV』には、ジオン軍の機雷敷設はルウム戦役直前から大戦末期近くまで行われ、機雷敷設型の
06Fとムサイ巡洋艦1隻でチームを組んで作業に当たったと記述される。また『ザクII マインレイヤー』
キットインスト(文献85)には、ランドセルの質量によって機動性は併殺されるが、5倍の航続距離を
持ち、ムサイで補給をしながら長時間の地道な作業を行い、連邦艦艇にかなりの損害を与えたと記
術される。
ここで注目すべきはこのタイプの機体が06Fという型式番号のままであるという事である。ジオン軍に
は、高速機動ブースターを付けたゲルググが14Aから14Bと型式番号を改められたのに対し、ザクマ
インレイヤーにおいては型式番号が変更されていない。燃料供給デバイスや航法、AMBACシステム
の再調整などを余儀なくされると推察されるため本来ならば06Fではなく別の型式番号を与えられる
のが妥当であると思われるが(ボードゲーム「トワイライト・オブ・ジオン」では、この機体を06Hという
型式番号を与えている)、実際には変更されなかったのは、あくまで機雷敷設ランドセルが武装オプ
ションとしてしか認識されてなかった可能性がある。
また、ルウム戦役直前からこの種の機体が活動していたとの記述であるが、この時期06Fは生産さ
れ始めたばかりの最新機種であり、多数を06Cが占めていた頃である。06Cや05ベースのマインレイ
ヤーが存在しなかったのか、あるいはそれらも含めて06Fと呼んでいたのか全く不明である。
但し、対核装備をオミットして生産された06Fは大戦初期においては最も軽量な機体であった事は確
かであり、その点においては06Fをベースにしたことは妥当であるかもしれない。 |
221/151/Sシール有
| なし |
23〜24弾? |
B |
 |
レッド・ウォリアー
初代プラモ狂四郎の京田四郎が製作したガンダ
ム。ワールドシミュレーション大会で初登場し圧
倒的な強さをみせた。両肩に可動バーニア、右
腕の内蔵型ビームサーベルなど格闘戦に重点
を置いている。 |
レッド・ウォーリアとも表記される、プラモ狂四郎オリジナルガンダム。
元々はパーフェクトガンダムマークIIIとして企画されていたものらしい。
武装としては他に、ランドセルに一体化されたバズーカ砲や胸部の隠しミサイル等がある。
MS-Xでデザインされたガンキャリーに似たガンキャリアーというサポートメカとの合体が可能で、Gア
ーマー的な運用が可能であった。
初代パーフェクトガンダム、パーフェクトガンダムMk.2(HCMパーフェクトガンダム)が重装甲重装備を
目指していたのに対し、この機体は軽量化・高機動化を目指した機体となっている。 |
222/152
| ティターンズ |
24弾 |
B |
 |
バウンドドック NRX-055
H:29.7m W:129.4t
強化人間用に開発されたバウンドドックはオー
ガスタのニュータイプ研究所でサイコミュ調整を
してドゴス・ギアに配備された。 |
この機体はプロトタイプであり、複座型であった。正式な型式番号はNRX-055-1。
パイロットはバスク・オム大佐が設立した強化人間部隊のゲーツ・キャパ大尉及びニュータイプ研究
所博士のローレン・ナカモトであり、2号機のロザミア・バダム中尉の精神安定役としても任務を兼任
した。
『Zガンダム大辞典』には、バウンド・ドックはMAN-07グラブロをベースに水中用・陸上用として開発
されたと記述され、改造によって宇宙空間での活動も可能になったとされる。また、サイコガンダム
と同じサイコミュシステムを使用していたとも記述される。 |
223/152A
| ティターンズ |
24弾? |
B |
 |
バウンドドッグ NRX-055-1
H:29.7m W:129.4t
ティターンズのバスク・オム大佐は強化人間に
よる可変MS部隊編成を計画した。その部隊に
試作機として3機配備されたMS。この1号機の
み複座のコックピットになっている。 |
裏面の解説はプロトタイプ機のものであり、222にプロトタイプ機を持っていってしまったために起き
た入れ替わりミスだと思われる。
『ニュータイプ別冊 機動戦士Zガンダム』には、他の可変MS同様マグネットコーティングによって非
常にスムースに変形できると記述される。またこの機体は、MA時のほうが特に戦闘能力が優れて
いるとも記述される。 |
224/152B
| ティターンズ |
24弾 |
B |
 |
バウンドドック NRX-055-2
H:29.7m W:129.4t
ティターンズの強化人間MS部隊に配備された
3機のバウンドックの2号機は記憶操作された
ロザミア・バダムが乗り込んだ。その後この機
体にはジェリド・メサが乗るかZガンダムに破壊
される。 |
こちらも裏面の説明が2号機(ロザミア機)のものに入れ替わりミスが起きている。
この黄色のカラーリングの機体はジェリド機(NRX-055-3)という設定がもともとあったが、劇中では
ロザミア死後に2号機にジェリドが乗ったことによってこの3号機は表に出てこなかった。
バウンドドックはニュータイプあるいは強化人間用に作られているので、そのようなパイロットでない
限り最大限の能力を発揮することはできないが、ジェリド中尉はオールドタイプでありながらこの機
体を乗りこなした。 |
225/153
| エゥーゴ |
24弾? |
B |
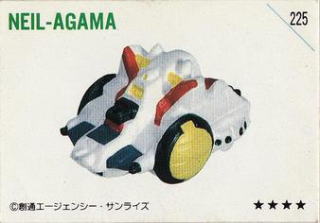 |
ネェル・アーガマ
月にあるアナハイム・エレクトロニクス社で建造
した新型戦艦。兵士たちの意見をとりいれMSカ
タパルトとソーラーウィングなどが追加され武装
もハイメガキャノン砲が装備されている。 |
ネェル・アーガマとは、「アーガマに近いもの」という意味である。しかし、アーガマ級に似た部分はあ
るものの、全くの新造戦艦である。形状はむしろホワイトベースに近くなった。
左右と中央にMSカタパルトを配置する他、艦後部に着艦専用のデッキを持つ。『ニュータイプ別冊 ガ
ンダムZZ』によれば、推力はアーガマの1.2倍で、搭載MSは最大12機。また『EB グリプス戦争編』に
よれば、操艦及び火力使用をコンピュータサポートによりブリッジからの指示だけで5名ほどの人員
で対応可能が特徴的と記述される。
なお、『ガンダムUC』でもロンド・ベル隊の中核艦として近代改修を受けた後、単艦配備されていた。 |
226/154
| エゥーゴ |
24弾? |
B |
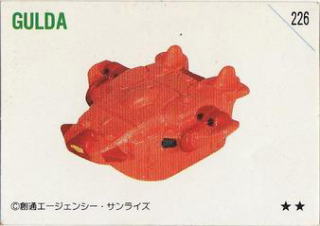 |
ガルダ(アウドムラ)
本来はスペースシャトルの高高度基地として
開発された世界最大の輸送機。アウドムラは
ジャブロー基地攻撃などにその力を発揮した。
このガルダタイプは4機が製作されている。 |
シールにはエゥーゴ所属とあるが、実際にはカラバが使用している。
『Zガンダム大事典』によれば、全長317m、翼長524m。また『ニュータイプ100%コレクション Zガン
ダム』によれば、旧ジオンのガウ攻撃空母の流れを汲み、数十機のMSを収容できるとある。
20発のエンジンで空を飛び、輸送機の割には自衛用に多数の機銃座を持つ。
なお、アウドムラとは北欧神話で最初に生まれたという雌牛のことである。 |
227/154A
| 地球連邦軍 |
24弾 |
B |
 |
ガルダ(スードリ)
アウドムラと色違いのガルダタイプ輸送機。M
Sの長距離輸送など多目的に使用されている
。スードリ、アウドムラなどの名前は方角の神
の名前からとったものである。 |
元々はアウドムラと共にジャブローに配備されていたがエゥーゴに奪取され、その後再び地球連邦
軍に制圧された数奇な運命の機体。後にアウドムラを追いかけたベン・ウッダー大尉の部隊が度々
戦闘を仕掛け、最後にはベン・ウッダー大尉アウドムラに特攻をかけるが撃墜される。
元々ガルダ級は、世界の四方を守る四神の名前をつけたという設定があり、このスードリは北欧神
話で南方を守護する小人「スズリ」を意味していると考えられる。但し、スードリ以外は特に方角を
守護する神の名前は付けられていないようである。
『EB グリプス戦争編』には、0082に一番艦ガルダが就役したとある。また、ほとんどの参考文献で
4機が製造されたと記述されるが、『EB』では5機が製造されたと記述される(註31)。
同型機としてメロゥドが劇中で確認されるが、これは別項を立てるべきであった(154B)。また、一
番艦のガルダであるが、『EB』以外で言及されたことがなく、機体の塗装色なども不明である。
なお、『ガンダムUC』では灰白色のガルダ級が登場している。これとは別に、『劇場版Zガンダム』
においてブラン・ブルターク少佐の部隊が青緑色のガルダ級に所属しているというが未確認。 |
228/155
| 地球連邦軍 |
24弾? |
B |
 |
チベ改
一年戦争時ジオン軍が使用していた重巡洋艦
チベを終戦後地球連邦軍が改良を加えた。船
体の3連装ビーム砲、ミサイルの他にメガビー
ム砲が新たに装備された。 |
ガシャポンでは船首に増設されたMSカタパルトが表現されておらず、旧チベ級と言っても過言では
ないフォルムであるが、船体後部側面に砲塔表現があるためチベ改として造形されたと思われる。
シール説明は『ニュータイプ100%コレクション Zガンダム』にほぼ準拠しているが、かなりの誤解の
ある表記となってしまっている。船体前後の3連装ビーム及び両舷のミサイルはチベ級から存在す
る。船体後部側面には単装ビーム砲が増設された。しかしチベ級との大きな違いはそれらよりも船
首に増設されたMSカタパルトであり、MSの運用に重点を置いた改修となっていることである。また、
この艦はジオン共和国所属であり、地球連邦軍によって改修されたという事実は存在しない。
EB『グリプス戦争編』には、一年戦争の終戦条約の条項の中にジオン共和国には宇宙艦の制限
の項目があり、新造艦を製造できない中で艦隊の中心的存在として運用されていると記述される。
ジオン共和国は、敵の敵は味方という理論でティターンズに協力して共同作戦などを行った。しかし
装備が旧式ゆえに、劇中でのシロッコのセリフ等からも戦力としてほとんど期待されていなかった。
なお、ジオン公国軍のチベ級に関しては228EX/155Aを参照のこと。 |
229/156
| 地球連邦軍 |
24弾? |
B |
 |
Gブル
ガンダムの強化パーツ「Gパーツ」のバリエー
ションの1つ。Gパーツの前部とガンダムの上
半身+コアブロックが合体して高機動タンクと
なったもの。 |
『MSV』には、強大なRX-78の反応炉を十分活用でき、高出力ビームキャノンと高機動性で無敵の
重戦車といえるような怪物だったと記述される。その一方で、重量がRTX-44並になり運用できる
地形が限られていたとの記述も併記される。
興味深いのは『MSV』『1/250 Gアーマー』メカニカルファイルに記述される、コアブロックを使用しな
いGブルの形態の記述があり、後者文献ではそれを「Gブルイージー」と呼称している(通常のGブ
ルは「フルサイズ」と表現している)。但し、この形態だと後部(コアブロック接続部)に攻撃を受けた
場合RX-78に換装できなくなる恐れがあるため、コアブロックを入れた状態で運用すると記述され
る。側面のシールドも現場で生まれた運用であったとの記述もあることから、当初はコアブロックも
シールドも使用しない防御面が脆弱な重戦車だったものと考えられる。
なお、シールで正面になっている側は本来後部であり、こちらを戦闘面に向けるのは自殺行為で
ある事は容易に想像できるので、正面を誤認しているものと思われる。 |
註26 『ガンダム・センチネル』(文献85)において、G-VはORX-013 ガンダムMk.5との設定がなされた。その中で、アクシズに忠誠を誓った
ローレン・ナカモト博士がネオ・ジオンに1機を送り、それがAMX-014の原型になったとされる。しかしZガンダム劇中において博士は
ドゴス・ギアのブリッジでコロニーレーザーの直撃を受けて死亡しており矛盾が生じる。
註27 例えば、指揮官が左利きだった場合、ヒートロッドを使う格闘が右手で行われるのは違和感が強かったとも想定でき、左右の配置を
逆にしたような"レフティ・カスタム"のような例もあったのではないだろうか。
註28 MSV当時に一番最初に発表された14Bの画稿は、一般的に知られるライデン専用カラーとは異なる赤系の機体にブースターを取り
付けた背面画稿であるが、これをにゃご神はシャア機と考えた可能性がある。
註29 フライダーツは、FF-3S セイバーフィッシュでも採用されたロケットエンジンを使用しているために大きなトラブルもなくロールアウト
されたものと思われる。FF-6 TINコッドが「比較的後期に開発」という記述があることからも、フライダーツはFF-6よりも以前に型式
番号を与えられた可能性が高い。また、『コミックボンボン』83.9では、空間戦用機として型式番号不明の「トマホーク」がセイバー
フィッシュと同時期に開発されたという記述がある。この「トマホーク」はFF計画の4.空間戦用攻撃機と考るのが妥当であろう。
この他に型式番号不明の偵察機フラットマウスが存在し、これは20世紀末の技術の延長ということから比較的初期に製作された
と考えられる。一方で判明していないFFナンバーは、1・2・5であるので、フラットマウス、フライダーツ、トマホークがそれぞれにこの
ナンバーが振られていたものと推察できる。他方、タンクバスター型のマングース攻撃機はヴィックウェリントン社製であると明記され
ているが、この他に地上で局地戦闘機として運用されていた3発ラムジェットのフライアロー戦闘機もVW社製である可能性が高い。
註30 量産型キュベレイは、試作型キュベレイAMX-004及び004Bから性能向上を果たしたが、キュベレイというフォーマットはそのまま
維持されている。ネオジオンの他機種の類例からも、同系列機種に別型式番号を与える例が他に見当たらず、現在主として使用
されているAMX-004Gナンバーが妥当である。推定ではあるが、当初はキュベレイを超えるNT専用機としてAMX-017ナンバー
で新機種を開発していたものの、早期投入の必要性などから結果的に既存機種の改良版に留まったのではないだろうか。
NZ-000クィン・マンサが先に完成してしまったというのも新型ナンバーの開発が断念された一因となったであろう。
註31 『EB』の記述を肯定的に考えるならば、『EB』は第二次ネオジオン紛争の後に書かれた書籍という設定であることから、撃墜された
スードリの代わりに、0088以降に新造艦が製造されて4機体制を保ったという可能性がある。
参考文献
79. 『1/144ドーベンウルフ』キットインスト 1986,バンダイ
80. 『1/250 Gアーマー』メカニカルファイル 1984,バンダイ
81. 『1/144 シャア専用ザク(限定版)』メカニカルファイル 1985,バンダイ
82. 『1/144 パーフェクトガンダム』メカニカルファイル 1984,バンダイ
83. 『1/144 ジャムル・フィン』キットインスト 1986,バンダイ
84. ボンボンスペシャル31『SDガンダム カラー完全大図鑑』 1989,講談社
85. 『ガンダム・センチネル』 1989,大日本絵画社
【BACK】