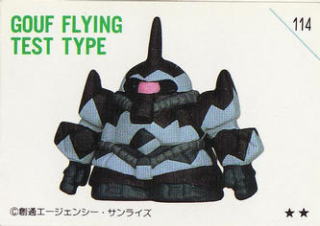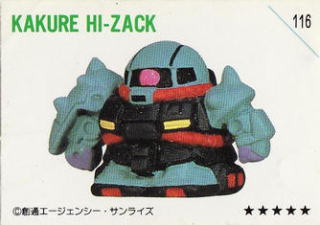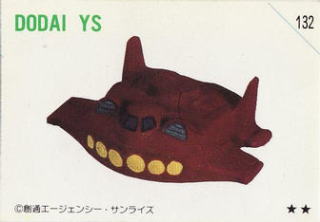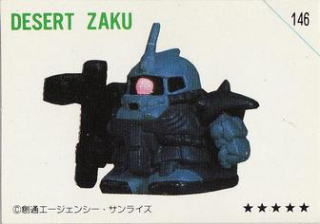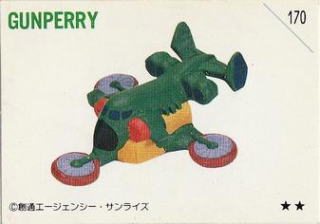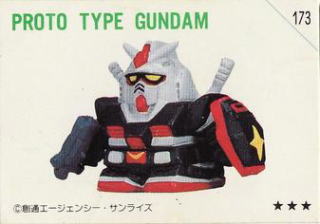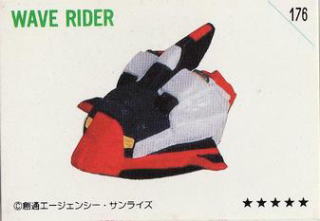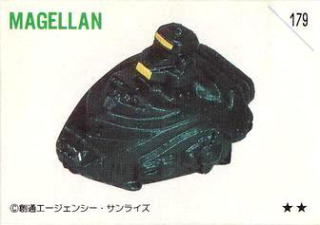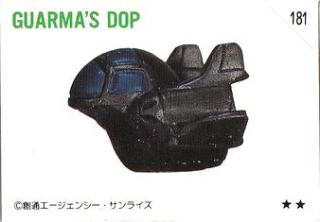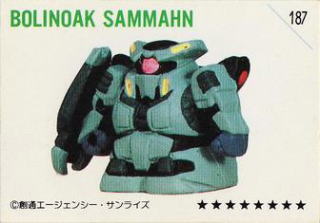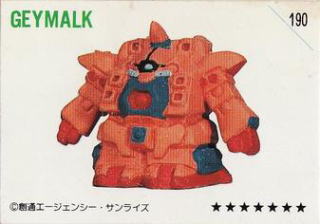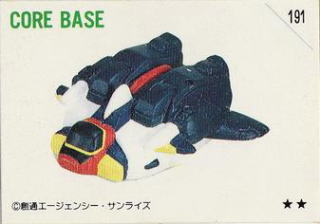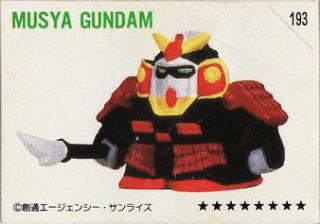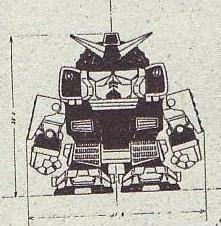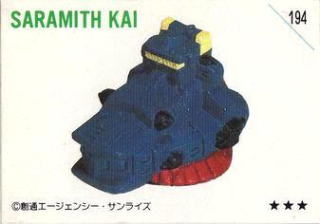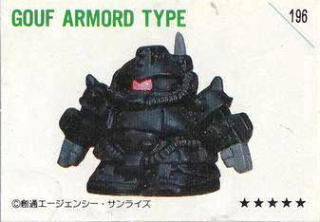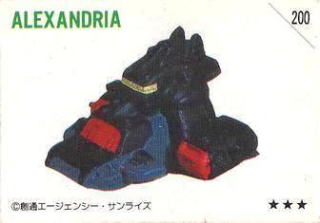SD写真シール No.101〜200
凡例
シール通しNo./キャラNo./
| 所属 |
封入弾 |
入手困難度 |
画像
|
シール裏面解説 |
| 備考 |
skip to No.150
ガンダム6弾
101/62C
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
砂漠用ザク ピンクパンサー機 MS-06D
H:17.6m W:73t
局地戦用モビルスーツとしてはMS-07がす
でに配備されていたが、アフリカ戦線向きと
してはMS-07よりも低コストなMS-06Dを中
心に配備していった。この機体はピンクパ
ンサー隊のもの。 |
MS-06Dが配備された隊の中で最も戦果を挙げたのが、カラカル隊とピンクパンサー隊であったと
『MSV ポケットカード』(文献38)に記述がある。ピンクパンサー隊には早くから06Dが配備され、
サハラ砂漠〜ジブラルタル海峡までを制圧し、ジオン軍のヨーロッパ侵攻の足がかりを作ったこと
でよく知られている。
なお、『1/144ザクデザートタイプ』インスト(文献39)にはピンクパンサー所属機の右肩の盾の部
分にキラービーのエンブレムの指示がある。一方で、『コミックボンボン』83年5月号には、特殊部
隊用の胸部エンブレムとしてキラービーを挙げている。ピンクパンサー隊が大きな戦果を挙げたと
いう記述から、この「特殊部隊」というのはピンクパンサー隊であったことが窺える。
また、06Dには4機で取り扱うG92組立式砲座という特殊な武装も存在したと文献34には記載され
、航空機支援が受けられない地域でも大きな戦果を挙げたという記述がある。これも非常に特殊
な武器であることから、ピンクパンサー隊の記述であった可能性が高い。 |
102/63
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ドズル・ザビ専用ザク MS-06F
H:17.5m W:78.5t
ザクIIをベースに徹底的なチューンナップ。
巨体のドズル中将に合わせてコクピットの
容積を拡大。両肩はスパイク付きアーマー
に変更されている。武装は特製の大型トマ
ホークを持つ。 |
一般に高級将官のカスタム機はステータスシンボルとして存在するが、ドズル中将は戦場視察の
名目で、実際にルウム戦役で3個戦隊のザクを率いて実戦参加した。
なお、本機はソロモン陥落の際に格納庫で焼失した。 |
103/64
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクII 黒い三連星(オルテガ)
MS-06R-1A
H:17.5m W:79.5t
MS-06RはFタイプの性能を向上したタイプで
ある。主な改修点はランドセル、腰スカート、
脚部で、ここを中心にエンジンのパワーアッ
プがはかられた。 |
F型の各部配置を見直して推進剤容量を増やし、それに伴って電気系統も変えてあるため、中身
は06Fとは全く別の機体となっている。更に姿勢制御のために微細なコントロールを要求されるた
め、コントロールスティックは中央の1本から、両サイドコンソールの2本に変更され、操縦系統も
大幅に変更された。また、ジオン初の(簡易)脱出装置も標準装備されている。推進剤は全開で
15分噴射可能。
『1/100MG 06R』インストでは、06Rの脚部は、歩行装置としての機能を最小限に残しただけで、
基本的には推力ユニットとして機能し、そのために06Fや06Sと違って純空間戦用MSとして特化し
た機体、と位置づけられている。また、この資料には、0079年6月に配備された機体と紹介されて
おり、少なくとも6月の段階でロールアウトしたことが分かる。 |
104/64A
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクII 黒い三連星(マッシュ)
MS-06R-1A
H:17.5m W:79.5t
ザクIIは、それまでのFタイプに比べ、かなり
の高性能ではあったが熟練パイロットにしか
操縦できず、また生産コストが高いため各指
揮官やエースパイロットの申請による受注調
整で生産された。 |
生産コストが高いことと、稼動調整の難しさから量産化は断念されるものの、非常に高性能なため
にエースパイロットからは引き合いが強く、「連邦の戦艦を沈めるよりも、Rタイプを手に入れるほう
が難しい」とまで言われた。
生産機数は、生産ライン上にあったR-1型から転換された11機を含め100機あまりであったと、メカ
ニカルファイル『MS-06R ザクII』(文献40:註7)に記載されるが、近年の『MG 06R』インストに記載
された56機+R-1改修分10機=66機が現在一般的に認知されてしまった模様。 |
105/64B
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクII 黒い三連星(ガイア)
MS-06R-1A
H:17.5m W:79.5t
ザクIIのパイロットの中で有名なのはキシリア
少将直属の黒い三連星である。彼らはチー
ムを組んでからMS-05B、06C、06S、06R、
09とモビルスーツを乗り継いでいった。 |
胸に付いている機体ナンバー「06」は、本来オルテガ機のものであり、ガイア機は「03」、マッシュ機
は「02」の機体ナンバーである。
なお、黒い三連星使用06Rはグラナダ製であり、他の06Rと多少細部が異なっている。
ガイア小隊が09を与えられて地球に降下した後は、この06Rはオーバーホールを受けて再配備さ
れている。 |
106/64C
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクII 一般機 MS-06R-1A
H:17.5m W:79.5t
ザクの燃費配分の問題を解決するために開
初されたモビルスーツ。燃料タンクはカートリ
ッジ化され、編隊行動の時はカートリッジを搭
載したザクが随伴した。 |
R-1型は極めて高性能であったが、06Fをベースにした制約から推進剤不足は否めず、配備された
直後はパイロットの不慣れなせいもあって、作戦途中で推進剤切れを起こす事例がしばしば報告
された。元々はムサイやバルキリータイプの空母で推進剤補給が可能であったが、この欠点を重く
見た開発部は脚部の燃料タンクをカートリッジ化してこの問題の解決を図った。カートリッジは06R
のみで構成された小隊でも、指揮官機のみ06Rの小隊であっても、06Fが予備を持って随伴した。
なお、『MSV 宇宙編』では、R-1型からの改修点として、稼動不良が多かったジオニック社製のロケ
ットからツィマッド社製に変更したと記述され、開発部は猛反対したものの開発責任者のエリオット・
レム中佐の強い要望によって実現したとある。これにより06R-1Aの完成度は飛躍的に高まった。
『ミリタリーファイル』では、エース部隊に14Bや14Cと一緒に配備されたグリーン系の機体が掲載さ
れる。なお、作例のカラーリングは確実なものは文献資料には見当たらないが、『高速機動型ザク』
ボックスアートに描かれる06R(R-1か1Aかは脚部カートリッジが見えないため不明)はこの塗装例
の可能性もある。 |
107/64D
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクII 試作タイプ MS-06RP
H:17.5m
ザクIIのテスト用に2機試作されたモビルスー
ツ。テストは月のグラナダで行われ、エリオッ
ト・レム少佐が2週間かけて行った。このテス
ト結果が良好だったのでザクIIの量産化が決
定した。 |
06F後期型を改修して作られた機体。ランドセルの推力は06F型の2倍を有する。テストには06F型
以上の新兵装も試され、420mmと360mmロケット砲が試作状態で供された。420mmロケットは生産
上の問題から却下され、360mmロケットの装弾数を増やすことで標準兵装に承認された。試作機
は2機ともディグロウオレンジに塗装。レム少佐は1号機でテストを行った。
レム少佐は、ジオニック社の社員としてMS-02、03、04の開発を手がけ、MS-05、06では軍属とし
て佐官待遇で出向した。06R-1、R-2の開発では主任となり中佐待遇となった。その後、06R-3開
発の主任にも任命されたが、軍の開発研究をよそに自分のテーマも研究していた。終戦後は連邦
軍の強い要望により技術本部付き士官となっている。 |
108/64E
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクII 先行量産型 MS-06R-1
H:17.5m
ザクIIのうち初回生産分として造られた22機は
先行量産型と呼ばれていた。初めは本国防衛
本隊やパトロール艦隊に配備されたが燃料を
すぐに使いきってしまうことが多く、性能を生か
しきれなかった。 |
06R-1は、プロトタイプから生産効率を上げるために腰部に集中していたインテグラルタンクを脚部
や胴体上部に分散させた。配備は実戦テストを兼ねて本国防衛隊を含む各要塞やパトロール部隊
に行われたが、燃料を使い切ったり、脚部エンジンの作動不良などにより多くが撃破された。また、
燃料搭載量の少なさは母艦からの行動半径を狭め、以上の欠点を指摘されたために、生産ライン
上のR-1から全てR-1A仕様に変更された。
なお、カラーリングは指揮官機を除いてグリーンのマニュアルカラーが正式塗装となっている。
『戦略戦術大図鑑』では、R-1として紹介されている代表の機体(260、腕部にエンブレム)を、派手
な塗装を嫌う「ワンショット・ワンキラー」のブレニフ・オグス中佐機と紹介している。他にR-1型の配
備例としては、ソロモンを基地とする特殊部隊やグラナダの第7師団が挙げられる。 |
109/65
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
サイコミュシステム試験用ザク MS-06Z
H:18.7m W:145t
サイコミュシステムをザクに導入するため極秘
で3機だけ試作されたモビルスーツ。コードネ
ームは「ビショップ」。ザクの最終型ともいえる。 |
『Z10本』には、やや細身の06Z2号機が所収されており、別項を立てるべきであった(65A)。
MAN-03と同時に開発が進められていたが、腕部のビーム砲の小型に手間取り、MAN-03に10日
ほど遅れて完成している。グラナダで製作され、実験艦レムリアに搭載されコレヒドールで稼動試験
が行われた。推力は388tと、06Sの3倍、06Rの1.5倍を有したが、稼働時間は10分と短く戦場での
性能は疑問視された。またパイロットの能力不足もあって、本機の性能を十分に引き出すことがで
きなかったため、2号機はグラナダに戻されMSN-01への改修を受けて更に試験を重ねた。
06Zは14と同系統のケーブル内蔵式の構造となっている。
なお、06Z1号機、3号機及びMSN-01は実験終了後ア・バオア・クーへ移され実戦参加している。
また『ミリタリーファイル』によると、コレヒドールでの実験中に連邦パトロール艦隊と遭遇、これを全
滅させるも、1号機小破、2号機が中破したため、これを契機としてMSN-01への改修を行ったとある。
06R以上の機動力とビーム砲装備なので、個人的には★1つは全く納得できない。 |
110/66
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
高機動試作機 YMS-08A
陸戦用ザクを改良して機動性を高めた試作モ
ビルスーツ。しかし期待したほどの高性能化が
できず、試作機だけで計画は中止されてしま
い、同時期に開発されたグフに量産機の座を
奪われた。 |
シール解説では陸戦用ザク06J型を改良したとあるが、『MSV』では06F型をベースにしていると記述
される。開発中の新型推進装置(『MSV地上編』では大型ロケットモーターとしている)を背部と脚部
に配置し、短距離ジャンプ飛行も可能なように設計されたが、実際には満足できる性能ではなかっ
た。結局5機が試作されただけで07計画に吸収された。07は08の背部ランドセルの機構を組み込み
短距離ジャンプ飛行が可能になった。
『コミックボンボン』83年9月号ではYMS-08の開発経緯に触れ、その中で「08Aでプランは07へ統合
されている」と記述があり、YMS-08と08Aは別の機体であったことが示唆されている。
なお、『MSV地上編』では、YMS-08Aはツィマッド社による07計画への競作機であり、この失敗が09
開発で結実したと記述される。 |
ガンダム7弾
111/67
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクキャノン MS-06K
H:17.6m W:80t
北米キャリホルニアの秘密工場で開発された
陸戦用モビルスーツ。全機が実戦配備された
が、重量バランスに問題があり、9機だけで量
産はされなかった。 |
作例は、2弾のザクキャノンの頭部を流用している。
当初は06Jに対空砲をオプションとして付けただけのプランであったが、連邦軍のRX-77タイプの出
現によって、プランを対MS戦闘の支援機として0079年10月にロールアウトした経緯を持つ。
対MS戦闘には、背部ランドセルに取り付け可能のビッグガンを装着する事もでき、実戦使用された
記録も存在する。このシングルアンテナタイプの機体は、ラム・アルフレディーノ少尉機が有名。
『1/100 ザクキャノン』インストによれば、試作された9機は、まず米国南西部で実用評価に06Jへ
の支援部隊として投入、その後キャリホルニアベースに戻されるまでがこのサンドカラーであった。
続くカナダ方面への投入では、標準としてダークグレー、森林地帯向けにはダークグリーンの迷彩
が施された。また量産検討機は一時期通常のザクと同色だった。これら3種のカラーリングは別項
を立てるべきであった。 |
112/67A
| 地球連邦軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクキャノン(宇宙空間用) MS-06K
H:17.6m
陸戦用の06Kの背中に宇宙用バーニアを装備
して宇宙でも使用できるように改造されたもの
。コクピットはリニアシートに改造され、右肩の
キャノンはビームではなく実体弾を発射する。 |
戦後連邦軍に接収され改造された機体。レプリカとして増加試作された機体も存在したと思われる。
ティターンズのアレキサンドリア級ハリオに搭載されており、ラビットタイプの隊長機も存在する。 |
113/68
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
ザクタンク MS-06V-6
H:12.5m W:85t
MS-06Vザクタンクと同じ再生モビルスーツだ
が、人が乗って作業をするクレーンや強化マ
ニピュレーターを装備している。ミサイルポッド
を再武装して実戦投入されたものもある。 |
ボルネオ戦線でグリーンマカクと呼ばれたザクタンクのバリエーション。大型の強化マニピュレータ
ーを使い、高密度なジャングルを進むことができた。背面の設定画稿は存在しないが、ザクタンク
に準じていると思われ、オプション装備のクレーンを取り付けたスタイル。
ザクタンクには他のバリエーションとして、左右にストンパーを持ちロケットポッドで重武装にしたタ
イプや、後部に特殊トレーラーを牽いてキュイを2台縦置きにしたタイプなどが存在し、軍部に提出さ
れた順にナンバーが振られたが、数多くのバリエーションが存在したにもかかわらず殆どが戦火で
失われたしまったため詳細が残っていない。グリーンマカクは現存する少ない例である。
近年ではアーケードゲーム「戦場の絆」においてグリーンマカクが登場し、ストンパーのことを腕部
大型マニピュレーターによる格闘攻撃のこととしているが、おそらく間違った用法であろう。
なお、マカクとはニホンザルに近縁の中型猿のことであり、肩部のマーキングと関連があると思わ
れるが、マーキングが赤く、更にイモリのようでもあるため断定できない。 |
114/69
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
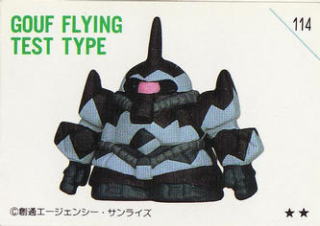 |
グフ飛行試験型 MS-07H-4
H:18.5m
試作された07Hタイプ4機のうち07Bをベース
として改修したタイプ。肩の装甲は整流効果
を考えて形状変更し腰にはフィンが付けられ
た。同機はエンジントラブルが続きテスト10日
目に空中爆発した。 |
試作された07Hであったが、エンジンの不調や搭載燃料の限界等によって一定巡航飛行ができる
ものではなかった。そこで改良として背部にドロップタンクを取り付けた07H-2仕様となったが、若
干の向上に過ぎなかった。そこで本部は脚部に新型エンジンを換装、フィンの大型化などの改修
を4号機に行い、これを07H-4として引き続き高調子であった3号機と共に試験が続けられた(註8)
。性能的には満足の行くものとなったが、エンジンの整備は難航を極め、テスト10日目にしてフラン
ク・ベルナール少尉を乗せたまま空中爆発、07H計画は中止された。本来の目的であったMS単体
の移動性能の向上は、ドダイYSとの連携によって後に達成された。背面の画稿は存在しない。
なお、『Z10本』では本機を「グフ空戦型」と紹介しており、一定の評価を与えた表記で興味深い。
『EB』等では07H-4のカラーリングを赤色系統で紹介しており、これが誤認ではないとするなら、
07H-4のロールアウト時には3号機と同様のカラーリングをしていて、後に制空迷彩が施されたと
いうこともできる。 |
115/70
| 地球連邦軍 |
22弾 |
E |
 |
ガンキャノン重装型 RX-77-3
H:17.5m W:79.1t
中距離支援用のガンキャノンを改良した武装
強化タイプ。単独戦や集団戦を目的に設計さ
れた。火薬式キャノン砲をビーム砲にして実
戦投入されたものもある。 |
RX-77-2は連邦軍内での中距離支援用MSの地位を確立し、前線に送られたが、一部はジャブロ
ーでRGC-80の研究が始まった後も単独戦用として重武装化する方向で研究が進められた。
結局火薬式キャノン砲の反動と重心の問題は解決されず、ビームキャノンを標準化する方向で改
良されることになり、試作されたビームキャノンを搭載した機体が『Z10本』に掲載される。
RX-77-3のうちの数機が更に改良されRX-77-4となった。逆に火薬式キャノン砲を装備したタイプ
はそのまま戦後ジャブローに残され、グリプス戦役でも使用されてMSA-003を撃破した例も有る。
なお、実戦記録やコアブロックシステムに関しての記述は『MSV』時には存在しない。 |
116/71
| ティターンズ |
22弾 |
E |
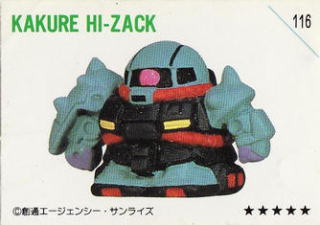 |
かくれハイザック RMS-106J
H:18m W:60.7t
狙撃用カスタムモビルスーツ。右肩のシール
ドが大きく、ランドセルは簡略タイプ。観光コ
ロニーや、農業用プラントにかくれて、高性能
の狙撃用ビームランチャーで敵をこっそり狙
撃していた。 |
かくれハイザックという名称はクワトロが揶揄で言ったもので、本来の名称はハイザックカスタム。
型式番号も混乱があり、現在ではRMS-106CSが一般的となっている。
専用の狙撃用ビームランチャーを使用するためにジェネレーターが若干強化されている。
『ガンダムUC』内で、ジオン共和国側の機体としても登場した。 |
117/72/Sシール有
| ネオ・ジオン |
22弾 |
E |
 |
R・ジャジャ AMX-104
H:20m W:67.5t
ネオ・ジオン軍の女性パイロット、キャラ・スー
ンが搭乗する指揮官用試作モビルスーツ。
18基もある姿勢制御バーニアのおかげで機
動性は高い。ハンマ・ハンマと協力してZガン
ダムを倒した。 |
作例はベストセレクション2のもの。
MS-15をモデルに白兵戦に特化した機体が試作されたが、量産化は断念された。その試作機を
上級士官用に専用機として艤装したのがAMX-104である。前段階の試作機については全く明らか
になっていない。
両肩のバリアブルシールドは前方にも展開し、盾・スラスター・武器(ミサイル内蔵)としても使える。
『ジ・アニメ』86年9月号では、ガルスJと共通のムーバブルフレームを使用していると記述され、こ
れが事実であるならば、MS-15のコンセプトを取り入れたガルス直系の機体という事になる。 |
118/73/Sシール有
| ネオ・ジオン |
22弾 |
E |
 |
ハンマ・ハンマ AMX-103
H:21.5m W:79.5t
マシュマー・セロが、ガルスJ、ズサの次に搭
乗した高性能モビルスーツ。ビーム砲つきの
両腕は有線でコントロールされる。一般人で
も使えるサイコミュの開発が間に合わず量産
されなかった。 |
作例はベストセレクション2のもの。
一般量産機にサイコミュを導入するために開発された試作機。腕部はジオングのビーム砲の改良
型で、機体を中心に半径100mのオールレンジ攻撃が可能。ネオジオン製試作機の中で最も高性
能であるが、機動力に出力のほとんどを使用するために、火器の使用が制限される。
『1/144 ハンマハンマ』インスト(文献41)には、試作機のうち1機が上級士官用としてマシュマー・
セロに与えられ、もう1機はAMX-107バウのような2機分離型のテスト機として使用されたと記述
がある。 |
119/74/Sシール有?
| ネオ・ジオン |
22弾 |
E |
 |
ガ・ゾウム AMX-008
H:18m W:58.2t
ガザC、ガザDにつづく、ガザタイプの量産型
可変モビルスーツ。肩のミサイルポッドは、
ズサと互換性を持たせてある。またハイパー
ナックルバスター、ビームサーベルも装備す
る。 |
本来はガザEとして開発されたが、予想以上の性能向上により名称を変更した。
ガザC、ガザDよりも対MS戦に比重を置いた機体。
『1/144 ガ・ゾウム』インストには、後期生産型としてAMX-008B(ガンナータイプ)が紹介されてお
り、後にガゾウムガンナーと呼ばれることになる。
グレミー軍に所属する機体が『ZZガンダム』劇中に登場したが、前半に登場した機体やハマーン
軍の機体と全く同じに塗り分けられていたのが確認できる(コラム『ガ・ゾウムのカラーリング』参照)
なお、センチネルにAMX-007ガザEというMA形態での戦闘に比重を置いた機体が登場するが、
近年、Zガンダム劇場版においてグワダンの格納庫で確認されたという。 |
120/75
| ジオン公国軍 |
22弾 |
E |
 |
強行偵察型ザク MS-06E
H:17.5m W:72.5t
MS-06Cや06Fを改修して、ザクの機動性を最
大限にひきだしたモビルスーツ。武装の軽量
化、バーニア強化、高性度モノアイに変換、カ
メラガンや探知システムなど、さまざまな改修
がされている。 |
一週間戦争では、通常のザク(06Cや06F)がそのまま偵察用に使用されたが、ザクの宇宙戦闘機
としての視点から、それ以降偵察部隊が確立された。06Eは、06Cや06Fをベースに軽量化、06Sの
エンジンをボアアップして使用、積載燃料の増加などにより、武装転換した際には06S型と同等の戦
闘能力を持っていた。パイロットは主に宇宙戦闘機乗りであり、エースパイロット並の塗装やマーキ
ングをした機体もあったという。総数としては100機程度が生産された。
『1/144 ザク強行偵察型』インストによれば、大戦初期は"ノーマルカラー"、中期以降はノーマル
カラーに加え、濃灰色や濃紺の暗視塗装したものが多く見られると記述される。この"ノーマルカラ
ー"が通常のザクグリーンを指すかは明らかでないが、少なくとも濃灰色カラーは別項を立てるべき
であった(75B) |
121/75A
| 地球連邦軍 |
22弾 |
E |
 |
強行偵察型ザク(連邦軍タイプ) MS-06E
H:17.5m W:72.5t
MS06Eは、その特殊な任務のために機動力
が高く、MS-06Sとほぼ同じ能力を持つ。この
機体は、一年戦争後に連邦軍が押収したも
ので、アンマン市偵察に使われた。 |
コクピットはハイザック同様にリニアシート化され、ハイザックと同じシールドを持つ。
なお、『MSV 宇宙編』では、一年戦争時に連邦軍の追撃機を非武装状態で返り討ちにした事例に
よって有名になった機体、と記述される。 |
122/76
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
プロトタイプドム YMS-09
H:18.2m W:95.0t
陸戦用に機動性を増すためのホバージェット推
進機能をもつ試作モビルスーツ。サイド3で2機
試作され、その後地球へ降ろされて各種テスト
に使用された。 |
モビルスーツの地上での移動力向上の問題は、MSとドダイYSの連携で一時的に解決を見せたが、
根本的な解決には至らなかった。そこでツィマッド社はホバークラフトを利用したMSの移動手段を
思いつく。当初は純粋なホバークラフトを使用する予定であったが、出力不足になる恐れがあり、
実験用にMS-07C-5グフ試作実験機を製作して新型推進エンジンをテストし、結果的に熱核ジェット
+熱核ロケットの複合エンジンによる推力をホバークラフトのように下方に噴出して推力と浮力を得る
方式に決着した。
同時期に開発された360mmロケットの試射がキャリホルニアベース北で、軍事式典の一冠として行
われた。この時のパイロットはフレデリック・クランベリー大佐。この人物は不明であるが、人気のあ
る高級将校だったらしい。これと、『灼熱の追撃』でMS-14Cに乗っていた「鉄のサソリ」隊長クランベ
リー大佐とが同一人物であるかは不明。 |
ガンダム8弾
123/77/Sシール有
| ティターンズ |
復刻9弾 |
D |
 |
サイコガンダムMKII MRX-010
H:40.7m W:283.9t
ティターンズがサイコガンダムのデータをもとに
改良、発展させたモビルスーツで、リフレクター
ビット、有線制御式メガ粒子砲などが装備され
た。ロザミア・バダム、プルツーなどが搭乗した
。 |
サイコガンダムの実戦データに基づき、その弱点を補強しより強化した機体。
リフレクタービットを飛ばすことによってオールレンジ攻撃が可能となり、接近戦用には腕部からビー
ムソードを形成することができるが、パイロットの負担は大きくなった。
グリプス戦役末期にティターンズが実戦投入したが中破し、それを極秘にネオジオンが回収、ミノ
フスキークラフトを搭載して完成形に仕上げ(これによりMA形態へ変形可能)、再び実戦投入した。
なお、M-MSVで発表されたMRX-007プロトサイコガンダムは28弾、MRX-011量産型サイコガンダ
ムは29弾にてガシャポン化された。 |
124/78
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
アクトザク MS-11
一年戦争時、開発が進められていた試作モビ
ルスーツ。機体にはマグネットコーティング処
理が施されている。終戦後連邦軍がコクピット
をリニアシートにしてオーガスタ研究所などに
配備した。 |
作例のカラーリングはグリプス戦役時の連邦軍仕様のもの。一年戦争時の一部に白色を配したカラ
ーリングで別項を立てるべきであった(78A)。また、『コミックボンボン』84年7月号(文献42)では、
全身が青カラーのアクトザクが紹介されている。
戦争末期、小惑星ペズンにおけるペズン計画の所産の試作モビルスーツで、マグネットコーティング
の運用試験を行っていたとされる。本来MS-11ナンバーは次期主力機ゲルググ用であったが、情報
を混乱させるために急遽アクトザクに振り替えられた。武装は試作ビームライフルの他、プルバップ
ガン、大型ヒートホーク等であり、性能的にもザクをベースにしたものとしては大幅な向上が見られ
たようである。
終戦後、連邦軍によって接収、増加試作された機体は、マラサイ用ビームライフルやハイザック用マ
シンガンなどを装備していた。なお、Zガンダム放映当初は、アクトザクではなくYMS-08Aが登場す
る予定であったが、(性能的にそぐわないためか?)変更された。 |
125/79
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムキャノン RGC-80
H:18.0m W:65.0t
ジムキャノンはRX-77ガンキャノンの量産タイ
プである。ただしRGM-79との共通部品が60%
もあるため見た目にはジムのキャノンタイプと
言われていた。 |
本来ならばRX-77を多少手直しして生産されるはずであったが、RX-77自体が試作機の領域を出ず
に量産性に問題があったために、戦時中の急場しのぎということでRGM-79の部品を60%使う事に
よって量産化が可能となった。
このRGM-79同様のカラーリングは試作2号機以降一般的であり、レビル及びティアンム艦隊に配備
され宇宙に上がった機体や、北米戦線の一部の機体にも使用された。
武装は、右肩のロケット砲の他、ビームスプレーガン、そして宇宙戦においてはバルザック式バズー
カも携行できた。またビームライフルの標準装備化も進められたが、結局RX-77と同型式のものが
5機分作られたのみに終わっていると『1/144ジムキャノン』インストに記載される。
戦後の調査で宇宙艦隊所属のジムキャノンの戦果があまり見られないのは、ソーラレイによる損害
によるものだと考えられている。『1/144ジムスナイパーカスタム』のボックスアートには、スナイパー
カスタムやジムライトアーマーと混成部隊を編成している姿が見て取れる。
『原典継承』のMSV-Rにおいて、脚部装甲を取り外した空間用ジムキャノンが新たに公開された。こ
れは宇宙空間においては重量バランスを気にしないでよいため、デッドウェイトとなる脚部装甲を取
り外したものと思われる。 |
126/79A
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムキャノン アフリカ戦線機 RGC-80
H:18.0m W:65.0t
RGC-80の総生産機数は48機で全機ジャブロ
ーで生産された。そのうちアフリカ戦線には19
機が配備されていた。 |
ジムキャノンの中で最も配備数が多いのがアフリカ戦線であるが、大戦末期の反抗作戦には北米
戦線から回された機体も多数参加した。サンドカラーの濃淡を基本したカラーリングであるが、これ
は正式塗装ではなく、現地の部隊カラーであったとされる。
『戦略術』には黒い専用機を駆ったとされるリド・ウォルフ少佐の名前があり、『ギレンの野望』等で
は、アフリカ戦線で黒いジムキャノンに乗っていたとされるが、連邦軍のような組織優先の大組織
の中でパーソナルカラーの使用は懐疑的である。 |
127/79B
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムキャノン 北米戦線機 RGC-80
H:18.0m W:65.0t
北米戦線にはRGM-79ジムとともに6機のジム
キャノンが配備されていた。ジムキャノンの武
装は肩のロケット砲のほかビームスプレーガ
ンやバルザック式バズーカなども使用された。 |
ジムキャノンが一番初めに配備されたのが北米戦線アラスカ方面軍であった。ホワイトベース隊が
北米司令部を撃破したのを契機に始まった連邦軍の反攻作戦から一ヵ月後にジムキャノンが配備
され始め、その時は量産初号機と同じカラーリングであったが、キャリホルニアベース攻防戦前に
グレーの濃淡を配したカラーリングが施され、終戦まで用いられた。ジムキャノン及びジムの混成部
隊はこの反攻作戦でジオン残存部隊に壊滅的打撃を与えたが、この戦闘はあまり知られてない。 |
128/79C
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムキャノン ジャブロー配備機 RGC-80
H:18.0m W:65.0t
14機のジムキャノンは宇宙用の装備をしてティ
アンム艦隊へ配備された。ジャブロー防衛用に
は9機のジムキャノンが残った。 |
このカラーリングはZガンダム登場時のもの。ほとんどの機体が79Dのカラーリングであったが、一部
の機体のみ頭部のみが白色であった。『1/144ジムキャノン』インストには、ジムキャノンの正式塗
装は2種類と明記されており、それが量産型と北米戦線機のカラーリングを指すと考えられることか
ら、ジャブロー防衛部隊も量産型と同じカラーリングであったと推察され(註9)、この赤色系統の塗装
は終戦後に施されたと考えられる。なお、映像では首の部分は黄色でなく胴体と同色の赤である。
Zガンダム登場時には、ジムII用のビームライフル及びシールドを装備し、コクピットはリニアシート化
している。 |
129/79D
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムキャノン ジャブロー配備機 RGC-80
H:18.0m W:65.0t
ジムキャノン1号機のテストの結果、キャノン砲
発射時のバランスに問題があったため量産さ
れたRGC-80は下半身を中心に重心を下げる
改良が行われている。 |
このカラーリングはZガンダム登場時のもの。79C同様、終戦後に施されたカラーリングだと考えられ
る。『1/144ジムキャノン(Z-MSV)』インスト(文献43)によれば、所属はキラービー隊でMS-06Dとの
混成部隊であったと記述される。映像には登場しなかったが、06Dもジャブローに配備されていたと
考えられる。なお、一年戦争時に特殊部隊用(ピンクパンサー隊?)のエンブレムとして06Dにキラ
ービーが施されたことが明らかになっているが、両者は無関係とは考えにくい。一年戦争時に特殊
部隊に所属していたジオンパイロットが終戦後に何らかの経緯で連邦軍に所属し、キラービーを引
き続き(今度は隊名として)使用したものではないだろうか。 |
130/80
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
グフ試作実験機 MS-07C-5
MS-07グフのバリエーションの1つでモニターア
イをドムのように十字形に変更し固定武装とし
てヒートサーベルを正式採用している。このC-5
タイプは一機のみ生産された。 |
C型のグフの中でもC-5は異色であった。固定武装を廃し、ヒートサーベルを標準装備としているが、
これは次に開発されるYMS-09のためのデータ収集用テスト機であったと『MSV』に記載される。
また、C-5で行われた実験のうち、最も重要なのが新型推進エンジンを用いた高速移動のテストで、
可能な限り背部バーニアを強化し、脚部に補助推進エンジンを装備、テストには成功しているが実戦
参加はしていない、とも記述される。また、『コミックボンボン』83年6月号(文献44)では、MS-07Bを
基本にYMS-09のテストベースとして作られたが、改造に手間取り実戦参加しなかったと記される。
上記の記述からは非常に重要なことが読み取れる。"新型推進エンジン"とは熱核ジェット・ロケット
複合エンジンと『センチュリー』から想定され、脚部の5本のノズルからプラズマジェットを噴出させて
浮力を生み出し、背部のバーニアによって推進力を得る構造と考えられる。ドムは更に腰部スカート
内のバーニアで推進力、足裏のプラズマジェット噴出及び脚部フレアの大型化によって更なる浮力を
得ているものと推察される。背部バーニアについては化学ロケットの可能性が高いと思われる。
また、ツィマッド社はジオニック社最新鋭の07系機体を改造に使えたという点も重要である。これは、
ライセンス生産或いは量産機ならどの開発メーカーも自由に閲覧使用できた証左であろう。
なお、『MSVハンドブック』に「脚部の推進機を大幅に変更した」としか記述のないMS-07C-4につい
ては、07C-5に関する記述や位置づけから、ある程度推察できる(註10)。 |
131/81
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ホワイトベース
RX-78ガンダムと同時に開発された地球連邦軍
戦艦。V作戦の中枢であり、宇宙空間、地上など
あらゆる所での作戦が可能である。空母としても
戦艦としても一流の性能を誇る。ア・バオア・クー
の戦いで沈没した。 |
大艦巨砲主義に傾いていた連邦軍であったが、増大するジオン公国の軍事力を目の当たりにして、
ようやく宇宙空母が建造されるに至った。当初はマゼラン級に開放型カタパルトを付け、トマホーク型
空間攻撃機(註11)12機或いはパブリク型宇宙攻撃艇6機を搭載するトラファルガ級が8隻就役した
が、艦載機運用には制限があり正規空母として分類されなかった(註12)。そこで77年度戦力整備計
画においてSCV-27A計画が承認され、翌78年2月にジャブローで同型艦3隻が同時に建造開始され
た。本来は建造順にSCV-69ペガサスの名を取ってペガサス級になるはずであったが、機関部に問
題が起こり設計を変更したためにホワイトベースのほうが早く竣工、その結果SCV-70ホワイトベース
が1番艦のホワイトベース級に名称が変更された。2番艦ペガサスは終戦間際にルナII艦隊に配備さ
れたが、戦果はない(註13)。
ホワイトベースは当初FF-S3セイバーフィッシュ12機を搭載予定であったが、開戦直後のジオンMSの
活躍から急遽RXスーツを搭載するV作戦に組み入れられることになった。その結果、RXスーツ最大6
機、FF-7Xコアファイター、ガンペリーなど戦闘機10機を搭載できる宇宙攻撃空母となった。ミノフスキ
ークラフトによる地形に影響されない浮遊移動及び単独での大気圏突入・離脱が可能。 |
132/82
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
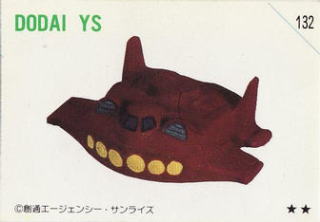 |
ドダイYS
グフの空中移動用に開発されたジオン軍の要爆
撃機。機種部に8連装大型ミサイルランチャーを
装備している。 |
元々は爆撃機として開発されたが、熱核ジェットエンジンの推力の余裕があったためにMS単体の移
動性能向上の苦肉の策として、MSを載せる改装がなされた。これが07H計画(或いはおそらく06Gや
07C-4などの従来機種改造計画)を結局押しのけて採用されることになった。元の爆撃機はゲーム『
ギレンの野望」において「ドダイGA(Ground Attackerの略か)」と呼ばれるが、公式設定ではない。
なお、『ポケットカード ガンダムモビルスーツコレクション』(文献45)においては、グリーン系の迷彩塗
装が施されており、別項を立てるべきであった(82A)。また『EB MS大図鑑part8 SPECIALガンダム大
鑑』(文献46)には、ツィマッド社がサブフライトシステムの実績を持つと記述があり、ドダイYSはツィマ
ッド社製であることが明らかになっている。
グリプス戦役においては、エゥーゴがドダイYSを改良、大型ミサイルを廃する代わりにより高出力・高
推力を得たドダイ改が使用されており、こちらも別項を立てるべきであった(82B) |
133/83
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ザクマリナー RMS-192M
H:19.4m W:68.3t
MS-06Mザクマリンタイプをベースに地球連邦軍
が改修を加えた機体。水中移動用にフロントレッ
グハイドロジェットを装備している。ネオ・ジオン
軍に徴収された。 |
『1/144ザクマリナー』インストによると、この機体はジオン軍の06M-1を戦後に連邦軍が改修した機
体と位置づけている。06M-1は06Mの初期仕様で、防水シーリングがされておらず、06M-2型に比べ
ると耐水圧能力が低く代わりに水中航行速度は06M-1のほうが高いと記述される。『Z10本』では、
「ザク水中作業型」と「ザク水中攻撃型」として別々に紹介されており、これが06M-1、06M-2にそれ
ぞれ相当すると思われる。また『ザクマリナー』インストには、「ザクマリナーを始めとしたジオンの局地
戦用MSは、連邦軍に接収され、各地の連邦軍基地に配備された。」と記載され、"ザクマリナー"とい
う名称が一年戦争当時から06Mに対して使用されていたと想定でき、戦後の改修機と差別するため
に、後に06Mを「ザクマリンタイプ(水中型ザク)」と呼び変えたものと思われる。なお、同じ連邦軍内で
2系統の水中型ザク(06M-1由来のザクマリナー、06M-2由来の?マリンハイザック)が開発された
理由は不明である(註14)。 |
134/83A
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ザクマリナー(中隊長機) RMS-192M
H:19.4m W:68.3t
ネオ・ジオン軍の水中戦闘用モビルスーツ。両肩
に3発づつ、背中に8発のサブロックを装備。左腕
にはマグネットハーケンを装備している。指揮官
用は一般用とアンテナ形状が異なる。 |
ネオ・ジオンがダカール制圧の時に奪取され、そのまま使用された経歴を持つ。当時ネオ・ジオンには
AMX-109カプールが試作機として存在していたが、スペースコロニーで理論だけで設計された機体に
疑問を持つパイロットも多く、外見も06系に似ていることからザクマリナーのほうが好んで使用された。 |
135/84
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ドワッジ MS-09G
H:18.2m W:81.7t
MS-09ドムの最終量産型。一年戦争時にアフリ
カ戦線に配備されていた。砂漠戦闘で有効なホ
バリング能力を増強するため燃料タンクが増設
されている。 |
『ドワッジ改』インストによると、09Gと09H合わせて88機が生産されたと記述される。
『模型情報』86年9月号(文献47)には、ロンメルがジオン兵器開発局部隊付きとしてアフリカに降下
したと09Hのキット説明と共に記述されることから、ロンメル自身が09Gの開発に深く携わっていた事
が推察される。おそらくは、既に少数が試験的に配備されていた熱帯線用量産型ドム09Dをベース
とするような形で発展した機体と思われ、09F→09F/tropの系統とは異なる系譜と思われる。
なお、ネオジオン抗争時には反応炉が強化された状態で現役兵力となっていた。 |
136/85
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
リゲルグ MS-14J
H:21.0m W:82.6t
ネオ・ジオン軍がゲルググをベースに改造を加
えたカスタムモビルスーツ。両肩は大型のウィ
ングバインダーに変更され背中のバックパック
は大出力化にともない大型化されている。 |
『1/144 リゲルグ』インスト(文献48)によれば、旧式化した14タイプを改修し、0088時でも一線級の機
体性能を持つと記述される(リゲルグはリファイン・ゲルググの略)。肩のバインダーはキュベレイを参
考に開発された。同文献によれば、14に標準装備された旧型のビームライフルは、アクシズでも訓練
用として使われ続けたようである。また、『ジ・アニメ』86年11月号(文献49)によると、この機体は本
来マシュマーがアクシズで訓練用として使用していたものであり、左遷後は好んで使用していたが、
ザクIII改に乗せるためにイリア・パゾムが乗り込んだと記述される。これらの事、及び『Zガンダム』劇
中に旧式のMS-14Aが配備されてる描写があることから、本機はAMX-004以降に開発された特殊
訓練用機体であると推察され、高機動の機体を与えられる上級士官やエースパイロットなどが高G下
での挙動などを訓練するための限定生産されたものだと考えられる(註15)。 |
137/86
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ガズアル AMX-117R
H:22.7m W:70.8t
一年戦争時に製造されたMS-17ガルバルディ
に改造を加えたネオ・ジオン軍親衛隊用モビル
スーツ。専用のヒートランスと大型ビームサーベ
ルを装備する。双子の兄弟ニー・ギーレンが搭
乗する。 |
『1/144 ガズR/L』インスト(文献50)によれば、この機体の本来の名称はロイヤルガード・ガルバル
ディ。当初はキュベレイの護衛用であったが、後にゲーマルクの護衛(及び監視)を務めるようになる
。『ジ・アニメ』87年1月号(文献50)によれば、ハマーンの親衛隊は全身銀色のガズアル/ガズエル
を乗機とし、劇中に登場する青髪の士官(親衛隊長?)と金髪の士官もこの機体に乗っていたとの裏
設定が存在する(註16)。
ガズアル/エルはガルバルディをベースとはしているが、出力や武装は常に改良が続けられており、
連邦製のガルバルディβとは性能に大きな違いがあるとの記述があり、アクシズで運用されていた
ガルバルディorガズアル/ガズエルは何段階かグレードアップしたようである。おそらくは、ガズアルと
の呼称以前に、AMX-117という素体が存在したものと推察される。
なお、外見は奇妙なほどに地球連邦軍製のガルバルディβと酷似しており、何らかの裏側での技術
協力・流出があったものと考えられる。『1/144ガルバルディβ』インストでは、ガルバルディαのプロ
トタイプ1号機は連邦軍に接収されたことが記載されており、そうなるとアクシズではガルバルディを
戦後にデータのみから復元して運用していた可能性が高い。幾多の改良が積極的に行われたことを
考慮するならば、ガルバルディはアクシズ内で高性能機種として確固たる地位で生産が行われたと
考えられる。 |
ガンダム9弾
138/87
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ガズエル AMX-117L
H:22.7m W:70.8t
双子の兄弟ランス・ギーレンが搭乗する親衛隊
用モビルスーツ。メタルシルバーのボディにゴー
ルドの彫刻を入れた彼らの機体はロイヤル・ガ
ード・ガルバルディと呼ばれている。 |
武装はヒートランスの他、大型のビームサーベル兼ビームキャノンという白兵戦に特化したものとな
っているが、もちろん本来のガルバルディ用のビームライフル等もドライブできる。
『1/144 ガズR/L』インストによれば、肥大した肩アーマーは、当初飾りのためであったが、後に機雷
やミサイルランチャーのラックとして改造された記述がある。 |
139/88
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
シュツルムディアス RMS-099B
H:18.0m W:61.3t
エゥーゴが開発したリックディアスに大型のグラ
イバインダーを装備したタイプ。しかし元ジオン
軍の兵士に奪われネオ・ジオンのモビルスーツ
になってしまった。
|
本来は、クワトロ専用の強化型専用機として開発されたが、クワトロに百式が与えられてしまったた
めに、エゥーゴの選抜されたエリートパイロット専用機として少数が改造された。しかし、政治的な裏
取引やエゥーゴ所属の旧ジオン兵のネオジオンへの寝返り等で数機が流出し、そのままネオジオン
所属の機体としてサトウ隊で使用された。バインダーにはメガ粒子砲が装備され火力も増強された。
サトウ隊長亡き後もマシュマー靡下で運用され、ハマーンの宮殿の警護にあたっていた。
なお、指揮官機は頭部形状が異なり、別項(88A)を立てるべきであった。 |
140/89
| 地球連邦軍 |
23弾? |
C |
 |
EWACザック RMS-119
H:19.2m W:73.5t
アイザックを改造して作った偵察用モビルスー
ツ。頭の後ろに大きなロトドームをもち背中の
ランドセルも偵察用の電子機器と航続距離を
のばすためのプロペラントタンクを備えている。 |
開発ナンバーから分かるように、RMS-106をベースに地球連邦軍がルナIIで開発した機体。
EWACとはEarly Warning and Cotrolの略であり、本来は早期警戒を目的に開発された機体(註17)。
しかし実際には06E同様の強行偵察や一般偵察、また最新の『ガンダムUC』内ではミノフスキーレ
レーダーの欺瞞など、偵察機や電子戦機としての複合的な使われ方をしていたようである。
正式名称がEWACザックであるが、ベースのハイザックの語呂と部隊の目という意味で"アイザック"
という愛称で呼ばれる。なお武装はRMS-106に準ずる。 |
141/89A
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
EWACザック 青の部隊 RMS-119
H:19.2m W:73.5t
青の部隊が使っていたアイザック。主に偵察
が任務の機体のため機動力はあっても戦闘
には不向きであった。 |
グリプス戦役後、ティターンズの残存部隊がネオ・ジオンに合流することによって引き渡された機体
という設定(モノアイを有した機体は全て敵側=ネオ・ジオンというバカげたオトナの事情による)。
ネオ・ジオンでは0095前後までこの機体を使用していた描写が連載中の『ガンダムUC』にある。
なお、ティターンズも使用していたとの設定なので、ティターンズカラーのEWACザックがあって妥当。 |
142/90
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
グワジン
ジオン公国軍の大型戦艦。装甲、戦力ともに並
の戦艦を上まわるため原則的に上流階級の者
が艦の責任者になっていた。デギン・ザビ公王
の「グレート・デギン」などがこれにあたる。 |
大型連装メガ粒子砲3門、搭載MS20機以上を誇る空母的戦艦。
少なくとも5隻以上が建造されたが、配備が分散されたことや高級将官の乗る性格から後方待機が
多く、戦力を最大限発揮できたとはいえない。
本来、シップクラスネームは1番艦に与えられるが、グワジン級は特例でキシリアの載る3番艦がクラ
スネームとなっている。1番艦は「グレードデギン」でデギン公王が乗艦したが、ゲル・ドルバ空域で
戦没。2番艦「グワメル」は開戦直後の地上降下作戦時に大気圏突入試験を行ったが分解四散し、
以降大気圏突入は行われていない。3番艦「グワジン」は、ア・バオア・クーで戦没。4番艦以降は
シップネームとの整合が取れないが、ドズル乗艦の「グワラン」、ギレンが乗艦したと思われる「グワ
リブ」、グラナダ配属でアクシズに向かった「ズワメル」、その他アサクラ大佐の乗艦した同型艦や、
ソロモンにもう1隻同型艦があったとされる。
なお、グリプス戦役時には直接後継の「グワダン」級、更に進化した「グワンバン」級、第一次ネオ・
ジオン紛争時には「サダラーン」級などがシンボル的旗艦としてそれぞれ就役しているが、ガシャポン
化はされなかった。 |
143/91
| エゥーゴ |
復刻9弾 |
D |
 |
アーガマ
反地球連邦軍組織エゥーゴが主力戦艦として建
造した。スペースコロニー「スウィートウォーター」
で極秘に作られていた。「アーガマ」という名称
は出資者のメラニー・ヒュー・カーバイン氏が命
名した。 |
『MS大図鑑 グリプス戦争編』によれば、第2世代と第3世代の中間の強襲機動巡洋艦。一年戦争時
のホワイトベースを強く意識しており、カタパルトデッキやミノフスキークラストの搭載にそれが看て取
れる。また、バリュートシステムにより大気圏突入が可能。メガ粒子砲2門、単装砲4門、MS8機程度を
搭載できる。第一次ネオ・ジオン抗争時にダカールに降下した後はカラバによって運用された。 |
144/92
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ディザートザク MS-06D
H:19.6m W:69.5t
一年戦争時にジオン軍が使っていた砂漠用ザク
の改良機。基本的には同じ機体ではあるが局地
戦用の装備などがより強化されている。 |
一年戦争時のMS-06Dをベースに、連邦軍から奪った資材などを使って現地改修した機体。ジェネレ
ータ出力もアップしており、ゲルググ用のビームライフルもドライブできた。 |
145/92A
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ディザートザク 中隊長機 MS-06D
H:19.6m W:69.5t
ディザートザクは砂漠で使われるためのダクト等
や関節部に防砂加工がされている。砂の中にも
ぐって待ち伏せ攻撃をかけることも得意。中隊長
機は頭のアンテナと頭部バルカン砲が強化され
ている。 |
改修はジェネレータ出力の他、プロペラントタンク装備による燃料積載量増加など総合的に行われ、
第一次ネオジオン抗争時においても各アフリカ戦線で現役稼動していた。
なお、この中隊長機設定は『ディザートザク』インスト(文献51)にしか表れていない幻の設定である。 |
146/92B
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
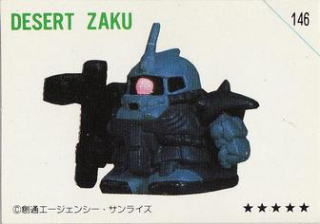 |
ディザートザク(青の部隊) MS-06D
H:19.6m W:69.5t
ディザートザクには専用マシンガンのほか、ロケ
ットランチャー、ヒートトマホーク、クラッカーなど
多くの武器が装備できる。また機動力を上げる
ためのジェットスキーをはくこともできる。 |
ロンメル隊や青の部隊などで主力機であった。
なお、砂漠という意味の「Desert」は「デザート」と発音するのが正しく、「Desert」を「ディザート」と発音
してしまうと「見捨てる・脱走する」という意味になってしまう。「デザートザク」が正しい。 |
147/93
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ロンメル専用ドワッジ MS-09H
H:19.3m W:87.4t
MS-09G一般用ドワッジを改造した機体で両肩
にブースターを増設、その他頭部形状など細か
い所で改造を加えてある。ロンメル中佐はこの
機体でZガンダムを追いつめるが敗れてしまう。 |
MS-09の最終生産型であるMS-09Gをベースに改造した指揮官機。09Gと合わせて88機が生産され
たと『ドワッジ改』インストに記載されるが、09Hが複数機存在した記述は確認されていない。
09Gの肩部に4基のブースターを増設し機動力を上げた他、リニアシートへの変更、装甲材質の変更
などが行われた。なおビームカノンは固有の武装ではなく、連邦軍から奪取したものである。 |
148/94
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
キュベレイMK-II(プル専用機) AMX-004B
H:18.9m W:57.2t
ネオ・ジオン軍のニュータイプの少女、エルピー
・プルの搭乗するモビルスーツ。基本性能はハ
マーン・カーンの1号機と同じだがビームサーベ
ルの仕様だけ変更されている。 |
旧ジオン軍MAN-08の流れを汲むMS。詳細は「キュベレイ」の項目に譲るが、このAMX-004Bは1号
機であるAMX-004のマイナー・チェンジバージョンであり、腕部ビームサーベルの基部が3方向に展
開する。 |
149/94A
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
キュベレイMK-II プルツー専用機
AMX-004B
H:18.9m W:57.2t
ネオ・ジオン軍のニュータイプ、プルツーの搭乗
するモビルスーツ。基本的にはキュベレイと同じ
であるが、プルツーが使用するサイコミュ・コント
ローラーで機外からも操縦することができる。 |
これは3号機にあたる。AMX-004Bは、当時アクシズ内で進められていたクローン・ニュータイプの査
定用として宛てられた。 |
150/95
| ティターンズ |
復刻9弾 |
D |
 |
バイアラン RX-160
H:18.6m W:54.7t
ティターンズのキリマンジャロ基地で開発中だっ
たモビルスーツ。飛行性能に重点を置き大出力
の熱核ロケットエンジンを装備している。 |
型式番号的にはキリマンジャロ基地で10番目に開発された機体。変形しないでMSを単機飛行する
ことを主眼に開発されたが、その結果飛行性・機動性は十分な性能を得たものの武装が貧弱且つ、
空力特性のために汎用性も犠牲になり、キリマンジャロ基地が陥落したために開発は中止された。
一説には降下急襲用MSとしてガンダムマークIII MSF-007と競合したとも、高価で複雑なNRX-044
の代替機として開発されたとも言われる。
背部スラスターの換装によって宇宙でも運用することができた。
なお、ロールアウト時は灰色のカラーリングであり別項(95A)を設けるべきであった。 |
151/96
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ゲルググキャノン MS-14C
H:21.0m W:110.0t
MS-14Cゲルググキャノンは重火器使用形モビ
ルスーツとしてMS-14を改造して作られた。改
造パーツは122機分用意されていたが15機の
改造がすんだところで終戦を迎えた。 |
作例は12弾の武器セット中のビームキャノンを装備している。
エース部隊に配備されたYMS-14は24機であるが、そのうち12機がMS-14B仕様に改造されたと『M
SV』に記載があるので、逆算した残りの12機は14C仕様に改造されたと推察される(註18)。
機体バランスや性能はすこぶる良好で、両手に360mmバズーカを持って出撃した例も知られる。
プラモ紹介用小冊子『MOBILE SUIT VARIATION GUNDAM』(文献52)では、このカラーリングと「
REVENGE OF IDE」のエンブレムをジェラルド・サカイ機と紹介している(註19) |
152/96A
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ゲルググキャノン エース部隊機 MS-14C
H:21.0m W:110.0t
YMS-14初期生産型ゲルググのうち24機はパ
イロットに応じたチューニングがされ、増速ブー
スター付きのものがMS-14B。ビームキャノン砲
付きのものはMS-14Cとして承認された。 |
エース部隊は、ザンジバル級キマイラを旗艦とし、当時のジオン軍の軍種を問わずエースパイロットを
31名集めた特殊部隊である。連邦のニュータイプ部隊と目されたホワイトベース隊に対抗するように
キシリアの肝煎りで編成された。判明している参加パイロットは、ジョニー・ライデン少佐、トーマス・ク
ルツ中尉、ジェラルド・サカイ大尉。編成としては、12機のMS-14Bと12機のMS-14Cの他、『ミリタリ
ーファイル』の描写に06R-1Aが少なくとも2機存在する。『コミックボンボン』83年4月号(文献53)に
は、エース部隊は変則的な3個中隊という編成であったことが記され、3人の中隊長による機数の異
なる編成だったことが窺える。『1/144 ゲルググキャノン』ボックスアートに見られる14B×1、14C×4
or5の描写はこれを反映している可能性がある。また文献53には、この部隊がジム・ボール合わせて
62機を撃墜し、逆に8機損害を受けたことも記述される。
このスプリンター迷彩機についてであるが、『MSV』当時から90年代までの資料にかけて"エース部
隊所属機"とだけ記載され、誰かの専用機という記述は存在しない。しかしながら『新エースパイロッ
ト列伝』(参考資料)において、この迷彩機はトーマス・クルツ中尉が搭乗した描写がなされ、以降ガ
ンコレ、MIAなどでトーマス・クルツ専用機と明記され、現在は定着してしまっている。
なお、1/144ボックスアートと1/60ボックスアートから、「58」の機体番号を有するこの機体は同一で
あり、96のカラーリングから塗り替えられたと考えられる。これがパーソナルカラーなのかは断定でき
ないが、スプリンター迷彩の機体は現在まで複数は確認されていない。
『1/144 ゲルググキャノン』インスト(文献54)には、ゲルググキャノンのカラーリングについて、「特殊
部隊に配備されたものが正式塗装で、全体にザク系を継承するグリーンが用いられた」とある。これ
をスプリンター迷彩と捉えるのか、それとも一般的な14Aの塗装を指すのかは明らかでないが、前者
であるならスプリンター迷彩が一般的(複数存在)したということになり、後者なら同様の塗装が14B
で確認されているため14Cにも同様の塗装が施された可能性はあるが、今のところ14Cの一般的な
塗装は96のグレー系のものと認知されている。 |
153/96B
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ゲルググキャノン ジョニーライデン機
MS-14C
H:21.0m W:110.0t
エース部隊のMS-14Cのパイロットの中にはジョ
ニー・ライデン少佐も加わっていた。大戦末期に
招換されたエースパイロットは31名であった。 |
初出は『テレビマガジン』84年9月号付録ポスター(文献55)。その後、HCM『ゲルググキャノン』イン
スト(文献56)にも掲載されるがモノクロ画稿。長らく入手困難の画稿とされてきたが、『モデルグラフ
ィックス』08年4月号(文献57)にて背面画稿と共に再掲載される。
よく知られているジョニー・ライデン専用14Bとは、拳・膝周り・爪先が黒鉄色となっている他、獅子の
ようなエンブレムが14Cでは胸部、14Bでは左前腕部、また機体番号が14Cでは「011」、14Bでは
「010」と差異が見られる。ミッション用途に応じて塗装を変更するのは不可能と考えられるので、この
違いは時期差か、或いは別機体と思われる。前者であるなら14Bで最終決戦に臨んだために、この
14Cはエース部隊召喚直後の型式だと思われる。後者であるなら、ライデンが14B、14C両機種のテ
ストパイロットとして他のメンバーより早い段階で召喚、2機によるテストを行ったのではないだろうか
。その後「010」はライデン機に、「011」は他のパイロットの機体となったと考えられる。
なお、作例の塗装はよく知られた14Bのものと同じになっている。 |
ガンダム10弾
154/97
| ジオン公国軍 |
復刻10弾? |
C |
 |
ゲルググ MS-14
H:21.0m W:102.0t
シャアのゲルググとマ・クベのギャンのデータか
ら量産化はゲルググの方が採用された。ア・バ
オア・クー防衛戦の時にはかなりの数が配備さ
れていた。 |
ジオン軍初のビームライフル標準装備の機体。バックパックの簡単な換装によって汎用型、高機動
型、支援砲撃型となり、それぞれMS-14A、14B、14Cと呼称された。量産型は、基本的に汎用型の
14Aタイプである。14Aは製作時期や工廠によって細部に違いがあり、『1/144 ゲルググイェーガー』
インスト(文献58)には各部にスラスターが追加されたタイプが紹介されている。
14Aの生産機数は明らかになっていないが、『MSV』では14系全体の生産機数を738機としている。
また『リゲルグ』インストにはア・バオア・クー戦では67機が実戦参加したのみ、と記載されるが、これ
には14B、14Cの数もカウントされている可能性がある。但し近年のMG資料では14Aの生産機数は
83機としている。
なお、近年の設定には、YMS-14の量産化にあたってツィマッド社製スラスターを採用した、各部ブロ
ック構造のため生産、メンテ、改造の効率が良かった、シールドは両軍唯一のビームコーティングを
施していた、などが後付けされている。
『ZZガンダム』劇中では、MS-06Fと一緒にアクシズに配備されている描写が見られ、リゲルグの素
体となっていることからも、少数が0088年においても現役稼動していたことが分かる。 |
155/97A
| ジオン公国軍 |
復刻10弾? |
C |
 |
ゲルググ(青の部隊) MS-14
H:21.0m W:102.0t
一年戦争末期に量産されたゲルググには参戦
せずにそのまま残された機体も少なくなかった
。また高性能機だったためにレプリカ機も多く
作られた。この機体は青の部隊で使われてい
たもの。 |
連邦軍の本格的なMS開発の情報などから、ザクの将来的な性能不足を見越した軍部は、第二次
主力MSの開発を各企業に命じた。ジオニック社はMS-06R-1Aを改造しビーム兵器をドライブできる
機体を目指しMS-06R-2Pを開発したが、メインジェネレーターの出力不足は否めず、新規の機体を
開発せざるを得なくなった。新規の機体は当初MS-11と呼ばれたが、連邦軍を攪乱するために一度
欠番にし、その後MS-11ナンバーはアクトザクに譲られた。
06R-2Pはジェネレータを06Rの改良型のものに戻し06R-2として暫定時期主力MSのコンペに出るべ
く完成されたが、暫定時期主力MSはツィマッド社のMS-09Rに決定された。そこでジオニック社は06
R-2のうちの1機を更に改造してMS-06R-3ザクIIIを試作し、この機体をベースに新型のジェネレータ
を搭載してYMS-14を作り上げた。
YMS-14は0079年10月頃には完成したとされるが、ビーム兵器の完成には機体より1ヶ月近く遅れ
た。実際に量産型14Aが配備されたのは0079年12月10日であったと『ビジュアルブック ガンダム00
80』(文献59)に記載される。
なお、青の部隊が使用した機体はレプリカだったことが『ニュータイプ100%コレクションブック ZZガン
ダム』(文献60)等に明記され、また『ジ・アニメ』86年10月号(文献61)には、この機体は砂漠用に改
造してあるが、補修部品が少ないためハイザックの部品も流用しているとの記述がある(註20) |
156/97B
| 所属なし |
復刻10弾? |
C |
 |
ゲルググ(マサイ機) MS-14
H:21.0m W:102.0t
ゲルググはその機動性の良さから宇宙戦だけ
でなく地上においても活躍した。格闘戦向けに
はビームナギナタも装備している。この機体は
アオシスに住むマサイが恋人のかたきうちのた
めに使用した。 |
『ゲルググイェーガー』インストには、地上用として少数が生産され、主戦場が宇宙に移った頃にアフ
リカ戦線などに補充用として送られたという記述がある。元々14Aは地上での用兵も考慮に入れた
設計だったために、上記の「地上用」とは特に地上用仕様として別型式だったとは考えにくい。
なお、『ZZガンダム』に登場した機体は、元ジオン兵タグの搭乗する機体だったが、現地人のマサイ
と恋仲になり戦後も地球に残り、その後死亡、その敵討ちのためにマサイが搭乗した設定である。
MSが単独で7年間もメンテ完全状態で残存しているのは不自然であり、アフリカ解放戦線などに関
連があったものと思われる。
またシールではシャア専用ゲルググと同様のカラーリングであるが、劇中では寧ろイリアが搭乗した
リゲルグと同様の濃赤系によるカラーリングであった。 |
157/97C
| エゥーゴ |
復刻10弾? |
C |
 |
ゲルググ(レプリカ)
H:21.0m W:55.6t
レコア・ロンドがジュピトリスに潜入する時に使
ったゲルググのレプリカタイプ。改造にはネモの
ムーバブルフレームにゲルググの外装をつけた
だけのものであった。武装はしていない。 |
0087年に漂流していたグワジン級の中にあった機体。メインジェネレーターが生きていたため、応急
処置をしてジャイアントバズを放ち、エゥーゴ陣の危機を救った。『MSV』には、戦後の調査でグワジン
級ズワメルとゲルググ10数機が行方不明になる事件が発覚したとの記述があるが、これがその艦で
ある可能性もある(またはアクシズに向かった船の一隻であるとも考えられる)。なお、ビームライフ
ルではなくジャイアントバズを装備していた事は、当時のジオン軍の武器事情を物語っているとも言
える。
この機体は後にジュピトリスに潜入するためにネモのムーバブルフレームを使用してゲルググを偽装
した機体になったが、ある意味で正しい「レプリカ」である。また、百式のメガバズーカランチャーのエ
ネルギー供給源として出撃したこともあり、一年戦争の配備時よりも活躍したとも言える。 |
158/98
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
コアブースター FF-X7-B
Gファイターの強化用として開発されたブースタ
ー。出力には熱核ロケットが採用され、武装も
メガ粒子砲を2門装備している。このブースター
によりコアファイターの戦力は格段にアップした。 |
コアファイターは他の航空機の持つコンピューターの10倍の情報処理能力を有する高性能戦闘機で
あったが、その形状からくる搭載武装と積載燃料の少なさはいかんともし難いものがあった。そこで
Gアーマーと同時に進められたコアファイターを有効活用し支援用兵器とするプランが急遽上げられた
。コアファイターを純粋な戦闘機としてグレードアップするこのブースタープランは性能的に成功し、大
戦中に16機が製作され6機が実戦参加した。うち2機はホワイトベース隊に配備された。
なお、『MSVハンドブック』には推進器として大型ジェットロケット複合方式と記述されるが、『MSV』で
は反応炉の出力をビームに使うと記述されており、熱核システムを使用していたことを窺わせる。
ビーム兵器の使用及び空間・大気中両用ということからも熱核システム使用でよいと思われる。
また、『ポケットカード ガンダムモビルスーツコレクション』では、他の武装として対潜多弾頭爆弾2発
も装備していることが記述されている。 |
159/99
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
作業用ザク MS-06W
大戦中期にアジア西部を中心に損傷を受けた
ザクのパーツを中心に作業用として組み立てら
れたもの。ジオン軍のMS型式分類上、正式に
は採用されていないもので都合上MS-06Wと呼
ばれていた。 |
『MSVハンドブック』には、地上での運動性能が思わしくなかった機体や能力不全の機体を流用した
との記述があり、損傷を受けた機体のみの再利用というわけではなかった模様。パーツはMS-05、
06を中心に使用されたが、中にはMS-07のパーツを使用した機体もあった。地域的にはアジア西部
〜アフリカ戦線に限られていたため知名度は高くない。全く同じ仕様の機体は存在しないが、ある種
のスタンダードはあったようで、右手にスコップ、左手にウィンチ、背部は荷物デッキという仕様である
。06Vよりも出現は早く、破壊された06Wとマゼラベースを組み合わせる研究をしていた証言がある。
06Wの多くはMS不足を補うために再武装され戦闘に参加したようである。
また、『模型情報』50号(文献62)では、迷彩塗装された機体もあったとの記載がある。 |
160/100
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ヘビーガンダム FA-78-2
フルアーマーガンダムが増加装甲をつけて強化
したものであったのに対して、ヘビーガンダムは
RX-78の装甲そのものをより強いものにして総
合的にRX-78の性能を向上させたものである。 |
作例では肩部を改造しビームキャノンを装備できるようにしている。
FSWS計画で提案されたRX-78を母体に攻撃力を強化する第2試案。FA-78-1が増加装甲を行った
のに対し、この案はRX-78自体のAパーツや脚部補助推進装置を改造したもの。背部ランドセルには
可動式のビーム砲が装備され、攻撃力の強化を行っている。『MSV宇宙編』では、RX-78の攻撃力に
不安を持っていた軍部がこの案を出したのに対し、実際にアムロ機が多数のMA・MSを撃破する現実
を見て、0079年11月末には廃案になった、と記載される。なお、『コミックボンボン』84年7月号では、
白を基調として黒が混じるカラリーングが示されている。
ヘビーガンダムには、ガンキャリーという支援爆撃機のサポートを受けられ、合体しての移動などが
考案されていた。このコンセプトは後のガンダムMk.2+Gディフェンサーで結実したと言える。
「MS-X」は「MSV」の続編としてストリームベースを中心に設定が考えられたが、富野監督の「Zガン
ダム」構想が出てきたことによって中止になった。「MS-X」の仕様書の全てが公開されていない現在
では不明な部分も多いが、明らかになっている部分によれば、極秘に計画が続けられていたこのヘ
ビーガンダムが完成したことによって、ジオン残党の新たな動きを探るという一年戦争後の話であっ
たようである。この時のヘビーガンダムのパイロットには、特殊部隊隊長デン・バザーク大佐が予定
されていた。
なお、「プラモ狂四郎」がサッキー竹田との戦いにこの機体を使用したことにより、機体そのものの説
定や背景はほとんど知られることなく、機体だけが有名になってしまった。それ故にMS-X出身の機
体の中では、「Zガンダム」に登場したMS-11 アクトザクと並んで別格の扱いになっている。 |
161/101
| エゥーゴ |
復刻9弾 |
D |
 |
ディジェ MSK-008
H:23.0m W:51.8t
地球上でのエゥーゴの支援組織カラバがリック
ディアスのデータを参考にして開発したMS。ム
ーバブル・フレームなどの内部メカを流用したた
め短期間で完成した。 |
戦いに戻ることを決意したアムロ・レイのために開発された機体。『1/144 ディジェ』インスト(文献63)
では、ジオン系の技術者が開発したことによりゲルググのような外見になったと記述される。また、
アムロ機は試作機であったことが記され、少数が生産されたようである。また『MJマテリアル ZZ&Z
設定資料集』(文献64)には、ツノの無いタイプ(量産型?)が生産された記述も見受けられる。
近年の資料になるが、『デイアフタートゥモロウ』では、当初は伝説の「連邦の白い悪魔」が搭乗する
ということでガンダムタイプの外見が予定されていたが、カラバ内の士気とアムロ自身の希望もあっ
て、ジオン風の外見になったことが描かれる。
なお、元々はハマーン用のMSとして藤田氏によってデザインされたが、内部の混乱によってアムロ
機となってしまった経緯がある。これに反感を持った近藤氏は自作の漫画内で、この機体を「チャイ
カ」と称し、旧ジオンMSの発展形としてアクシズに配備させている描写がある。 |
162/102
| ティターンズ |
復刻9弾 |
D |
 |
パラスアテネ PMX-001
H:27.4m 80.0t
木星帰りのニュータイプ、パプティマス・シロッコ
が設計した大型試作モビルスーツ。重武装、重
火力で設計したため27mもの巨大モビルスー
ツとなった。 |
作例はベストセレクション2のもの。
固定装備の腕部の大型メガ粒子砲、肩部の拡散ビーム砲だけでも重武装であるが、フル装備状態
になると、背部の大型ミサイル×8、2連ビームガン(グレネード付)、小型ミサイル内蔵シールドなど
更に重武装化される。このフル装備状態は設定だけで、劇中には登場しなかった。
シロッコによるワンオフ製作機であるが、この時代のMSの趨勢である重武装化の方向性を先進的
に示した機体といえる。 |
163/103
| ティターンズ |
復刻9弾 |
D |
 |
ゲター
ティターンズが使用する宇宙用モビルスーツト
ランスポーター。このゲターを使用することによ
り本来航続距離の短いモビルスーツの移動力
を格段にアップすることができる。 |
ティターンズだけでなく、連邦軍制式宇宙用ブースター。化学ロケット推進方式。MSの行動範囲を3
倍にすることができる。スペースジャバーとも呼ばれる。ゲターという名称は、日本語の"下駄"から
来ており、「ゲタを履かせる」というようにMSに対しても使用される。
一年戦争時においては、ジオン軍のみが大気圏中でドダイYSというサブフライトシステムを使用し
ていたが、グリプス戦役以降は連邦、ティターンズ、エゥーゴのいずれの陣営もサブフライトシステム
を重要視するようになった。これは一年戦争時の連邦軍は拠点防衛か大規模軍団による波状攻
撃という戦術スタイルだったものが、終戦以降はジオンの残党狩りや拠点強襲などの任務が主要
になったための戦術の変化によるものと思われる。
エゥーゴでは宇宙用SFSとしてシャクルズを使用し、逆襲のシャア時点ではネオ・ジオンが使用して
いる。性能的にはゲターより劣る。なお、シャクルズはガシャポン化されていない。 |
164/104
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
バウ AMX-107
H:22.1m W:34.7t
アクシズで開発されたネオ・ジオン軍の可変攻
撃型モビルスーツ。上半身と下半身が分離し
て各々戦闘機へ変形する。このカラーリングは
試作機でグレミー・トトが使用した。 |
『1/144 バウ』インスト(文献65)によれば、本機はガザシリーズの可変機構の実績から、機体を2
つに分離させ、それぞれを戦闘機として運用するという新しいコンセプトによって試作されたが、1機
のMSにパイロットを2名使用するのは非効率として一時は開発中止された。ネオ・ジオンの慣例通
り、試作機は上級士官用としてグレミー専用に改修しようとしたが、グレミーがバウナッターに大型
爆弾と慣性誘導装置を取り付けさせ大型ミサイルとして戦略的価値を付随させた。これにより再度
量産化が決定された数奇な運命の機体である。
なお、砲口が可動するメガ粒子砲内蔵の攻守一体型シールドも装備している。 |
165/104A
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
量産型バウ AMX-107
H:22.1m W:34.7t
ネオ・ジオンで製造された量産型可変攻撃型
モビルスーツ。上半身と下半身がそれぞれバ
ウアタッカー・バウナッターへと変形する。 |
量産化されたバウのカラーリングはグリーン系となった。
なお、後に叛旗を翻したグレミー軍は、グレーのカラーリングのバウを主力機としており、これは別
項を立てるべきであった(105B)。
なお、『1/144 ドライセン』インスト(文献66)によれば、バウは量産化が決定されたものの、主力機
として多量に生産されたわけではなく、ある一定数の少数量産だったことが示されている。これは
汎用性と生産性に欠けると判断されたためのようである。 |
166/105
| ネオ・ジオン |
復刻9弾 |
D |
 |
ドライセン AMX-009
H:23.4m W:66.8t
MS-R09をベースに開発されたネオジオン軍量
産型重モビルスーツ。パワーを重視して開発さ
れた。本来宇宙用に開発されたのだが陸上で
も十分運用が可能である。 |
ネオジオン初の汎用量産型MS。エゥーゴ製MSに比べて基本性能、量産性、操縦性が高いこと、そ
して旧ジオンのドムやザクの本流後継機として、このドライセンとAMX-013ザクIIIが汎用量産型MS
として決定されたと『1/144 ドライセン』インストに記載される。
格闘戦を重視した武装形態となっているが、試作段階ではドライセン専用のビームバズーカが思案
されていた。しかし、地球侵攻作戦はMS同士の格闘戦の機会が増えると予想されたために、トライ
ブレードを装備した出力の少ないランドセルに仕様変更されたことにより、これは廃案となった。後
期にはジェネレーター出力が改良され、ハンドビームガンの性能も上がったが、ビームバズーカを装
備できるような劇的な改良ではなかったようである。
なお、試作機はラカン・ダカラン大尉が搭乗した(註21)。
劇中では、グレミーが叛旗を翻した時にドーベンウルフと共に出撃しているので、グレミー軍仕様の
塗装機体が存在する可能性は高いが、画面には登場しなかった。配備数としてはハマーン軍所属
のほうが多かったらしく、メイン機種として登場した。
なお、『ガンダムUC』内で小惑星パラオ守備隊として現役で稼動している姿がある。 |
167/106
| エゥーゴ |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムIII RGM-86R
H:18.6m W:56.2t
反地球連邦組織カラバとエゥーゴの技術者た
ちが協力して開発した量産型モビルスーツ。
ジムIIをベースにガンダムMK-IIの技術を取り
入れて製造された。 |
ネモが、ジムIIをベースにムーバブルフレームやガンダリウム合金を採用して完全に第2世代MSとし
て完成したのに対し、ジムIIIはあくまでジムIIの近代化改修型である。バックパックはRX-178のもの
を使用し、ビームライフルはRX-78のものをリアレンジしたタイプを使用し、結果として0088年当時に
量産機としては一線に出られるほどの性能に仕上がっている(註22)。更にオプションとして肩にミサ
イルポッド、腰に大型ミサイルバインダーを装備することも可能。
機体の使用期間は長く、0093のシャアの反乱時にも相当数が連邦軍の制式機体として運用され、
更に『ガンダムUC』内でも首都ダカールに配備されていた。 |
ガンダム11弾
168/107
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ミディア
一年戦争当時、物資を各戦線に送るために活
躍した連邦軍主力輸送機。5基のローターで上
昇し、4基のジェットエンジンで前進する。機銃し
かないので防御力に欠ける。 |
ミディアに関しては、近年に至るまで詳述されたことがない機体のために非常に情報が少ない。
近年刊行された『MSV 地上編』によれば、地球屈指の航空機メーカーであるミデア社の製作であり、
戦前〜戦後にかけて活躍、多くの派生型の原型となったという記述がある。『0080 ポケットの中の
戦争』においては、機首の形状を変更し、より航空機っぽい形となったミデア改が登場している。 |
169/108
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
マゼラアタック
一年戦争時、地上最強を誇ったジオン軍陸上
部隊主力戦車。砲塔部分が分離して攻撃機
マゼラトップになることができる。マゼラトップに
は主砲、本体のマゼラベースには3連装機銃
が装備されている。 |
『センチュリー』によれば、上面装甲の薄い地上機甲車輌を上空から攻撃するために無理矢理産み
出された兵器という位置づけ。主砲は175mm砲で、マゼラトップは5分の飛行が可能。この場合、射
撃精度は極端に低下し、有効射程は600mであった。『MSV』によれば、ジオン軍の戦車は対MS戦
や移動要塞のコンセプトを盛り込み、大口径・重装備化していった。マゼラアタックの原型はM1型戦
車であり、ここからM1発展型を経てプロトタイプのマゼラアタックとなった。この試作機は砲塔の横に
埋め込み型のコクピットが特徴的である。次いで、生産型のマゼラアタックになった時には、一般的
に知られた形態になっている。『コミックボンボン』83年5月号には、中期以降、主翼面積を増大させ
たタイプへ変更されたという記述があり、複数の型式が存在したことを示している。『1/144 局地戦
型ドム』ボックスアート(文献67)には、サンドカラーでシャークマウスのマーキングを施した機体が
確認でき、アフリカ戦線では現地に沿ったカラーリングがなされていたようである。
なお、近年のプラモ「EX マゼラアタック」には、本機がHT-01Bの型式番号を持ち、元々はホバーク
ラフト装備を予定していた等の詳細な記述が見られる。 |
170/109
| 地球連邦軍 |
復刻10弾? |
C |
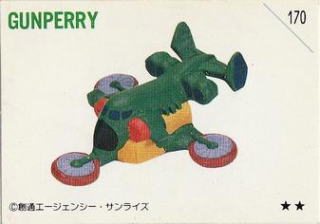 |
ガンペリー
RX-78ガンダムを輸送するために開発された
VTOL(垂直離着陸)機。ガンダムまたはA・B
パーツ各パーツごとでも搭載できる。最高速
はマッハ1.3まで出せる。 |
ポケットカード『モビルスーツコレクション』によれば、RXスーツを2機搭載する他、ハンガーに対潜
ミサイルを4発搭載可能、また機体上部に15名の戦闘員を乗せてAPCとしても使用できることが記
される。また、『MSV 地球編』には、この機体のコンセプトを、RXスーツの戦場への迅速な展開を目
的とした戦術的意義を持つ機体としている。 |
171/110
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
ジムトレーナー TGM-79
連邦軍のモビルスーツパイロットの養成用に
つくられたMS。通常コクピットの上に教官用コ
クピットが増設されている。ただし装甲板は低
コストのもので実戦には使えなかった。 |
パイロットの養成には、シミュレーションとこの訓練用ジムの併用で行われた。ジムトレーナーは、
装甲材が安価なものを使用しているが、ジムと構造や機体バランスは同じである。コクピットはタン
デム式で、教官用コクピットはガラス張りとなっている。ビームサーベルを装備しているが、装甲材
の対弾性不足により実戦には使用できず、訓練及び一般作業用として使用された。『MSV 地球編』
によれば、この機体は前線に配備された例はなく、一般作業用として使用されたのは留守部隊が
重機のように扱った事例を指しているとのことである。 |
172/111
| ジオン公国軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
トロピカルテストドム YMS-09
H:18.2m W:97.0t
ジオン軍が地球専用に開発をすすめていたモ
ビルスーツ。機動性を満たすためホバージェッ
ト推進機能を装備しており、地上用ということで
重火器も装備できるようになり、後のドムへと
開発は続いた。 |
北アフリカ戦線の要請により、ドムの熱帯地仕様が作られることになった。研究母体として、一ヶ月
に試験を終えたプロトタイプドムの2号機が選ばれ、背部ランドセルと冷却機能強化、近距離通信の
強化などの改修を行った。この機体はキャリホルニアベースやアリゾナで試験を行った後、成績も上
々ということで中東のカラカル部隊に送られ実戦試験を行った。この時、カラカル部隊に送られた熱
帯仕様のドムは4機であり、うち1機はYMS-09ベース、2機は先行量産型ドム(MS-09Aか)ベース
、残り1機は量産型ドム(MS-09Bか)であった。『1/144 局地戦闘型ドム』ボックスアートでは、「3」
「631」のマーキングのあるYMS-09ベースと見られる機体にカーミック・ロム大尉のパーソナルエン
ブレム「アラビアン」が確認できることから、同機にはロム大尉が搭乗したと考えられる(註23)。
なお、この機体は一般的にYMS-09Dの型式番号で認識される。しかし、戦時にはこの機体はあくま
で研究機扱いで、制式採用されていないためYMS-09と表記された(註24) |
173/112
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
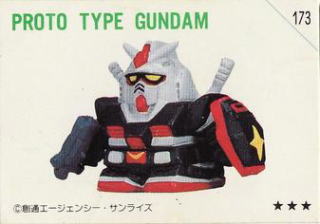 |
プロトタイプガンダム RX-78-1
H:18.0m W:60.0t
地球連邦軍がジオン軍のザクに対抗するため
に試作したモビルスーツ。宇宙空間での戦闘
に耐えられるよう腰には冷却用ユニットが装備
されている。この機体はジャブロー基地で完成
した。 |
77タイプが重火器の固定武装化の概念を引きずっていたのに対し、78タイプではシールドという分離
装甲を持ち、接近戦も考慮に入れた概念を有するMSへと昇華している。『コミックボンボン』83年11
月号には、RX-77-1からX-78 ガンダム原型機を経てRX-78-1の系譜が掲載される。メカニカルフ
ァイル『プロトタイプガンダム』(文献68)には、ジャブローで母体と呼べる機体がロールアウトした後、
ルナツーに運ばれ熱核反応炉と冷却用ユニットの強化が行われた。また、当初はハンドショットガン
型式だったビームライフルの装備方式も、サイド7で3号機同様の分離方式に改められている。
なお、1〜3号機はそれぞれG-1〜3と呼ばれていたが、G-1はRX-78-1そのものではない。G-1、2
号機は揃って同様の小改修が行われており、『MSV』では駆動方式と装甲に若干の相違があると記
されるものの、基本的には同じ機体である。すると、ジャブローでロールアウトした状態が78-1で、
ルナツーで小改修を受けた状態が78-2仕様であると解釈すべきではないだろうか。 |
174/112A
| 地球連邦軍 |
復刻9弾 |
D |
 |
プロトタイプガンダム トリコロールカラー
RX-78-1
H:18.0m W:60.0t
ジャブローでロールアウトした3機のガンダムは
その後サイド7に運ばれ、そのうち1号機は白地
に青と赤のトリコロールカラーへと塗り変えられ
た。 |
『1/144 プロトタイプガンダム』(文献69)インストには塗装の変遷が記述される。それによると、ジャ
ブローでロールアウトしたG-1は銀地に黒、そして赤のアクセント(一般的に78-1として知られる塗
装)、G-2は銀地に白で、それに赤のアクセントが入っていた。この時は78-1仕様だったと考えられ
る。サイド7に運ばれた後(この時には小改修を受け78-2仕様になっている)、G-1はこの画像の塗
装(一般的にトリコロールカラーと言われる)になり、G-2は銀地に赤という塗装後に、銀を白に変更
している。3号機も2号機同様に、白地に赤という塗装であった。更にその後、3機ともに1号機同様の
トリコロールカラーに統一された。この時点でザクの襲撃を受けたものと推察される。 |
175/113
| ティターンズ |
復刻10弾 |
C |
 |
ガブスレイ RX-110
H:18.5m W:56.2t
パプテマス・シロッコが設計したティターンズ側
可変試作モビルスーツ。装甲内部に22基のバ
ーニアの高機動能力と戦闘にあわせて3形態に
変形できる戦闘能力のため従来のMSをしのぐ
性能を誇る。 |
『1/144 ガブスレイ』インスト(文献70)には、シロッコがメッサーラの次に設計したMS。開発番号から
は、グラナダで10番目に開発されたMSになる。武装として、ビームサーベルにもなる長距離ビーム
砲であるフェダーインライフルをはじめ、両肩にメガ粒子砲、両腰に拡散ビーム砲、頭部にバルカン砲
、そしてMA形態や中間形態時に使用する大型クローアームがある。戦闘力が高い割に少数試作(2
機のみ確認される)で終わったのは、22基のスラスター及び16機のサブ・バーニアを搭載しているこ
とから、高機動であっても戦闘稼動時間が短かかった可能性を指摘でき、それが要因となったことも
考えられる。 |
176/114
| エゥーゴ |
ガンダム23弾? |
B |
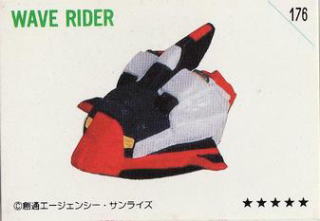 |
ウェイブライダー MSZ-006
H:24.32m W:62.3t
Zガンダムはウェイブライダーに変形することに
より単独で大気圏に突入することができ、大気
圏内でも自在に飛行することができる。このシ
ステムの発案者はパイロットとなったカミーユで
あった。 |
『ニュータイプ100%コレクション 機動戦士Zガンダム』(文献71)によれば、背部にセットされたフライ
ングアーマー部とシールドが機体を熱とショックから保護する形になっており、背中から降下していく
形態を取る。変形は0.5秒〜0.8秒で行われ、ムーバブルフレーム技術がなければ実現不可能であ
った。後方にせり出したロングテールと脚部は可動式となっており、ある程度のAMBAC性能を持つ。
またロングテールの下方噴射による水上のホバー走行も可能。腰部にセットされたビームサーベル
は、WR形態の時には前方へのメガ粒子砲にもなる。
百式やキュベレイを背中にしょって大気圏突入など、SFS的な運用のされ方をしたこともある。 |
177/115
| ネオ・ジオン |
復刻10弾? |
C |
 |
カプール AMX-109
H:16.5m W:57.5t
ネオ・ジオン軍の本拠地、小惑星アクシズで開
発された水中用可変モビルスーツ。腕・脚を縮
めることにより水中を高速で移動できる。武装
は胴体に8連装ミサイル、格闘用クローを装備
する。 |
作例はベストセレクション2(リメイク)のもの。
『ニュータイプ100%コレクション 機動戦士ZZガンダム』によれば、火力・機動性ともにアクトザクを凌
ぐとされ、MS形態では水深120mまで、水中航行形態では2300mの深海まで活動可能とある。また
モノアイ上方の装甲内には可動式のビームアイ(レーザーアイ)が装備され、他にも正体不明のソニ
ックブラストという武装を持つとされる。性能的には申し分なかったようであるが、現地の旧ジオン兵
には信用されず、ザク・マリナーのほうが偏重された。但し、劇中ではハーケンをカプールにつなげ
て曳航させる描写があり、水中航行性能も非常に高かったようである。
なお、ポケ戦に登場したMSM-03/C ハイゴッグはカプールを意識したスタイルで描かれ、ゴッグから
の直系の開発系統という位置づけの後付け設定がなされた。 |
178/116
| ネオ・ジオン軍 |
復刻10弾? |
C |
 |
ザクIII AMX-011
H:23.9m W:68.3t
ネオ・ジオン軍が開発したザクシリーズの最終
型。ザクの性能を極限まで追求することにより
完成したザクの正当後継機。同時期に開発さ
れたドーベンウルフが量産となったため試作
のみとなった。 |
『1/144 ザクIII』インスト(文献72)によれば、ハイザックをザクの後継として認めない旧ジオンの技
術者が粋を集めて作り上げた機体。ネオ・ジオン初の汎用量産機としてドライセンと同時期に地上
用として開発されたが、地上侵攻作戦がMS同士の格闘戦の機会が多くなるとの予想から、主力量
産機としての座はドライセンに譲ることになった。その一方で、宇宙用ランドセルを装備したタイプは
研究・改良が重ねられ、最終的にはMC型を生み出している。宇宙用として活路を見出したザクIIIは
少数ながら生産されたようである。武装としては専用のビームライフルの開発が遅れ、Rジャジャの
ものを流用しているが、固定武装として腰部に強力な可動式のメガ粒子砲を装備しており、MS兵装
の概念を大きく変えたと言われている。
『ZZガンダム』劇中では、非常に小さく分かりづらいがグレミー軍仕様の機体が確認され、胸部の
赤色部分が灰色になっただけの塗装がなされたようである。
噂では、MSV当時の06R-3のラフデザインを元に小田氏が提案したデザインが採用されたらしい。 |
ガンダム12弾
179/117
| 地球連邦軍 |
ガンダム23弾? |
B |
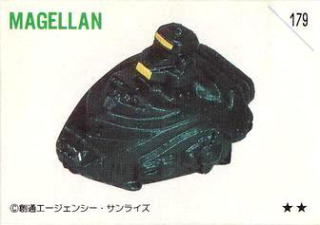 |
マゼラン
一年戦争時の地球連邦軍主力戦艦。地球連
邦の本部のあるジャブローで製造された。マゼ
ランタイプ一番艦は船名も「マゼラン」である。
武装として2連装砲塔7門、2連装機銃14基な
どを装備する。 |
『EB MS大図鑑』によると、0059年に創設された宇宙軍は、60年代いっぱいまでは、巡航用にプラズ
マ推進・戦闘機動用に化学ロケットを備えた複合型式の宇宙戦艦が主力であり、武装も高度にレー
ダー誘導化したミサイル群と防御用としてファランクスシステムスタイルの機銃がメインであった。70
年代に入り、ミノフスキー粒子を利用した熱核ロケットとメガ粒子砲という新技術の導入により新しい
形態の艦船が建造された。これがマゼラン級戦艦とサラミス級巡洋艦である。治安維持を主目的と
していたため、艦載機を搭載する空母は発達せず、またメガ粒子砲と多種のミサイルにより、大艦巨
砲主義が復活したものと思われる。空母としては、マゼラン級に甲板を取り付けただけのトラファル
ガ級が8隻のみ就役した記録が『模型情報』84年6月号に記載されるが、『コミックボンボン』83年9
月号には、トラファルガ級に艦載されるトマホークはセイバーフィッシュと同時期に開発されたという
記述があるため、比較的後期の就航だったと思われる。
一週間戦争とルウム戦役で、この大艦巨砲主義をなすすべもなく打ち砕かれた連邦軍は0079年4
月に失われた艦船の再建を目指すビンソン計画を立ち上げ、同時にV作戦としてジオンのMSに対抗
できるMSの開発を決定し、その完成の際にはMSを甲板に搭載できるような設計であった。これが
いわゆる後期型である。ビンソン計画はジャブロー本部で進められ、0079年11月末頃にはブースタ
ーを使用して多数のマゼラン・サラミス後期型が宇宙に打ち上げられた。
なお、0087年にはマゼラン級を使用している描写はなく、退役したものと思われる。参考であるが、
0083においてはまだ現役であったことから、0083〜0086の間に順次退役したと思われる。ただ、00
87においてもドゴス・ギア級のような大型戦艦を建造していることからも、象徴旗艦として大型戦艦
を使用するコンセプトは後代に受けつがれたようである。
なお、ルナツーのドックベイを塞いだマゼラン級(一番艦"マゼラン"という噂もある)は青色塗装であ
り、別項として立てるべきであった(117A)。また、他に有名な艦としては、ルウムでレビル将軍が搭
乗したいた"アナンケ"、ア・バオア・クー戦で旗艦を務めた"ルザル"などがある。 |
180/118
| ジオン公国軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
ドップ
ジオン公国軍が一年戦争時に使用した小型戦
闘機。ミノフスキー粒子下での戦闘になるため
コクピットを張り出し風防を大きくして視界を広
げるよう工夫されている。 |
地球侵攻を想定し、ガウ攻撃空母と連携することを前提に開発された機動力重視の小型戦闘機。
コロニーという空が狭い空間で生まれ育った人間が設計したために、地球上で開発された航空機と
は大きく外見やコンセプトが異なる。主翼は小さく揚力は少ないが、それを高推力ジェットで補って
いる。そのため航続距離は大変短くなっているが、ガウという空中空母を母艦として補給するために
ほとんど問題とならず、機動力のみを突き詰めた機体となった。ドッグファイト能力は非常に高い。 |
181/118A
| ジオン公国軍 |
復刻10弾? |
C |
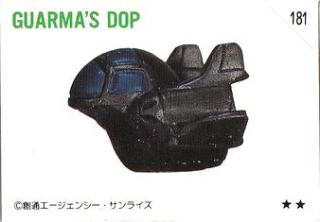 |
ガルマ専用ドップ
ジオン公国地球方面軍司令官ガルマ・ザビ大
佐が搭乗していた機体。一般兵用は緑色であ
るが彼の機体は黄土色の塗装が施されてい
た。ドップには6連装ミサイル2基とバルカン砲
が装備されている。 |
ガルマ・ザビ大佐は専用のザク06FS型を所有していたが、好んでこちらのドップ戦闘機に乗って前
戦に参戦したと記録されている。性能的には一般機と変わりない。
ガルマの地球方面軍司令という肩書きは名ばかり要職の最たるものであり、北米方面軍は独自に
に司令官を持ち、キャリホルニアベースを本拠地としていた。ガルマの地球方面軍は組織的にはそ
の上位に位置するが、半ば独立戦隊のような型式であったらしい。これはガルマの指揮能力の未
熟さと、実弟を激戦地に回したくないというキシリア少将の意向であったとされる。 |
182/119
| 地球連邦軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
ジム ライトアーマー RGM-79
RGM-79ジムに改造を加えた機体で戦場にお
ける一撃離脱戦法を取るために徹底した軽装
甲化がなされている。武装はガンダムと同じ
エナジィキャップ方式のライフルを使用してい
る。 |
練度の高いA級パイロットからは、ジムの個別能力を改善する要求があった。それに応えたのが、
ライトアーマーモデルとスナイパーモデルに代表される改造ジムである。あくまで「改造」であり、型
式番号の変更はなされていない。便宜上、ライトアーマーをLA型、スナイパーカスタムをSC型と呼
称することはある。
メカニカルファイル『ジムスナイパーカスタム』(文献73)によれば、改造ジムは合計で50機に満たな
かったが、戦闘リーダーとしての役割を十分果たしたとの記述がある。スナイパー系には個人カス
タム仕様や、ガード仕様、インターセプター仕様等の各種仕様が存在することから、ライトアーマー
仕様は多くて10〜20機程度の生産であったと考えられる。このタイプは仕様に差異のある機体は
ほぼ存在しなかったとも記載され、ギャリー・ロジャース大尉の乗機が特に有名であった。
『1/144 ジムスナイパーカスタム』ボックスアートには、スナイパーカスタム3機、ジムキャノン1機と
共に混成部隊を形成している姿が単機で確認され、レビルorティアンム艦隊直属の特殊配備例だ
った例が存在することが明らかである。
ライトアーマーは、ビーム戦という直撃すれば終わりという概念から、装甲を増やすより極限まで軽
量化して攻撃を避けるというコンセプトで生まれており、より戦闘機に近い存在となっている。元々、
戦闘機パイロット出身ばかりの連邦軍にあってこの考えは受け入れられやすかったようである。
極限まで軽量化したことにより、加速性能は非常にアップしたものと思われ、一撃離脱戦に特化し
た機体と言える。反面、機体の強度不足から高Gの機動格闘戦やドッグファイトには不向きであっ
たとも想定される。
なお、同様のコンセプトを持つ機体はジオン側には存在しないが、0087年においてこの概念はMS
装甲の根底を流れるものになっている。 |
183/120
| ジオン公国軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
グフ飛行試験型 MS-07H
H:18.7m W:80.0t
モビルスーツの機動力アップをはかるために
大気圏内の飛行プランとして試作されたモビル
スーツ。YMS-07Aを改造して3機が作られた。 |
『1/144 グフ飛行試験型』インスト(文献74)によれば、ザクによる電撃的な地上侵攻作戦は、その
破壊力により大きな成果を収めつつあったが、一方で走行速度の限界による制圧区域の拡大に支
障をきたし始めていた。軍部はMS単体の機動力を上げるべく多種のプランを考えたが、そのうちの
1つがMSの飛行計画であった。開発班主任としてアイザック・ウーミヤック大佐が指揮を執り、ホバ
ーボートとの一体化案を退けて浮上したのは、簡易性を追求したロケットバーニア強化と熱核エンジ
ンの脚部集中化案であった。開発はサイド3で行われたが、既にMS-07Aが生産され始めていたた
め、ベースとして用意された機体はYMS-07Aが3機とYMS-07Bが1機であった。同じ仕様で統一し
た4機は地球に降り、アリゾナで合計8週間のテストが行われた。チーフパイロットは空軍からビリー
・ウォン・ダイク大尉であり、他に5人のテストパイロットが参加した。
後述するが、このカラーリングのこの機体は、MS-07H-3仕様の3号機だと考えられる。 |
184/120A
| ジオン公国軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
グフ飛行試験型 MS-07H
H:18.7m W:80.0t
試作されたMS-07Hは短時間の飛行は可能で
あったが本格的に飛ぶことはできなかった。そ
のため実戦ではドダイYSとグフがペアを組んで
戦う方法がとられた。 |
『MSV』によれば、このカラーリングは7回目のテスト飛行の時のものである。一方で、『1/144 グフ飛
行試験型』インストには作例としてライトブルーとツートンのグレーで塗装された機体が掲載されてお
り、別項として立てるべきであった(120B)。注目すべきは、作例の塗装2種(グレー系、赤系)とボッ
クスアートのサンドカラー系の機体のマーキングがほぼ一致していることである。これは、塗装のバ
リエーションが4機の識別用のパーソナルカラーとして施されたものではなく、テストステージに伴う時
間的配列を持つカラーリングだったことが推察される。
赤系塗装は、『EB』等で07H-4にも見られることから、07H-4が存在したテスト後期の塗装と考えら
れる。テスト後期には3号機と4号機しか参加していないので、前項の赤系塗装の機体は3号機であ
る蓋然性が高い。
一方で、カラー配置やマーキングの差異を詳細に見ると、サンドカラー塗装とグレー塗装は左腕のマ
ーキングが完全に一致する。逆に、腰や左脛や左肩スパイクのマーキングはオミットされている。こ
れは茶→灰という順序を想定できる。次に、グレー系と赤系塗装を比較してみると、ライトブルーの部
分は全く同じ、薄いグレーの部分がそのまま赤系にと、配色パターンが完全に一致している。これも
直近の時間系列を想定しうる。つまり、茶→灰→赤の時間系列で塗装されたと考えられる。
インターバルを取っての後期試験であるが、機体の調子が良かったとはいえ07H-2仕様のまま後期
ままテストに臨むことは想定しにくく、4号機ほどの改修ではない小改修を3号機に行っていたものと
推察される。この仕様を07H-3とすることによって、07H-4という型式番号も生まれたのではないだ
ろうか。 |
185/120B
| 地球連邦軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
グフ飛行試験型 MS-07H
H:18.7m W:80.0t
グフ飛行試験型のレプリカ機。ジャブローに4機
配備されていた。ジャングルの多いジャブロー
では大型のドムよりも細身のMS-07Hのほうが
機動力を生かせた。改良によってホバー走行
ができる。 |
解説にある「レプリカ機」「細身の07Hの方が機動力を生かせた」等の記述は他に確認できない。
『1/144 グフ飛行試験型(Z-MSV)』インスト(文献75)や『MJマテリアル』などでは、連邦軍によって
引き続き開発が続けられ、少数が生産されたという記述がある。07Hは一年戦争当時、飛行MSとし
て開発・試験されたが、開発を引き継いだ連邦軍は飛行を諦め、09系などで実績のあるホバー機動
を導入したようである。元々飛行すること念頭に置かれた推進装置は、より噴射制御の難度が高い
装置に改良が加えられた模様であり、本来ならばMS-07H-5以降の型式番号を有するべきであろ
う。また、この07Hのホバー機構は09系からのフィードバックが考えられるが、07系の機体を利用し
ての構造配置やデバイスは、同様に補助推進装置を強化したMS-07C-4の技術が関与した可能性
があるとも考えられる。 |
186/121
| 地球連邦軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
バーザム RMS-154
H:24.2m W:62.3t
地球連邦軍がハイザックの次に量産したモビル
スーツ。一般兵でも使いこなせる汎用型タイプ。
頭部にはガンダムMK-IIのバルカンポッドが使
用できるなどいろいろな武器が装備できる。 |
『MJマテリアル Z&ZZ設定資料集』によれば、本機はエゥーゴとの戦闘激化により多量のMSを量産
する必要に迫られたために開発されたと記され、『ニュータイプ100%コレクション Zガンダムメカニカ
ル編2』(文献76)によれば、密集形態による集団戦に真価を発揮するように、機体は極端な軽量化
省略化が図られている、と記述される。しかし、その機動性や火力はガンダムマークIIに劣らないとも
記される。武装としては専用ビームライフルの他、マラサイやジムII、ハイザックのライフル、ビームサ
ーベルも使用可能であり、消耗戦の中でも稼働率が高かったものと推定される。バーザムには後継
機種は存在しないが、以後大規模なMS戦闘が少なかったことから存在意義を失い、RGM-89ジェガ
ンの系統にコンセプトが引き継がれて吸収されたものと考えられる。なお、型式番号的にはニューギ
ニア基地で4番目に開発された機体ということが読み取れる。汎用MSということで宇宙のみならず地
上でも稼動できるような設計がなされており、劇中でもジェリド中尉靡下でSFSに搭乗した形で参戦。 |
187/122
| ティターンズ |
ガンダム23弾? |
B |
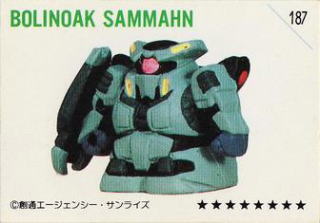 |
ボリノーク・サマーン PMX-002
H:19.9m W:56.2t
パプテマス・シロッコが輸送艦ジュピトリスで開
発した重モビルスーツ。各部に高出力バーニア
を多数装備している。頭部にはレドームがあり、
クラッシュ・ハンドという特別な武器も持っている
。 |
作例は頭部を改造し、中央にモノアイが設置されている。
本来は索敵用として開発され、頭部にレーダードーム、左腕にもセンサーを持つがあまり効果は無か
ったようである。クラッシュ・ハンドは巨大なカニバサミ風の機構を持つシールドであり、ビームサーベ
ルを内包する。ビームサーベルはゲルググ同様に柄の両端に刃を形成し、ビームトマホークとしても
使用できる。肩には炸裂弾が内蔵されている。高機動な機体、強力な格闘用武装を持つが遠距離
攻撃可能な武器を持たず、他のMSとの連携で使用されるのが前提である。 |
188/123
| 無所属(個人所有) |
ガンダム23弾? |
B |
 |
ゲゼ
サイド1にあるコロニー「シャングリラ」にあるジャ
ンク屋のボス的存在であるゲモン・バジャックが
製造したモビルスーツ。ジャンクパーツを処理す
るための特殊合金製ステッキを装備している。 |
ゲモンがジャンクから作り出したハンドメイドMS。本来はジャンク処理用の作業機なので武装は許さ
れず、怪力と特殊合金製ステッキのみの装備となったことが『ニュータイプ100%コレクション ZZガン
ダム』に記述される。しかし、それでもZガンダムを圧倒するあたり、機体自体のポテンシャルは高い。
このカラーリングは、ゲモンの搭乗した1、2号機に施されたものである。 |
189/123A
| 無所属(個人所有) |
復刻10弾? |
C |
 |
ゲゼ
3台製造されたゲゼの中の1台。ジュドーたちに
助けられたヤザン・ゲーブルがZガンダムを倒す
ために使用したが逆にジュドーの乗るZガンダ
ムに倒されてしまった。 |
作例は自作した特殊ステッキを装備している。
このカラーリングはヤザンの搭乗した3号機のものである。『MJマテリアル ZZ&Z設定資料集』によれ
ば、この他にもジャンク屋仲間に売り渡した黒のカラーリングの機体が存在したことが記述される。
ゲモン搭乗の2号機が一度は仲間に売り渡された黒のカラーリングの機体だった可能性もあるが、4
号機以降の機体だった可能性もある。いずれにせよ、全く同型のMSを製造するには非常に高度な
知識と設計技術・製造技術が必要であり、ゲモンは元々はそのような高度な技術を有する軍事関連
産業に所属していた可能性がある。モノアイを使用していることから、ジオン系だったと思われる。 |
190/124
| ネオ・ジオン |
ガンダム23弾? |
B |
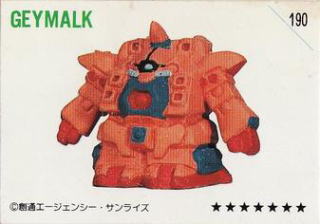 |
ゲーマルク HMX-015
H:25.5m W:78.7t
ネオ・ジオン軍が開発したサイコミュを装備した
重モビルスーツ。胸部中央にあるハイパーメガ
粒子砲をはじめ全身にビーム砲を装備した動く
要塞である。強化人間のキャラ・スーンが搭乗
する。 |
シール表記の型式番号HMX-015は「AMX-015」の誤りである。
重装備のほうに目を奪われがちであるが、姿勢制御バーニアを28基持ち、同時期の機体の中でも
群を抜いた高機動化を目指している。コンセプトとしては、キュベレイを発展させたようなオールレン
ジの重火力と、ジ・オのような高機動化を併せて持たせたものと考えられる。
武装は、手の甲に装備されたグレネード以外は全てビーム兵器であり、胸部のハイパーメガ粒子砲
の他、15基のビーム砲を装備、更に本体から分離するマザーファンネル2基とそれに収納される28
基のファンネルがサイコミュによってオールレンジ攻撃を行う。また膝にはビームサーベルが収納さ
れている。また足はガザシリーズのようにクロー化することもできる。
このような重火力、高機動化の機体だと、機体の稼働時間はかなり限られていたのではないかと
考えられ、高コスト、更には搭乗するに適正なパイロットが限定されることなどから、ワンオフの製作
だったのではないかと思われる。 |
191/125
| エゥーゴ |
復刻10弾? |
C |
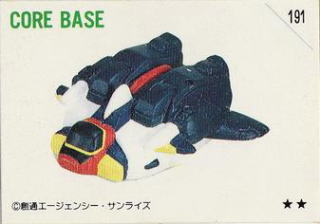 |
コア・ベース
H:22.06m W:49.1t
ZZガンダムのBパーツとネオコアファイターが合
体した大型攻撃機。3.2メガワットのビームキャ
ノン、ミサイルポッドなどの武装が装備されてい
る。 |
13弾のコアトップと合体させてGフォートレスになることが可能。
ZZガンダムの下半身とバックパックが変形した攻撃機。武装はバックパックに装備された大型ビー
ム砲とミサイルポッドをそのまま使用できる。コアファイターがなくても無線誘導できるが満足な戦闘
はできない。一年戦争当時のコアブースターと近い形態である。 |
192/126
| ティターンズ |
ガンダム23弾? |
B |
 |
ジ・O PMX-003
H:28.4m W:86.3t
パプテマス・シロッコがジュピトリス内で製作し
た最後のモビルスーツ。全身をガンダリウム
合金の装甲で覆い、その重さを高出力バーニ
アでカバーしている。 |
全身に50基のバーニアを持ち、重量の割に非常に機敏な高機動を可能としている。本体重量は57
.3tであるが、全備重量が86.3tとなり、その大部分が推進剤であると思われ、これが高機動戦闘を
可能としている。武装は専用ビームライフルとビームソードと重火力ではないが、本来はPMX-001
PMX-002と連携して作戦にあたるように開発されたためにさほど重要でないと考えられる。また、
腰部後方にはビームライフル用Eパックのラッチがあり、戦闘稼動時間を長くしている。フロントスカ
ートアーマー裏には隠し腕があり、ビームソードを使った不意討ちが可能である。背部のスタビライ
ザーは各種センサーが付いているほか緩やかに可動し、多少なりともAMBACに役立つと思われる
。脚部の歩行は可能であるが、装甲が干渉するために緩やかな動きしかできない。
放映当時の設定では無かったが、「EB」の段階になるとバイオセンサーを搭載していたことになっ
ており、現在もその設定が定着している。
高機動戦闘という面においては、ある種の到達点を持った稀有な機体であるといえる。
なお、小説版「Zガンダム」において、「The=O(ジ・オ)」とは"神の意志"という意味であることが記
されている。 |
ガンダム13弾
193/127/Sシール有
| なし |
ガンダム23弾? |
B |
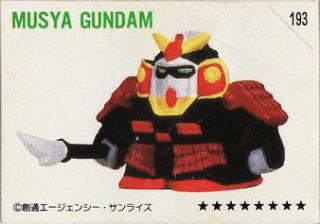 |
武者ガンダム
初代プラモ狂四郎、京田四郎が模型秘伝帳
の「木の巻」をめぐって茂合岩男の竜と戦う時
に使用した。このガンダムは手足は消しゴム
、ボディーは硬化スポンジのため敵の攻撃を
受けつけない強さを誇った。 |
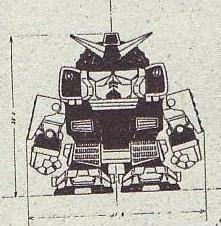 |
13弾の武者ガンダムには、足裏に名前が彫
られていない。武器パーツのランナーはベス
トセレクション2時と違う位置にあるが、切り離
してしまうと、見分けが非常に難しくなる。
現在のところ設計原図が明らかになっている
唯一のキャラであるが、設計原図と製品では
形状に大きな差異が見られる。
← 武者ガンダムの設計企画原図 |
194/128
| 地球連邦軍 |
ガンダム23弾? |
B |
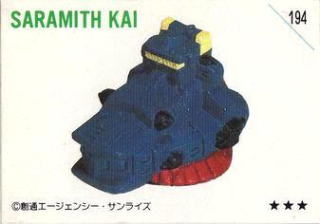 |
サラミス改
一年戦争で活躍したサラミス型巡洋艦に改造
を加えたタイプ。対空火器を増設してある。
「モンブラン」をはじめ何隻かが、エゥーゴ側の
戦力になっている。 |
一年戦争当時、ジムやボールのキャリアを増設したのがサラミス後期型であるが、それを更に改良
し、前方にモビルスーツ射出カタパルトを備え2ブロック製に区切ったタイプがサラミス改である。
『EB グリプス戦争編』によれば、武装は2連装ビーム砲(副艦橋から変更)×2、単装ビーム砲×5
、2連装機関砲×2、ミサイル発射管×2となっているが、設定画を見るとこれ以外にも艦橋付近に
大幅に機関砲が増えているのが確認できる。但しカタパルトデッキを設けたことにより、艦首付近
の兵装は減っており、より空母的な形態に変更されている。 |
195/128A
| エゥーゴ |
復刻10弾? |
C |
 |
サラミス改
一年戦争時に活躍したサラミス型巡洋艦の改
良型。エゥーゴに所属するサラミス改はこの塗
装が施され「モンブラン」や連邦軍から奪い取
った「サチワヌ」もこの塗装になっている。 |
グリプス戦役時の主力巡洋艦であり、「ボスニア」「ブルネイ」「サチワヌ」「モンブラン」「シチリア」な
ど多くの同型艦を確認できる。カラーリングは、地球連邦軍所属艦がハイザックやティターンズのM
Sによく見られる濃青色であり、一年戦争時の薄紫色から変更されている。
一方、エゥーゴはジムIIと同系統の白を基調としたカラーリングに変更されているが、第一次ネオ・ジ
オン抗争時にはエゥーゴは連邦正規軍に編入されたため、この塗装もなくなったものと思われる。
一年戦争当時のサラミス、サラミス後期型は別項目を立てるべきであった。 |
196/129
| ジオン公国軍 |
ガンダム23弾? |
B |
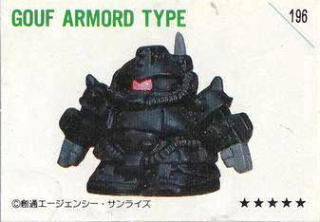 |
ヨーロッパ戦線用グフ MS-07C-3
MS-07Cグフには、いろいろなバリエーション
が存在した。このC-3タイプは両腕がマシンガ
ンへと改良を加えられヨーロッパ方面へ配備
された。重装型グフとも呼ばれる。 |
『模型情報』83年8月号(文献77)によると、実戦経験上ヒートロッドの有用性に疑問が持たれ、C-1
以降両腕にマシンガンを換装したとあり、また75mmマシンガンを85mmにすることで固定武装の強
化に重点を置いたとある。更に『MSV』では、多様化する局地戦用に基本装備の07B型では対応で
きなくなったために、Cシリーズとしてより局地化した機種を開発、特に07C-3は重装甲重武装で知
られるとある。装甲も厚くなっており、シールドは不要であったとの記述もなされる。
武装は他に頭部に06FS型と同じ40mmバルカン砲を装備し、腰には85mmマシンガンの予備弾倉を
装備する。両肩のスパイクは森林での戦闘の妨げにならぬよう小型化された。なお、比較的後年
の資料であるが、WS『MSVS』のマニュアルの中で、07C-3はキャリホルニアベースで開発されたこ
と及び、フィンガーバルカンがマニュピレーター機能を兼用させた開発陣の苦労話が掲載されてい
て非常に興味深い。
C-3型は実用配備時期の関係から主にヨーロッパ方面、特にフランス北部戦線に多数投入された
が、『MSV』にはヨーロッパ戦線のみでなく各地で使用されたとの記述もある。『戦略術』には、ジャ
ブロー降下作戦にもC-3が2機投入されたと記述される。また『MSV地球編』においては、C-3は歩
兵支援のための直協砲兵として歩兵大隊に優先的に配備されたと記述される。
07C-3を使用したことが明らかなのは、フランス南部のブリッツ中隊であり、部隊マーキングとして
三日月に狐のものが使用された(註25)。 |
197/130
| 地球連邦軍 |
ガンダム23弾? |
B |
 |
ガンタンク II RMV-1
モビルスーツ部隊支援用に製造された量産型
ガンタンク。コアブロックを排除し3人乗りとなっ
た。しかし6機しか量産できず北米と中央アジ
ア方面に配備された。 |
『1/144 プロトタイプガンダム』インストによれば、RX-75はMS化を目指しコアブロックを導入する改
修を受けたが結局空間戦の使用に足るものではなかったとして生産中止となった。一方で、MS部
隊の陸戦作戦時に支援を行う移動要塞としての役割に再び脚光が当てられ、コアブロックを排除し
て重装戦闘車輌として就役することになった。『MSV』によれば、戦闘車輌に徹することにより問題
点も少なく、ただちに量産が決定したが配備できたのは6機にすぎず、実戦には参加することなく
終戦を迎えた。但し、地上用RXスーツとしては完成の域に達したとの評価がなされている。
グリプス戦役時においてもジャブロー防衛用として1機が確認されており、一年戦争後も運用、実戦
に参加したことが明らかになっている。なお、シールのカラーリングはグリプス戦役時のものであり、
一年戦争時には青系のカラーリングの機体が紹介されており別項を立てるべきであった(130A)。 |
198/131
| エゥーゴ |
復刻10弾? |
C |
 |
スーパーガンダム RX-178
スーパーガンダムはガンダムMk-IIの強化用
として開発されたGディフェンサーと合体する
ことにより、それまでの欠点であった出力、航
続距離等を強化することができた。 |
Gディフェンサーと合体することにより、Gディフェンサーのジェネレーターを利用したロングライフル
の使用が可能となり、両肩にバインダー状にGディフェンサーを配置して装甲を強化し、更にブース
ターによって長距離航行が可能となった。そのため、Zガンダムに近い戦力となったと評価されて
いる。しかし、後の第一次ネオ・ジオン抗争時には、グリプス戦役末期にGディフェンサーが撃墜さ
れ、その後に同型機は補充されず、この形態になることはなかった。 |
199/132
| ティターンズ |
ガンダム23弾? |
B |
 |
ギャプラン飛行形態 ORX-005
H:20.3m W94.7t
ギャプランは機動性、加速性を高めるために
飛行形態へと変形することができる。バーニア
がすべて後ろに向くために爆発的な加速が得
られ、またブースターを接続することにより大
気圏突破もできる。 |
オークランドのニュータイプ研究所で開発されたNT・強化人間用TMS。『EB グリプス戦争編』によれ
ば、ギャプランはムーバブルフレームとγガンダリウムの採用により飛行時にもバインダー部分や
両脚スラスター部分の可動が可能であり、およそ航空機とは思えないような挙動を行うことができ
ると記述される。また、NRX-044よりも機動力・加速性に優れるが、爆発的に推力を使用するため
に長時間稼動はできなくなっているとも記される。さらに、初期型は推進システムが熱核ジェットで
あったが、後に開発された宇宙用は熱核ロケットに変更されたとも記述され、ドム⇔リックドムの違
いぐらいの型式変更がなされている。 |
200/133
| ティターンズ |
ガンダム23弾? |
B |
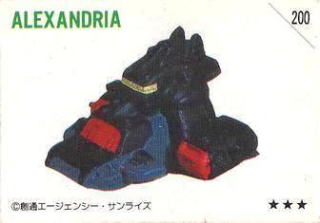 |
アレキサンドリア
地球連邦軍が建造した宇宙巡洋艦。初めは
ティターンズの旗艦としてバスク・オム大佐が
指揮をとった。グリプス戦役でコロニーレーザ
ーの直撃を受け四散した。 |
『EB グリプス戦争編』によれば、このクラスは旧ジオン公国のムサイ巡洋艦を参考に建造された
第二世代の宇宙艦。艦首上下にカタパルトデッキを備え、装備として二連装砲×4、単装砲×4を
持つ。また、ブリッジを大型化し、二連装砲×2を増設した「ハリオ」タイプも作られた。
ティターンズの主力巡洋艦として運用されたが、後の第一次ネオ・ジオン紛争時には地球連邦軍
の艦艇としてはサラミス改級のみしか確認できず、建造コスト高やMS偏重主義などによって建造
数は少なかったのだろうと考えられる。
ティターンズは他に、試作巡洋艦「ロンバルディア」級(一隻のみ)、大型戦艦ドゴズ・ギア級(後に
旗艦、一隻のみ)を有しているが、ガシャポン化はされなかった。なお、ドゴス・ギア級は、『ガンダ
ムUC』内において2番艦「アドミラル・レビル」が登場している。 |
註7 『1/144 高機動型ザク』キットインストには、キットに同梱されていた通常版と、後に店頭キャンペーンでのみ
入手できた非売品のメカニカルファイル型式のものがあり、生産機数についての記述は後者のみに記載される。
註8 『MSV』の記述からは、燃料搭載量の不足のために改修の必要が生じた旨の記述があることから、全機が07H-2に早い段階で
改修されたと考えられる。その後、2週間のタイムラグを置いて3号機と07H-4に改修した4号機のみで試験を行っている。
ということは、大幅に仕様を変更した07H-4とは違った方向で、3号機は07H-2の延長上で細部の改修をされた可能性が高く、
自然と「MS-07H-3」が浮かび上がってくる。
なお、07H-4の迷彩塗装は、ロシアや欧州で使用されている戦闘機の制空迷彩と同様のものであることを補記しておく。
註9 『MSVコレクション』には、ジムキャノンは全機実戦参加したと記述され、『MSV』には残りの9機はジャブロー配備であったと
言われている、と含みを持たせた言い方をしていること、北米戦線への配備は早くても11月後半を想定しうることから、残りの
9機は公にならない特殊部隊等で運用されていた可能性も否定できない。無論、11月30日のジャブロー攻防戦に実戦参加し
たことをカウントしている可能性もある。
註10 C-5の記述で「固定武装を廃し」たことを異色としているため、C-4はC-1やC-3同様のマニュピレータ兼用マシンガンを装備して
いた可能性が高い。また、ジオン軍はMSの単体移動性能の向上に腐心していた。軍開発局が中心となって進めた07H計画など
も存在するが、ツィマッド社が独自に在来機種(06、07)の高速移動化への改装を試作運用していなければ、いきなりYMS-09や
07C-5のような高度な機体は製作できないと考えられ、それら在来機種の改良がそれぞれMS-06G、MS-07C-4に対応するので
はないだろうか。
06G、07C-4段階では熱核ジェット・ロケットエンジンを装備できたとは(機体のキャパも考慮して)考えづらいので、脚部には熱核
反応炉を持たず通常のファンジェットエンジンを搭載し、大気によるジェット噴射で浮力を得る機体構造だったのではないだろうか。
この方式だと、内蔵推進剤に運用時間が左右されることになり、浮力的にも巡航時間的にも不満足な出来であったと予想される。
但し、同時期だと推察される07Hには脚部に熱核エンジンを標準装備化しており、06Gや07C-4でも同様の技術が使用された可能
性もある。どちらの方式にせよ、『MSVハンドブック』の記述とは矛盾せず、また従来の化学ロケットによるバーニアとも違う推進機
となる。
註11 この戦闘機は、小説版ガンダムに登場したトマホーク型戦闘機を指していると考えられ、『コミックボンボン』83年9月号には小田氏
による解説が掲載される。それによると、トマホークはセイバーフィッシュと同時期に開発されたFF計画の機体であり、『MSVハンド
ブック』に記されるFF計画の4機種のうちの宇宙用攻撃機に相当すると考えられる。FF計画の機体のため、型式番号は「FF-*」を
有すると考えられ、セイバーフィッシュと同時期であるならばFF-2が相当する可能性が高い。
註12 一年戦争中には、コロンブス級輸送船を改造した補助空母アンティータム級が24隻就役している。
註13 SCV-71・3番艦は、1番艦の戦果にあやかりホワイトベースJr.として竣工したが、終戦時には慣熟訓練中であった。終戦後1番艦
のクルーによって運用され、ホワイトベース2世と名を変更した。4番艦以降は、1番艦、2番艦で問題のあった機関部を設計変更
して、後部に推進機関を集中させカタパルトと艦載機を増やして、急ピッチで終戦までに竣工させた。SCV-72・4番艦はサラブレッド
と名付けられ、星一号作戦では主力艦隊に配備され物資運搬に従事したが、実戦経験はない。『1/144ジムスナイパーカスタム』
ボックスアートに見られる船影はこのサラブレッドだと思われる。SCV-73・5番艦はトロイホースと名づけられたが、終戦時には慣
熟訓練中であった。後に「0080」においてグレイファントム(当初はトロイホースと呼ばれていた)が5番艦として登場、ジムスナイパ
ーIIやガンキャノン量産型を搭載して、サイド6宙域でジオン部隊と戦闘になった様子が描かれる。SCV-74・6番艦は工程の37%が
終了したところで、ホワイトベースのドック入りの特定修理によって部品が転用され、その後解体された。
註14 『ザクマリナー』インストにはM-1型由来の機体がダカール基地に、M-2型由来の機体がニューギニア基地に配備されたとあり、
開発基地が異なっていたことが示唆される(ザクマリナーはジャブロー製)。グリプス戦役時の連邦軍各基地は、それぞれがコン
セプトは同じで競合しても独自の機体を開発した例が見られ(アッシマーとギャプラン等)、この例も同様と考えられる。
註15 このマシュマー機以外のリゲルグが存在した証拠は存在しないが、大型バインダーを持つ機体や各所にスラスターを持つ機体が
ネオジオンには多く存在することから、複数存在したことは想定できる。
註16 この裏設定とは、『ジ・アニメ』誌上で86年9月号〜87年1月号(最終号)に連載された、ZZガンダム制作スタッフとプラモの解説を
手がけた伸童社との対談の中で明らかにされたものである。
註17 一年戦争においてミノフスキー粒子によるレーダーの無力化がセンセーショナルな戦術の変化をもたらしたが、戦後になってミノ
フスキー粒子の存在が逆に戦闘地域を特定させるという逆転の発想から、地球連邦軍が従来のレーダー戦術を再活用する試み
がEWAC理論を復活させたものだと思われる。なお、現代戦においてEWACとは理論そのものを指し、EWACに必要な電子機器を
搭載した機種はほぼ航空機に限定されるために、AWACS(エーワックス:Airbone early Warning and Controll
System)と呼ばれる。
註18 すると実戦参加した15機のうち12機はエース部隊ということになるので、残り3機が他で使用されたことになる。この残り3機について
は、信用性の高くない資料ではあるが、大戦末期にギレン勅命で地上に降りた「鉄のサソリ」隊の隊長クランベリー大佐が搭乗して
いたとされる。また近年であるが、「ガンダムウォー」にて、ブレニフ・オグス中佐専用機が登場している。この機体はサンドブラウン
系のカラーリングが施されているが、『戦略戦術大図鑑』ではオグス中佐はパーソナルカラーを好まなかったとして、通常色(グリー
ン系)の06R-1に搭乗したと記載され矛盾する。残り1機は不明であるが、ライデン少佐の14Cを1機分にカウントすれば(あくまで改
造が15機)という記述から、全ての行き先が網羅されたことになる。
註19 但し、「REVENGE OF IDE」のエンブレムは『MSV』で元はア・バオア・クーの防衛戦隊で使用された、とあり、ジェラルド・サカイ大尉
の経歴(グラナダで技術士官→エース部隊)と合わないため、資料としての信憑性に疑問を否定できない。
註20 通常レプリカとは、その機体を模して新規に製作された後年の機体を指す。すると、青の部隊で使用されていた機体は当時の14A
とは別物の機体である可能性が高い。しかし、0087年当時の機体をベースに外装だけゲルググに模すのは不可解な現象であり、
それ以前に青の部隊そのものが新規にMSを製作できるような技術・資金を持っていたとは考えにくい。よって、レプリカとレストア(
修復再現)を混同した表現ではないだろうか?
註21 ネオ・ジオンでは試作機を上級士官用に改修して与えるという慣例があり、マシュマーのハンマ・ハンマ、キャラのRジャジャ、グレ
ミーのバウなどが明らかになっている。一方、ドライセンは試作機をラカン大尉が使用しているにもかかわらず、上級士官用に改修
された描写はない。このことから、上級士官用として専用MSを与えられるのは基本的に佐官以上であったことが推察される。
註22 なお、型式番号の「86」という数字であるが、素直に考えて0086年に制式化されたものと考えられる。但し、ジムIII自体の初陣0088年
のダカール攻防戦にカラバが12機投入した時との記述が『ミッションZZ』(文献78)にあり、映像でもそれ以前(グリプス戦役を含む)
に確認されないことから妥当と考えられる。その時に生じる2年間の間隙は末尾の「R」が意味を持つのではないだろうか。つまり、
元々地球連邦軍は0084頃にロールアウトしたジムIIを更に改良する方向にあり、試作型としてRGM-86が製作されたが、何らかの
理由で量産化採用は破棄された。それを0087頃に再度引っ張り出し、更に改良を加えたのがRGM-86Rなのではないか。
註23 カーミック・ロム大尉は、「スコルピオ」隊隊長として知られており、その乗機はMS-06Dとされる。おそらくは、YMS-09Dの試験後に、
ロイ・グリンウッド少佐のカラカル隊から出向という形で新部隊の隊長に就任し、その際にはMS-06Dに搭乗したものと思われる。
註24 『ミリタリーファイル』には戦争末期にはMS-09Fが少数生産されていたとの記述がある。YMS-09(D)のフィードバックとしてキャリホ
ルニアベースで熱帯戦用の簡易改修キット(MS-09Dとして)の生産が少数に終わったのは、熱帯戦用の機体としてバックパックを
分離しないタイプの09Fの生産が始まったからではないかと推察される。MS-09F/TROPの設定では、YMS-09Dを元にキャリホルニ
アベースで生産されたとされ、これを裏付けていよう。
註25 ブリッツ中隊は、南欧で展開された第三次掃討作戦で有名であり、個人及び小隊規模でザクレディのマーキングを施していたこと
でも知られる中隊である。即ち、ブリッツ中隊は06Jと07C-3が少なくとも混成配備されていた部隊ということが判明する。第三次
掃討作戦については他で記述が見られないが、TV版でククルス・ドアンが参加した「焦土作戦」に近いニュアンスがあることから、
ジオン軍が優勢であった大戦前期頃の作戦と考えられ、07C-5の開発時期を考えてみても0079年4〜5月頃にはC-3がヨーロッパ
方面に多数配備されていたと思われる。
参考文献
38. 『MSV Collection』ポケットカード 1984,講談社
39.『1/144 ザクデザートタイプ』キットインスト 1984,バンダイ
40. メカニカルファイル『MS-06R ザクII』 1984,バンダイ
41. 『1/144 ハンマハンマ』キットインスト 1986,バンダイ
42. 『コミックボンボン』84年7月号 1984,講談社
43. 『1/144 ジムキャノン(Z-MSV版)』キットインスト 1986,バンダイ
44. 『コミックボンボン』83年6月号 1983,講談社
45. 『ポケットカード ガンダムモビルスーツコレクション』1982,講談社
46. 『EB ガンダム大図鑑part.8 SPECIALガンダム大鑑』1993,バンダイ
47. 『模型情報』86年9月号 1986,バンダイ
48. 『1/144 リゲルグ』キットインスト 1986,バンダイ
49. 『1/144 ガズR/L』キットインスト 1986,バンダイ
50. 『ジ・アニメ』87年1月号 1987,近代映画社
51. 『1/144 ディザートザク』キットインスト 1986,バンダイ
52. 『MBILE SUIT VARIATION GUNDAM』プラモ販促用小冊子 1984,バンダイ
53. 『コミックボンボン』83年4月号 1983,講談社
54. 『テレビマガジン』84年9月号付録ポスター 1984,講談社
55. 『1/144 ゲルググキャノン』キットインスト、ボックスアート 1984,バンダイ
56. HCM『ゲルググキャノン』メカニカルファイル 1984,バンダイ
57. 『モデルグラフィックス』08年4月号 2008,大日本絵画社
58. 『1/144 ゲルググイェーガー』キットインスト 1989,バンダイ
59. 『ビジュアルブック ガンダム0080』上下巻 1989,バンダイ
60. 『ニュータイプ 100%コレクション7 ZZガンダム』1987,角川書店
61. 『ジ・アニメ』86年10月号 1986,近代映画社
62. 『模型情報』50(83年10月)号 1983,バンダイ
63. 『1/144 ディジェ』キットインスト 1985,バンダイ
64. 『1/144 バウ』キットインスト 1986,バンダイ
65. 『MJマテリアルNo.10 ZZ&Z 設定資料集』1986,バンダイ
66. 『1/144 ドライセン』キットインスト 1986,バンダイ
67. 『1/144 局地戦闘型ドム』ボックスアート、キットインスト 1983,バンダイ
68. メカニカルファイル『プロトタイプガンダム』 1984,バンダイ
69. 『1/144 プロトタイプイガンダム』キットインスト 1983,バンダイ
70. 『1/144 ガブスレイ』キットインスト 1985,バンダイ
71. 『ニュータイプ 100%コレクション1 Zガンダム メカニカル編1』1985,角川書店
72. 『1/144 ザクIII』キットインスト 1986,バンダイ
73. メカニカルファイル『ジムスナイパーカスタム』1984,バンダイ
74. 『1/144 グフ飛行試験型』キットインスト 1983,バンダイ
75. 『1/144 グフ飛行試験型(Z-MSV版)』キットインスト 1985,バンダイ
76. 『ニュータイプ 100%コレクション1 Zガンダム メカニカル編2』1986,角川書店
77. 『模型情報』48(83年8月)号 1983,バンダイ
78. 『ガンダムウォーズII ミッションZZ』1987,大日本絵画社
その他参考資料
『灼熱の追撃』1989,ケイブンシャ
『1/100 MG MS-06R-1A』キットインスト 1999,バンダイ
『1/100 MG MS-14,MS-14B/14C,YMS-14』キットインスト 1999,バンダイ
ワンダースワン『MSVS』マニュアル 1999,バンダイ
『ガンプラファクトリー』2005,バンダイ
『原典継承 大河原邦男画集』2009,角川書店
【BACK】