
■ 「茶壷」の世界 ■ ■ World of [Cha Hu] ■ |
中国茶が好きな人はかなり高い確率で「茶壷」にはまります。しかし、「茶壷」について詳しく知っている人は多くありません。日本では「茶壷」に関した書籍が少ないということもあります。しかし、大陸・台湾・華僑の間では「紫砂壷」は珍重され、マイセンのティーポットなどよりはるかに高い値段で取引されます。良い物を確実に手に入れるには、基本知識を押さえることは絶対に必要なのです。ちなみに20世紀前半の上海では「一両紫砂、一両黄金」と言われ、50グラムの紫砂と50グラムの黄金は同価値として扱われたそうです。現在の「紫砂壷」に対する加熱を見ていると、そのような時代がまた訪れつつあるのではないかという気がしてなりません。 |
 |
■ 「茶壷」の各部名称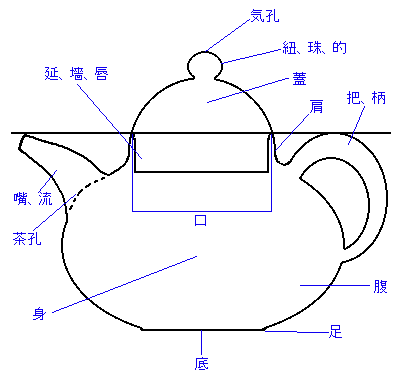 全て中国語での呼び方に基づいています。 |
■ 「茶壷」の基本3種類
|
|
■ 「泥料」 中国「宜興」がこんなに有名なのは、ひとえに素晴らしい「泥料」が取れるからです。「紫砂」とは、「紫泥」「緑泥」「紅泥」の三つの総称で、この三つの「泥料」を俗称で「富貴土」と言います。読んで字の如くとてもすばらしいく貴重な土であるということです。 良質の「紫砂」は地下の岩石層と、粘土層の間、10Cmから1mくらいの厚さしか無い層から採取されます。もちろん、地下では硬く高まっており、石の塊(「生泥」)のようになっています。それを天日で乾して風化させ、砕いて砂状にします(「初砕」)。ここから種類の良いものを選びとります。その後、陳腐処理を施し(この状態の泥を「腐泥」と言います)、その後真空状態で泥を練り上げ(「練泥」)、「紫砂壷」に使用する「泥料」(「熟泥」)を作り上げます。ちなみに、「紫砂」の主要成分は雲母(ウンモ)・石英(セキエイ)・高嶺(カオリン)です。「練泥」の時に使用する水も良い物を使わないと、強度や収縮率に影響します。 3種類の土を基本として、これらを混ぜ合わせたり、金属気化物、着色剤を使用して色々な色を作り出していきます。焼き上げの温度を調節することによっても、色や光沢を変化させることができます。 「天青泥」のように、すでに枯れてしまった鉱脈もあります。また、1999年の大洪水時に泥の鉱脈が大きな被害を受けたそうで、良質な「泥料」を手に入れるのはますます難しくなっているようです。
「緑泥」は「紫泥」に挟まれた部分に存在し、「泥中泥」と呼ばれることもあります。「紅泥」は泥層の一番底の部分に存在し、”硬いこと岩の如し”と言われています。実物を見たことは無いので知りませんが・・・。また、「紅泥」と「朱泥」は基本的には同じ泥であり、どちらの名前を使うかは、適当であるという話を聞いたことがあります。その他、「団山泥」と呼ばれる物がありますが、これは、「紫泥」と「緑泥」が混じっている層から取れた泥です。 |
|
■ 製作方法 大陸「宜興」の「茶壷」は「泥錘」(ni2 chui2)という扁平な金槌のような器具を使ってたたき出して形を作っていきます。 台湾・スワトウ・一部の「宜興」作品は、「手拉」(shou3 la1)と言われる技巧で、ロクロを使用して形を作っていきます。 「宜興」の作家物で、私は「手拉」のものを見たことがありません。基本的な見分け方ですが、「茶壷」の中を見てみてロクロ製作だったら「宜興」の作家物ではありません。こんな基本的なところで騙されないようにして下さい。 |
■ 装飾技法
|